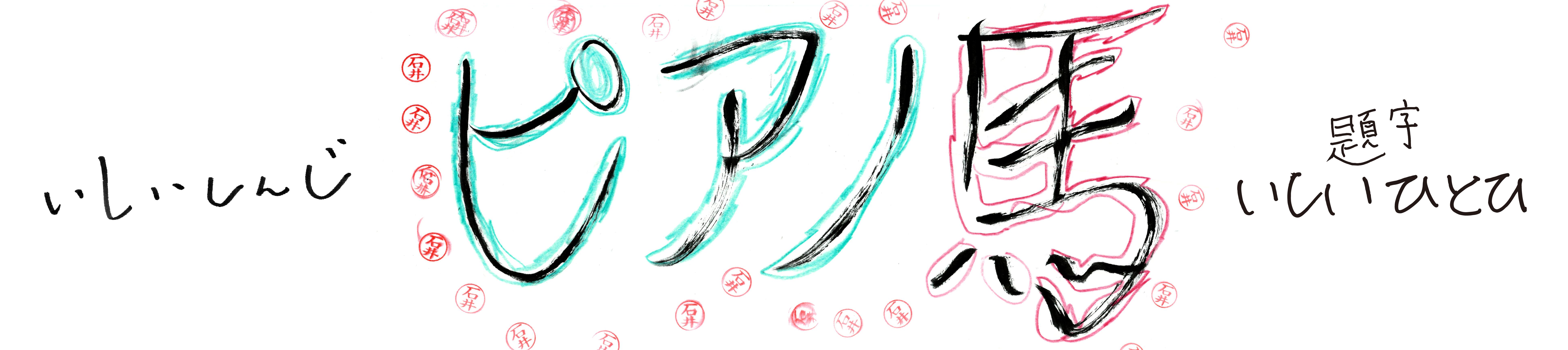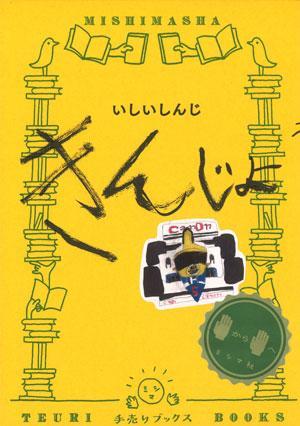第9回
ボブ・ディランが来た
2023.06.17更新
ピアノを習いはじめて1年が経つ。今週も月曜の午後、真裏に住まう山下さん宅のドアベルを押した。
「どうぞー」
居間にはグラウンドピアノが2台ある。そのうち、奥に置かれた、たぶんより新しいほうがレッスンに使われる。椅子の高さ、位置を調整し、ピアノにむかう。
はじめの10ヶ月ほどは、レッスンの手はじめに、先生のさしだすトランプサイズの音譜カード(6オクターブ分)を一瞥し、その音を鍵盤で叩く、という練習をつづけた。今年にはいって、厚い「ハノン」のテキストを渡され、毎回一曲、指ならしに弾かせてもらえるようになった。楽譜の分量からみても、この習慣はこの先もずっとつづくはずだ。
メインとなる練習曲としては、1年でテキスト「おとなのためのピアノ教本」を一冊終え、現在は二冊目の「おとなのエチュード」を三分の一ほど過ぎたところ。片ページの一曲を、だいたい3週、かかってひと月半ほどで卒業する。
「教本」のはじめのほうをめくってみると、ハ長調、四分音符、二分音符、全音符ばかり、曲の長さも八小節ほどだ。それが、いま弾いているのはト短調、十六分音符のグリッサンド二小節、装飾音など出てくるし、くりかえし記号を守れば、およそ三十二小節ほど弾くことになる。
前回に書いた、ひとひのピッチング練習、あれとまったく同じだ。毎日つづけていれば、ピアノはけして裏切らない。日々少しずつでも、着実に上手になる。
だから、毎日の書きもののあいまにピアノを弾くのが、単純に楽しい。ピアノの響きがぼくに移り、ぼくの高鳴りが音になって返る。音の響いているあいだ、生きているこの世界が、ほんの少し色づく。
この4月、ボブ・ディランが大阪に来た。チケット会社の先行予約抽選で、ひとひの分と合わせて申し込んだら、大阪フェスティバルホールの、いちばん高い席が2枚当たってしまった。園子さんにその旨告げると、パソコンのキーを叩きながら、「それが、しんじさんの誕生日のお祝いね」と視線をあげずにいった。
ひとひの入学祝いでもある。中学の入学式を終えた、その足で大阪へ向かい、午後7時の開演を待つことになる。
「ディンユー!」のフレーズを連発していた頃だから(『ライク・ア・ローリング・ストーン』のキメのフレーズ)、もう小1の頃から、ひとひはボブ・ディランのファンである。ディランからの流れで、ザ・バンド、ブルース・スプリングスティーン、ジャクソン・ブラウンなどが好きになった。
そのライブに行ける、しかもいちばんいい席で、というニュースに、ひとひは俄然もりあがった。毎日、お風呂にブルートゥーススピーカーを持ちこみ、首までお湯につかって、いちばん好きな『我が道を行く』(『ブロンド・オン・ブロンド』の2枚目の1曲目)をハミングしつつ湯あたりするほど。
とはいえ、ぼくには、懸念材料がふたつあった。
そのいち。
昨今は、全世界のミュージシャンが最近ライブでどんな曲をやっているか、ネット上でたしかめることができる。ほぼすべての公演のセットリストが、アップロードされているからだ。
アメリカ、ヨーロッパをまわって日本にやってくる、ディランの今回のツアーは、そのタイトルを「ラフ・アンド・ロウディ・ウェイズ・ツアー」といって、つまり、2020年に発表した最新アルバムのタイトルを冠してある。
ぼくは非常に好きなのだけれど、この『ラフ・アンド・ロウディ・ウェイズ』、全曲そうとうに地味だ。正直、ディランに興味がないひとの耳には、どれも同じ楽曲にきこえてしまいそうなくらい。
家でくりかえし耳にしているとはいえ、12歳の少年にはハードルが高くないか。
セットリストで確かめてみると、やはり、ディランの最近のステージでは、演奏される17曲中9曲がこのアルバムの楽曲だった。しかも、昔のヒット曲は、ものの見事に見当たらない。『ライク・ア・ローリング・ストーン』も『ハリケーン』も『コーヒーもう一杯』も『ミスター・タンブリン・マン』も演らない。奇跡的にひとひフェイヴァリットの『我が道を行く』が2曲目に入っている。ディランの公演セットリストは、この3年間ほぼまったく変わっておらず、アンコール演奏は一度としてない。
そのに。
前回、前々回と、ディランの来日公演に足を運んだファンには周知のことだが、ディランはいつも、ライブステージにおいて、もとの歌がなんだかさっぱりわからないくらい大胆なアレンジを、すべての楽曲にほどこす。昔のライブ盤をきけばわかるとおり、ずっと前からその傾向はあったわけだけれど、最近は、その度合いがメーターの針を振り切っている。
ききとりずらい発音の歌詞をきいて、「あれ、これ、ひょっとして・・」と、ファン同士、ライブの途中で耳打ちし合う。一曲目からラスト曲までが、ひとつらなりの長大な組曲のようなもの。それはそれで、ディランの凄みを芯から味わえるのだが、ことばが通じず、なんの曲かさえわからないのでは、やはり12歳の少年には、一時間半のステージは苦痛ではないのか。
4月7日の夕方5時半、ぼくとひとひは京阪電車の渡辺橋駅におりたった。早い晩ごはんに、お好み焼きの「ながい」で、焼きそば、とん平、広島焼きを平らげ、6時半にはフェスティバルホールに向かう。とちゅう、革ジャンの老人、ロンTのおばちゃんふたり連れなど見つけては、「あれ、ぜったいボブ・ディランのお客さんや」などといいあい、幅広のレッドカーペット階段をあがっていく。受付でチケットを出し、天井をはるか真上に見あげつつ、ホール内にはいる。
席はボックス席。ステージ正面に、他の席より一段高い位置に、周囲と距離をとって設えられた、32席の特別シートだ。小6のひとひが座るとあきらかに浮いている。まわりには、60代、70代の、男性ふたり連れの姿が目立つ。半世紀にわたるロック友だち、といったところだろう。ディランは今年、82歳になるのだ。
午後7時10分、夕暮れのように、灯りが落ちてゆく。
バンドメンバーを従えたディランが暗がりに出てくる。場内に喝采がわきあがる。音楽家たちは淡々と楽器に向かい、それぞれに決められた演奏の位置につく。
ディランは、ステージ中央に置いたキーボードに向かう。客席を埋めるオーディエンスと正面から向きあうかたちになる。
赤い照明がつくや、ドラムとベースがうなり、どんちゃん騒ぎ、といった風のエレキギターが鳴りひびく。客席から手拍子。一曲目は、ここ何年ものライブで必ずこの歌で先陣を切る『川の流れを見つめて』(Watcing The River Frow)。1971年に発表されたシングル曲に、ほどよいアレンジが施され、どこかしら現代風にきこえる。生声が届くほどの距離で、ディランがいま歌っている、そのことだけでもう胸がいっぱいになる。
二曲目に、ひとひの大好きな『我が道を行く』(Most Likely You Go Your Way And I`ll Go Mine)。こちらが教えなくても、ひとひには「あれか!」とわかったようで、間奏のとき、ぼくの耳に口を寄せて、「おとーさん、すごいな! いまのディランがやったら、こんなんになるねんな!」と叫んだ。たしかにそう。目の前にいるのは『ブロンド・オン・ブロンド』の頃ではない、まさしく「いま」のディランだ。
そうして三曲目、事前に調べたセットリストでは、ここから『ラフ・アンド・ロウディ・ウェイズ』の曲がはじまる。レコードではA面の1曲目に配置された『アイ・コンテイン・マルチチュード』。ギターのつま弾き、揺れる音像。そしてディランが、語りかけるように歌いはじめる。
Today and tomorrow,and yesterday,too
The flowers are dying like all things do
驚いた。アレンジが、聴きなじんだアルバムと寸分変わらない。ギターもベースもドラムスも、録音されたどおりのラインをたどり、交差しあい、目の前のサウンドをうみだしている。そして、アレンジはまったく変わらないというのに、いま演奏されている音楽は、アルバムできいたのと比べものにならないほどかっこよい。音にキレがあり、艶やかであたたかな雲が、こちらを包みこんでくるかのようだ。これがやりたかったのか、と、ライブで音を浴びてはじめて実感した。
そして声。ディランは82歳、とさっき書いた。そのディランの「いま」の声は、『ブロンド・オン・ブロンド』の声より、『血の轍』の声より、『ラブ・アンド・セフト』の、『モダン・タイムズ』の声、幾多の映画で会ったディランの声より、きわだって美しかった。これまでにきいたあらゆるディランのなかで、現在のディランが、いちばん歌がうまいとは、これは実際、ものすごいことではないだろうか。
ぼくがたどたどしく弾くピアノと同じく、ディランもいまだに、毎日うまくなっている。だからきっと、いまだに、音楽が楽しくてしようがない。およそ60年前、ジョン・レノンをびびらせ、イギリスのロッカーたちに大麻を教えた、あのディランが。
フェスティバルホールの場内全体が、ぼくと同じことを感じていた。客席でみな前にのめり、一音すら聞きのがすまいと、耳を目のように見ひらいて聴きいった。
『ファルス・プロフェット』『ブラック・ライダー』『マイ・オウン・ヴァージョン・オブ・ユー』。アルバムからの曲がつづいた。どれも聴いたことがある。それなのにたったいま、すべての音が、目の前で産みだされてゆく。これこそがライブ、つまり「生」ぼくたちは音楽の魔法にかかりっぱなしだった。ひとひは背を伸ばし、ステージに見入りながら、ディランの喉と導火線でつながっているみたいに、顔じゅうを真っ赤に火照らせていた。
デビュー時からディランは、くるくるとイメージを変える、といわれてきた。フォークからロックへ。カントリーからゴスペルへ。はたまたアメリカン・スタンダードな楽曲へ。声もそのつど変わった。挑発の響きを帯びたかと思うと、つるつるに滑らかになり、しわがれ声に変わる。
このライブを目の当たりにしながら、ようやっと腑に落ちた。ディランはなんにも変わっていない。ただ、「好きな歌を、好きなように歌う」、そのことだけをデビュー以来、一歩も譲らず貫いてきた。外からみれば、「好きな歌」「歌い方」が、時々によってちがうだけだ。その変わり方、あるいは変わり様のなさは、日々齢をかさねる月と同じ、あるいは、雪をいだいて照り輝くアルプスの嶺にそっくりだ。
ロックの創始者がつなぐ終わりのないライブに立ち合っているばかりではない。ぼくたちはいま、惑星がギターを奏で、夜の山脈が歌う様をそのまま目撃している。人類でもっとも音楽を愛し、音楽に愛された人間が奏でる音楽とは、宗教や祭礼、儀式、エンターテインメントをこえた、音楽のなかの音楽。ホールの天井が割れ、月が笑う。夜闇が波うち、ディランの声がこの地球を覆っていく。
ファンへの語りかけ、なし。曲紹介、なし。アンコール、なし。歌の神、詩の神が許すかぎり、やりたい音楽をただ一心に、やりたいように奏でる。無駄なことはなにもしない。すべてを歌に、音楽にこめ、捧げ、歌いぬく。それがディランだ。
ライブ後半、いっときだけ、客席がざわめいた。曲の演奏が終わると、ディランは動きをとめ、喝采に聴きいるように下をむいた。そうして、なにを思ったのか、いきなりキーボードの横から、ステージ最前のやや左寄りに歩み出た。客席とディランをさえぎるものはなにもない。なにか話すのか。メッセージを送るのだろうか、オーディエンスは息を呑み、ディランの姿に見入った。
ディランは仁王立ちしていた。顔をあげ、ゆっくり、ゆっくり、客席全体へ視線を、右、左、右へと這わせると、まったく表情を変えないまま、おもむろにキーボードの背後へと戻り、次の曲をはじめた。
ホールを飛んでいく自分の声が見えたのかもしれない。
(了)