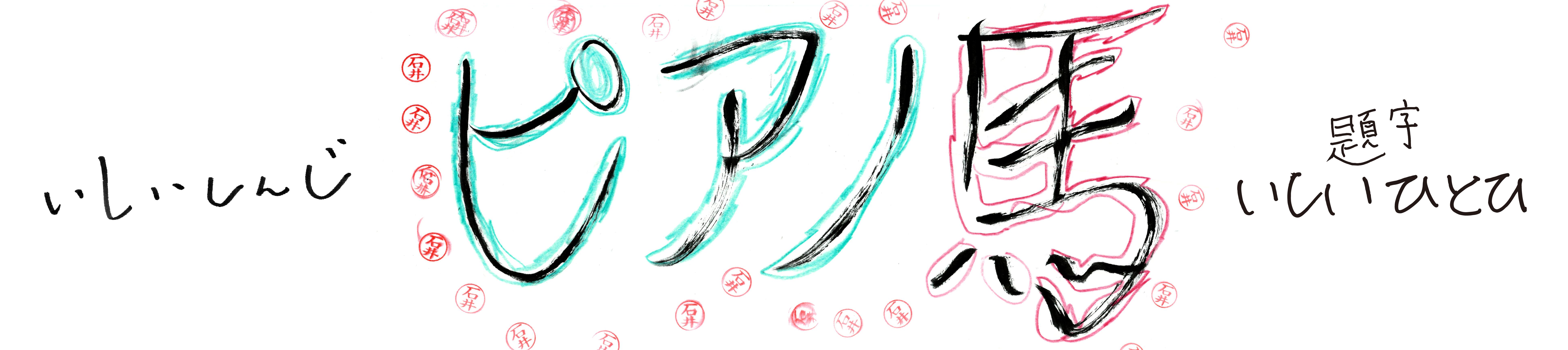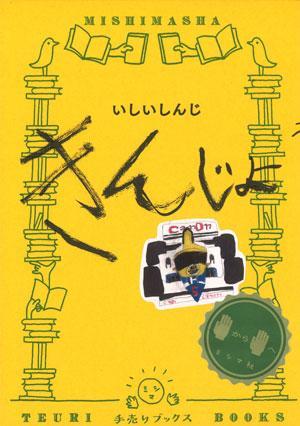第10回
名馬に会いたい(上)
2023.09.25更新
八月九日の朝、午前4時半。
じょじょに明けゆく曙の空。星空の余韻のような雲がうすくたなびく。
「桃色の空気」というふしぎな名のエアラインに乗って、関空からおよそ2時間と少し。新千歳空港に着くころ、からだのリズムはもうすっかり、書くひとから旅のひとのそれに変わっている。
レンタカーはトヨタのヤリス。運転席には園子さん、ひとひは後部席で『優駿』のページをめくり、ぼくはその隣で、本日の旅程を再検討し、ヤリスのカーナビさんにていねいに伝える。
7年ぶりの北海道。前回は十勝の小学校で小説の授業をした。6年の児童全員と2時間にわたり、教室内から廊下、壁、階段まで、水性マーカーで短いストーリーを書きまくった(あとで掃除すると校内がぴかぴかになり校長先生に感謝された)。
今回は、中1のひとひたっての希望。というか、長年の念願、宿願。北海道の牧場をまわり、馬たちに会いにいく。ただの馬ではない、もと競走馬、現在は種牡馬として第二の競走馬人生を歩んでいる、バリバリの名馬たちだ。
まずは日高町の「Yogibo ヴェルサイユリゾートファーム」へ。ヨギボーとはあのクッションのヨギボー。馬がクッションを枕に芝生に寝ころぶコマーシャルフィルムを憶えているひとも多いだろう。あの寝ころんでいた馬たちは、みなじつは有名なもと競走馬だ。ヴェルサイユリゾートファームは、種牡馬や引退馬の放牧地にコテージが隣接する、馬好きにはたまらない宿泊施設なのだ。
驚いた。
駐車場のヤリスからおりるや目の前にヒルノダムールがいた。ひとひは目を顔ぐらいにふくらませて歩みよる。ヒルノダムールも柵によってきて、新参の客をちらちらと見ながら足もとの草をほおばる。
ひとひが肘を向けると、なになに、といわんばかりに頭をあげ、匂いをかごうとごしごし鼻をすりつける。
「すごいな、おとーさん」
感慨の波に揺られるような声。
「G1馬やで。ヒルノダムール、春天、勝ってんねんで」
2011年春の天皇賞だから、ひとひは生後4ヶ月。当然、レースは見ていないものの、『優駿』や『サラブレ』、『馬まんが日記』など熟読し、JRAのホームページ、またレース映像を見あさって、21世紀にはいってからのG1レースなら、ほぼすべての勝ち馬と、レース内容を把握している。
「あっ」
小さく声を漏らすや、厩舎のむこうの大きな放牧地めざし、大股であゆむ。あわてて駆けださないのは、繊細で驚きやすい、馬の心理をわきまえてのこと。
「おとーさん!」
とはいえ声は、巨大隕石のようにはずんだ。
「オジュウやで、オジュウ、オジュウ、ほんまもんのオジュウ」
黒っぽい鹿毛の、大柄な馬体。やさしげだったヒルノダムールとはちがい、空気をおしのけるような独歩で、のっし、のっし、肩を揺らせて進む。日本競馬史上最強の障害競走馬。中山グランドジャンプ5連覇、年度最優秀競走馬に輝くこと5回、JRA重賞20勝の最多記録をもつ、怪物オジュウチョウサンが目の前を闊歩している。
2022年末まで現役だった。柵に寄るのがためらわれるくらい、まだバリバリの競走馬オーラを青い雲みたいにまき散らしている。首をかしげも、ポーズを決めも、匂いを嗅ぎにこようともしない。オジュウはただオジュウらしくのしのしと草地を歩く。ひとひは直立し、ただひたすらみいっていた。まさしくこのような時を過ごすため、ぼくたちは北海道の地へとやってきたのだ。
ここ数年、北海道に馬の見学に来るひとが爆発的に増えている。ゲーム、アニメの世界で、アニメ絵の美少女が、「ウマ」としてレースを戦うコンテンツの、もりあがりのせいだ。部屋を出て、わざわざ北海道までやってくるくらいだから、それはもう熱心なファンなのだろうが、当初から、牧場側がとまどい、悲鳴をあげている、というニュースを頻繁に耳にした。
実際の馬の間近に寄るのはこれがはじめて、という集団が、スマホを握りしめ、一気に柵の前へと殺到する。キャアキャアと歓声を発し、馬の鼻先でフラッシュを焚き、不用意に差しいれた指をガブリと噛まれる。ハサミでたてがみや尾毛を切りとるやからまでいたそうだ。
信じられない話だが、とある牧場の厩務員は、厩舎から顔をだす芦毛の名馬を前に、サンダル履きの女性ふたりがこうつぶやくのを耳にしたそうだ。
「なにこれ、ただの馬じゃん」
「キモいね」
牧場は、観光客相手に開けているわけではない。そこにいるひとたちはみな、それぞれふだんから、日々の激務に追われている。生きもの相手だから、休憩中も夜中も、一瞬たりとも気を抜けない。しかも種牡馬は、一頭いっとうが、特別な血と努力と運と夢の結晶だ。馬をよく知らない見学者を相手にする時間も余裕も、本来はあるはずもないのだ。
ことの自然として、見学にはいくつものルールが導入されるようになった(窓口の一括化、事前登録制の導入、見学時間の短縮など)。コロナ禍もあいまって、見学は当面おこないません、とする牧場も出てくるのも当前の流れだった。
初日の午後、ひとひの今回の最大の目的地(どこもそうなのですが)、「ブリーダーズ・スタリオン・ステーション」を訪ねた。
なにしろこの牧場にいるのは、ジャスタウェイ、シュヴァルグラン、アルアイン、グローリーヴェイズ、フィエールマン、ラブリーデイ、ダノンスマッシュ、ディープブリランテ、アンライバルド、それにキセキと、ひとひがよだれで溺れそうになるほどの名種牡馬ばかりだ。
待ちきれず、見学開始の15時より30分も早く、牧場の門前にヤリスをつけた。
と、牧場から走り出てきた軽トラから、五十がらみのおじさんが顔をだし、
「オーイ、なか入って待っとって、かまわんよお!」
と声をかけてくれた。
事務所前の駐車場にクルマをとめる。その後もつぎつぎと乗用車がやってきては、白枠のラインに整然とならぶ。
集合時間の15時ちょうど、三十代半ばの厩務員さんが前に出、来訪者の前で見学にあたっての注意事項を読みあげていった。まわりのみな、真剣な眼差しをむけてききいった。見学者は八組、二十名ほど。ゲーム、アニメファンというより、競馬場のスタンドから必死で声援をおくった大切な一頭に、ひと目でいいから会いにきた、熱心な競馬ファンばかりにみえた。
今回は放牧場でない。厩舎にはいっている馬に、外から対面する。
見学者はカメラを手に、それぞれ目当ての馬房にむかった。こういうときは律儀なひとひは、厩舎のいちばん手前から徐にめぐりだした。
いきなり、馬房の窓からジャスタウェイが横顔をみせた。日本調教馬史上発の世界ランキング1位に輝いた名馬。涼しげな瞳で、こちらをちらりと睥睨する。思わず身ぶるいするほどの威厳。生物種をこえた「格」のちがいに、大きく息をのむ。
小4のころのひとひが「この馬がいちばん好き」といって追いかけていたシュヴァルグラン。ジャパンカップ1着、有馬記念3着、春の天皇賞2着、ドバイシーマクラシック2着。巨体をふるって7歳まで走りつづけた。このスターホースの目の前、たった1メートルほどの距離にいることに、ひとひははじめ驚き、実感がわいていないようだった。そのうち、表情がやわらいだ。その名も「偉大な馬」シュヴァルグランが、こうしてまだ元気でいる。元気なうちに、こんな間近で対面している。その嬉しさ、喜びを、ひとひは周囲の芝生に、スプリンクラーみたいにふりまいていた。こころなしか、シュヴァルグランもまぶしげに目を細めてみえた。
そしてキセキ。菊花賞馬。ジャパンカップの2着でだした、芝2400の世界レコード。競馬を見なれはじめた頃からずっと、ひとひはこの馬に声を送りつづけた。そうしていつも、あと一歩、というところで口をつぐんだ。
その負けかたにはいつもどこかしら筋がとおってみえた。自分のレースを曲げない。距離にもコースにも、騎手にも合わせない。この馬自身がそうと決めた走りかたで、国内でも、外国でも、ゴールの最後までまっすぐに走りきる。
ひとひがキセキの前に立つ。馬はずっと馬房から顔をだしたままだ。ときおり首をかしげ、きょろきょろと瞳を動かす。ひとひが近づく。キセキは目を丸くし、鼻孔をふくらます。耳をまっすぐに立て、息づかいをきいている。
「おとーさん、キセキ、こんな馬やったんやね」
とひとひ。
「もっと、気ぃ強くて、ちょっと怖い感じなんかと思とった」
その通り。ぼくも内心びっくりしていた。人気馬キセキの前には、つぎつぎにファンがやってきて、(フラッシュなしで)何枚も写真をとる。キセキはそのたび、顔を傾けたり、ペロッと舌を出したり、ことなった表情をみせる。ポーズをとっているのではない。ひとがやってくるのがおもしろく、楽しく、嬉しそうだ。そういえば、春の天皇賞2連覇のフィエールマンも、香港ヴァーズ2勝のグローリーヴェイズも、G1・Jpnl競走11勝のコパノリッキーも、みんな馬房の窓からずっと顔を出し、寄ってくる見学者を興味深そうに出迎えている。
牧場の方々の、ふだんからの、馬への接しかたがすばらしいのだろう。馬が人間という存在を認め、信頼している。さらにいうなら、ここまでの名馬たちは、もともと頭がよく、自分をとりまく世界への、あふれるほどの好奇心を持ちあわせている。だから強かった。と、そんな風にもいえるのではないか。
キセキから、なかなか離れられないひとひがつぶやく。
「馬って、ひとがその馬を好きなきもちが伝わるんやな」
厩舎のなかでは、皐月賞・大阪杯の勝ち馬アルアインが、扇風機の送る風を浴びながら、目を細め、首を振るその動き、ファンのたてる音を一心に楽しんでいる。薄くらがりで、ディープインパクトのお兄ちゃん、スプリングステークスを勝ったブラックタイドが、寝わらの香りを嗅ぎながら、うつらうつら首を上下させている。
「馬を好きなきもち」が、この牧場には、隅々まであふれている。軽トラから飛んできたおじさんの声にもそれは詰まっていた。注意事項を読みあげていた若手の厩務員さんは、牧場の名物の猫を抱きながら、ひとひの投げかける質問ひとつひとつに丁寧にこたえてくれた。馬のきもちはどう読みとるか。ひとは馬のきもちにどうこたえるか。いい厩務員になるためにはなにが必要か。
もちろん馬は好き。馬を好きなきもちをもつひとも好き。だから、こころから歓迎する。
「ぴっぴ、ここで働きたいなあ」
とひとひ。レンタカーに乗り込み、牧場ぜんたいに手を振る。厩務員さんも手を振りかえす。馬房の窓から、キセキがまだ顔をだし、最後のひとりがいなくなるまで漆黒の瞳を輝かせている。
(つづく)