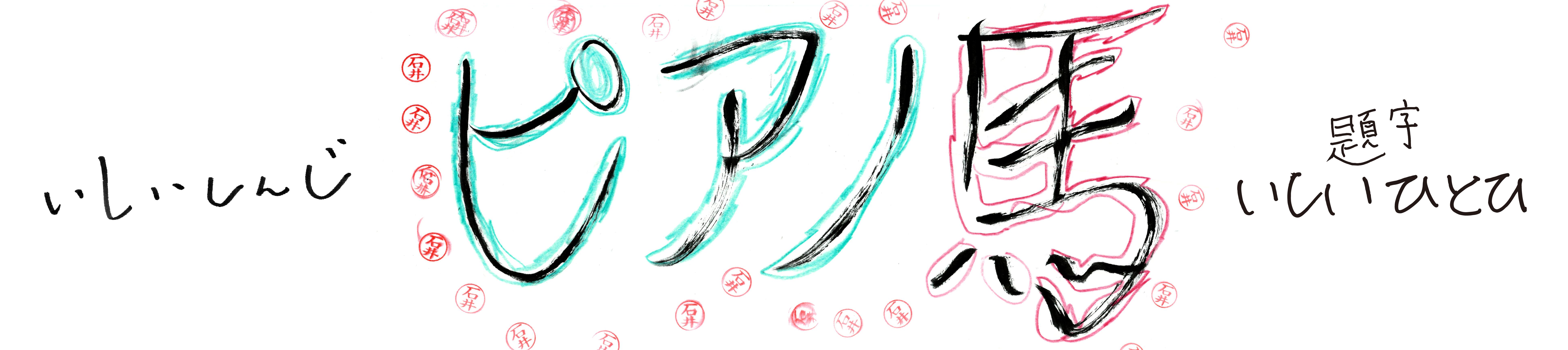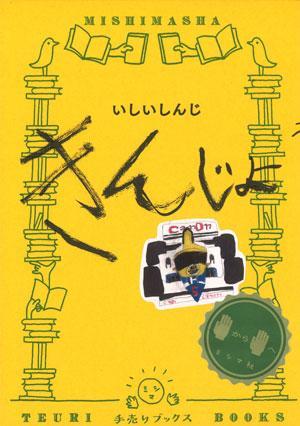第11回
名馬に会いたい(下)
2023.12.19更新
朝起きて宿の窓辺に立つと、薄日の下、牧草地の柵の前で、天皇賞馬ヒルノダムールが草を食んでいる。まさしく夢のなかの光景そのものだ。
レンタカーの後部席に乗りこむ直前まで、ひとひは、オジュウチョウサン、タニノギムレット、スズカフェニックスらににんじんを食べさせてまわった。北海道二日目、今日は日高から東へ2時間ほど走った、浦河の地をめざす。海沿いにあるこの街も、競走馬の生産で有名な土地だ。
道南の海に面した国道を東へ、東へ。この日は曇り。灰色の波が野生馬の群れのようにつぎつぎと逆巻く。海中でこんぶの森がぼくたちをさしまねく。そういえば、「こんぶ」がアイヌ語であることも、この夏の旅で知った。もともと「コンプ」と呼んでいたものが中国に伝わり、昆布、の漢字をあてられ、日本へ逆輸入されたという。
午前10時、「JRA日高育成牧場」の玄関口で集合。とりどりの家族、若いカップル、年を経た夫婦、ひとひ以外の子どもも何人もいる。
ここ育成牧場では、うまれたばかりの若馬の育成、繁殖の研究、ひとと馬との交流を深める取り組みをおこなっている。とにかく広い。総面積1500ヘクタール。みわたすかぎり、草、草、草。マイクロバスに乗り込み、見学ツアーに出発。
「敷地の三分の二は、まだ使われてないんです」
とガイド役をつとめる、職員の駒沢さん。
「ときどき、絶景ポイントで停まります。ご自由に写真をとってください」
丘陵のそこここにこんもりと繁る森。スペースをとって建てられた厩舎、柵などないグラス馬場、ゆるやかな勾配の芝の坂路。駆けめぐり、草を食み、この地の息吹を吸いこんでいるだけで、自然と一頭ずつ、若駒として最高の状態にしあがっていく。
ウッドチップの敷きつめられた屋内直線馬場は、全長1000メートル、横幅は14メートル。
「おとーさん、ここ、『優駿』の写真で、しょっちゅう出てくるとこや」
ウッドチップを踏みふみ、調教馬が、軽い速足でこちらへ駆けてくる。円筒形のスタートポイントでUターンし、今度はチップを蹴たて、ギャロップで駆けてゆく。手綱をとる調教助手はインド出身。もと英国領の植民地で、競馬文化の根づいたかの地から、ここ浦河へ出稼ぎにやってきた。家族を呼びよせともに暮らすひとも多く、現在浦河には300人近いインド人が住みくらしている。こんな交流のことも、北海道に来なければ知らなかった。
マイクロバスは最後に厩舎の前でとまった。なかで、おだやかな目の馬たちが待っていた。子どももおとなもヘルメットをかぶり、鞍にまたがって、若い職員さんたちに付き添われ、広い厩舎を一周させてもらえる。
年少の子らにつづき、ひとひも嬉しげに鞍にすわった。ふだん乗馬でサラブレッドには乗り慣れているが、ここにいる馬たちは特別だ。JRAがじきじきに調教をほどこした馬なのだ。
十年後どういう境遇にあり、いったいなにをしているか、それはひとひ本人もわからない。ただ、この日はじめて、JRAの管理する馬に乗った記憶が、からだの底に刻まれたことはまちがいない。
エンジンをかけ、マイクロバスが出発しようというとき、厩舎の前に職員のみなさんが並び、こちらを見あげて、いっせいに手を振りはじめた。馬たちもその後ろで遠のくバスをみていた。まちがいない。馬とともに働いているひとたちはみんな、馬はもちろん、遠くからやってきた馬好きたちのことも好きなのだ。
この日の宿泊は、育成牧場にほぼ隣接した「うらかわ優駿ビレッジ AERU」。菊花賞馬オウケンブルースリ、高松宮記念を制したスズカフェニックス、春の天皇賞馬マイネルキッツにあいさつをし、小学生たちに混じって乗馬をたのしんだ。
おみやげコーナーでひとひは迷った末、スズカフェニックスとタイムパラドックスがならぶモノクロ写真がデザインされたTシャツを買った。タイムとスズカはふたごのように見た目がそっくりな上、競馬ファンのあいだでは有名な親友同士だった。
今年の2月、タイムはひとり先にこの世から常足で歩み去った。24歳だった。ひとひはTシャツの胸の二頭を見くらべ、
「ほんま、どっちがどっちかわからへん」
吐息まじりにいった。
3日目の朝、浦河「イーストスタッド」を訪ねた。20頭以上の種牡馬が厩舎を出、柵で区分けされたそれぞれの放牧地で、のんびりと歩き、草を食み、見なれない来訪者を興味深そうに眺めている。
一見のどかな、田舎風の光景。だが、今この草地を歩いているのは、エイシンヒカリ(イスパーン賞1着、香港カップ1着他)、グアンチャーレ(シンザン記念1着、マイラーズカップ2着他)、サンライズソア(平安ステークス1着、名古屋大賞典1着他)、ダノンレジェンド(JBCスプリント1着、東京盃1着他)、ホッコータルマエ(チャンピオンズカップ1着、東京大賞典2連覇他)、マスターフェンサー(名古屋GP1着、マーキュリーカップ2連覇他)、キングオブコージ(AJCカップ1着、目黒記念1着他)、スマートオーディン(京都新聞杯1着、阪急杯1着他)、マジェスティックウォリアー(ホープフルステークス1着他)など、火を噴いて競馬場を走り抜けた名馬たちばかりだ。
それがいま、こんな伸びやかで、おちついた物腰で、思い思いの姿勢でときを過ごしている。種牡馬はもちろん大切にされる。だが、イーストスタッドの職員も、遠来のお客も、この馬たちに敬意を払い、馬たちが元気にしてくれている、そのことを知っただけで今日一日があまねく光かがやく、そんなひとたちばかりなのだ。馬たち自身の態度が鏡のようにそう教えてくれる。
正午をはさんで、浦河から日高にもどり、ここもひとひの外せない目的地、「ビッグレッドファーム」の駐車場にクルマを乗りいれた。運転席からおりるなり、園子さんは伸びをし、
「すごいねえ、ここ!」
外気を胸いっぱいにはらみながら、
「こんな景色、ほかのどこにもないよ」
うねり、ひろがり、どこまでも続いていく草地。あふれかえる陽光の下、空いっぱいに枝をのばす木々。水場には空の青が落ちかかり、空気は涼やかに澄みとおり、はるか先には、この緑地からそのまま立ちあがったような山々の尾根がそびえる。
「夏の北海道」、その語から浮かぶイメージをはるかに越えた、理想以上の光景。そのただなか、牧草にとりまかれた池沿いをのびる小径を歩き、アメリカ風にしつらえられた厩舎へとむかう。
人だかりがしている。南側の柵の手前。初日、2日目と訪れた、どの牧場にも見られなかった気配がたちこめる。
ひとひの足が鈍る。園子さんも異様さに気づいた模様。ぼくは遠巻きに、柵のなかの薄闇を見つめた。灰色の暗がりのなかにうっすらと浮かぶ白い背中。馬は、けして柵の外に顔を出そうとしない。柵の前のひとびとはじっとカメラをかまえている。とれるものはなんだってとっていこうとでもいうように前にのめって。馬は気配をよむ。ひとの目にみえなくとも、なまぬるく毛むくじゃらの壁がせまってくるような重い圧を、全身の肌で感じ、だから、けして柵の前に顔を出さない。
ゴールドシップ。G1を6勝、という並外れた戦績以上に、競走馬としての常識をくつがえす様々な逸話で知られる(ゲートでなぜか仁王立ちしたり、他の馬がぜったい通らないコースを飛んで勝利したり、気に入らない騎手は振り落としたり)。勝っても負けても「ゴルシらしい」振る舞いに、競馬ファンは笑い、呆れ、引退までずっと声援を送りつづけた。見ていて楽しく、「次はなにをしてくれるのか」と、期待してしまうオーラがあった。「気が荒い」「へんくつ」とはちがう、「頭のよい」「自分をもっている」馬だった。
だからこそ、突然、競馬を見たこともないような若い男女が厩舎に押しよせ、遠慮会釈もなくフラッシュを浴びせ、はさみを差しいれてたてがみを切る、そんな行為の連続に、みずからを閉じた。カメラを構えたひとびとの前に、頑として、姿を現さないと決めた。
薄闇のなか、芦毛の馬体がかすかに揺れる。ちら、と遠い横顔がかすかにのぞく。オオッと声が上がりスマートフォンのシャッターがつぎつぎと切られる。フラッシュを焚くひとは誰もいない。柵から身を乗りだして馬に触れようとするものも無論いない。
アニメを作ったひとは、きっと馬が、ゴールドシップが好きだったのだろう。そうでなければ人気の出そうな個性あふれる美少女キャラクターになどしない。カメラを手に押しよせたファンにも悪気などなかった。同時に、馬に会った経験もなかった。アニメのキャラとじっさいの馬(ゴールドシップはオス)を、同一視するとは想像しにくいけれど、馬の天国ともみまがうこの牧場で、ふだんならけして生じない重なりあいが起きてしまったのは確かなことだ。人間にはフィクションが想像できるけれど、馬はとことん、むきだしの現実を生きている。リアルな世界へ無造作にさしはさまれたフィクションは、ときにむきだしの暴力として働く。
ゴールドシップはむろん、一度として外のひとびとに向きあうことがなかった。そうして自身でみずからの傷をいやしていく。見学時間が終わってまわりが静かになれば、放牧地に出され、のびのび自由に駆けまわるそうだ。
「そういうときのゴルシは、もとのゴルシそのものですよ」
と、厩舎の端で、年かさの厩務員さんが教えてくれた。
「お客さんが来てくださるんは、まあ、ありがたいことだね。マナー違反のひとも最近はぜんぜんおらんし。だんだんと、もとどおりになっていくんじゃないかね」
午後の陽ざしがボウルのコンソメスープみたいに緑の窪地にあふれかえっている。風がそよぎ、そら豆型の池を波立たせ、樹林から瑞々しい香りを運んでくる。こんなすばらしい環境に包まれた馬は、この世のどんな生きものより、ぜったいに幸せであるべきだ。
厩舎から離れた放牧地で、思いもよらず、名馬コスモバルクに会えたひとひは、柵を握りしめ、えんえん、時がとまったように凝視した。史上はじめて海外G1を勝利した「道営のエース」は、黄金色の光の底でゆっくりと草を食んでいた。
駐車場にむけ、芝の丘をよぎる小径をのぼりながら、
「もっともっとやな」
とひとひはいった。
「もっともっと、ぼくたちは、馬のことを好きにならへんとあかんわ」
この日三軒目の牧場「レックススタッド」。馬房から顔を出して待ちかまえていたのは、スマートファルコン(JBCクラシック1位)、マカヒキ(日本ダービー1位)、スクリーンヒーロー(ジャパンカップ1位)、ゴールドドリーム(チャンピオンズカップ1位)、エイシンフラッシュ(日本ダービー1位)、レッドファルクス(スプリンターズステークス1位)、ロゴタイプ(安田記念1位)、オメガパフューム(東京大賞典1位)、トーセンラー(マイルチャンピオンシップ)、ノヴェリスト(キングジョージⅣ世&クイーンエリザベスステークス)ら、超弩級の名馬たち。
強い馬は、かしこい。「ブリーダーズ・スタリオン・ステーション」のキセキ、そして「ビッグレッドファーム」のゴルシが、身をもって教えてくれたこと。
オメガパフュームはあくびしながら耳をぴんとこちらへ向けている。マカヒキは来客をじっと見つめ、目ぢからでにんじんを要求している。前から立ち去ろうとするとトーセンラーは「え? 待ってよ、待ってよ!」と視線を送り、「もっと! ぼくの写真もっと撮って!」といいたげに蹄を鳴らす。この牧場でも、ふだん種牡馬たちは一頭ずつ大切に扱われ、幸福で、だから、牧場の外につながる世界も大好きだ。
翌日、4日目は新千歳空港近くのノーザンホースパークへ足をむけた。観光馬車、ポニーショー、乗馬体験やホーストレッキングも楽しめる、馬文化のテーマパーク。ここに、ぼくもひとひも、誰よりも会いたかった馬がいた。針葉樹に囲まれた涼しげな放牧地に、全身、虫除けのネットを被せられ、ゆっくり、ゆっくり、その呼吸と同じようなリズムで蹄を前へ運んでいた。
「いはった!」
ひとひが柵へ忍び寄る。
「ウィンドインハーヘア!」
<彼女のたてがみを吹きぬける風>。こんな素敵な名前の牝馬から、稀代の名馬ディープインパクトが生まれた。1991年アイルランド生まれ、イギリス育ち。ディープを産んだのは2002年、11歳の春。現在、32歳。日本じゅうで大活躍してきた競走馬たちの、伝説のおばあちゃんだ。
「ヘアちゃん、オーイ」
常連さんらしい、70がらみのおじさんが声をかける。「ヘアちゃん」は首をかしげ、ゆっくりと立ち止まる。
「ヘアちゃん、あんたが元気だから、わし、明日もたぶん生きとる。なあ、ヘアちゃんよ、ここ来る人間は、みんなそうよ。同じ気持ちよ。ありがとうなあ、ヘアちゃん」
放牧地をかこんだ全員、なにもいわないまま、小柄なその牝馬を見つめた。さ、行こか、とうなずき、ひとひは駐車場へ歩きだした。三泊四日、食事、睡眠を除き、「馬に会う」こと以外、まったくもってなにもしない北海道旅行が、かくして終わった。
(了)