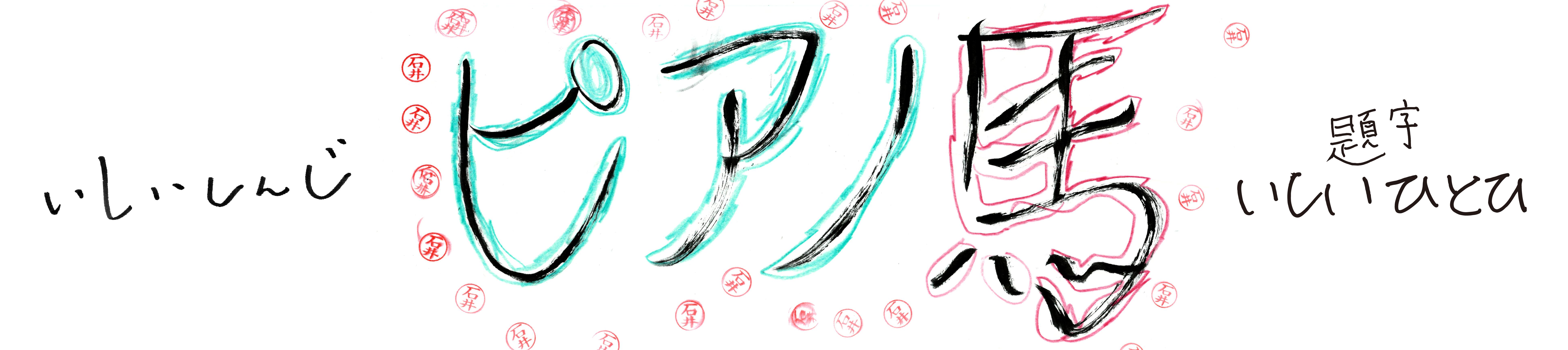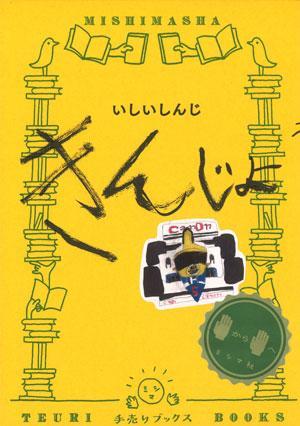第14回
生きがい(下)
2025.03.19更新
10月の末、介護タクシーで車いすのまま自宅の居間に帰ってきた父は、ベッドの上で退院祝いのお寿司を食べ(好物のあなごは最後までとっておいた)、お猪口に一杯の日本酒さえ口にした。
11月にはいってからは、入院中とことなり、60年以上なじんだ母の手料理のせいもあって、出された食事は完食するようになった。
ただ、母は様子をみて分量を減らしていた。酸素吸入器の目盛りが日々少しずつあがった。楽しみにしていた入浴だったが、仰向けのまま介護士3人の手で全身洗ってもらったあと、呼吸が苦しくなってしまい、その日以降は、暖めたおしぼりでからだを拭うばかりとなった。
日一日と、からだのあちこちで灯火が消えていく、ベッド脇からはそんな感じにみえた。病い、衰えというより、大きな自然な一プロセスとして、生物としての父はその活動を終えようとしていた。
人間としての父は、どうだったろう。
11月末、本を持つこともかなわなくなっていた。ベッドの足のむこうに置かれた大画面テレビで、朝から夕方まで漫然と、見たくもないワイドショーをつけっぱなしにしていた。
みかねたぼくは、
「YouTubeなんかで、好きなもの選んでみたらええのに」
「なんやと」
父は不審げに、
「ユーチューブいうのんは、えらい、お金とられるんやないんか」
「とられへんて。警戒しすぎやねん」
ぼくは「インターネットテレビ」のボタンを押しこみ、YouTubeの画面一覧をテレビに表示させると、
「な、この長細いウィンドウに、キーワード打ちこむねん。らくご、せんそうえいが、しばりょうたろう、ドキュメンタリー、なんでも。そしたらその映像がぜんぶタダで見られんねん。YouTubeって、父さんに向いてると思うよ」
すると父は、とつぜん激しく咳きこみはじめた。
ぼくは慌てて背中をさすり、
「ごめん、しゃべりすぎたわ。ちょっと静かにしてよか」
「ちゃう、ちゃう」
父は首を振り、バアック、バアック、と咳きこむ声をくりかえし、
「バアック、入力してくれっ」
「あ、バッハね。音楽ききたいんか」
バッハ、と打ちこむと「バッハ 名曲集」というチャンネルがあらわれた。ボタンを押しこんだ瞬間、ブランデンブルグ第3番第1楽章が流れだし、目をつむって聴きいる父をベッドに残して、ぼくは台所で書きものをはじめた。
15分ほど経ったろうか、
「しんじ、しんじっ!」
「なんやな」
すぐに席を立ち、枕元にしゃがんだ。父は手にしたリモコンをテレビに向けながら、
「シュー、シュー、シュー」
とつぶやき、呼吸に勢いをつけて一気に、
「シューベルト、て、どない打ちこんだらええのんや」
と訊ねた。
シューベルト名曲集のあとは、自力で「メンデルスゾーンのバイオリン協奏曲」と打ちこんだ。その日は一日じゅう居間からクラシック曲が流れていた。父がこんなにも音楽を求めていたとは正直意外だった。
ただ、ふりかえってみれば、うちの2階にはテクニクスの巨大なオーディオセットが鎮座していたし、3、4歳のころ、「ピーターとおおかみ」「はげ山の夜」など大音響で聴かせてもらった記憶もある。後世、息子たち4人とも、ジャンルこそ違えそれぞれが音楽好きにそだった。
昭和36年の思い出をつづった父の日記にはこうある。
当時、千恵子は髪を長くし、巻き上げた感じがとても印象に残っている。
八月に会って後、大阪フェスティバルホールで開かれたパリオペラ座歌劇団の特別公演「歌劇カルメン」の入場券(当時の収入とはかけ離れた価格ではあったが)を送り、上阪を促し、母登喜子と共に来阪、初めてのデイトとなる。
11月27日、京都で大阪へ向かう支度をしていると、その千恵子さん、実家の母から電話があった。今夜、父の大好物の牡蠣フライを作るから、とちゅうどこかで牡蠣を買ってきてほしい、とのこと。京阪電車、地下鉄と乗りつぎ、天王寺の近鉄百貨店で牡蠣とサバを買っていった。
母のつくる牡蠣フライは、ひいき目を差し引いても相当なレベルに達している。貝のサイズに合わせた衣の付け方と揚げ具合のバランスが絶妙なのだ。
今回の牡蠣はかなり大ぶりだった。しかもぼくは奮発して15個入りの大袋を買った。
「うわあ、食べきれるかしら!」
揚げ物を作るとき、母はいつも以上にテンションがあがる。
この晩の父の献立は、牡蠣フライ3個、キャベツ千切り、ポテトサラダ、牡蠣と野菜のすまし汁。
「かあさん、おかあさん!」
張りのある父の声がベッドから響いた。母が駆け寄っていくと、
「もう、ないんかな。牡蠣フライ」
「あるある。あるわよ」
結局、大ぶりなフライをまる5個たいらげ、サラダもすまし汁も完食したあと父は、いやあ、おかあさんの牡蠣フライはせかい一やなあ、と本気で叫んだ。8月からこの方、最大の食べっぷりだった。
洗い物のあと、買ってきたばかりの詩集を2冊、あらたにベッドに差しいれた。前の日に、詩や俳句みたいなものなら、ちょっと読んでみたい、と父がつぶやくのを聞いた。
「おお、谷川俊太郎さんのんか」
父は感慨深そうに、
「今月、亡くなったんやな。おいくつやったんかな」
「92歳、やったかな」
ぼくは座り、ふと思いつき、枕元のメモ帳を手にとって、
「そういうたら父さん、『生きがい』っていうことばの『がい』って、なにか知ってる?」
「『生きがい』の、・・・」
父は考えこみ、
「漢字では、『甲斐の国』の、甲斐って書くな。でも、甲州だけの言葉とは思わんな。うーん、なんやろうな」
「いきものの、貝のことやねんて」
ぼくはいった。
「貝って、なんで」
父は目を瞬かせた。
「古代の中国で、貝殻って、お金として使われてたやんか。貨幣の貨も、貝が化けるって書くやん」
「ふん、ふん」
「貝って言葉は、昔から『たいせつなもの』っていう意味で使われとってな。生きるためにたいせつにしてることのことを、『生きがい』っていうねんて」
「ふーん。おもしろいな」
父は深々とうなずいてから、
「そういうたら、牡蠣も貝やな」
といって、いたずらっぽく微笑んだ。
父の日記は、基本ことばをさわらず、読みやすいようまとめ、50ページほどの冊子にして「偲ぶ会」の来場者に配ることにした。編集・デザイン・製本等、ミシマ社には全面的にご協力いただいた。
タイトルは父の手書きの文字で、『最高に嬉しかった』。記述に合わせ、白黒、カラーの写真もふんだんに入れた。中学生時代、学習塾のたちあげ、千恵子さんとのデート、塾の最盛期、合宿、引退、趣味の世界など、その場の喧騒とともに父の声がページから湧きあがってきそうだ。
最後の最後、大好きだった妻の、大好物だった牡蠣フライをたらふく詰めこんで父は逝った。「生きがい」に充ち満ちた一生だった、と、いまにしてようやく、自分でもふりかえっている気がする。
(了)