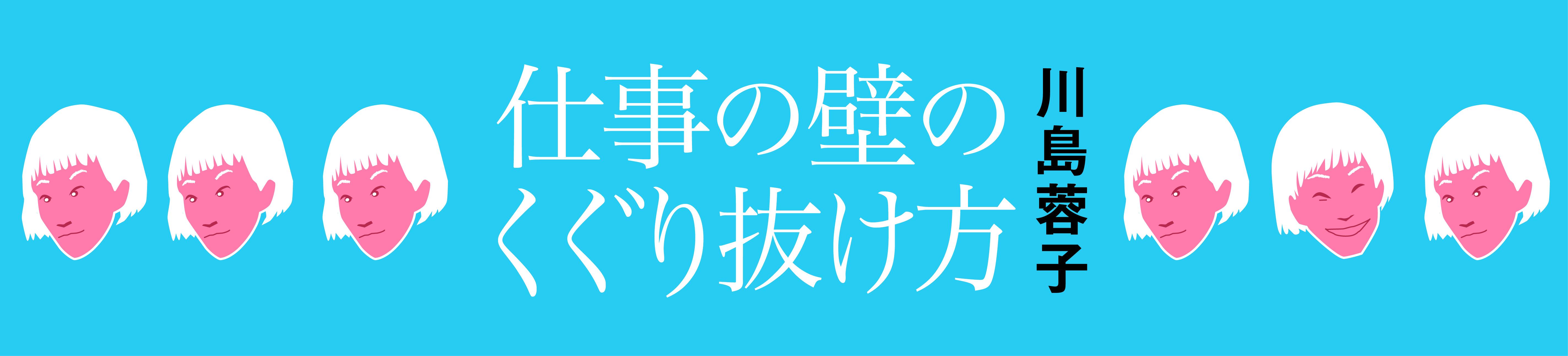第2回
壁・その1 上司と部下 ~理屈よりも語調をきく
2024.12.05更新
ときは、男女雇用均等法施行の前年。上司はニューヨーク帰りで三〇代前半、いわゆるキャリアウーマンだった。
今、振り返ると、米国版『VOGUE』の敏腕編集長として名を馳せたアナ・ウィンターそっくり。髪型からメイク、靴まで、隙のないスタイルで決めている。肩をいからせて早足で歩きながら、周囲に次々と指示を飛ばす。ハイヒールのカツカツした音が聞こえてくると、「あ、何か言いつけられる」と身構えたのを覚えている。
上司を信奉すると恐ろしい活力になる。新入社員だった私は、朝は始業前の八時半に出社して、机ふきやお茶くみ、昼は電話番とコピー取りと、彼女の雑用全般が担当で、目まぐるしかったが気持ちは充実していた。
けれど、必死で取り組んだにもかかわらず、仕事はミスの連続だった。役に立ちたい、認めてもらいたいと焦ってしまい、生来のおっちょこちょいが勃発したのである。「コピーを三部ね」と言われると、ページが歯抜けになっている。英文の書類作りを任されると、タイプミスが多く、ホワイトマーカーの修正だらけの書類になる。
「バリバリ働きたい」と宣言して採用された経緯もあり、使ってみてのギャップが大きかったのだろう。アナに叱られ、がっかりされると、仕事ができないことを突きつけられているようでつらかった。
しかもアナは、叱る剣幕や気迫がすさまじい。せっかちで、頭の回転がものすごく早いのだ。「これじゃ使いものにならないわ!」と何度言われたことか。
叱りながら次の指示が飛んでくることも少なくなかった。タイミングをはかって謝りながら、次の指示が出たら受け止め、即、実行しなければならない。彼女のことが好きという一心で、即座に、かつ全力で取り組むものの、凡ミスは止まらない。
ただ、あれだけ叱られ、呆れられたわりに、なぜか嫌われなかった。あまりにミスが多いので、「『すみませんの佐野さん(私の旧姓)』っていうあだ名がぴったり」とからかわれるくらいだったのに、だ。
アナのアシスタントはもう一人、先輩の女性がいた。私と真逆のタイプで冷静沈着、ミスが少ない。が、やっぱり叱られている。
やりとりを聞いていると、会話のタイミングが嚙み合っていない様子。せっかちなアナの気分が盛り上がっているのに口を挟んでしまったり、即答を求められているのにじっくり考え込んでいたり、ミスを指摘されると長い言い訳をしていたり――アナの語調が強まったり弱まったりという波長と、答える先輩の波長がぶつかっていると思った。
そう気づいてから、アナの語調に心を配るようにした。
幸いアナは、私の母と同様、語調と感情がストレートにつながっていて、割合と理解しやすかった。語調がきついときはキビキビと、ゆるやかなときは「貴女のためなら何でもやります」モードでのぞんだら、これがうまくいったのだ。
小さい頃からそそっかしくて、ものをこぼしてばかりいた。ケーキをいただこうとなると、ティーカップを滑らせひっくり返す。お醬油さしに手を伸ばしたら、煮物の汁に袖口が浸かっている。カレースプーンからルウがこぼれて服にたらり。
「あっ」と気づいたときは、もう取り返しのつかないことになっている。そんなつもりはなかった、マズいと思っている間に、床や服がみるみる染まっていく。
そしていつものように、母の"小言攻め"が始まる。「そもそも蓉子は何事にも注意が足りない」「今のうちに直しておかないと大変なことになる」と、片づけながら、ずーっと小言を言われるのだ。
始まってしまうとこれが長い。「ごめんなさい、これから気をつけます」と言えば、「いつもそう言うけれど、こうやって何度も繰り返すのは本当に反省していないからよっ」となる。何も言わずにいると、「いったい、あなたはどう考えているのっ」と問い詰められる。
剣幕がすさまじいので、泣き落とし作戦でベソをかいたこともあったが、「泣けばすむってことじゃないでしょ!」とさらに勢いが増す。父と違って、泣き落としは通用しなかった。
悪気があってやらかしたわけじゃないし、やらかすたびに叱られるのだから、気をつけて生きているつもり(本当に今もそう)なのに、なぜそうなってしまうのか、自分でもわからない。心の中でつぶやいてみるものの、そんなことは言えない。
それでも、何百回と繰り返すうち、少しずつわかってきた。こぼしたものの処理がすむまで、とにかく母は小言を言い続ける。その間は、何をどう言っても止まらない。
だから"小言攻め"の渦中は、聞いているふりをしながら、ひたすら謝りモードを続けた。"ふり"というと、こざかしいとうつるかもしれないが、深い知恵があったわけではない。真に受けて聞き入っていると、同じ言葉の繰り返しで飽き飽きしているのが態度に出てしまう。目にした母はさらに怒り"小言攻め"が長引いてしまうのだ。
あるときから、音としての語調を聞くことにした。
最初、けたたましかった語調は、片づけの目処がついてくると、徐々に落ち着きを見せてくる。ここを逃してはいけない。
聞き耳を立てていて、「ごめんなさい! これから絶対に気をつけますから許してください」と三回くらい唱えると、「本当にわかったの?」と休戦モードになる。
ここまでくれば大丈夫。ぺこりと頭を下げたらスタコラサッサ。「ったく仕方がない子ね」と言われたら、振り向いてにこっとする。幕引きである。
これを、アナとのかかわりでも実践してみた。すると半年くらい経った頃、「佐野さん、この原稿、書いてみる?」とチャンスを与えてくれるようになったのだ。もちろん、相変わらずミスの連発だったし、どんなに一所懸命やっても、結果がダメだと叱られた。でも、大好きなアナがチャンスをくれたことに、私の心は浮き立った。
とはいえ、その頃の私は月に一回くらい、お腹を壊していた。生来、丈夫なたちなのに珍しいことだった。アナも心配してくれ、「お医者さまにきちんと診てもらったほうがいいわよ」と言われて病院にも行った。が、悪いところは何もないとの診断だった。
ストレスからくる軽い胃炎を起こしていたのだと思う。
それくらいアナの語調を気にしていたし、彼女の役に立ちたいと思って、身の丈以上にがんばっていた。
入社して一年半後、優秀なアナは他の会社に引き抜かれていった。「半年待っていてね。必ずあなたを呼び寄せるから」と言われ、本当に私のポジションを用意してくれた。
ものすごく嬉しかったが、ものすごく悩んだ。そして結局、アナからの申し出を辞退したのだ。
大好きなだけに、語調ばかりを気にする日々を、身体も心も少し嫌がっていた。過剰にがんばってしまう自分を"自分らしくない"と感じていた。だから、少し距離を置いてみようと思ったのだ。
その選択が正しかったのかどうかは今もわからない。
が、アナから学んだ厳しさとあたたかさは、かけがえのない財産になっている。
仕事でぶつかる壁のほとんどは、コミュニケーションに関係している気がする。「なぜこうなるの?」「どうしてスムーズにいかないのだろう?」という悩みのもとを手繰っていくと、根っこにはコミュニケーションという障害物の塊があって、解きほぐそうとしてもうまくいかない。そんなふうに感じる。
そういうときは真正面からぶつかるのではなく、ちょっと引いて「リズム」を感じてみる。そうすると、「間が合っていない」「テンポがズレている」など、コミュニケーションの不協和音が聞こえてくる。
相手の「リズム」に合わせることがすべてではないけれど、「リズムを聴く」を試すのは悪くないと思う。