第3回
壁・その1 上司と部下 ~負けそうなときは、むしろ踏み込む
2025.01.07更新
毎朝、会社に行くのが嫌でたまらない時期があった。
今の時代でも、入社してしばらくの間は、上司のアシスタントとして働くことが少なくないと思う。
私の時代は、女性はみな、アシスタントワークをするのが当たり前だった。電話番、お茶くみ、書類整理など、上司が求める雑用もろもろをやる仕事。一対一だから、上司次第で、日々の仕事が天国になるか地獄になるかが決まってしまう。
同期で入った女性がアシスタントを務めていたのは、四〇十代前半の係長。彼は「アシスタントになりたくないナンバーワン」だった。目の前の仕事は優先順位なくすべて「大至急」で、締め切りは何でも「今日中」。今と違って残業は果てしなくOKだった(もちろん残業代はつかなかった)ので、彼女は毎日が深夜に及ぶ残業だった。
会社も彼のやり方のまずさに気がついていて、さりげなく注意したり指導するのだが、直らないので手を焼いていた。
彼のキャラクターも、人好きするものではなかった。せっかちで落ち着きがないのでそばにいると疲れる。貧乏ゆすりが激しいし、電話の声が大きくて仕事に集中できない。机の上はちらかし放題で、アシスタントの机に書類がはみ出してくる。自分の都合だけで声をかけてくるので仕事が中断される――彼女から毎日のように愚痴を聞かされ、「仕方ないけど、やってられないよね」と慰める立場だった。二人でこっそり「今日中オジサン」とあだ名をつけ、愚痴や悪口を言い合ってやり過ごしていた。
ところがある日、人事異動で「今日中オジサン」が私の上司になったのだ。
地獄の日々が始まった。連日、山のような仕事が降ってくる。やれどもやれども終わらない。同期の彼女に愚痴って発散するものの、日々のことだから、はけ口を求めるにも限度がある。ストレスでヤル気がなくなり、出勤電車に乗りながら、ため息ばかりついている自分がいた。
ただ「今日中オジサン」を観察するうちに気づいたことがあった。気だては決して悪くない。いわゆる「いい人」なのだが、自分のこと以外は視野に入らないし、相手の反応に興味がない。相手が誰であろうが自分のペースでことを進める。そもそも他人に関心がないので、悪口や意地悪はしない。逃げ道が少し見えた気がした。
たとえば「今日中」と指示された時、思いっきり嫌な顔をしても気づかないし、おっちょこちょいミスが多い私の仕事に、嫌味を言ったり、ひどく叱ったりということもない。目の前で言われたことに、即、対応しておけば、隣の部署の人と四方山話をしていても気にしないし、注意されることもない。
そんな折、いつものように残業していたら、隣りの部署の男性係長が声をかけてきた。「毎日、大変そうだけど大丈夫?」
涙が出そうになりながら、「何とかやっています」と返事した。
「そちらこそ忙しそうですが、どんな仕事か聞いてもいいですか」と見せてもらったら、おもしろそうな提案書を作っている。
「私に手伝わせてもらないでしょうか」
「残業が増えるけど、それでも大丈夫なら手伝ってもらおうかな」
「ぜひ、お願いします」と勝手に口が動いていた。
幸い「今日中オジサン」は、人のことに関心がないから、テリトリー意識も強くない。隣りの係長から「忙しいので、その間だけ、川島さんの手を借りたいのですが」と頼まれ、「こちらの仕事に支障ないならいいですよ」と、交渉は無事、成立した。
そして二足の草鞋が始まった。仕事はきつくなったけれど、「今日中オジサン」と向き合わずにすむ時間ができただけで、気持ちはぐんと軽やかに。嫌な時間の間に好きな時間があることが、心地をこんなに変えてくれるのかと驚いた。
「今日中オジサン」の仕事をほどほどにやりながら、隣りの係長の仕事はうんとがんばった。その成果が認められ、「次の仕事もサポートしてほしい」と言われたのは、ささやかな自信につながった。
結局、「今日中オジサン」のアシスタントは一〇カ月ばかりで終わりを告げ、彼には次のアシスタントが付くことになった。あの一〇カ月、私は会社から与えられた仕事が楽しくなかったから、どこかに解決策はないかと探していた。
仕事は仕事と割り切る手もあったのだが、働きたくて入った会社だから、負けを認めるようであきらめきれなかった。隣りの係長からもらう仕事を自ら増やすことで、仕事を楽しくしたかったのだ。
負けそうなとき、それでも逃げたくなかったら、あえて踏み込んでみるのもありだと思う。


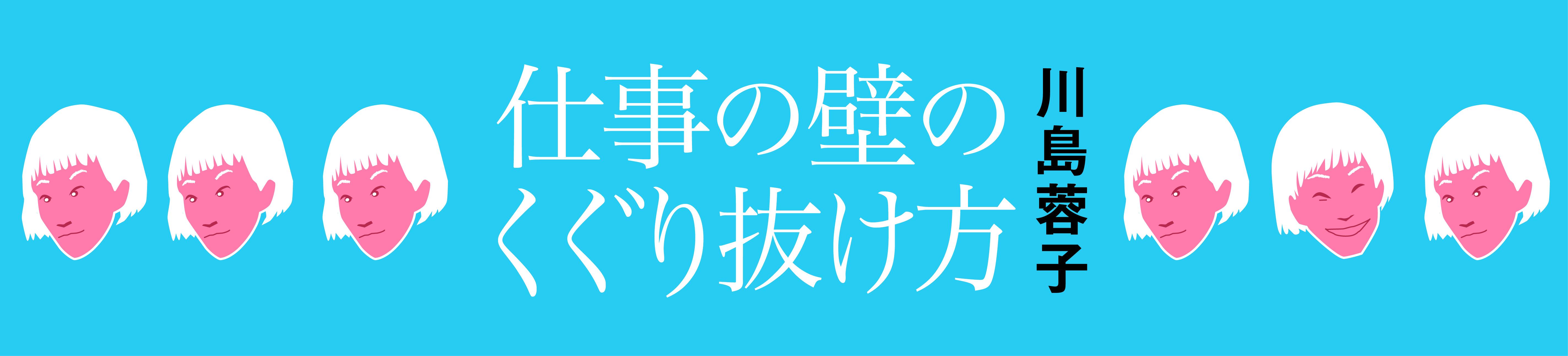


-thumb-800xauto-15055.png)



