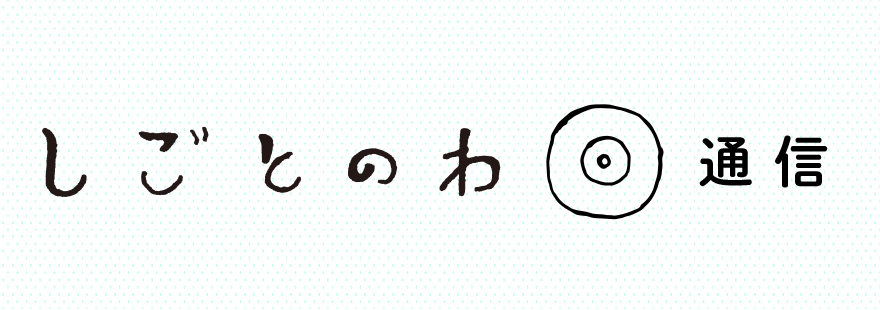第7回
「つくりすぎない」理由
2019.11.11更新

前の記事では、本書『ほどよい量をつくる』をつくるに至った経緯を書いた。今回は、本でも最初に取り上げた「つくりすぎない」にフォーカスしたい。
ここでいう「つくりすぎない」とは、つくる数を意図的に絞ること。仕事の量を減らして、よりいい仕事をしようとする試みである。
本で最初に紹介したのは、兵庫県明石市を拠点とする出版社ライツ社だ。社員わずか4名で一年間に出している本の数は年に6〜9冊。一般的な出版社に比べるとかなり少ない。それでも重版率の平均が71.4パーセントと、業界平均10〜20パーセントを大きく上回る。
代表の大塚啓志郎さんはその理由を「つくる本の数を絞ったからだ」と話していた。もちろん、出す本の数を減らしただけで誰もが売れる本をつくることができるわけではないし、実際には彼らの経験や腕に依るところが大きい。
でもライツ社を立ち上げる前、大塚さんが100名規模の会社で出版事業に携わっていた頃は年に一人12〜15冊は手がけていたため、一冊にかけられる時間も、結果としてできる本の質にもムラがあったそうだ。
今は、出版点数が少ないぶん、心からつくりたい本しかつくらないし、時間をかけていいものをつくることができる。
今の出版業界では一日に出る新刊が200点、その40パーセントが返品されて裁断されるという。「数打ちゃ当たる」の考え方で、たくさんつくって自動的に配本され、多くが捨てられる構造になっている。
それだけの仕事量をまわすために出版社にはたくさん人が必要で、そのお給料を賄うためにまたたくさん本をつくる。一方ライツ社では社員が4名なので、同じ"売れた"でも、利益が出る基準が大手出版社と比べれば少なくて済む。
"つくりすぎない"を実践している企業がそうするのには、いくつかの理由がある。たとえば棄てる量を減らすため。売れ残りを出さないよう必要以上につくらない。また、つくっているものの品質を高めるため。量を我慢して質にかける。さらには働き手が無理して働かなくて済むよう。残業しなくてすむ量におさえる。有機野菜や在来種の栽培など、自然の時間軸に沿って生産するため、そもそも量産にそぐわない商材もあった。
きちんとつくろうとすれば「この範囲しかできない」という量が見える。「この数しかつくれません」、「2種類しかできません」、「これが売ることのできる限界です」。量の限界を見極めること、あらかじめ設定することは、けして努力不足でも力不足でもないのではないか。取材を進めるうちに、そう思うようになった。
仕事をほどよい量にすることは、むしろ、いい仕事をするための潔さかもしれない。
そんな潔い仕事、"欲しい人にのみ届ける"を実践している極みではないかと思うのが、編集者の温野まきさんが2018年12月に立ち上げた「時雨(しぐれ)出版」だ。温野さんは長年編集や執筆の仕事に携わってきて、環境をテーマにしたウェブメディアの運営や「自然栽培」で知られる木村秋則さん監修の本などを手がけてきた。出版社設立の翌年7月には一冊目の本『最初に読む料理本』を発行。
時雨出版でつくる本は、本屋にもamazonにも売っていない。公式サイトから直接注文をくれた人にのみ、温野さん自ら梱包して配送している。初刷は2000部のみ。新人の初版が5000〜7000部と言われる一般的な数に比べるとずいぶん少ない。
「毎年、書店に並ぶ雑誌や本の30〜40%が断裁されています。日本で使われる紙の原料パルプの70%は海外の森林を伐採して輸入されていて。断裁された後はリサイクルされますが、一本の木が生長する年月を考えると当たり前のように断裁されていいとは思えなかったんです。そこで本当に読みたい人だけの手に直接届く、通販を中心に書籍販売を行うことにしました」
温野さんと話をしているうちに、そうした環境への配慮に加えて「つくりすぎない」ことが納得のいく仕事をする上でも大切な要素になっていることに気がついた。多くの人に受け入れられる売れる本をつくろうとすれば、どうしても最大公約数的なものづくりになって、個人が面白い、つくりたいと思うものから離れていってしまう。
「売ることを目的にした本ばかりがつくられるようになって、本が売れなくなってきた気がするんです」と温野さんは言った。
「誰にでも自宅の本棚に一生の間に何度も読み返したい本がありますよね。情報を伝えるだけなら今はデジタルでも十分。本という形にして意味のあるものにしたいなと思って。たとえば直接誰かに会って話をすると、メールやラインでは伝わらない多くが伝わってきます。そうやって時々直接会って話したいと思う人がいるように、本にも人格があって、その本に会うために何度も開きたくなるようなものがあると思うんです。それが、"形を伴う意味のある本"ではないかと思っています」
温野さんが出版社を始めたのも、ある本を思うような形で出したいという強い思いがあったから。それが『最初に読む料理本』だった。

この本はとても不思議な本で、ひとことで言えば古谷鴨康(ふるや・のぶやす)さんという方の料理のレシピ集。ただし、ただの料理本ではなく「料理をすることは、生きること」をテーマにした本である。
開くと美しい料理の写真もたくさん載っているのだけれど、表紙に料理の写真は一切見当たらず、濃い青に白い文字のタイトルのみ。和食の基本を教えるレシピ本かと思えば、イタリアのクレープやトルコの粉もの料理、獣肉を用いたレシピなど目新しい料理も載っていて、「土を食べる」「農家から買う」「"清浄な肉"とは」など「食べる」ことにまつわるメッセージ性のあるコラムがレシピの間に掲載されている。
執筆と編集は温野さん自身が担当しているが、撮影、装丁・デザイン、印刷などは信頼を寄せる人や、熟練の職人にお金をかけて依頼している。一方、出版社を始めるからといってオフィスを借りるなどのコストをかけず、宣伝費も一切かけていない。一人で自宅で始めたことだからできたことだという。温野さんにとってもっとも納得のいく誠実な本のつくり方、売り方がこの形だったということだろう。
「きれいごとばかり言っていられないけれど」と前置きした上で、温野さんは「この本は売上を目的につくった本ではないので」と言った。
温野さんは編集のプロだし、本は売り物でちゃんと値段が付いている。ただし売ることを第一義につくっているのではないということ。こんな本をつくりたいという気持や伝えたいことが先にあって、その手段として売っている。どちらが先か?という話かもしれないと思いながら聞いた。
この目的と手段の履き違えが、多くの本が"ほどよい量"から離れてきた一つの理由かもしれない。
時雨出版の本は、刷っている数は少ないけれど、関わった人たちの熱量がお客さんに伝わるためか、多くの反響がある。本を学校教育の場で使いたいという声や、自分の子どもが大人になった時に渡したいといった感想など、温野さんの元に直接届く。
「ずっと手元に置いておきたいといった声をもらうと、本当につくってよかったなぁと思えます。本棚にしまっておかずに、ページの余白にたくさんメモして自分なりに使ってもらえたら嬉しいですね」
仕事には、お金を稼ぐこと以外に誰かを喜ばせるとか、他者の役に立つ、生活を豊かにするなどの目的がある。その目的と手段のバランスが、仕事のほどよい量を決めるヒントなんじゃないかと改めて考えた。
甲斐かおり(かい・かおり)
フリーライター。長崎県生まれ。会社員を経て、2010年に独立
編集部からのお知らせ
『ほどよい量をつくる(しごとのわ)』出版記念イベント開催決定!
2019年12月3日(火)19時15分~、
かねてより「これからのビジネスは個人から始まる」
「しごとのわ」から新しい本が発刊になりました!
大量生産・大量消費による食品ロスや環境負荷など、
成長のためにはとにかく多くつくって多く売ることが当たり前とい
そんななか、従来とは違う「つくりすぎない」