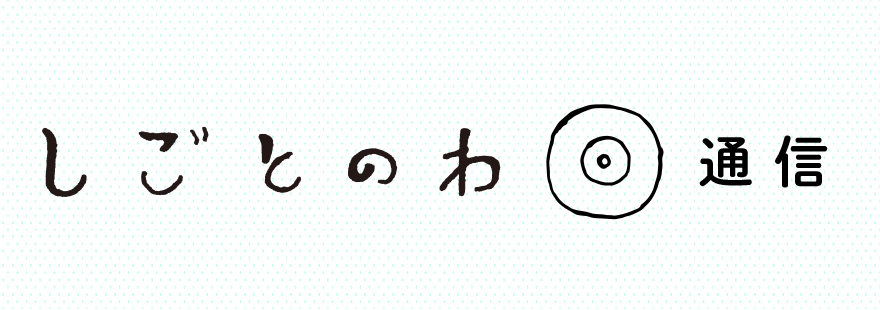第10回
響き合う、届け方
2020.01.20更新
いまの仕事は、つくる人、売る人、届ける人がばらばらで、自分の仕事の始まりと終わりが見えなくなっている。そう『ほどよい量をつくる』に書いた。それが、ちょうどいい量の仕事から離れてきた一つの理由ではないかと。
自分はつくるだけ、届けるだけ、売るだけ。ここからここまでをやればいいと範囲を区切られると、その前後が見えにくくなる。
ものをつくって売るまでの間に何重にも人や会社が入るしくみは、大量にモノを売りさばくには便利だ。でもつくり手に相応の利益がまわらなかったり、自分の仕事が価格のみで判断されたり、誰かの役に立っているという実感がうすれてしまう。
すべての工程を一社で行うのが難しいとしたら、つくったものの価値を理解してくれる、共感者とつながるのは一つの方法ではないだろうか。
間が入ることの弊害
以前、フランス菓子の店を40年以上営んできた夫婦の奥さんが、話してくれたことがある。
「フランス菓子だから、材料も輸入品が多かったんです。あるとき海外で天災が起きて、商社から仕入れているバニラやアーモンドなどの値段が軒並み上がりました。今だけだからと言われて、お客さんに出す値段は変えずになんとか乗り切ろうとした。でも状態が落ち着いても、値段は元に戻らなかったんです。それって誰がプールしているか、明らかですよね。ああ自分たちではどうしようもないところで搾取されるってこういうことかと実感したのがその時でした」
きっとその商社の担当者も、悪い人ではないだろう。組織の理論で動いているだけで、そこに個人の思いはない。でも、それが一つの問題かもしれない。
私も会社勤めの頃は、いかに自社に有利な交渉ができたかで評価された。取引先のことまで考える余裕はなく、いい取引きができたら勝ち誇ったような気持ちになった。業界全体にどんなプレイヤーがいて、それぞれの立場の人に支えられて自分の仕事があると想像もできずに。
あるテレビ番組で、築地市場で働く仲卸業者が「漁師あっての俺らの仕事やから、交渉はするけど、漁師がやっていけないほどに安くは買い叩かない」と話しているのを聞いて、自分はそんな風に考えたことはあっただろうかと省みた。答えは否だ。
書く仕事を始めていろんな仕事を見てきた今なら、もう少し想像できるとも思う。取引先も納得いく条件をめざして自社の側を説得しようとするかもしれない。でもその時は、そんな余裕も発想もなかった。
直接つながることで広がる世界
その点、本書で紹介した人や企業の中には、仕入れも、卸も販売も他社に頼らず100パーセント自社で手がけているところが多かった。たとえば、「パンと日用品の店 わざわざ」の平田はる香さんは、店で扱う品を仕入れる際、必ず生産現場に足を運ぶだけでなく、時間をかけて自分たちで使い込んで、自信をもって勧められるモノしか扱わないと話していた。売り手としての矜持。
自分の仕事を、ただの金銭の対価としてのモノにしないために、売り方、届け方を考えることが大切なのではないか。島田潤一郎さんの『古くてあたらしい仕事』を読んだ時も、改めてそう思った。島田さんは一人で夏葉社という出版社を立ち上げた一人出版社の先駆的な存在で、雑誌などで知ってはいたけれど、なぜ出版社を立ち上げたのかなど詳しい事情は知らなかった。
この本では、島田さんに起こった私的な出来事と本をつくる仕事の話が交錯して描かれる。詳細は本書に譲るが、驚いたのはその本の売り方だ。全国の本屋を一軒一軒自分の足でまわり、取引先を100軒見つけるという。100軒とは、一人で歩いて開拓できる目安の数。島田さんはこう書いている。
「まったく顔も出さずに本だけを置いてほしい、というような仕事の仕方はしたくなかった。そういう仕事を続けていれば、いつか本屋さんからは愛想を尽かされるはずだし、それこそお金だけの関係になりかねない。
...(略)...
きちんとした人間関係を築き、そのうえで本を売ってもらうこと。...経営論的には大間違いなのかもしれないが、ぼくが思い描いていたビジョンとは、つまりそういうことだった」
そして実際に島田さんはその方法で営業をし、夏葉社の本に関心をもつ書店員さんたちとの関係を築いていく。それは、世の中の流行り廃りなどに左右されない、関わる人たちがよいと思う本を届けたい思いでつながっている強い関係。
この話に私は励まされる思いがした。世の中に求められることに自分を合わせるのではなく、自分の幹でしっかり立って枝葉を広げていくと、自ずと共鳴し合える人たちとつながっていく。それはマスではないかもしれないが、気づけばそこに新たな経済圏が生まれている。相手の見える仕事とはそういうことかもしれない。
売り手と買い手がフラットな関係に
島田さんの話は、本のつくり手と売り手の話だが、売り手とお客さんの間に関係性を生むような新しいタイプの本屋もある。吉祥寺のバツヨンビル地下1階にある「ブックマンション」がそうだ。
ブックマンションは84の小さな本屋の集合体ともいえるレンタルボックスの本屋版。月額3,850円で誰でも本棚を借りて小さな本屋を始めることができる。いま84の棚はすべて埋まっていて少しずつ増えている。棚ごとに個性があり、世の中の売れ筋とは関係なく、多彩な本が置かれていてとても楽しい。プロの漫画家による漫画本の棚もあれば、「書き込みOK」で読んだ人の跡を本に残し、いつもと違った読書体験をしてもらう「読跡(よみあと)文庫」なるものまである。本を買うだけでなく、本を通じて人と人がつながったり、本屋のオーナーがイベントを開催するなどコミュニティの生まれる場になり始めている。
ブックマンションを始めた中西功さんはこう話す。
「これまでは、一人の目利きをする本屋さんがその人の人生をかけて本を売っていたわけですよね。でも複数人で一つの店舗を共有し合うことで、一人のもつリスクを減らして、いろんな人のセレクトを楽しむことができます。お客さんと売り手の間には明確な境界線がなくて、ここを訪れる人は、買い手でもあるし売り手にもなれるんです」
最近、本に限らず、洋服も、野菜も、こうしたつくり手、売り手、買い手の距離が近い売り場が増えている。従来は「これがかっこいいよ。だからこれを着なよ」とプロのデザイナーがつくった洋服が、特定のブランドやショップを通して広がった。それが最近では、つくる人、売る人、買う人がよりフラットにつながり、共感し合う関係性の中でモノとお金がめぐる。ブックマンションはそうした世界をはっきり可視化しているケースかもしれない。
「人に何かものを教えようとすると、はたと自分がいかに理解できていなかったかに気づいたりするじゃないですか。それと同じで、素人さんでも売り手の立場にたつと、本や本屋さんに対する見方が変わるんです。ああ、いつも本を買っているあの店は、じつはセレクトがすごいよかったんだなとか、いい本ってこういうものかとか。普段意識せずに享受していることに自覚的になる。本を見る目の解像度が上がるんです」
売れる本ばかりが並ぶ画一的な売り場ではなく、多彩な本がある店ほど、新しい出会いがある。自分たちが欲しいのはどんな売り場なんだろう。モノがあふれるこの世界で、あなたはどんなモノ、文化、世界に一票を投じたいだろうか。
編集部からのお知らせ
1/23(木)『ほどよい量をつくる』刊行イベント@B&Bを開催します!
今回は、本書の著者であり、ものづくりや農業、
テーマは、「僕たちがこれを選ぶ理由。これからの売る・
奮ってご参加ください!
「しごとのわ」から新しい本が発刊になりました!
大量生産・大量消費による食品ロスや環境負荷など、
成長のためにはとにかく多くつくって多く売ることが当たり前とい
そんななか、従来とは違う「つくりすぎない」