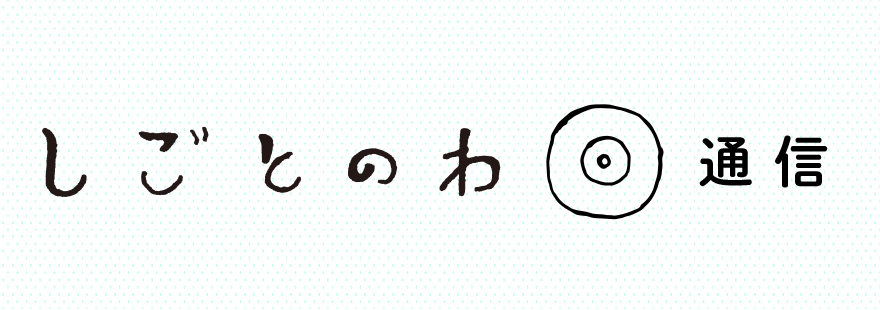第12回
不揃いでも少量でも。多彩で豊かな世の中を
2020.04.16更新
「種市(たねいち)」というイベントを知ったのは、何年前のことだろう。在来野菜を販売するマルシェと、農家が集まってタネについて語り合うトークイベントが行われた。私自身、在来種という野菜の存在を知ったのはこの時がきっかけだった気がする。
その主催者の一人が、warmer warmer(ウォーマーウォーマー)の高橋一也さんだった。warmer warmerとは、一般流通にのりにくい、在来野菜の流通販売を行う「八百屋」である。
この連載では、"ほどよい量"をつくる、売る、届けるを実践する人たちに話を聞いてきた。高橋さんにインタビューしたのは、世の中がコロナでこれほど大変な状況になる前のこと。今、コロナ前と同じ前提ではものを書けなくなっている。でも大切なこと、そうでないことが浮き彫りになる今だからこそ、高橋さんのタネの話に考えさせられることも多い。
ほどよい量を扱う仕事は、今までにあった流通、マーケットにのりにくい商材を、新しいしくみで届けようとする点で共通していた。warmer warmerではなぜあえて、各地で少量しか生産されない、流通に不向きな在来野菜を扱うのか。そこには、どこまでいっても自然の力を越えられない、人の生き方へのヒントが含まれている気がする。
「在来野菜」を扱う八百屋
東京にある高橋さんの自宅には、全国の農家から毎日のように在来野菜が届く。スーパーでは見かけない、赤紫色の大根や、根っこのついたほうれん草、ごつごつしたキュウリなど個性豊かな野菜ばかり。それを袋詰めして個人、飲食店、百貨店向けに販売している。
今流通する野菜のほとんどは、形や大きさが均一に育つF1種と呼ばれる野菜である。一方で在来野菜とは各地域で代々タネ採りをして、その土地に土着し、育てられてきた作物。F1種と違い、収量は少なく、姿かたちや収穫時期もばらばらなものが多い。そうした在来、固定、伝統、地方野菜などと呼ばれる作物を、高橋さんは総じて「古来種野菜」と呼び、取り扱っている。
「人間の都合で、欲しい規格で欲しい時に欲しい量を収穫するのが"農業"だとすると、僕らが関わっているのは"農"の世界。品種改良が間違っていると言いたいわけではないんです。世の中にはF1種の野菜を必要とする人たちもいます。在来野菜は収量も限られるし、今の"農業"の流通のしくみにはのりにくい。でも、新たに流通を確立することで、野菜の多様性や地域に残る食文化を守ることができたらと思っているんです」
高橋さんは、約13年にわたり自然食品専門店「ナチュラルハウス」で働いてきた人だ。ナチュラルハウスといえば、有機野菜などを積極的に取り扱うオーガニックに強い小売店。ところがここでも、在来野菜を扱うのはハードルが高かったのだそうだ。
「やはり量の問題です。30店舗あってすべてのお店に在来野菜を置けないと、経営上効率が悪いんです。不揃いでいつできるかわからない点も、今ある流通のしくみにそぐわない。
また、一緒にして語られがちですが、有機野菜と在来野菜を扱うのとはまったく違う話なんです。有機野菜は農薬などを使わない、環境に配慮した農法で栽培するもの。それはそれで大事。でもタネの話は、自然のしくみ、命の根源を考えることに近い。タネを知ることで命が代々つながる自然の連鎖を知ることができます」
野菜を売るだけでなく「表現する」
一般の流通にのらないということは、独自でお客さんを開拓しなければならないということだ。開業以来、高橋さんはいろんなマーケットに出店してきた。それでも初めの頃は、なかなか売れなかったという。
「どうやったら目の前を歩く人、町中ですれ違う方々に興味をもってもらえるのかなって、四六時中考えていました」
売り場にタネの入った野菜のサヤごと持ち込んだこともある。期間限定で在来野菜を扱う食堂を営んだことも。数知れない工夫を重ねてきた中で、続けてこられた秘訣をひとつ挙げるとしたら?と聞いてみた。
「野菜の "面白さ"と"おいしさ"を伝えること、です」
高橋さんは、野菜を「表現する」という言葉を使う。在来野菜の魅力をよりクリエイティブに、伝わりやすい形で届けたい。自然の野菜がどれほど美しいか。スーパーマーケットに並ぶ野菜と何が違うのか。どう調理すると美味しいか。
2013年4月に初めて開催した「種市(たねいち)」には、2日間で約800名もの人が集まった。翌年の2014年3月にはワタリウム美術館から声がかかり、美術館の入り口で在来野菜の販売を行ったこともある。
その過程でさまざまなお客さんの反応に出会った。野菜の個性、形、色、姿をじっと見て面白がってくれる人。根っこの形に「すごい」と感動したり、「美味しそう、食べてみる」と買ってくれる人がいた。
営業はしない、市場に合わせない
でもあえて営業らしい営業はしない。高橋さんの奥さんの晃美さんはこう話していた。
「無理にお客さんを説得しない、相手を変えようとはしないってことです。熱心に話してその時は買ってくださっても、長続きしないことがわかっているので。自発的に興味を持ってもらえる方には自ずと届くのかなって」
宅配の「古来種野菜セット」は、10〜12種類の野菜が入って4,590円(消費税・送料込み)。農家からその時収穫できたものが届くため、箱を開けてみるまで何が入っているかわからない。それでもいいというお客さんが買ってくれる。
今、一番多く売れているのが新宿伊勢丹の売り場だという。先方から声がかかった時、高橋さんたちはこれでもかと、在来野菜のデメリットを挙げたのだそうだ。
「収量が少ない、色も形も揃わない、個体差も大きい、予定していたものが収穫されないこともある。だから数を指定される注文は受けられない、流通に乗りにくい野菜ばかりですよ、と」
それでも伊勢丹の担当者はそれでもいい、お任せしますと言ってくれたそうだ。はじめの3年間は週に1、2回、高橋さんたち自ら売り場に立ち、接客した。おかげで固定客もついた。新宿伊勢丹地下の生鮮売り場には、今も「LOVE SEED」のシールが貼られたwarmer warmerの扱う在来野菜が並んでいる。
「結局、僕らがやっていることってずっとマイノリティ。それでいいんです。在来をもっと広げようとか多く売ろうとは考えていなくて、とにかく農家さんたちがこの野菜をつくり続けられたらと。自然界の多様性と同じで、いろんな野菜が共存できる方が豊かですよね。それを流通やマーケットの都合で画一的にしてしまうのは違うんじゃないのってことです」
たとえ野菜が不揃いでも、生産量が少なくても。その土地々々の味を守っている農家と豊かな食文化があるのなら、次の世代へつなぎたい。
『古来種野菜の100日食堂』で裾野を広げる
広げることが目的でないとはいえ、新しいお客さんが入りやすい間口はつくっておきたい。2019年は吉祥寺の飲食店「キチム」にて『古来種野菜の100日食堂』を開催した。週末や休日を中心に年100日間オープン。高橋さん自らが調理した。
私が訪れたとき、運ばれてきたお重には根菜などの野菜がぎっしり詰まっていた。それぞれの野菜の味を生かす調理がされている。雲仙赤紫大根、弘岡かぶ、とっとき1号なるエリンギ。焼もの、煮もの、素揚げしたもの。
野菜の特性が書かれたプリントに目を落としながら、じっくり味わって食べる。こう調理すると美味しいのか、カブってこんなに濃い味がするんだ。どれも味わい深く、驚きがあって、平らげるのに時間がかかった。
高橋さんたちは在来野菜の販売を通じて、あるメッセージを伝えようとしている。
「遺伝子組み換えやゲノム編集など、どんどんテクノロジーは進んでいます。僕はそれを否定はしません。ただもっと進化する分野だから、これから生まれてくる次の世代が、『野菜とは何か』って考えたときに立ち返れる場所と原点を残すことが大事だと思っているんです。タネはその一つの手段。たとえ1%でも、今残しておかなければタネはなくなってしまう。それからでは遅いので」
在来野菜には、その土地でくりかえし採種、栽培されるうちに風土に適応してきた歴史と性質がある。そのタネはタイムカプセルのようなもの。自然のはたらき、命の連鎖を知ると、世界は違って見えてくる。さまざまな生き物が共存する社会こそ豊かだ。高橋さんの話はそう教えてくれた。
これにて『ほどよい量をつくる』特集の連載はおしまいです。
コロナの影響により百貨店が閉まり、warmer warmerでは生活圏内で買っていただけるようにと4月19日(日)より5月初旬まで、吉祥寺にて在来野菜の販売を行うとのこと(詳細はこちら)。オンラインでの活動が活発化していますが、この「生活圏内で」という点にも、これから先の世界で大事になる一つのヒントがありそうです。
これまでに紹介してきたほどよい量の仕事は、いずれも多様な社会を実現するための試みだったと言っていいかもしれません。人はどこまでいっても自然の一部で、自然の力を越えては生きられない。大変な時代ですが、その大きな力を忘れずに道を選択していけたらと願ってやみません。
これからも、ほどよい量をつくる仕事の先を見て書いていきたいなと思います。
半年間、ありがとうございました。
warmer warmer公式サイトはこちら
編集部からのお知らせ
『ほどよい量をつくる』好評発売中!
大量生産・大量消費による食品ロスや環境負荷など、
成長のためにはとにかく多くつくって多く売ることが当たり前とい
そんななか、従来とは違う「つくりすぎない」