第3回
豚の息(2)
2025.04.22更新
マブイウトゥシとマブイグミ。
魂をどこかに落としてしまったとき、なぜ豚小屋のそばでマブイグミをするのか。夜半に外から帰ってきたとき、なぜ豚を起こして鳴かせるのか。
豚と魂。その関係がちょっとした謎として頭の片隅にあったとき、「豚の息」という言葉が閃いたのは、ちょうどその頃、私がアニマという言葉について調べていたからだ。
アニマルやアニメーションの語源でもあるアニマは、ラテン語で魂や生命、風や息を意味する。この言葉は、ギリシャ語で風や空気、呼吸を意味するアネモス(ἄνεμος)と同じく、「息を吸う」を意味する印欧祖語(*ane-)に由来するという。
一九世紀末から二〇世紀初頭のヨーロッパで盛んになった宗教の起源をめぐる議論の中で、この言葉はオセアニアからもたらされたマナ(mana)という言葉とともに、広く知られるようになった。マナという言葉が、一九世紀の南太平洋で活動していた宣教師たちに注目され、超自然的で霊的な力を表す概念として翻訳された過程や、この言葉がヨーロッパに広まり、アニマという概念と同一視されるようになっていった背景には、南太平洋の島々における宣教師と現地の人びとの関係や、ヨーロッパの学術界における論争が関わっている(1)。いま私たちの知っているアニマやマナという概念は、だからヨーロッパと非ヨーロッパの諸地域の邂逅によって可能となった、さまざまな相異なる概念の比較や混淆を通して創りだされたものだ。
ただ、そのような概念のなりたちをめぐる複雑な背景を考え合わせながらも、私が興味を惹かれたのは、アニマという言葉に含まれる流動するもののイメージだった(2)。それは海や空や大地をめぐりながれ、人やものを生気づけ、自然現象を引き起こし、世界に動きを与える力だ。この言葉において、魂や生命は風や呼吸でもある。
風と魂と息。
マブイが魂であるのなら、それはアニマという言葉で呼ばれてきたもののように、目にみえない気息や力の流れ、風のようなものなのではないだろうか(3)。
それはあらゆるものの中に流れこみ、いっとき留まってそれを活気づけ、ふたたびそこから抜け出して大きな流れの中に戻っていく。それが自分の中に留まっているかぎり、私は動くもの、生きているもの、一個の人間としての形を保っていられる。
他方で、たとえば三尺先も見えない深い闇の中を歩くうち、自分の輪郭がだんだんと曖昧になり、周囲の闇に溶け出ていくような感覚に襲われるとき。あるいは、突然何かに驚かされ、文字通り「たまげた」とき――そんなとき、魂を自分に結びつけていた結び目がほどけて、それはどこかへ漂いながれていってしまう。闇の中へ、森の中へ、海の果てへ。
マブイグミは、そうした漂流する魂、あるいは息を自分の身体に結びなおすことだ。放っておけば遊離していくそれを自分の中に、また人の世に呼び戻し、しばらくそこに留まるように。
屋敷地の内と外。人の領域と野生の領域。此岸と彼岸。その境目にウヮーフールはあり、そこにはウヮーノカミがいる。
離れていった魂をいくら呼んだとしても、戻ってこないことはあるのだろうか。どんなときに、それは私の元を離れ、二度と還ってはこないのか。身体に宿る生気、私の内と外をめぐりながれている息は。
それは、私が死ぬときだろう。
メラネシアの贈与交換について書かれた、一篇の論考を思いだす。
それはフランスの民族学者であるダニエル・ドゥ・コッペの書いた、ソロモン諸島の伝統的な葬儀についての論文だ。彼によれば、マライタ島南部のアレアレに暮らす人びとの間では、人間は身体と息、
アレアレの人びとにとって、タロイモは主食となる作物であり、豚は大切な家畜であると同時に贈与交換される財でもある。そして、貝貨はあらゆる交換を媒介するだけでなく、それらをつないで編んだ紐の束は、祖先たちの像を表すものとされる。つまり、人びとの生命を維持し、やりとりを媒介し、共同体の存続と再生産を可能にしているのは、これらのものの存在であり、その生長と増殖であり、交換と分配である。
人が亡くなると、その葬儀の場で、故人の身体はその分身であるタロイモとして人びとに食べられる。また、故人の息は豚の息となり、その豚は屠られて料理され、人びとにふるまわれる。そして、故人の像は貝貨に転化され、祖先たちを表す貝貨の束の中に取り込まれることで、故人もまた祖先たちの一部になる(5)。
そのようにして、ある人が生きていた間、その存在を形づくり、活気づけ、動かしていたそれぞれの要素はその暫時的な形を失い、結び目を解かれ、ひとつの身体から離れて共同体の中に戻っていく。その過程は、故人の分身であるタロイモと豚を皆が分け合って食べ、その像を宿した貝貨が祖先たちの貝貨に包摂されるという葬儀のプロセスを通して実演され、共有され、現実のものとなる。死者はそうやって弔われ、大きな流れの中に還っていく。
アレアレの人たちの葬儀において、死者の息は豚の息になるという。
なぜ、ここでもまた、豚なのか。
人と野生の境目にいて、世話され、生長し、仔を産み、屠られ、分けられ、食べられる、それ自体が息を宿した、循環の中にある生きもの。
自分たちの家で豚を飼っていた頃の、人間とこの生きものとの関係の近しさについて、大城さんはこんな風に語っていた(6)。
豚というのは、みんなが朝から晩まで、家族と一緒に。食べるのも、出すのも。また、正月とかそういう行事の時は、つぶして、肉にもなるし。人の血となり肉となるから、たいへん大事なものだから、そういう風に、〔ウヮーノカミとして〕崇め祀られているんじゃないかなあと......。
そして何より、豚は親しい人たちの集まる特別な機会に屠られ、食べられるものだった。大城さんと湧上さんは、正月のお祝いや、それに続く日々に喜びと愉しみをもたらすものとして、豚肉の思い出を語っている。
大城さん 豚はまた、行事がありますよね。盆正月とか、そういう大きな行事には、ヤギの肉では通らない。量というより質が違うんですよ、豚肉と全然。重箱を詰めたり......。
湧上さん いろんな行事に使うのは豚肉なんですね。だから豚の場合はですね、つぶすとき、量が多いもんですから、いっぺんに食べられないですからね、塩蔵して。塩もみして、壺に貯蔵できるんですよ。冷蔵庫のない頃ですからね。スーチチャー〔豚肉の塩漬け〕(笑)。
大城さん スーチカー。おいしかったねえ。
湧上さん それでもって、正月あとのサトウキビの収穫とか、田植えなんかによく食べてたですね。おいしかったよね。
呑殿内の屋敷地にひっそりと立つウヮーフールが示唆していたのは、この場所を中心とするミニマムな物質の循環であるとともに、そのようにして人と豚がともに参与する生成と分解の、生と死の循環でもあっただろう。人はイモを食べ、豚を食べる。豚もまたイモを食べ、その皮や蔓を食べ、人の排泄物を食べて生長し、仔を産み、屠られて、食べられる。そのようにして人の息は豚の息になり、豚の息は人の息になる。
この循環の中で、人の息と豚の息は等価である――というより息、あるいは魂やアニマとも呼ばれるものは、人と豚のあいだを、そのそれぞれを暫時的な容れものとしてめぐりながれている。個々の身体の境界や、種の境界を越えて。
そういえば、家で豚を屠っていた頃の話として、大城さんはこんなことも語っていた。
――豚が神様だとしたら、豚をつぶす前に、何か儀式をされたりしてたんでしょうか。
大城さん 儀式はしませんが、あの、「ナーチュンカイナインドー」と。「もう人に変わるよ」と、うちのおじいは言ったね。もう人になる、豚ではなく。人が食べるから〔...〕「人の肉に変わるよ」と。〔...〕やっぱり豚の生命というのはとっても大事だと、生きものですからね。あれ、包丁で刺すんだからよ、血を採って。ちゃんとほどいて、やるんだから。
――それはその、豚に話しかけてたんですか。
大城さん 豚に。豚を前にして、包丁を刺す前に。
そうして私たちは、マブイグミに戻ってくる。
何かの拍子に魂を落としてしまったとき、なぜウヮーフールのそばでマブイグミをするのか。夜半に外から戻ってきたとき、なぜウヮーフールにいる豚を起こすのか。
夜の闇に紛れて自分の輪郭が曖昧になり、魂のありかも覚束なく、何か魔性のものがついてきたような気がするとき。そんなときに豚を眠りから呼び覚まし、夢の中にさまよい出ているその魂を呼び戻すことは、自分の魂のありかを確認し、結びなおすことの隠喩、あるいは実演となりうる。
内と外、人と人ならざるもの、我と彼の交わる場所で、豚の息と人の息を結ぶこと。それは、風のようにめぐりながれている魂をとらえて、豚を媒介としてこの世に結びつける行為ではなかったか。
それはドゥ・コッペの描くアレアレの人びとの葬儀と似た、けれど逆のベクトルをもつ儀礼であるようにみえる。アレアレの葬儀で、死者の息は屠られる豚の息として人びとに食べられることで他と混ざり合い、共同体の中へ、さらに大きな流れの中へ還っていく。ある人の身体に留まり、その個としての存在を形づくっていたものは豚の息となり、人びとの息となって、ふたたび無形の流れになる。
一方でマブイグミでは、ある人の身体からさまよい出て、大きな流れの中に消え去りそうな息あるいは魂を、豚の存在を仲立ちにして取り戻し、結びなおす。この身体に留まり、生気を与え、しばしのあいだ、個としての形をつくりだすものとして。
それはきっとありえること、理にかなったことだ――もしも豚の息が人の息であり、人の息が豚の息であるのなら。
そのようにして魂の流れ、息のめぐり、風のしるしは人と人、人と生きもの、人と世界をつなぎながら循環し、広がっていく。屋敷地の片隅にあるウヮーフールで生まれた小さな渦巻が、集落から村々へ、村々から丘陵へ、丘陵から海へと幾重にも広がって、はるか遠くの島々に生きる人びとの営みとも共振していくような。
そんなふうに夢想するとき、ウヮーフールの苔むした石囲いの前に、山の上から吹いてきた風が小さな渦を巻いて、また去っていったような気がした。
クバの林はしんとして、ただ鳥の声だけが空気を震わせている。
(了)
(1)エドワード・タイラーやロバート・R・マレットを主な論客とする、当時のヨーロッパにおける宗教の起源をめぐる議論とアニマやマナという概念の関係については、マレット他(二〇二三)、Ishii and Fujihara(forthcoming)参照。また、マナという概念の翻訳と流通についてはKolshus (2013)、Tomlinson & Tengan(2016)参照。
(2)Papapetros (2012)、Ingold (2006)も参照。
(3)マブイの一般的な解説としては加藤(一九八三)、アニマという概念にふれつつ奄美と沖縄における魂の観念について考察した論考として高橋(二〇一五)参照。
(4)ドゥ・コッペがこの論文で「身体」、「息」、「イメージ」としているのはそれぞれ、アレアレ語のrape、manomano、nunuという言葉である。このうちrapeは「外形」、nunuは「表象」とも訳される(de Coppet 1995: note1, 2008: 10)。ここでの「イメージ」とは、息と同じく固定的なものではなく、パンパイプの音響やあやとりの型のように、ある順序をもって展開していく動きを通して現れる現象を含んでいる(佐本 二〇二一:九四−一〇四参照)。「食べる−食べられる」という関係を通して、人の息と豚の息が相互に転換していく過程については、de Coppet(1985: 87, 2008: 11)も参照。これらの概念については、アレアレで調査を行ってきた佐本英規さんのご教示を受けた。
(5)Barraud et al.(1994: 40-65)参照。
(6)本章に登場する大城勲さんと湧上洋さんの語りは、いずれも二〇二五年三月十九日、南城市玉城前川で行ったインタビューに基づいている。この聞き取りは堀川輝之さん(沖縄国際大学非常勤教師)のご協力を得て行った。
参照文献
加藤正春 一九八三「マブイ」『沖縄大百科事典 下巻 ナ−ン』沖縄大百科事典刊行事務局編、沖縄タイムス社、五二七頁。
佐本英規 二〇二一『森の中のレコーディング・スタジオ――混淆する民族音楽と周縁からのグローバリゼーション』昭和堂。
高橋孝代 二〇一五「
R・R・マレット他 二〇二三『マナ・タブー・供犠――英国初期人類学宗教論集』江川純一・山﨑亮監修、国書刊行会。
Barraud, Cecile, Daniel de Coppet, Andre Iteanu, Raymond Jamous. 1994. Of Relations and the Dead: Four Societies Viewed from the Angle of Their Exchanges, trans. S. J. Suffern, Berg.
de Coppet, Daniel. 1985. '...Land Owns People', R. H. Barnes, Daniel de Coppet and R. J. Parkin (eds.), Contexts and Levels: Anthropological Essays on Hierarchy, JASO, pp. 78-90.
―――. 1995. ''Are'are Society: A Melanesian Socio-Cosmic Point of View. How are Bigmen the Servants of Society and Cosmos?', Daniel de Coppet and André Iteanu (eds.), Cosmos and Society in Oceania, Berg, pp. 235-277.
―――. 2008. 'From the Western 'Body' to 'Are'are 'Money': The Monetary Transfiguration of Socio-Cosmic Relations in the Solomon Islands' (trans. Hattie E. Hill), Pamela J. Stewart and Andrew Strathern (eds.), Exchange and Sacrifice, Carolina Academic Press, pp. 3-24.
Ishii, Miho and Fujihara Tatsushi. Forthcoming. 'Introduction: Towards a Novel Philosophy of Life', Ishii Miho and Fujihara Tatsushi (eds.), Nature, Disaster and Animism in Japan: Anima Philosophica, Bloomsbury.
Ingold, Tim. 2006. 'Rethinking the Animate, Re-animating Thought', Ethnos: Journal of Anthropology 71 (1): 9-20.
Kolshus, Thorgeir. 2013. 'Codrington, Keesing, and Central Melanesian mana: Two Historic Trajectories of Polynesian Cultural Dissemination', Oceania 83 (3): 316-27.
Papapetros, Spyros. 2012. 'Movements of the Soul: Traversing Animism, Fetishism, and the Uncanny', Discourse 34 (2-3): 185-208.
Tomlinson, Matt & Ty P. Kāwika Tengan. 2016. 'Introduction: Mana Anew', Matt Tomlinson and Ty P. Kāwika Tengan (eds.), New Mana: Transformations of a Classic Concept in Pacific Languages and Cultures, ANU Press, pp. 1-36.


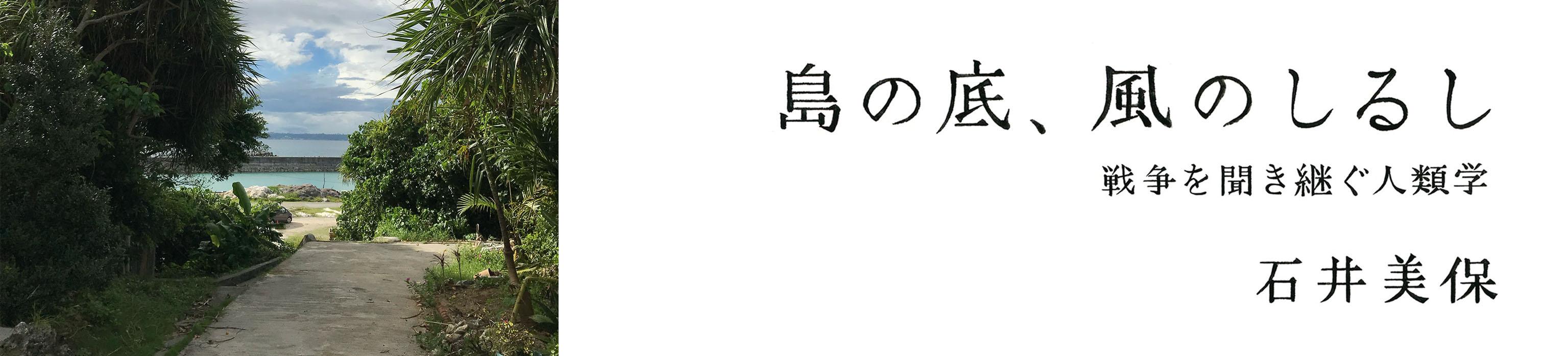


-thumb-800xauto-15055.png)



