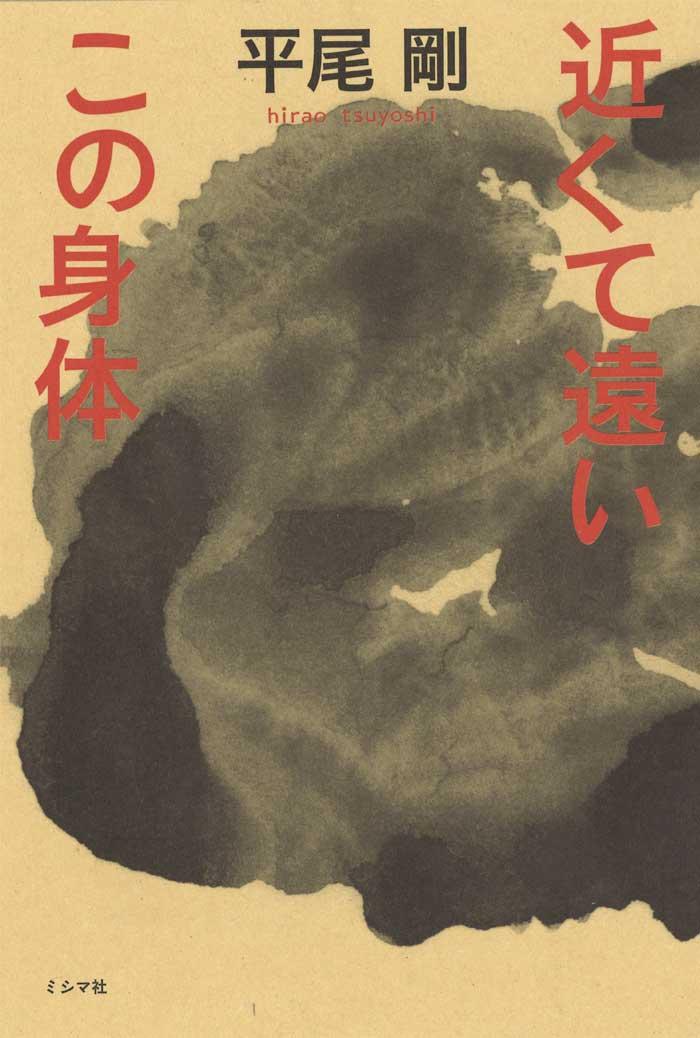第1回
スポーツ、これからどうなる?
2021.04.18更新
【お知らせ】
本連載が、書籍『スポーツ3.0』になりました!
加筆を経てさらに充実した、これからのスポーツ論を
お楽しみいただけますとうれしいです。
「『する』『観る』『教える』をアップデート!
根性と科学の融合が新時代をひらく。
元アスリートとして、声を上げつづけてきた著者の到達点がここに。」
今、日本では聖火リレーが行われている。新型コロナウイルスの感染が広がる前の2017年から東京オリンピック・パラリンピック(以下、東京五輪)の返上を訴えてきた僕は、いたたまれない気持ちになる。列をなすスポンサー車両には開いた口が塞がらないし、なによりランナーや沿道に駆けつけた人たちが浮かべる屈託のない笑顔を、心穏やかに見ることができない。
本当にこのまま開催してよいのだろうか。
思い起こせば東京五輪をめぐっては今日に至るまでさまざまな問題が生じている。
IOC総会での「アンダーコントロール」(汚染水は完全に制御できているという意)という虚偽発言、招致のために票を買ったとされる裏金問題、エンブレム選考に関する騒動、建前だけの「復興五輪」や「アスリートファースト」、記憶に新しいところでは元組織委員会会長の女性蔑視発言や開閉会式を演出する組織人事のゴタゴタなど、ざっと振り返るだけでもこれだけある。
スポーツに求められるものは、なによりも「公正さ」である。そのスポーツの祭典であるはずの五輪が、まったくもって公正ではないというのはなんという皮肉だろう。
いや、正論をまくし立てたいわけではない。正論だけで現実が変わらないことくらい僕にもわかっている。人は100%清廉潔白であらねばならないと無邪気に叫べるほど、僕も若くはない。正しくありたいと願いながらも、つい出来心で悪事に手を染めてしまうこともあるのが人間だ。たぶん僕たちは理性と欲望の葛藤から死ぬまで逃れられない。少なくとも僕はそうだ。「すべき」と「やりたい」とのはざまで、これからも人生におけるさまざまな場面で決断を下していくことだろう。
こうした人間理解から、百歩譲って東京五輪をおおらかに捉えてみよう。
ここまで大会関係者の並々ならぬ尽力があったことは認める。日本を元気づけよう、経済を活性化させよう、子どもたちが夢を持てる社会をつくろう、スポーツから社会をよくしようなど、開催に向けての動機は純粋だったに違いない。オリンピック特有の祝祭的な雰囲気でそれらの目的を果たそうとした意図は、十分にわかる。一部を除いた大会関係者に悪意がなかったことは、スポーツに慣れ親しんでいる僕としては積極的に認めたい。
でも、である。
初発の動機が純粋であっても、もたらす結果に災厄があるとわかれば、その時点で軌道修正するのが「おとな」である。オリンピックを開催することで得られる社会的な成果とふりかかる厄災を天秤にかけ、その内容を冷静に吟味する。責任者は言わずもがな、関係者ひとりひとりのこうした心がけと、それにもとづく行動によって「公正さ」は保たれる。
そもそも「公正さ」とは、不断の努力ができる「おとな」に支えられて、かろうじて成り立つものである。一度達成したからといって未来永劫続くという静的なものではない。理性と欲望のはざまで揺れ動く人間が集まる社会で、揺らぎながらもある一定の範囲内に収めておかなければならない動的なものである。今を生きる私たちが、移りゆく時代の流れを考慮しながら、手の届く範囲で「公正さ」を保つための行動を積み重ねる。ウソをとがめる、金の流れを把握する、差別や人権侵害には声を上げるなど、閾値を超えるまえにその芽を摘むひとりひとりのアクションが不可欠なのだ。
「公正さ」はたえず揺らいでいる。つまり「幅」がある。
この「幅」を東京五輪は超えてしまった。超えるどころか、公正さそのものを破壊しつつある。このパンデミックの最中であっても開催を強行する姿勢に、それが現れている。国民の健康よりも金銭や名誉や権力を優先するのは、本末転倒も甚だしい。ほんの一握りの人たちの「夢」や「希望」を叶えるために、なぜ大多数の健康が脅かされなければならないのだろう。経済活動の停滞によって職を失い、生活がままならなくなった人を差し置いてまで開催する意義があるのか。医療従事者にさらなる負担をかけることにうしろめたさはないのだろうか。
主催する組織に「おとな」の数が足りない。
大手広告代理店の緊急アンケートによれば約7割の人が、またスポンサー企業においても約65%が今夏の開催に否定的な意見を述べているという[1]。
またスポーツ関係者のあいだでも、ポツポツ声が上がり始めている。
現役アスリートでは、水泳の松本弥生選手が毎日新聞のインタビューに葛藤を抱える胸の内を吐露し、「一国民として言うなら、今やるべきではないとも思う」と話した[2]。陸上の新谷仁美選手も、国民が望まない状況下で開催することに一貫して疑問を投げかけており、「選手だけが『やりたい』では、わがまま」だと述べている[3]。
元アスリートに目を向ければ、元陸上選手の有森裕子氏がアスリートファーストではなく「社会ファースト」を[4]、元柔道家でJOC理事の山口香氏は「オープンな議論」をと、開催ありきではなく本質的な視点から大会のあり方を見直すことの大切さを訴えかけている[5]。
世論が否定的で、スポーツ界からも異論が出てきている。パンデミック以前を振り返れば、この変化には驚かざるを得ない。なぜなら僕が東京五輪の返上を訴えた2017年ごろは開催に否定的な意見はほんの一部だったからだ。当時の僕は、元アスリートでありながらスポーツの祭典に反対の意を表明する奇特な人だった。
スポーツ関係者と話をすると、ほとんどの人はまるで腫れ物に触るように東京五輪の話題を避けた。話題がふと東京五輪に移りそうになればスッと話を変える。この話題を逸らす仕草にふれるたびに感じた寂しさは今でも忘れない。
議論を戦わせてもいいから真正面から話をしたい。スポーツに関わる者同士で今こそきちんと語り合おう。こっちとしてはその用意ができているのに、なぜ話をしようとしないんだ。
もどかしかった。自らの主張がかき消されてゆくようで、虚しかった。
ときに「不都合なことは見えないフリをして、それでいいのか?」と、苛立つこともあった。擁護してくれる人はいたものの、そのほとんどはジャーナリストやスポーツ以外の研究者で、スポーツ分野の当事者と名乗れる人は皆無だった。それが歯痒かった。
あのころを振り返れば、東京五輪を否定的に捉える意見が多数を占める現在の趨勢は、隔世の感すらある。
ちょっと感傷的になってしまった。冷静になろう。
話を戻す。
今、世間は「オリンピック幻想」から醒めつつある。新型コロナウイルスの蔓延が東京五輪を覆っていたベールを剥ぎ取り、多くの人がその実態に気づき始めている。肥大化したオリンピックの存在に、ようやく懐疑的なまなざしが向けられるようになった。コロナ禍で生活が限定されるなか、なぜスポーツの祭典であるオリンピックだけが「特別扱い」されるのか。そうした疑問を投げかける人が、長らく続く自粛生活への不満とともに増えてきているように思われる。
それにともなって、スポーツそのものの価値もゆっくりと、でも確実に下落しはじめている。その気配を感じた水泳の萩野公介選手は、五輪組織委員会元会長である森喜朗氏の女性蔑視発言を批判した上で、「アスリートが一番、スポーツの価値を考えていかないといけない」と選手のあり方について持論を展開している[6]。
アスリートのみならず、関係者すべてがスポーツの価値を考え直す必要があると僕は思う。
もし東京五輪が強行開催されればスポーツに対する世論の目はさらに厳しくなるだろう。たとえ開催が中止されたとしても、これまでの騒動がもたらしたスポーツに対する懐疑のまなざしは、そうかんたんには解消されないはずだ。今の情況をただ静観すれば、もしかすると50年後には「スポーツなんてやってんの? めずらしいねえ」という人が出てくるかもしれない。大げさに思われるかもしれないが、それほどの危機感が僕にはある。
これからもスポーツが多くの人に愛されるように、本連載では「スポーツのこれから」について書いてみたい。まずはオリンピックの話を皮切りに、スポーツにまつわる事象を取り上げつつ、その本質にまで迫れればと思う。これからの社会でスポーツはどうあるべきか、僕たちにとってスポーツとはそもそもなんなのかを、じっくり腰を据えて論じたい。
このままだとスポーツが廃れてしまうと焦る元アスリートの研究者が、切々と語るスポーツ論に、どうぞおつき合いください。
[1]大手広告代理店が14歳以上のテレビ視聴者男女各900人を対象に実施した緊急アンケートでは約7割が開催に反対。スポンサー企業を対象にしたアンケートでも、条件的不支持、全面的不支持を合わせて65%を占めた(「週刊フラッシュ」2021年3月23日号)ちなみに民間が実施した新型コロナウイルスをめぐる日米欧6カ国の世論調査では、今夏予定の東京五輪開催に反対する回答が日本と英国、ドイツで過半数を占めた(「JIJI.COM」2021年3月3日)。
[2]「毎日新聞」2021年2月18日
[3]「JIJI.COM」2021年1月20日
[4]「NHKスペシャル あなたはどう考える?東京オリンピックパラリンピック」2021年3月21日放送、「LITERA」2021年3月22日・2017年8月4日
[5]「共同通信」2021年1月28日
[6]「日本経済新聞」2021年2月10日