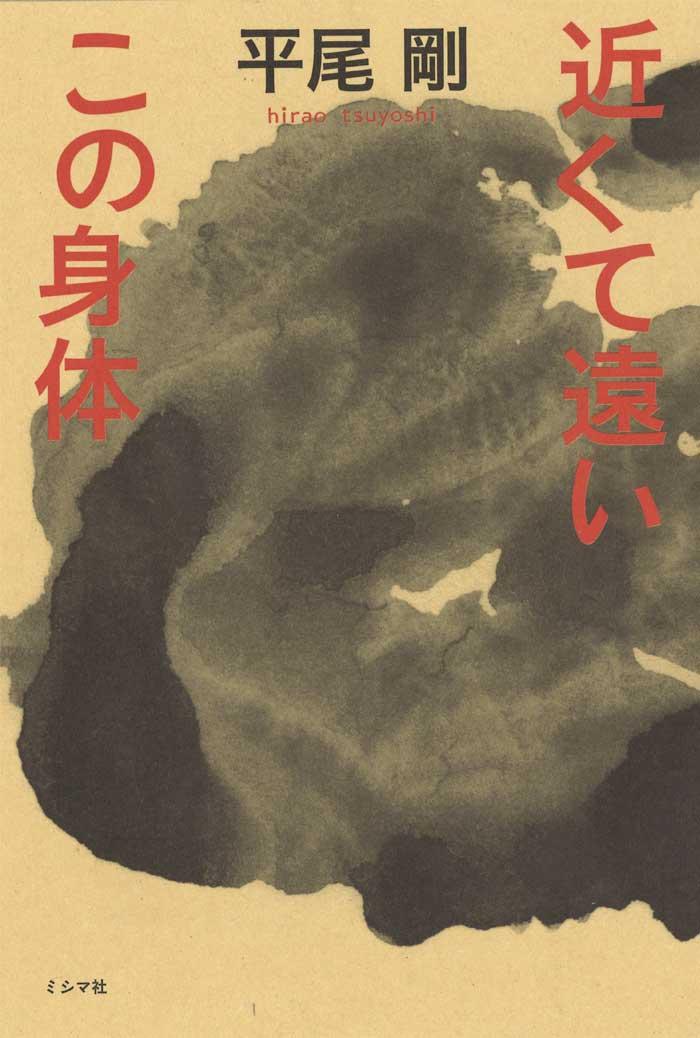第17回
程度の見極めと厳しさの確保
2022.09.27更新
【お知らせ】
本連載が、書籍『スポーツ3.0』になりました!
加筆を経てさらに充実した、これからのスポーツ論を
お楽しみいただけますとうれしいです。
「『する』『観る』『教える』をアップデート!
根性と科学の融合が新時代をひらく。
元アスリートとして、声を上げつづけてきた著者の到達点がここに。」
8月の終わりに娘を連れて公園に出かけた。「キックバイクに乗りたい!」と家を出るまでワクワクしていた娘だったが、公園に向かう道すがらだんだん言葉数が少なくなっていく。やがて「あちゅい(暑い)・・・」としか口にしなくなった。顔を見れば額からは汗が滴り落ちている。みるみる元気がなくなるその様子を心配した私は踵を返して自宅に戻り、冷房の効いた車でドライブすることにした。
天気予報によれば、この日の最高気温は35度だった。風もほとんど吹いておらず、容赦のない陽射しが皮膚を焼きつけ、生温い空気が息苦しさを誘う。地表がアスファルトで覆われた街中での体感温度は、おそらく40度を超えていただろう。まるでちょっとしたサウナに入っているみたいだった。心身が発達途上で、身長が低く地面にほど近い娘は、私より過酷だったはずだ。
思い起こせばいまから40年ほど前の、私が幼いころはここまで暑くはなかった。
外遊びが好きだった私は真夏でも元気に走り回っていた。遊びへの衝動が萎えるほどの陽射しもなく、空気も乾いていた。熱中症警戒アラートが発表されることもなかったし、あったのは光化学スモッグ注意報くらいで、当時は暑さよりも大気汚染が懸念されていた。とはいえ嫌な匂いも息苦しさも感じなかったから、なにも気にかけることなく陽が沈むまで遊び呆けていた。
今年で47歳になった私は、もしかすると加齢による体力の衰えから暑さへの耐性が落ちているのかもしれないとも思う。冷房の効いた部屋でのデスクワークにからだが慣れてしまい、ちょっとした暑さであっても身に応えるようになっただけではないか。そういう面も少しはあるに違いない。ただ、それを考慮したとしても、あのころに比べれば夏の暑さは格段に増しているように感じる。「猛暑日」なんてことばも当時は耳にしなかった。
遊びたい盛りで元気いっぱいの4歳児からその気力を奪うほどに、いま、日本の夏は暑い。暑すぎる。
夏の風物詩である全国高校野球選手権大会(以下、甲子園)は、仙台育英が優勝を収めた。東北勢初の全国制覇に世間は賑わい、春夏連覇がかかる絶対的な優勝候補の大阪桐蔭が準々決勝で下関国際に敗れたことも話題になった。
主催する朝日新聞社および後援の毎日新聞社を中心としたマスメディアは、連日にわたって大会の模様を伝えた。甲子園への興味が年々薄れつつあるこの私が、いやが上にもその様子が知れるのは、これらの報道を目にするからだ。
紙面や画面には高校球児の爽やかさを強調した記事や映像が躍る。不自然に装飾された「感動物語」に辟易としながらも元アスリートとしてはついそれに惹き込まれそうになるのだが、やはり、ちょっと待てよと思う。この炎天下でスポーツをするのって、どう考えてもおかしいだろと。
大会3日目の第1試合、海星対日本文理の試合では2人の球児が守備の前後に足がつって倒れ、担架や味方に抱えられてベンチ裏に運ばれた[1]。「足がつる」のは発汗による体内の水分不足がおもな原因だ。日々の練習で鍛え抜かれたからだであってもそうなるほどの酷暑だということである。前日にも3人の球児が担架で搬送されており、また地方大会の開会式では毎年熱中症で倒れる生徒が続出しているという[2]。
暑熱下での運動を控えるよう国民に注意を喚起しながら、酷暑の中でプレーする高校球児にはそれをしない。室内にいても熱中症になる恐れがあるにもかかわらず甲子園だけは例外的に挙行する。まったくもって異常というほかない。球児の健康を第一に考えれば、大会時期を見直すなどの暑熱対策を打って然りのはずだ。地球規模の気候変動で気温が上昇しつつあるのだから、それに応じて甲子園のあり方を抜本的に見直す時期に来ているのは自明である。
いやいや、厳しい環境であってもめげることなく懸命にプレーする球児の姿に感動するんじゃないか。それが甲子園ってもんだろう。なにをいまさら野暮なことをいうのだ。
こういう人は多いだろう。ひたむきなプレー観たさに甲子園を心待ちにしている人は、少なからずいる。
もちろんファンの楽しみを奪おうとは思ってはいない。ただ、少し立ち止まって考えてみてほしいだけだ。自らは涼しい部屋のなかにいて、心身の発達が未熟な高校生が過酷な環境下で苦しみながらプレーする姿に感動している。この構図を、やや引いた目で俯瞰的にみれば、いかに常軌を逸しているかに想像が及ばないだろうか。教育が目的の高校野球をエンターテインメントとして消費する大人側の都合に、子供が振り回されているとは思えないだろうか。
ここにピリオドを打たなければならないと私は主張したいのである。
伝統を重んじることは大切である。しかし、社会や環境の変化を考慮せず頑なに継続にこだわるのは避けなければならない。既成の仕組みに疑念を抱かず変化を恐れるのは思考停止にほかならず、むしろ従来の価値観を手放そうとしないこの態度は、甲子園を飯の種にする主催者側の欲望に加担することになる。改善すべき課題があるのに黙して異論を唱えないのは、「おとな」がとるべき態度ではない。
これはなにも甲子園だけにとどまらない。運動部活動や地域クラブではたとえ真夏の日中であっても練習や試合を行っている。それを思えば、子供を取り巻くすべてのスポーツにおいて暑熱下での取り組み方を抜本的に見直さなければならないはずなのだ。指導者が然るべき知識を身につけるのはもちろん、猛暑となる日中ではなく朝夕に活動する、あるいは練習時間を短くするなどの対策を講じなければならない。地球温暖化が進むいま、子供の健康や健全な成長を第一に考えたスポーツ環境の整備は喫緊の課題といえる。
もし甲子園がその開催の仕方を大幅に見直せば、他のスポーツもそれに追随して若年層のスポーツは健全化へと向かうだろう。それを期待して、私は現行の甲子園を、中止も視野に入れつつ抜本的に見直さなければならないと考えている。
酷暑への「やせ我慢」は不要である。
ここまで書いておいて、いまさらなにをいうかと思われるかもしれないが、一点だけ、私のなかでどうしても引っかかっていることがある。元アスリートからすれば、この考え方を素直に咀嚼できない自分もいる。というのも、からだというのはその限界を越える経験を通じてたくましくなるからである。
厳しさを乗り越えることでからだは鍛えられる。だから「少々の暑さ」であればそれもまたスポーツには必要ではないか。快適さを追い求めすぎればスポーツの醍醐味が削がれることになるのではないだろうか。そう私のからだが訴えかけてくるのである。
だからこそ8月の終わりに暑いのがわかっていながらも娘を公園に連れ出した。多少の暑さならばそれに慣れることもまた娘の発達につながる。そう考えるからだ。ただあまりの暑さに、みるみるうちにバテてゆく娘の姿を見て思い直したのだが。
私のこの引っかかりは、おそらくすべてのスポーツ経験者の胸の内にわだかまっていると思われる。「暑い暑い言いすぎやろ、このくらい乗り越えんとどないすんねん」というマッチョな思考が、深層意識に根付いている。経験則からくるこの心理的な抵抗をどう乗り越えるかが、現実問題としてある。
つまり自らの経験則を書き換える作業が、指導者をはじめとする運営サイドに求められている。快適さおよび厳しさをどの程度まで求めればよいかを論理的および感覚的に掴むこと、すなわち「程度の見極め」が必要なのだ。快適に楽しめる環境を目指しつつ、からだの発達やパフォーマンスの向上に不可欠な厳しさをどのように確保するのか。これが酷暑下におけるスポーツ活動を見直す上での大切な視点になる。
この「厳しさの確保」という問題は、暑さだけに限らず指導そのものについてもあてはまる。暴力や暴言がともなう指導は明らかに度を越しているが、上達を目指すプロセスではそれなりの厳しさが必要となる。上手くなりたいと望む子供たちもまたそれを求めている。厳しさの下限と上限を正しく見極める目を、指導者をはじめとする私たちおとなは身につけなければならない。快適さはときに生ぬるさとなり、厳しさはときに暴力にもなるのだから。
[1]「デイリースポーツ」 2022年8月8日
[2]「産経新聞」 2022年7月6日