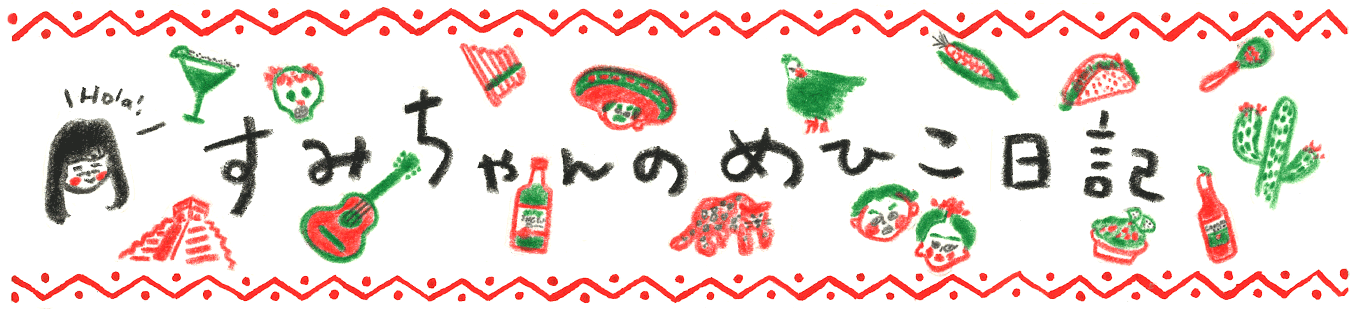第7回
メヒコで起きている「戦争」について(3)
2018.12.06更新
今夏に日本で行われたイベント「メキシコ麻薬戦争の真実」。そこに講演者として招かれたルシア・ディアスさん(麻薬戦争による行方不明者の家族の会代表。活動家)に、会場からこんな質問が投げかけられました。
「どうしてあなたは、『メキシコのほとんどの人は、麻薬戦争について本当のことを知らない』と言うのですか。また現にどうしてこれまで、大規模な抗議運動や告発がそれほど多く起きてこなかったのですか」。
「麻薬戦争」は、これまでに膨大な数の被害者を出し、各地の治安を悪化させており、メキシコが抱える最大の問題として認識されています。しかし前回の記事で書いたとおり、誰が関わっているのか、次にどこで事件が起きるのかなど、はっきりしない部分が多いことがこの「戦争」の特徴です。政府・警察・軍・麻薬組織が経済的利害と力(暴力、権力)をめぐって絡み合い、その利害や力は、一般の人びとの生活とも関係を結びます。危険性は、場所によって濃淡のグラデーションをつくりながらメキシコ全域に広がっていて、しかもその危険が誰によってもたらされるのかはよく見えません。びくびくしていても、日常の時間はとりあえず何事もなく過ぎていく。ふつうに生活を送っていたのに、突然失踪してしまう。
こうした状況を生きるとき、「麻薬戦争」についてどのような想像力がはたらくでしょうか。
「メキシコでは、ほとんどの人はこの問題について踏み込んで考えようとしません」。ルシアさんはそう言います。犯行の背景を知ったり、自分の知人が被害にあったりしても、声を上げたせいで報復を受けることを恐れて、まず波風を立てないようにしようと考える人が多い。また、「大多数の人びとは、事件に巻き込まれる人のことを自業自得だと思いがちです」。マフィアに誘拐され命を奪われるのは、麻薬を買ったことがあるとか、取引の手伝いをしたといった、狙われるだけの理由があるからだろう。「悪いこと」に関わらなければ自分は大丈夫、という発想です。ルシアさんはこう続けます。「でも、それは正しい理解ではありません。たとえば、一度も関わったことのないマフィアによって、ただ身代金の要求のためだけに自宅に押し入られ、連れ去られる人が大勢います」。
ただし、世間に流布する反応を「被害者の差別」や「間違った思い込み」としてためらわず批判しようとすると、居心地の悪さが残ります。誰かが濃い霧のむこうから自分に銃口を向けているかもしれないような状況で、そのことをつねに受け止めて生き、さらに告発まで行うことは、きわめて困難だと思います。恐れや無関心から問題を受け流すことは、「暗く残酷な事実にたいする、一種の防御反応なのかもしれません」。現地で長年奮闘する活動家が言い添えました。

講演会場のひとつで、質疑応答をうけるルシアさん(写真の右でマイクを持つ女性)
よくわからない「戦争」中に起こることは、そのつど「戦争」、「犯罪」、「街の安全」といった言葉によって、何度もイメージの差替えをほどこされたり、すっきりとした構図に整理されたりします。政府や多くのメディアの公式見解も、このやりかたによって、なるべく大事(おおごと)に見えず混乱を引き起こさないものになります。被害者や加害者の像が安定すれば、誰と誰が共謀しているのかや、自分の生活空間とどれくらい関係があるのかについて、いっそう考えづらくなります。
公式データによれば、2006年末から2018年4月までで、メキシコの殺人被害者は約25万人、行方不明者は約37,000人。この12年間のうちに起きた全国規模の抗議は、2011~2012年に活発化した「正義と尊厳ある平和のための運動」という社会運動と、国際的スキャンダルとなった2014年の「アヨツィナパ教員養成大学学生43人失踪事件」の告発です。現在は「メキシコにおけるわれわれの行方不明者のための運動」という全国ネットワークが活動を行っていますが、それでも「麻薬戦争」に対する抗議は、事態の深刻さに相当するほど多いとはいえないでしょう。
政府の情報操作という話題を出してしまうと、ちょっと仰々しくきこえるかもしれません。でも、やはり「25万人以上も犠牲となっているのになぜ」という疑問があるかぎり、この「よくわからない戦争」のなかで広がる想像力や反応について、いろいろな角度から真剣に考える必要があると私は思います。
2年前にメキシコに住んでいた私にとって、当時の日常と麻薬問題は、たしかに交差していました。だから私もある意味で、この「よくわからない戦争」のなかにいたと言えます。たとえば10月の記事で書いたように、私が通っていた大学構内のいくつかの場所では、マリファナの匂いがプーンと立ち、広い芝生の中庭でごろごろしていると、マリファナの葉を練り込んだカップケーキを愛想よく売り歩く学生をしょっちゅう見かけました。ただし、日常的にそうした場面と出くわしながらも、私は毎日ふつうに楽しく大学に通っていたのです。麻薬問題と生活は、奇妙なしかたで重なっていました。
メキシコの大学生ならみんなが知っているであろう、こうした日常風景は、ここ1年ほどでまた変化をみせています。麻薬の密売に関わる若者のふるまいが悪化し、危なくてふつうの学生が立ち入れないスペースが広がったと、たくさんの友人が言っています。「夜にひとりで○○学部のそばを歩かないほうがいい。殴られたり、スマホをとられたりするよ」。そして、今年の9月初旬に、この大学(メキシコ国立自治大学)で事件が発生します。構内の安全対策などを求めて(大学運営部への)抗議を行っていた学生のところへ、マリファナ密売グループが突然やって来て暴行したのです。
この出来事は、日常が淡々とすすんでいく場所に紛れこんでいるものが、事件に変わっていくようすを示していると思います。こういうリスクの散らばりかた、こういう事態の急転のしかたが、「麻薬戦争」のひとつのリアリティです。
ただし、この現実が暗い面ばかりを持っているわけではありません。実は、事件をうけてすぐに、大学の安全を訴える学生デモがはじまり、その参加者は3万人以上に膨らみました。リスクだけが広がっているのではなく、そこには、なにかがはじけるようにして抗議の声が上がるような可能性が眠っていたこともわかります。
日本に届くニュースや映画の多くでは、血で血を洗うマフィアの抗争や、たくさんの遺体が発見される秘密墓地といった、センセーショナルな題材ばかりが取り上げられます。そういうふうに切り取られる「麻薬戦争」は、ある意味での衝撃を与えてはくれますが、同時に、この問題やメキシコという土地自体の、現実味のなさを強調することにもなるでしょう。この記事では「メキシコ麻薬戦争という有名な問題」について、私がメキシコでふつうに暮らしていたときの感覚をあえて抑えこまずに書こうとしました。「疎遠さ」に支えられた劇的なイメージや安易な同情を避けてみると、もっとべつのそら恐ろしさがそこには残ります。
わかりやすいイメージを裏切って、非公式のグレーな領域で展開することが、「麻薬戦争」の技術です。だから、つくられた疎遠さを乗り越えて考えてみる。そうすると、日本で暮らす私たちも、この問題のなにが問題なのかについて、これまでとは違う感覚を持てるかもしれません。