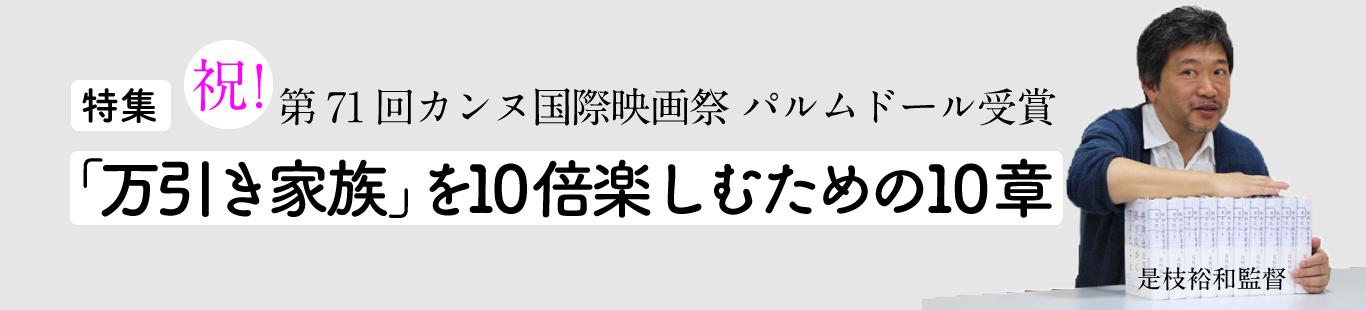第2回
「万引き家族」を10倍楽しむための10章(2)
2018.06.06更新
第71回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した是枝裕和監督。「万引き家族」のパンフレットには、「10年くらい自分なりに考えて来たことを全部この作品に込めようと、そんな覚悟で臨みました」という監督のコメントが載せられています。
2016年6月にミシマ社から発刊された『映画を撮りながら考えたこと』では、テレビディレクター時代から『海よりもまだ深く』まで、各作品をつくりながら考えてきたこと、試行錯誤してきたことの軌跡が、400ページ超にわたり綴られています。
本書を読んで、ぜひ「万引き家族」をより深く味わっていただきたい。そんな思いのもと、今回の特集では、『映画を撮りながら考えたこと』全10章からの引用ご紹介と、「是枝監督自著を語る」というイベントレポートのダイジェストを、2日間にわたりお送りします!


第2日目 是枝裕和監督 自著を語る
8年がかりで完成した『映画を撮りながら考えたこと』。最終的に400ページを超える大著となった本書は、どのようにしてできたのか。この8年のあいだに監督が経験したことが、本書にも色濃く反映されており、それは同時に、同時代を映し出したものであるにもちがいない。そんな確信のもと、本書を編集した三島が、司会という形で監督に「あれこれ」訊いてみました(@青山ブックセンター本店 2016年6月19日)。
(構成:堀香織)
テレビという出自
―― 映画初監督の『幻の光』から約20年、初のテレビドキュメンタリーからだと30年近いわけですが、振り返っていかがでしたか?
是枝 自分を振り返るほど"自分好き"じゃないんですが(笑)、いい機会でした。撮ったものを分析して、反省点を見つけて、何がやれて何ができなかったのかを意外と冷静に考えながら、じゃあ次何をやるかを考えてきたつもりなので、こうして20年経ったところで後ろを振り返って、テレビに対する興味や映画に対する考えを一度整理するタイミングとしては良かったかなと、ありがたい機会を得たと思っています。
―― 監督にそう言っていただけて嬉しいです。僕もテレビ、映画、映像に限らず、創作にかかわっている人にとっては避けて通れない1冊になったのではないかと。自分にとっても今後活動を続けていく上での、切実なバイブルになりました。
是枝 僕は「テレビ人である」というDNAみたいなものが年々色濃くなっていて、まえがきにも書きましたが、自分の映画というものがどういうふうにつくられ、世の中に出て、国際映画祭を回っていくのかをテレビディレクターの視点で見ていくのであれば書けるかなと思ったんです。それはうまくいったかな。
それから、出発点であるテレビマンユニオンの、村木良彦、萩元晴彦、今野勉という3人のテレビ人がいるのですが、彼らは番組をつくれて、そのことについてしゃべれて、書けた。それは素晴らしいことだなと常々思っていたので、現時点でのキャリアの中間報告としてはきちんとしたものができたかなと。特に僕をテレビの世界に引き入れてくださった村木さんには読んでもらいたいなとは思いました。残念ながら、もう亡くなってしまっているんですが。
―― 僕たちにとっては"映画監督"の是枝さんというイメージがありますが、監督ご自身はテレビが出自だということを強く意識されていますよね。
是枝 年取ると父親に似てくるじゃない? テレビはそういう感じ。目を背けていても仕方ないなと。逆に映画に対しては、畏怖みたいなものがむしろ年々強くなっているし、だからこそ近づきたいという気持ちと遠ざかっておきたい気持ちと相反する不思議な感じなんです。難しいです、映画について語るのは。でも、映画も作品数が10本超えたので、いいかなと。8年かかったけれど、いいタイミングでしたね。幸せな本だと思います。
開かれた状態で
―― 監督は一貫してひらかれているということを、この本づくりでもずっと感じていました。答えが全部自分の中にあるというスタンスでは全然なくて、「何でもきいてください」と座っていらっしゃって、質問させていただくと、ポンポンと応えられる中で生成していくという感じがして。
是枝 準備していくと失敗するんだよね。だから講演会は嫌なの。基本的に全部断っているんですけど。レジュメとかつくってしゃべろうと思うと、つまんないし、聴いていてもつまらないと思うし。なんかね、嫌ですね。
―― 今日は参考までに、本書の再校ゲラをもってきたのですが、これでもかというほど、すさまじく監督の赤字が書き込まれていまして。しかもこれで終わりではなくて、次の原稿にも、これくらい赤字が入っているんです。
是枝 それ、減らないんだよね(笑)。
―― その次をお渡ししたら、また同じくらい入っていたと思うんですよね(笑)。
是枝 どこかで終えないとね。でもね、それはしょうがないんだよな。直しの少ない原稿を書いてみたいんだけど。
―― たぶん、いまうかがっていてよくわかったんですども、常にそうやってひらかれた状態で、質問に対しても、原稿にも向き合っていらっしゃるので、そこのひとことなどに触発されて、そこに生成される言葉を書きとめておこうということに、どうしても火がついてしまわれるタイプのつくり手なんだろうなと。
是枝 それと同じことを脚本作りでも編集でもやるので、すごく遠回りするんですよね。ああでもない、こうでもないと。で最後に結局、最初のかたちに戻ったりするので、迷惑をかけているとは思うんですよね。それが最初から見えればいいんだけどね。なかなかそうはならないんだよね。経験値があがっても、そこがあんまり短縮されないというのはなんなのかな。きっと好きなんだよね。
―― 僕もそうなので、この本づくりがすごく楽しかったです。どんどん変わっていく感じというのが。
是枝 下手すると、脚本がそうなっちゃうわけです。しかも印刷された脚本が、翌朝くるとそうなっているという。役者は渡されて「えっ?」という。渡しておいて「覚えてこないでください」ということになりかねない状況が、いつもではないけれど、ときどき起こるんですよね。でも、これ、そのまま撮るようになったらもう・・・あれなんじゃないかと思います(笑)。
映画への愛だけでつながる
―― 最後に「自著を語る」ということで、話を伺いたいのですが、この本の「あとがきのようなまえがき」に、「映画は百年の歴史をその大河にたたえながら悠々と僕の前を流れていた。(中略)「すべての映画が撮られてしまった」というような言説がまことしやかに語られていた八〇年代に青春期を送った人間にとっては、今自分がつくっているものがはたして本当に映画なのか? という疑いが常にある。しかし、そんな『うしろめたさ』も、そして血のつながりも越えて、素直にその河の一滴になりたいと僕は思ったのだ。」という言葉をいただきまして・・・。
是枝 ちょっと素直に書きすぎたな。(会場笑)
―― でも素晴らしい序文をいただけたと思っています。「大河の一滴になりたい」という言葉を初めて拝読したとき感動したのですが、これはずっと撮っていらっしゃるなかでずっと思ってきたことか、この本を書いて思い至ったことなのでしょうか。
是枝 僕は何かに帰属することを避けてきたというか、帰属意識がそもそも嫌いなのね。偏屈だから、同じ大学で集まるとか、会社の忘年会とか、帰属意識を強めるために行うイベントが大嫌い。結局僕はテレビを経て映画に行ったから、テレビの人たちからは「あいつは映画に行ったヤツ」だと思われていて、映画の人たちからは「あいつはテレビのヤツだから」と思われていて、居心地が悪いんです。でもその居心地の悪いほうがいいわけ。べったり帰属してしまうと、ある種の自由さが失われていく。だから居心地の悪いのは大事だと思っている。
ただ、カンヌ国際映画祭がいちばん偉いわけじゃないけれど、何がいいって、あの場には、映画を愛している人たち、理解している人たちが大勢集まっていて、「映画」がいちばん偉いんです。それがとても気持ちがいい。自分が帰属している日本、日本語、日本人というのをいったん置いて、そこに集う。そして映画への愛だけでつながるというのが、いちばん純粋なかたちだと思うし、同一性も求められないから、そこには片足くらい帰属意識を持ちたいなと思ったんですよね。そこが気持ち良くなるとまた違うんだけど、そういう郷土愛に近いもの、なんて呼んだらいいか難しいけれど、自分もそういうことを感じてもいいのかなと思った。それを「あとがきのようなまえがき」に書きました。
「万引き家族」 2018年6月8日(金) 全国ロードショー
プロフィール
是枝裕和(これえだ・ひろかず)
映画監督、テレビディレクター。1962 年、東京生まれ。早稲田大学卒業後、テレビマンユニオンに参加。主にドキュメンタリー番組の演出を手がける。1995 年、『幻の光』で映画監督デビュー。2004年、『誰も知らない』がカンヌ国際映画祭にて史上最年少の最優秀男優賞(柳楽優弥)受賞。2013 年、『そして父になる』がカンヌ国際映画祭審査員賞受賞。2014年、テレビマンユニオンから独立、制作者集団「分福」を立ち上げる。最新作『万引き家族』で第71回カンヌ国際映画祭・パルムドール受賞。8回伊丹十三賞受賞。著書に『雲は答えなかった 高級官僚 その生と死』(PHP文庫)、『万引き家族』『歩くような速さで』(ポプラ社)、対談集に『世界といまを考える1、2』(PHP文庫)などがある。