第6回
『うしろめたさの人類学』を読んでみよう(2)
2018.11.04更新
こんにちは、京都オフィスの野崎です。昨日もお伝えしましたが、ミシマ社より2017年10月に刊行された『うしろめたさの人類学』(松村圭一郎著)が第72回毎日出版文化賞特別賞を受賞しました!!
毎日出版文化賞とは、毎日新聞社が主催する賞で、毎年11月に受賞者が発表されています。文学・芸術部門、人文・社会部門、自然科学部門、企画部門の4部門からなる本賞と特別賞があり、特別賞は「広く読者に支持され、出版文化の向上に貢献した出版物」に対して贈られます。今回この映えある賞に『うしろめたさの人類学』が選ばれました! この賞の受賞を記念して、ミシマガでは昨日と今日の2日間、『うしろめたさの人類学』を特集しています。
本日お届けするのは、『うしろめたさの人類学』が発売された直後の2017年10月5日に恵文社一乗寺店に行われた、松村圭一郎さんと藤原辰史さんによる対談の様子です。京都で学んだ気鋭の学者のお二人が、この本について、今の日本のおかしなところ、これからどのように世界を微調整してゆけばよいのか、などについて語り合いました。その記事が特別に復活します。(この記事は、旧みんなのミシマガジン上に2017年10月24日〜10月25日に掲載されたものです。)
ボケを引き受けること
藤原 今度、『うしろめたさの人類学』の書評を共同通信社から頼まれているので、その下書きの一部を紹介します。
著者は、構築されたものを崩したり、ずらしたりして、組み直す構築人類学を提唱する。その心構えとして「うしろめたさ」という感覚に注目する。たとえば、物乞いに恵みを施せなかったために抱く後味の悪さや、お年寄に席を譲れなかったときの自己嫌悪。長年にわたるエチオピアでのフィールドワークを続ける著者の自己凝視は、フィールドのみならず帰国後も驚くほど鋭い。
少し省略します。
言語の通じなさ、所有観念の齟齬、人間の距離感の違いなどに過剰すぎるほど悩み、山を動かすように自分を変えてきた著者だからこそ、これらの提案が心に響く。
松村さんは、『所有と分配の人類学』でフィールドワークと理論構築を見事にドッキングしましたが、今回の本は、積極的に自らの構想を提言しておられて、びっくりしました。関西のお笑いの文化の言葉を借りれば、「ツッコミ」ではなく「ボケ」を引き受けているんです。とても勇気づけられました。
松村 書評ありがとうございました。「ボケを引き受けた」っていい表現ですね、嬉しいです。でも、僕がボケられるのも、藤原さんが先人としてボケを引き受けてくださっているからなんです。我々世代の研究者のなかでは、明らかに先駆的な「はみ出し者」ですよね。
藤原 ありがとうございます(笑)。そうかもしれません。本来、研究者ってほとんどがツッコミになってしまうんですよね。重箱の隅をつつくように批判して、とにかくツッコむばかり。学問の世界でボケようものなら、総ツッコミを食らうかもしれません。けれど僕はボケの方が性に合ってるんですね。ときどき学問の世界に居づらくなることはありますが(笑)、松村さんは、学問の世界には居づらいですか。
松村 だんだん居心地が悪くなってきたかもしれません(笑)。たぶん、学問の世界に留まるのって、ある意味で気楽なんですよ。勉強して人を批判していればいいので。でも、そのままではだめだろう、と思うところはあって。思い切ってボケてみようと思って書いたのが、この本かもしれません。だからツッコミどころ満載です。
藤原 そうなると、今回のイベントはボケ二人になりますけど、大丈夫ですかね?(笑)
松村 なんとかなるでしょう。もう自分でツッコんじゃいますが、まずこの本のタイトル、もともと「うしろめたさ」なんてついていなかったんですよ。
藤原 そうなんですか! なぜこのタイトルに?
松村 私の知らないところで決まっていまして(笑)。ミシマ社の皆さんで「タイトル会議」をやってくださったんですけど、「そこで決まったので、これでいきましょう」って三島さんから突然言われて・・・。最初は、うしろめたさって危険な概念なので「ちょっとな・・・」と思ったんです。
藤原 危険な概念というと?
松村 例えば、祖先からの土地を譲り受けるとかって呪縛じゃないですか。誰かへのうしろめたい気持ちは、人を縛る力があって、ネガティブなものですよね。この本の中で贈与とかプレゼントを渡すという話も出てきますが、プレゼントを渡すということは慈愛に満ちた楽しいやり取りのように思われるんですけど、高価なものをもらってしまうと気が重くなるし、なんとなくその人に対して申しわけないとか、引け目を感じてしまう。まだ、うしろめたさが一つのキーワードとして出てくるだけならいいんですけど、さらに「人類学」とつくので、これはまずいな、と。
藤原 言い切っちゃいましたもんね。
松村 そんな真正面から「うしろめたさ」を研究してきたわけではないので。でも、タイトルを頂いた後にもう一回、最初から読みなおしてみると、たしかに使ってるんですよね、「うしろめたさ」っていう言葉。
藤原 おお!
松村 実際に私自身がエチオピアに行って路上で子供たちにせびられたり、体の不自由な人がずっとお祈りの言葉を唱えながら炎天下に立っていたりするのをみると、何不自由なく暮らせていること自体がうしろめたくなる。その思い自体は嘘ではないので、そのうしろめたさという感情をどう引き受けて、その意味とか可能性を考えることには意義があるんじゃないかと思い直しました。
藤原 なるほど。
松村 だから、現代思想のなかではけっこう危うい概念とされてきた「うしろめたさ」を前面に出すためには、本当に批判を甘んじて受け入れる覚悟を決めるしかないなと。それでボケを引き受けることにしたんです。
それでいざこのタイトルで本を出したら、みなさんから「いいタイトルですね!」って言われて、それがまたちょっとうしろめたいんです(笑)。あるアーティストの方は、「自分の創作の意欲の根源にあったのは、うしろめたさだったことに気づいた」と言ってくださいました。

人間性が削ぎ落とされる
藤原 この本を書くきっかけはどのようなものがありましたか?
松村 この本自体は、ミシマガジンで「<構築>人類学入門」として、2009年から連載をしていたものが元になっています。2010年から2014年までは東京の大学にいて、その約5年間が私にとって非常に大きかった。
藤原 ほうほう。
松村 東京にいる間に東日本大震災があって、地震そのものよりも、地震の後しばらくたって東京が「普通」に戻ったときが一番怖さを感じました。みんなが何事もなかったかのように生活をもう一回再開して、ぎゅうぎゅうの電車に時間通りに乗るような生活をまた始める。こんなことが起きたんだから、もっと違う社会のあり方を探すのが普通だと思うんですけど、何もなかったかのようにいつも通りの日常が再開してしまうのが怖かった。
藤原 そうですね。
松村 あれだけ大量の人間が朝から一斉に移動をするための効率的なシステムがあって、そのシステムに身をゆだねないと生きていけない感じがどうしても辛くて。
エチオピアの経験を振り返ると、エチオピアで生活している人は、例えば家を建てて雨漏りしていても自分で修理できる。庭には食べ物が植わっていて、誰かに頼らなくても食べ物を得ることが出来る。自分の生活を他の人の働きに頼らなくても自立して生きていく術を知っているし、技術を持っている。そのエチオピアと日本の差は一体何だろうと考えたんです。
藤原 そこがこの本の冒頭でいう「なんかおかしい」というところということですね。おかしいということで言えば、松村さんは以前、東京で大量の人とすれ違うときに、ぶつからずに歩くにはどうしたらよいかということについても話してらっしゃいましたよね。
松村 そうですね。僕は熊本の出身で、同じ田舎出身の方ならわかると思うんですけど、大量の人が前から歩いてくると足が止まっちゃうんですよ。なんで足が止まるかというと、「相手はどっちに進みたいんだろう」と考えちゃうんですね。すれ違う相手を「意志をもつ存在」と思ってしまうから、足が止まってしまう。だからあるときから、すれ違う相手を「ボール」だと思うようにしたんです。そうすると、全然ぶつからないんです。
藤原 なるほど。対面ですね。フランス文学者の大浦康介さんの著書に『対面的』っていうすごく面白い本があるのですが、それとも通じる。要は人間と人間のあいだに「磁場が働く」ということなんです。人間の目と目が向かい合ったときになんとも言い難い力の関係性が生まれて、玉をよけるようには思うように除けられなくなってしまう。
松村 その通りです。だから東京に行くと、人の顔を見ないんですよ。でもそれが当たり前になっている自分に気づいたときに、相手を物としてみなしているということは、同時に自分も物だとみなされているし、私も物のように動いているんだなということにも気づいたんです。そして、みんなが物のように動くとうまくいくシステムが作られているからこそ、朝から赤ちゃんを抱っこして電車に乗るとか、不規則な行動は許されないんですよね。そうやって、システムに縛られているうちに私たちの人間らしさがそぎ落とされていく気がしてきました。
「ツバメはいつ卵を産むんですか」
藤原 エチオピアだと全然違いますか
松村 そうですね。エチオピアに限らず、例えば海外に行くとレジのお兄さんとかお姉さんって大体不機嫌だったり、逆にたまにすごい陽気だったりするじゃないですか。それって、すごく人間的なことだと思うんですよ。でも日本ではお客さまは神様だから、そんな態度をとる店員はほとんどいない。ほぼマニュアル通り機械のように動いている。
藤原 ドイツだと買ったもの投げるレジのおばちゃんいますからね(笑)。かと思えば、すっごく優しい人はいます。
松村 すごく無駄話が長いとかね。でもそういう人間的なふるまいをするイレギュラーな人がいると、どうしても客の列がさばけなくなっちゃう。
藤原 イレギュラーな人で思い出したんですけど、院生だった頃、5月くらいに京大近くの鞠小路通を南に向かって歩いてたんですよ。そしたら明らかに陽気なおじさんが僕のところに来て、目が合ったらニコッとして「すみません、ツバメはいつ卵を産むんですか」って聞かれたんです。「え、ええーやっぱり春じゃないですかね」と答えたら「ありがとうございます」といって去って行かれました。ちょっとびっくりしたんですけど、僕そのときすごく気持ちよかったんです。春の気持ちのいい日に、ツバメはいつ卵を産むのかということをこういう場所できいてくれるという世界に、あとからじわじわといいな、と思って。この本を読んで思ったんですけど、松村さんって、そういうイレギュラーな人の観察が得意ですよね。
松村 藤原さんほどではないです(笑)。でも、そもそもみんなイレギュラーな部分を持っているというか、人間って気まぐれじゃないですか。仕事をしていても裏で変なことを考えていたりとか、寝てるのに目が開いてるとか。でもそれは人間である証だし、人間をそういうイレギュラーなものとして、そこからもう一回考えてみたい。
藤原 そうですね。
松村 でもシステムを批判して、スクラップ&ビルドで別の巨大なシステムを作ったって駄目なんですよね。だから巨大なシステムを批判するということには少し危うさもあって、それを別の同質なものと置き換えてもしょうがない。じゃあシステム的じゃないものといったら人間的ななにかです。このシステムにのらない何かでこのシステムを微調整したり、そこから距離をとってシステムから自律した「スキマ」を作ったりというやり方をするしかないのかなと思います。そこが「うしろめたさ」からできることなのかなと思いました。

食堂付属大学
藤原 なるほど。あと、うしろめたさってそれを感じる相手がいないと成立しないですよね。
松村 はい。祖先にせよ、友だちにせよ、対象があってそこにふっと共感することから生まれる感情です。しかもそれは体のなかから湧き上がるような身体的なもので、システムにとってはノイズなのかもしれない。でも、そんなうしろめたいと悩む存在であることで、他者に呼応して動く身体的な共感のネットワークを作ってきたんだと思います。藤原さんが食べ物に注目されたのも、そういう部分がありますか?
藤原 そうですね。誰もが食べずには生きていけないし、食べたら出るということは避けられません。でもその単純さゆえに強い部分もある気がします。
辺見さんの『もの食う人々』という本のなかで、辺見さんはチェルノブイリで汚染された野菜を一緒に食べることでそこの農民たちの心に迫ろうとしていきます。食べることであの事故の遺産を一緒に吟味していくんですけど、最後の最後でタイの大衆食堂の話が出てきて、ここでは老若男女どんな身分の人も宗教の人も大きな口を開けて食べ物をバリバリ胃袋に押し込んでいる。そのときだけ唯一人間は連帯できるかもしれないと感じた、と書いているんですね。
松村 面白いですね。そして藤原さん自身も食べることに関する活動をされていますよね。
藤原 はい。滋賀のおかあさんたちとごはんを持ち寄って食べながら話をする集まりに参加させてもらってるんですけど、そのネーミングを考えるときに「食堂付属大学」というのを考えました。それをもとに『戦争と農業』という本ができました。付属するものってだいたい下につくんですけどこれを上に持ってきたらなにかまた違った世界が見えてくるんじゃないかと思って。例えば京都大学にはルネという学食があるんですけど、「ルネ付属京都大学」となるわけです。だからごはんを出しているおばちゃんが先生で食べている教員が生徒なんですよ。
松村 そのひっくり返しっていうのは藤原さんの得意技で、鮮やかに僕らが考えていることをひっくり返してくれるんですよね。どちらが本質なんだという話になったら、それはもう食って生きていくことが本質だと。「食堂付属国会議事堂」とか。政治家がああだこうだ言ってるより、食って命を回していくほうがメイン。でも今やその本質が忘れ去られている気がします。
藤原 そうですね。そしてもちろん食べるための食堂も大切なんですけれど、人間を一本の管だとすると、出すところであるトイレも大切なんですよ。今の水洗トイレにしても、最終的には自然に帰らせるわけですし。
松村 そうすると、「食堂・トイレ付属大学」になりますね。
藤原 はい。僕はトイレで言葉の使い方、リズムを学んだと言っても過言ではないです。
松村 どういうことですか?
藤原 昔の大学のトイレって、落書きがしてあるじゃないですか。しかもそのレベルがいちいち高いんです。一番覚えているのは「カミに見放された。ウンを掴め。」と書いてあるんです。そういうすごい表現力を学びました。
松村 すごいですね(笑)

パーテーションはいらない
藤原 あと、食堂の話で言えば、京大の食堂がまず劣化したのはパーテーションが設置されたことだと思います。私は同じテーブルで見知らぬ人の顔を見ながら食べるのが趣味だったんです。「ささみチーズカツ」が大好きなんですけど、あれ食べてる人がいたら、思わず話しかけたくなっちゃう。
松村 いいですねえ(笑)
藤原 でもパーテーションがついたことでそういう対面性が発生しなくなってしまって。僕はそれはある意味劣化というか、おかしいなと思います。
松村 本当にそうですね。これは藤原さんが「紙版ミシマガジン夏号」(ミシマ社サポーターに送っている季刊誌。サポーターのお申し込みはこちら!)に寄稿されているんですけど、昔は食堂にもっと複合的な機能があったという話が印象的でした。例えば大衆食堂で食べるときにそこで政治談議もするとか。
藤原 そうです。昔の食堂は機能的でしたね。『居酒屋の世界史』という本があるんですけど、それによれば、中世のヨーロッパの居酒屋というのはそこでボーリングをしたり、ボクシングしたり、ひげをそったり、何でもできる場所だったんです。近代になってそれらが専門化していくんですけど。パーテーションで区切るっていうのは、そういう余計なことが生じないようにっていうことなんですよね。
松村 なるほど。京都来たときに思ったんですけど、関西は政治談議しているおじちゃんおばちゃんが多くて面白いですね。昔はそうやっておじちゃんおばちゃんが話し始めたら皆そこに加わってたと思うんですよ。人間が顔を突き合わせて物を食う場であれば、当然いろんな言葉が交わされて、喧嘩もあるかもしれないけど、面白いことも生まれる豊かな食の場になったと思います。でも今は、例えばイスが壁に向かっているとか、空間的な制約があって、そういう話したいという気持ちを抑え込むような仕組みになっている。
藤原 うんうん。例えば、昨日入った居酒屋で中国の観光客と一緒になったんですけど、僕が食べてたサンマが美味しそうだったみたいで、これと同じのくださいって英語でおっしゃってて。そのあと僕の顔をちらっとみるので「これすごくおいしいよ」と一生懸命言ったりするというのはパーテーションがあるとできないことです。
革命家ではなく、はみ出しの生活者
藤原 松村さんの本のなかで印象的なのは、エチオピアから帰ってきて関空に到着した瞬間に全部が自動的に済んでいくことに驚いているところです。エチオピアではすべてが面倒くさいと。
松村 そうです。荷物は出てこないし、換金しようと思ったらずっと窓口のおばちゃんたちが喋ってるんですよ。
藤原 換金できないんですか?
松村 いや、一人は働いているんですけど、あとの三人はずっとしゃべっているんですよね。分担してやれば、この行列さばけるじゃんって思うんですけど。
藤原 それは近代的な考え方なわけですね。
松村 そう。彼女たちは今喋りたいんですよ。レストランでも、隣に座った中国の人が僕のことを同郷の人間と思ったのかチラチラとこっちを見て「お前と交流したい」ってメッセージを送ってくるわけです。僕は中国語話せないから困るんですけど(笑)。日本ではそういう感情を押し殺さないといけない。お互いに気づかないふりばかりしている。
藤原 なんでなんですかね?
松村 行儀がいいのかもしれないけれど、たぶんシステムが効率よくまわっているほうが心地いいんですよ。自分がシステムの阻害要因になってないかという自己規制の中ではみ出すことを怖れる。我々もあえて大学の研究の世界からはみ出てますよね。そのはみ出ることで「こういうやり方もあるんだ」とか、そういう実験台になればいいかなと思います。
藤原 たしかに、同志だ、仲間がいたというか、はみ出してもいいんだという思いがありますね。以前アメリカの社会運動家の公演を動画で見たことがあるんですけども、ある広場でひとりの男が裸で踊っているんですね。そしたらそのうちにその踊りが楽しそうに見えたひとりの男の人がそれに加わるんですよ。これがフォロワーです。その社会運動家は、「フォロワーは、一人の馬鹿を革命家に変える」と解説します。誰かがフォローすることによってはじめてその裸のダンサーが革命家になる。だから松村さんと僕は、どっちが先かわかりませんが、お互い違う場所で踊ってたんだという感覚はありますね(笑)。
松村 嬉しいです。たぶん大変革を起こす「革命家」というよりも、「はみ出しの生活者」くらいでいいかもしれませんね。その踊り加わる人びとは、カリスマ的な革命家をフォローするまた別の革命家ではなく、普通の人が日常の暮らしのなかで、それぞれにはみだしていくイメージで。
藤原 そうですね。
松村 さっきのパーテーションなんかもそうですが、私たちの共感の回路を遮断しているものから、少しはみ出してみる。みんなで少しずつそれをやっていれば、「革命家」に頼らなくとも、凝り固まった社会を動かしていけるように思います。

プロフィール
松村圭一郎(まつむら・けいいちろう)
1975年、熊本生まれ。京都大学総合人間学部卒。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。岡山大学大学院社会文化科学研究科/岡山大学文学部准教授。専門は文化人類学。エチオピアの農村や中東の都市でフィールドワークを続け、富の所有や分配、貧困と開発援助、海外出稼ぎなどについて研究。著書に『所有と分配の人類学』(世界思想社)、『文化人類学 ブックガイドシリーズ基本の30冊』(人文書院)がある。
藤原辰史(ふじはらたつし)
京都大学人文科学研究所准教授。1976年、北海道生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程中途退学。京都大学人文科学研究所助手、東京大学大学院農学生命科学研究科講師を経て現職。専門は農業技術史、食の思想史、環境史、ドイツ現代史。著書に『カブラの冬』(人文書院)、『稲の大東亜共栄圏』(吉川弘文館)、『[決定版]ナチスのキッチン』(河合隼雄学芸賞受賞)、『食べること考えること』(共に共和国)、『トラクターの世界史』(中公新書)、『給食の歴史』(岩波新書)など。
編集部からのお知らせ
【11/7】ちゃぶ台Vol.4発刊記念 トークイベント
出演:松村圭一郎×三島邦弘
『うしろめたさの人類学』(ミシマ社)の著者でもあり、『ちゃぶ台Vol.4』には「人間の経済 商業の経済」をご寄稿くださった松村圭一郎さんをお招きして、編集長三島邦弘との対談イベントが実現します。
■タイトル:人間の経済をとりもどす!
■内容:『うしろめたさの人類学』でいきづまる世界に「スキマ」を空けた松村さん。年一度刊行の雑誌「ちゃぶ台」で、すでに始まっている未来の種をレポートする三島さん。ふたりが共通して求めるものに、「人間の経済」があります。「人間の経済 商品の経済」を『ちゃぶ台Vol.4』に寄稿した松村さんの考え、そして意図とは? 三島さんが雑誌づくり、出版社運営を通してめざす「経済」とは? 無二の親友でもある二人がこの日、ぞんぶんに語り合います。また、「ミニブックトーク」の時間を設け、「人間の経済」を取り戻すために必読といえる本も紹介してもらう予定です。
■開催日:2018年11月7日(水)
■場所:恵文社一乗寺店
〒606-8184京都市左京区一乗寺払殿町10
【11/23】ちゃぶ台Vol.4発刊記念 トークイベント
出演:松村圭一郎×三島邦弘
さらに岡山でも、松村圭一郎さんとミシマ社代表三島邦弘による対談イベントが開催決定!
■タイトル:もういちど「近代」を考える:次の『ちゃぶ台』Vol.5はどうなるの?
■内容:雑誌『ちゃぶ台』で、つねに時代の流れのその先を見つめてきたミシマ社代表の三島邦弘さん。今春、スロウな本屋で日本の近代を問いなおした石牟礼道子作品の寺子屋をはじめた松村圭一郎さん。
20年来の旧知の仲であるお二人が、いまあらためて「近代(菌代?)」について語り合います。『ちゃぶ台 Vol.4「発酵×経済」号』が発刊されたばかりですが、お二人の目は、もう次の Vol.5 で何を世に問うかに向けられています。さて、お二人は「近代」という時代をどう乗り越えようとしているのか? 岡山の地で、はじめてその先の話があきらかに!
■開催日:2018年11月23日(金)
■場所:スロウな本屋
〒700-0807 岡山県岡山市北区南方2-9-7


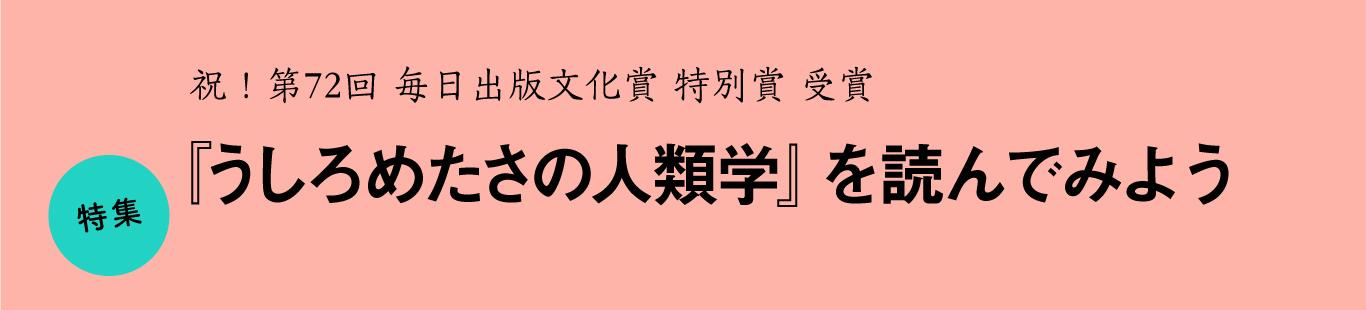
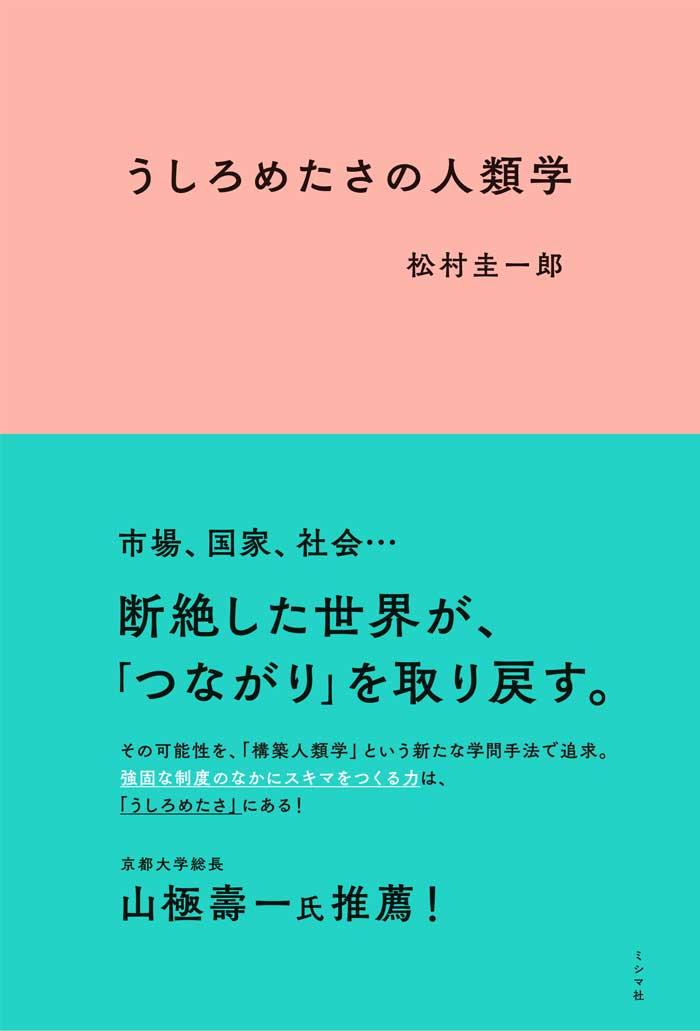




-thumb-800xauto-15803.jpg)
