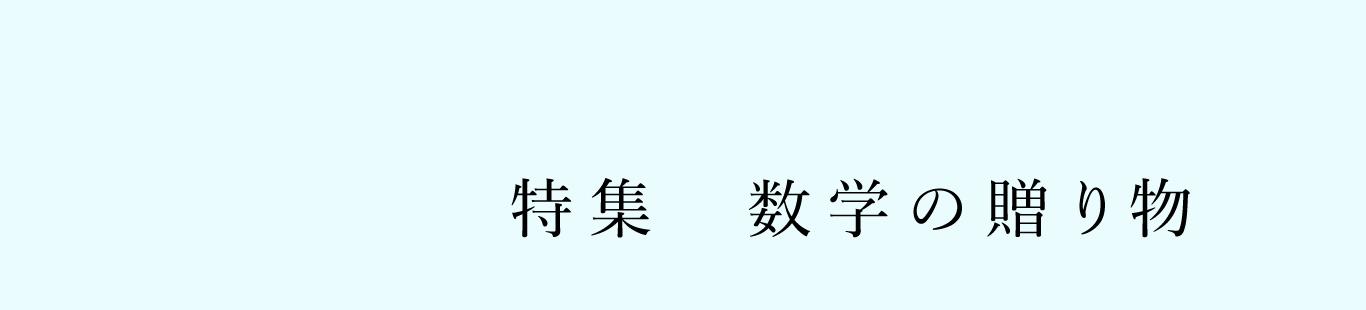第10回
森田真生さんに発刊直前公開インタビューしました。
2019.03.20更新
冒頭から司会の私(三島)をはるか後方に置いてけぼりにして、語りまくる森田さん。
「数学の贈り物(a mathematical present)」という言葉に込めた思い。
あとがきで書かれた「贈り」の意味についてなどなど、それだけで数冊の本になろうかという密度の話でした。
今回は、本書成立とライブの関係、エッセイと随筆の違いについて森田さんが語ったことをお届けします。
(聞き手:三島邦弘、構成:中谷利明、三島邦弘、写真:田渕洋二郎)
現代の「うたげ」はライブの場
―― 数学ブックトークをはじめ、ライブ活動の場での森田さんの爆発的なトーク量は想像を絶します。
それが本だと、かぎりなく削ぎ落とされて、選りすぐった言葉だけが最後に残っていっているというふうに感じます。「数学ブックトーク」などのライブ活動と本の関係は、森田さんのなかでどういうものですか?
森田 平安朝期の歌合にしても、江戸時代の連句にしても、あるいは古代の相聞歌にしても、日本の言葉は、小さく、親密な場のなかで育まれてきました。たとえば、芭蕉には、自分の句を、不特定多数の読者に向けて書いているという意識はおそらくなかった。あくまで、同じ座にいて、心が通い合っている人たちとともに、彼は言葉を紡いでいった。
だから、小林秀雄が岡潔との対談『人間の建設』のなかで、もし自分が芭蕉の実物を知っていたら、どれだけ彼の句を面白く読めただろうかと書いているんです。たしかに、芭蕉の句には、実物の彼と付き合った人だけにわかるニュアンスがあったのでしょう。彼はその機微を分かち合える人たちに向けて、言葉を紡いでいった。
不特定多数の人にではなく、心通い合う、親密な誰かへと言葉を贈っていくこと。詩人で評論家の大岡信さんは、詩的な言語が生まれるこうした場のことを「うたげ」と呼びました。芭蕉の言葉も、あるいはかつての宮廷の歌人の言葉も、すべて、背景には広い意味での「うたげ」があった。
「二人以上の人々が団欒して生み出すもの」すべてが「うたげ」だと大岡さんは著書『うたげと孤心』のなかで書いています。そこには、笑いの共有があり、心の感合がある。酒が入っているかどうかはどうでもいいんです。親密な、心通い合う者同士の集まりが「うたげ」です。その「うたげ」のなかで「孤心」を磨く。「うたげ」と「孤心」の緊張関係のなかからこそ、日本の詩的言語は生み出されてきたのだ、と大岡さんは指摘したのです。
では、現代においてうたげとは何でしょうか。僕は、こういうライブの場こそが、うたげだと思っているんです。ここでは、すべての言葉に宛先がある。同じ空間を共にして集まり、そこで言葉を分かち合う。
笑いが起きたり、緊張が生じたり、白熱したり、しんとなったり・・・。ひとつひとつの言葉に対して、自分を超えたものからレスポンスがある。こういう場で僕は言葉を模索し、思考を更新していく。「数学の贈り物」を書いているときの僕は「孤心」ですけど、書きながら、ライブの笑い声や、緊張感がありありと蘇ってくる。それはだから、僕の場合は決してレベルは高くないけど、それでも「うたげに支えられた孤心」と言っていいと思うんです。
ミシマ社とはじめて出会ったときに、この人たちとなら、素晴らしいうたげの場をつくっていけるんじゃないかと思った。出版社にライブの主催をお願いするのはおかしいと思われるかもしれないけど、僕にとっては、これはとても自然なことだし、三島さんも、同じように感じてくれたと思う。言葉を届けるだけじゃなくて、言葉を生み、育んでいくことすべてを含めて「本をつくる」ことだとするなら、言葉が生まれる「うたげ」から一緒につくっていこうじゃないかと。そういうことをこの五年間、僕はミシマ社のみんなとずっとやってきたんだと思うんです。

無に落ちていった言葉と残った言葉
―― この『数学の贈り物』、こういうかたちになってますけど、実を言うと去年の秋くらいまで違うかたちの本になる可能性があったんです。「数学ブックトーク」というイベントの、ちょうど1年前くらいの講演内容を一部収録しようかという話がありまして。実は去年の夏に、僕がひと夏かけてそれをまとめたんですよね・・・。
森田 三島さんがものすごい労力をかけてまとめたくれた文章を、僕は非情にも「うーん、ないですね」とお返ししてしまった(笑)。
―― そうなんです(笑)。それで単行本はエッセイだけにしようと森田さんから言っていただいて、「そうしましょう!」と。
森田 「ライブの延長の本というのはどういうことなのか」というのを「別冊」や「0号」というかたちでミシマ社のみなさんとひたすら模索してきたんですよね。それで、ライブのテキスト化を入れるかという話になったんですが・・・。いろいろなことを試しながら、ほとんどの試みは途中で捨てられていきました。
この本の冒頭で九鬼周造の「偶然性において、存在は無に直面している」という言葉を引用しましたけれど、この本が生まれるまでに、実にたくさんのものが無に転落しました。三島さんのひと夏も・・・(笑)。
―― (笑)。いえいえ、僕だけじゃなくて、森田さんも、「0号」のあとの冊子用に数カ月かけて書いておられた原稿は、結局かたちになってませんもんね。
森田 そう思うと、ほとんどのものが無に転落してるんです。
『数学の贈り物』の冒頭でも書いた通り、「無に直面しながら、無に転落することなく、偶々そうであったことのすべての果てに」この本は生まれた。でも実は、世界っていつもそうなわけですよ。いろんなことが、いままさにこの瞬間にも、どんどん無へと転落している。無に転落したものたちがたくさんあるからこそ、転落せずに残った「いま」に大きな力があるとも言える。存在は、無に支えられている。だから、三島さんの夏も無駄ではなかったわけです(笑)。
―― もちろんです(笑)!
エッセイか? 随筆か?
―― そして、エッセイだけを残そうと決めたわけですけど、最後の最後になって帯のコピーに、「著者初の随筆集」とつけました。「エッセイ」と「随筆」という言葉についてはどうとらえていますか。
森田 帯は、「随筆集」と謳われていますよね。
最初これを見たとき、なんで「随筆」にしたんだろうと思ったんです。僕は自分では、どちらかというと「エッセイ」かなと思っていたから。
「エッセイ」というのは、フランス語のessayerから来てますが、試みる(try)とか、挑む(attempt)というような意味の言葉ですよね。自分の仕事を最初に「エッセイ」と呼んだのはモンテーニュだと思いますけど、そこには「自分の思考を言葉にするぞ」という積極的なattemptの意志があります。
ところが、「随筆」の「随」というのは、自分を超えたものにしたがっていくということですよね。自分の意志で、「何かやってやろう」とか「何かを成し遂げてやろう」ということではない。
じゃあ、「数学の贈り物」はエッセイなのか、随筆なのかと、あらためて読み返してみると、一章の大部分は明らかにエッセイなんです。実際、書く前に構想をはっきりと決めて、それから「言葉」にしてやるぞと、挑む感じで書いてました。
ところが、だんだんこのやり方が苦しくなってきて、連載二年目になると行き詰まりを感じはじめた。それで、閉塞感を突破しようと、それまでとまったく違う仕方で書いてみたのが、一章の最後から二つ目の「白紙」でした。初めて、自分であらかじめテーマを決めずに、ミシマ社の京都オフィスで、原稿用紙とペンだけを持って、筆の流れに任せて書いてみたんです。いま思えば、殊更に挑んで随筆をやってるわけですけれど(笑)。結果的には、このとき生まれた文章が、ミシマガで連載するときの一番よいスタイルなんじゃないかと、「こういうふうに書ければいいのかな」と、手応えを感じたんです。
その後、息子が生まれたんですけど、それからは無理に「随筆」にしようと思わなくても、気づけば自分より大きなものに巻き込まれ続ける日々になった。おかげで、二章からはそれまでよりも自然に随筆の傾向が強くなっていると思います。
僕は、エッセイと随筆のどちらかが優れているとは思わないんです。トマス・カスリスさんというアメリカの哲学者が言っていることですが、文化には一般に、integrityを重視する文化と、intimacyが前景に来る文化がある。
integrityというのは、ラテン語のintegerと関連しています。integerというのは、整数のことですが、これはもともとin+tangereで、触れられないとか、不可分、不可侵という意味です。integrityを備えている人というのは、状況に流されない、一貫した原理(principle)に基づいて振る舞う人のことです。integrityを重視する世界では、変わらない原則を持っている人間が尊敬されるんですね。
他方で、intimacyというのは、心の奥深く秘めたもの(intimus)を親友(intima)に打ち明ける(intimāre)こと、とカスリスさんは解説しています。日本のように、intimacyを重視する文化では、状況に流されないことよりも、むしろ状況と合一化していくこと、春には春らしくなり、秋には秋らしくなってしまうような、造化随順の生き方が理想とされる。変わらないことより、適切に、自在に変容していくことの方が理想とされるわけです。
integrityを重視する文化では、書き手の主体的な意志を伴うエッセイがよしとされる。逆に、intimacyがベースにある文化では、随筆の方が自然な散文の形式になる。僕は、このどちらかだけを選び取るというより、バイリンガルに、というか、カスリスさんの言葉でいえばバイオリエンテーショナルに、両方をそのときどきに使い分けられるような仕方で言葉を紡いでいくのが理想なんです。
日本語がうたげのintimacyのなかで育まれた言葉だとすれば、数学は言語のintegrityを最もラディカルに追求してきた学問と言っていいでしょう。だからこそ、数学について日本語で書くというのは、とてつもなく難しい課題なんです。それでも、僕はその試みのなかから、intimacyをベースにしたintegrityというのを追求したい。『数学の贈り物』というのは、そういう思いで綴ってきた一冊でもあるんです。
四季の繊細な移り変わりとともにある京都の暮らしを「錘」としながら、日本の言葉を育んできた「うたげ」のintimacyを深め、同時に、数学を通してintegrityの感性を磨いていくこと。そうしながら、数学について随筆を書けたら、その過程で、数学も、日本語も、少しずつ新しい相貌を見せていくのではないか。僕はまだまだ「随筆」を書けていると自分では思わないのですが、理想であり、努力目標であることは間違いないんです。だから、三島さんがあえて「随筆」という言葉を選んでくださったとき、はっとさせられるとともに、何だか嬉しい気持ちになりました。

編集部からのお知らせ
森田真生さん出演イベント情報
3/30(土)森田真生さん「数学ブックトーク in 熊本 2019 春」
独立研究者・森田真生さんによるライブトーク「数学ブックトーク」、熊本で2年ぶり、2回目の開催が決定いたしました! 今回は、3月20日刊行予定の森田さん新刊『数学の贈り物』刊行直後の開催。本の執筆、制作にまつわるお話もうかがえそうです。熊本、そして九州のみなさま、ぜひぜひふるってご参加くださいませ!
■日程:2019年3月30日(土)14:00~(開場13:30~)
■会場:長崎書店3 階 リトルスターホール
■定員:80 名様
■入場料:3,500 円(税込) ※学生・ミシマガサポーターは3,000 円(税込)
4/7(日)森田真生さん×甲野善紀さん「この日の学校 in 京都」
独立研究者の森田真生さんと武術家の甲野善紀さんが全国で開催してきた「この日の学校」。今年もまた、ミシマ社主催で開催させていただく運びとなりました。テーマは、「偶然の贈り物」です。
■日程:2019年4月7日(日)14:00~(開場13:30~)
■会場:永運院(京阪 神宮丸太町駅から徒歩20分)
〒606-8331 京都府京都市左京区黒谷町33
■定員:80名様
■入場料:5,000円(税込) ※学生・ミシマガサポーターは4,500円(税込)