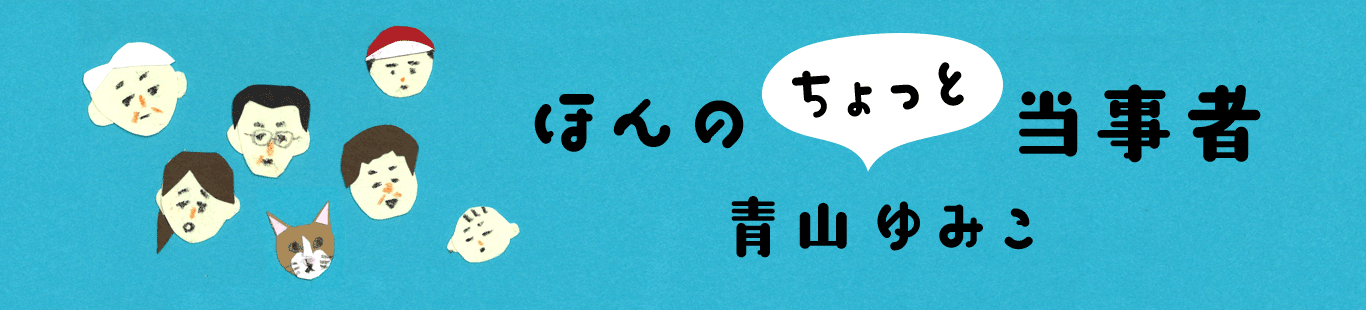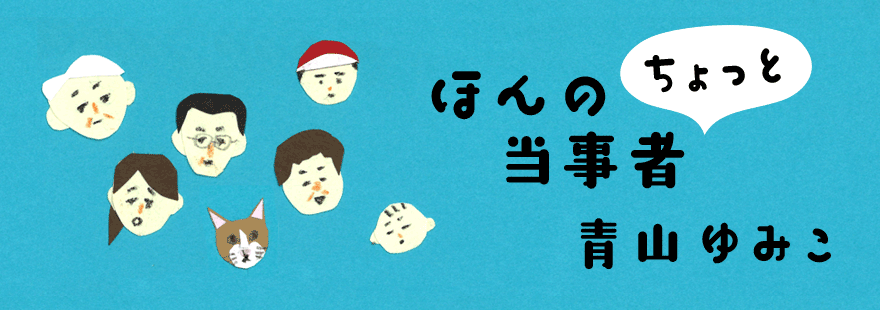第1回
暗い夜道と銀行カードローンにご用心。(1)
2018.06.08更新
お知らせ
この連載が本になりました。ぜひ書籍でもご覧ください。
『ほんのちょっと当事者』青山ゆみこ(著)
自己破産しかけたことがある。
内閣府景気基準日付でのバブル景気後退期は、1991年3月から1993年10月までとされているが、その真っただ中の1993年の春に、わたしは大学を卒業して地元神戸のアパレルメーカーに就職した。
毎月の給与は銀行振込みと決まっていて、わたしは「社会人になる」と同時に生まれて初めて自分の銀行口座を持つことになった。現在では二度の合併を経て名称が変わったが、当時は三和銀行と呼ばれていた、後に3大メガバンクの一つとなる大手都市銀行。キャッシュカードは、シンプルなものとスヌーピーの柄が選べて、普段はキャラクターものにまったく興味がないのになぜかスヌーピーを選んだ。大手銀行で「お客様」として扱われてどこか舞い上がっていたのかもしれない。
担当のお姉さんは、普通預金口座の開設とともに、積立式定期預金なんかも勧めてくれて、わたしの将来を親身に考えてくれているようだった。そんな彼女が熱心に説明してくれたのが、新社会人向けのクレジットカードだった。25歳くらいまでの入会ならこの先もずっと年会費が無料で、いくつかの特典があり、使わなくても何の損もない。でも何かあったときにとても便利だし、海外旅行の際には身分証明ともなるという。そんなに良いものならとりあえず、と気軽な気持ちでクレジットカードをつくった。
何かあったとき、はほどなく訪れた。
最初は、働き始めて半年ほどが経った頃、秋冬ものが店頭に並び始めて一目惚れしたコートか何かだったと思う。勤めていた中規模のアパレルメーカーの入社一年目の月給は、手取りで17、18万かそこらだったと記憶している。まだ貯金もほとんどない。スヌーピーのカードで銀行口座から現金を引き出して、月収の半額近いそのコートを手に入れてしまうと、翌月の給料日まで手元に現金がなくなってしまう。
諦めようとしたわたしに、ショップのお姉さんはカード払いも可能だとにっこり笑った。
「今ならボーナス一括でもいけますよ」
ぼーなすいっかつ?
まだクレジットカードの機能をよく理解していないわたしに、翌月払いとなる1〜2回の分割払いなら無金利(利子がつかない)で、ボーナス支給月の返済となるボーナス一括払いにも利子がつかないというのだ。つまり現金で買うのと同じ条件で(何の損もなく)、今すぐにそのコートを手に入れられて支払いは3カ月も先延ばしできる・・・まるで夢のようなボーナス一括。
驚き、激しく心を動かされて、まだもらったことのないボーナスの金額も知らずに顔がにやけているわたしに、お姉さんはご丁寧にもリボ払いというシステムまで教えてくれた。毎月定額の少額返済なので負担が軽いという。「ただ、ちょっと利子が高いけど・・・」という声はわたしの耳には届かず、少しずつ返せばいいなんて、なんという親切なシステムなのだろうと感動した。
一度やってしまえばクセになる。
わたしはクレジットカードを躊躇なく切りまくるようになった。欲しいものがあれば気軽にとりあえず購入して、気がつけば分割払いにボーナス一括、リボ払いを組み合わせて、月々の支払いを調整する高度な技を駆使し、「何かあったときのための」カードが何もない普段の生活に欠かせなくなり、スヌーピーのキャッシュカードを使う暇がないほど普通預金口座はたいてい空っぽで、通帳記入をすると、給料日の欄だけ瞬間風速的に数字が上がって、下がっていた。
欲しいものが手に入っても、現金が手元にないというのはなかなか不便だ。
思案してひらめいたのが、別の会社のクレジットカードを作ることだった(おいおい!)。正社員で毎月のカード支払いに滞りがなく、同居している親は不動産(実家)を所有しているという条件のわたしは簡単に審査に通り、新たに2枚のカードを持つようになると、3枚のカードを手裏剣のように切りまくった。クレジットカードは無尽蔵に湧く油田のようにも思えた。しかし再び徐々に資源は枯渇した。
そんなとき、マイバンクである三和銀行からカードローンの案内が届いた。通常のキャッシュカードによる現金の引き出しや、カード利用代金の自動支払時に預金残高が不足する場合、カードローンを申し込んでおけば口座から自動融資されるという、これまた夢のようなシステムだった。迷いもなく申し込んだ。すぐさま融資用の新しい通帳が送られてきた。いきなり50万をプレゼントされたような気分になった。すげーよ。
ほどなく普通預金口座で不足した金額がカードローン口座からがんがん引き落とされていったが、痛くも痒くもない。実感もない。動いているのは通帳に記された数字でしかないからだ。無感覚に身の丈に合わないお金を右から左へと動かした。思春期にぼんやり眺めていたバブルの風景や残り香がそうさせたのだろうか。いや、ただのバカだった。
1995年1月17日、阪神・淡路大震災が起きた。わたしの暮らす神戸は大変な状況になった。実家は神戸郊外で一部損壊だったが、職場はポートアイランドという人工島にあり、公共機関が復旧するまでは潰れた誰かの家をタイヤで踏みながら車で三宮まで出て、神戸大橋を歩いて渡った。人工島は地盤が沈下し、液状化で約50%が泥に覆われた。市街地にあった百貨店もブティックも倒壊などの大きな被害を受け、当然だが買い物どころではなくなった。
地震が起きて3週間ほどが過ぎた頃だっただろうか。まだまだ余震に怯えながら三宮を歩いていると、地震前月の12月にバッグを購入したショップが半壊し、営業を停止しているのが目に入った。崩れた建物にも強いショックを受けたが、同時に「じゃあ、ここのはカードの支払い請求も、もうこないかも?」とわたしの心に差し込んだ明るい光のそのどす黒さを今でもぞっと思い出すことがある(当然のことながら請求は来た)。その瞬間、わたしの中では「支払い」の方が地震による被害よりも重要だったのだ。お金にはそういう力がある。
震災から2、3年ほど過ぎた頃、勤めていたアパレルを退職した。何のビジョンも持たないままに。理由は山のようにあるが、次々に変わるトレンドを追いかけて服を作る行為は、自分を消費されているようで疲れてしまっていた。深夜2時まで当たり前のように行われていた残業状況をハローワークで告げると、失業保険は即時に発給され、ほどなく働いていた当時の給与の3分の2ほどの金額が口座に振り込まれた。雀の涙のような退職金も出た(と思う)。当面はそれでしのいでいた。
しかしながら、当時のわたしは既に火車であった。まったく根拠なく「なんとかなるだろう」と構えていたが、首は一ミリたりとも回るような状況ではなかった。支払いが滞り始めると、クレジットカード会社から最初の頃はやんわりとした文面で支払いを促され、どうすることもできずに放置していると、がんがん電話がかかってきて追い込みをかけられるようになった。それは生まれて初めて体験する、胃が締め上げられるような嫌な苦しさだった。何をしていても気持ちは重たい。お金がないというのは、怖くて辛いことだった。
電話口のお姉さん(かおばさんか知らんけど)は、意外や親身に相談にのってくれた。やんわりとした口調で、さまざまな提案をしてくれた。
とはいっても要約するとこうだ。
分けて払ろてもええよ。
親とか家族になんとかしてもらえや。
他のクレジットカードでキャッシングでもして返せよ。
とにかくなんとか用立てろやー。
借りたものは返さねばならない。どこにも逃げ場のない正論である。残念ながらクレジット会社からの提案のすべてがミッションインポッシブルで、正直にその旨を打ち明けた。そして恐る恐る訊ねた。
「どうやっても返せない。そうなったらどうなるんですか?」
お姉さんは最後通牒のように言い放った。
「自己破産ですかねえ」
「じこはさん? それをしたら、もうお金返さなくていいんですか?」
「個人の場合は、自己破産手続きにより免責許可決定が出ると、借入金の返済などの責務はなくなります」
「じゃあ、自己破産しますっ」
電話口には明るい声が響いただろう。正直、単語の意味すら理解できなかったが、これでもう支払いに追われる生活に終止符が打てる。そのことが心底嬉しかった。
「では自己破産の手続きのために、お客様の実印をご用意ください」
じついん?
この単語も初めて聞いた。普段使っている銀行印でも良いけれど、住民登録をしている地方自治体に登録した印影を押した判子でなければいけないという。わたしが自己破産のために最初に与えられたミッションは印鑑登録だ。簡単なことである。
翌日、地元の区役所の窓口で実印登録の申込みをすると、意外な事実が発覚した。わたし名義の印鑑登録はすでになされており、二重には登録できないというのだ。再登録するには現在の登録印が必要だと、区役所の職員さんは、バカ面をした26歳の女の顔を不審げにのぞきこんだ。