第5回
奪われた言葉(1)
2018.09.20更新
お知らせ
この連載が本になりました。ぜひ書籍でもご覧ください。
『ほんのちょっと当事者』青山ゆみこ(著)
今年の初めから、地域の寄合場を立ち上げて、月に1回細々と活動している。その一環として、以前よりやってみたかった「子どものための作文教室」を企画したのがこの8月のこと。
折しも子どもたちは夏休みで、読書感想文の宿題が出る。それを一緒に書いてみよう、という一石二鳥的なゆるっとした案配だ。
しかしなんとも間の悪いことに、予定日の前週、わたしは肺炎に罹患し、点滴による通院治療とその後の静養を余儀なくされた。
肺炎にもいろんな種類があり、感染力の強いものもある。不幸中の幸いかわたしはそのタイプではなかったが、抗体をまだ多く持っていない子どもに、もし肺炎ウイルスなんて伝染しでもしたら・・・というわけで、何人かで集まって行う教室にスタイルから変更して、それぞれの父兄を通じてやり取りをするいわば通信添削講座へと移行することになった。
参加者は少数限定だったが、熱心な子がいて、彼らとは最終的に三度のやり取りをさせてもらうことになった。子どもを育てたり、生活を共にした経験のないわたしには、手紙とはいえ、10歳ほどの子どもたちと生の言葉で対話を重ねることは、とても新鮮で刺激的でなにより驚きが多かった。
子どもらしい独創的な考え方に触れた、などとよく聞くようなありきたりの感想を抱いたわけではない。
子どもとはいえ、彼らはすでに一人ひとりがまったく異なる性質と考え方と感情を持っている。「小学5年生」とか「小学生男子」などでは括ることのできない、それぞれが一人の独立した人間として存在しているのだ。
ある意味、社会に飼い慣らされた大人よりも「個体」としてユニークだ。
それを実体験として知ることは、愉快でとても興味深かった。
フリーランスになって10数年、プロになりたい人を対象としたライティング講座の講師を定期的につとめており、ある意味「読むこと」にも「書くこと」にも擦れてしまったわたしだが、子どもたちとのやり取りは自分にとっても貴重な体験となった。
今回は、たまたまの流れで小学校5〜6年生を対象としたが、今後は中学生や高校生といった思春期ど真ん中の子に「思いを言葉にする」場がつくれたらとも考えている。
そんなことを考えるようになったのは、4年ほど前のある出来事があってからだ。地元の地方裁判所で、ひょんなことから、とある事件の裁判を傍聴した体験に遡る。
蝉の合唱がおさまりかけていた晩夏のある朝、大きな締切を抜けたところでいつになくのんびり新聞を眺めていたら、気になる記事が目に飛び込んだ。その前年に、ネットカフェで出産した男児を窒息死させたという女の初公判がその日から始まるという内容だった。
わたしはその事件をよく覚えていた。事件現場となったネットカフェや、嬰児の遺体を隠していたというコインロッカーの近くを自転車でよく通っていたからだ。
プライバシー保護のため一部を伏せるが、その事件について当時こんな記事が報じられている。
〈ネットカフェで出産〉男児死なせた『住所不定・無職』29歳女を逮捕
ネットカフェで産んだばかりの男児を殺害したとして、兵庫県警は●日、住所不定の無職、A容疑者(29)を殺人の疑いで逮捕し、発表した。「殺すつもりは無かった」と殺意を否認しているという。
捜査1課によると、A容疑者は●月●日午後1時20分ごろ、神戸市●区●丁目のネットカフェの女子トイレで出産後、男児を窒息死させた疑いがある。捜査関係者によると「泣き声を上げたので、とっさに口をふさいだ際、指を口に詰め込んでしまった」と話しているという。
A容疑者は翌●日に遺体をポリ袋に入れて●●駅近くのコインロッカーに遺棄したとして●月に死体遺棄容疑で逮捕、起訴されている。数年前から神戸市内のネットカフェなどを転々としていたという。
ーー朝日新聞デジタル某日配信ーー
手帳を繰ると、ぽこっと予定が空いていた。わたしはライターではあるが事件記者ではない。裁判を傍聴することも初めてだ。恐る恐る公判が行われるという地方裁判所に電話で問い合わせると、担当の部署の人が、公判開始時間と部屋番号まで丁寧に教えてくれた。
そうやってわたしはその日の午後から、まだ日差しのきつい太陽の下、自転車を20分ほど漕いで、神戸地方裁判所に3日間通うことになった。
前述の新聞記事に補足すると、彼女が手にかけたという赤ちゃんは、家出を繰り返した挙げ句、ネットカフェなどで寝泊まりしながら、お金に困ると援助交際を繰り返した結果妊娠したという、誰が父親ともわからない子だという。
ネットカフェのトイレで出産後殺害。息絶えた嬰児をコインロッカーに遺棄した30歳の女(事件当時は29歳)。そんな衝撃的な事件がわたしの身近な場所で起きていたという事実。
文字をなぞると鬼畜とも思える行為への憤りはもちろんだが、人が亡くなっているのに無神経な言い方になるが、「いったいどんな女なんや。顔が見たいわ!」という好奇心も正直あった。
ただ、さらにいうと「なぜ、そんなことに?」という疑問がなによりも大きかった。
これが15、16の女子ならまだわかる気もする。でも30にもなる女だぞ。そんな年齢ともなれば、自分で何らかの手立てを講じることくらいできたはずだ。それなのにこんな結果を生んだのには、よほどの事情があるのかもしれない。そのあたりに、数年前から関心を持っていた「女性の貧困問題」との関連をぼんやりと感じたのもある。
初公判の場。
手縄をつけてうなだれながら法廷に入ってきたA被告(以下、仮名でクミさんとする)は、わたしが持っていた援交を繰り返し妊娠する無責任な女というイメージからほど遠い、派手さの欠片もない、こう言ってはなんだが、地味すぎるほどに地味な女性だった。体型は細身ではないのに、影の薄さというか、あまりの存在感のなさにとても驚いた。
まず検察側の冒頭陳述が行われた。
タイトなダークスーツをすっきりと着こなした、見るからに効率よく仕事のできそうな女性検事(推定だがクミさんと同年代か少し上くらいに見えた)は、長めの黒く艶やかな毛を耳にかけ直しながら資料を読み上げて、クミさんがトイレで出産した男児の産声が漏れないように口元を覆った際に、左手の人差し指が口の中に入り、鼻も覆ったことを指摘した。
そうした行動により男児が弱ってきたことを認識しながら、5〜10分もの間、口や鼻を塞ぎ続け、その後も生かそうという行為を一切していないというのが殺人罪についての主張だ。
対して弁護側は、クミさんは口に手を当てただけで、それが男児の死を招く危険な行為とは思っていなかったと反論。
弁護人質問でクミさんは、手を当てたのはそこがネットカフェのトイレであることから、周囲に泣き声を気づかれたくない一心だったこと。手は口にかぶせる程度で鼻を圧迫した感覚はなく、男児が息をしていないことに気づいてパニックになったと、殺意を否認した。
また、検察側が読み上げた供述書について、そのようなことは発言したかもしれないが、取り調べに疲れていて、細かいところはよく覚えていないこと。読み上げられた文章も「(正確には)自分の言葉ではない」とかすかに反論した。
裁判のあいだ、クミさんは終始すでに何かに書かれた言葉をなぞるように、力なく声を発していた。その姿がわたしを落ち着かせない気分にした。
「殺意を否認する」という今後の人生に大きく関わる重大な課題を背負っているのに、なぜもっと自分の気持ちを、自分の言葉で伝えようとしないのだろう。
裁判慣れしていないわたしがわかっていないだけで、裁判での発言とはそういうものなのだろうか。
公判中、そんな彼女が一度だけ声を語気を荒くしたことがあった。
援助交際で複数の異性との性交渉を繰り返しながら、なぜ避妊をしなかったのかと検察側に詰問されたときのことだ。
通常は男性に避妊具を装着してもらっていたが、拒否されることがあり、自分の立場の弱さから、強く避妊を要求することができなかったと彼女は答えた。
その無責任さが事件を招いたのではないか。もし妊娠しても、早期に人工中絶など他に策を講じていれば、今回のようなことにはならなかったのではないか。女性検事は畳みかけた。
「中絶は一度もしたことがありません!」
それは公判中に耳にした、最も強い彼女の発言となった。
わたしは驚いた。結果として一人の人間の命を奪い、そうした行為に対する糾弾には覇気なく応えるだけなのに、人工中絶に対しては強く否定の意思を示す。意味がわからなかった。
その理由を後に少し理解することになるが、今は先を進める。
公判では、検察側の証人はおらず、弁護側が申請した二人の証人だけが証言台に立った。
証人の一人である医師は、新生児は鼻からしか呼吸しないことを指摘し、口を覆ったことが窒息につながるとは確証できないと説明した。
もう一人の証人は、女性と子どもを支援するNPO団体に所属する女性(仮にタケダさんとする)だった。タケダさんは、クミさんが逮捕・拘留以降に、弁護人の依頼によりクミさんと初めて関わるようになった人で、裁判までに面会を13回、21通の手紙をやり取りしたという。
タケダさんは事前に弁護人と相談して決めていたのか、クミさんの生育環境や、思春期における親娘関係について重点を置いて証言を進めた。次第にクミさんの生い立ちが浮かび上がってきた。
希望していた公立高校受験に失敗し、母親の期待に応えられなかったというのが彼女の最初の挫折だった。同時に、学費の高い私立に行かせてもらった恩義を両親に感じたという。
母親のしつけはかなり厳しかった。中学時代から門限を破ると、激しい体罰を受け、ベランダに放り出されることも少なくなかった。高校時代も同様に過剰に母親から干渉を受けた。
だからといって仲が悪かったわけではない。買い物に一緒に出掛けたりもしているし、母親は兄にも同様に厳しい教育をしていたという。
高校卒業後、医療関連の専門学校に進学したが、父親の事業が破綻し、経済的な事情により退学せざるを得なかった。そこでも彼女はまた挫折を感じたという。自己破産をした父親と母親は離婚し、彼女は母と同居することになった。
それまで以上に過干渉となる母親との生活のなかで、進学の道も閉ざされたクミさんは、次第にそこから逃げ出したいという思いを強くする。それが、その後の家出癖へとつながった。
何度かの家出の後、キャバクラで働きはじめた頃、ホストの男と付き合うようになった。ただし、キャバクラ嬢として派手に稼いで客として貢いだというのではない。単に路上でナンパされたのが出会いだという。
初めて受けた異性からの優しい言葉に、彼女は幸せを感じた。ほどなく、男は、自身の出身であるという北関東に戻らなくてはいけないという話を彼女に持ちかけた。クミさんにも一緒について来て欲しいと。
だが、心を躍らせていた男との新生活で待っていたのは、恋人としての甘い時間ではなかった。彼女に与えられたのは、マンションの一室で客を取らされるデリヘル嬢としての仕事だった。報酬の半分は男が得た。クミさんは、初めて「騙された」ことを知った。
彼女をそこから救い出したのは、行方知れずの娘を連れ戻した母親だった。祖父の危篤という事情から、どうしてもクミさんを探し出さねばならなかったのだ。
一時的には、それは彼女にとって幸運だったとも想像できる。そのままでは男によってもっと過酷な状況に追い込まれたかもしれないからだ。
関西に戻り、母親の元で厳しい監視を受けながらも、彼女は職業訓練所に通うようになり、ホームヘルパーとして働くようにもなる。正社員にも登用されたというから、誠実な仕事ぶりだったのだろう。その仕事をしていたときが一番楽しかったと彼女は小さな声で語った。
だが、もとより折り合いが悪い上に、家出、売春と転落した(としか思えない)娘に対する母親の態度は以前より硬化し、繰り返し過ちを責められ、体罰や叱責は激しくなる。その日々に耐えられず、彼女はせっかく得た職も放り出して、また家出を繰り返すようになってしまう。
そこで生きていくために選んだのが、援助交際という手段だった。


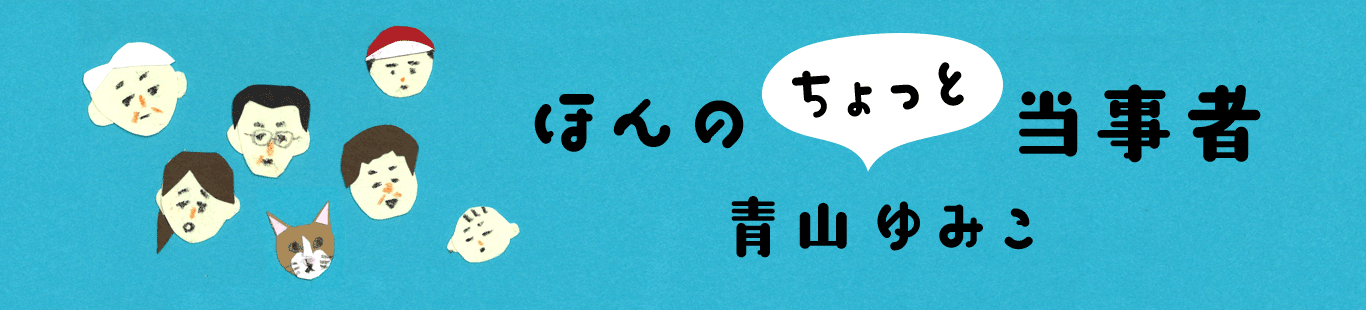
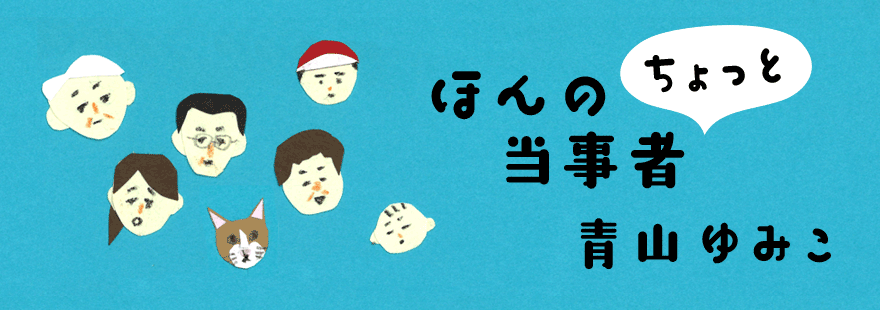



-thumb-800xauto-15803.jpg)


