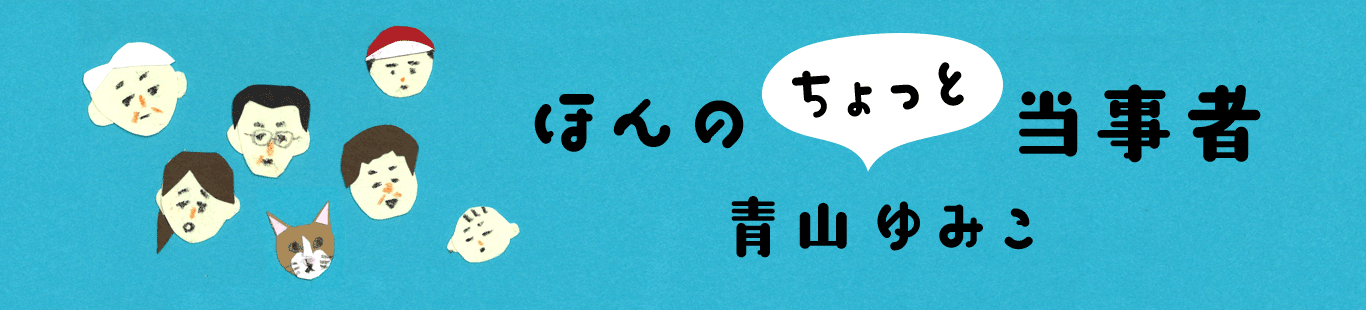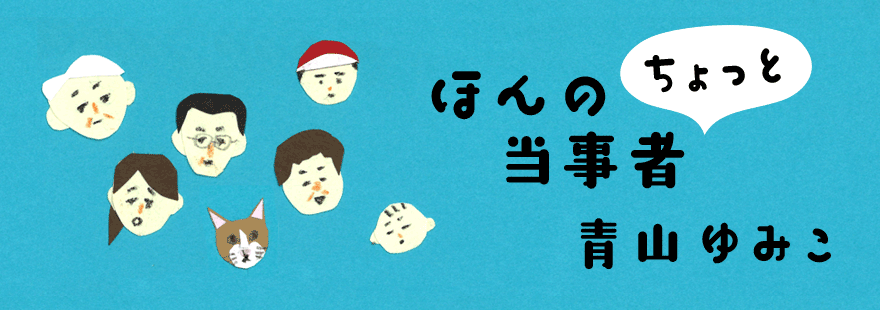第7回
あなたの家族が経験したかもしれない性暴力について。(1)
2018.11.14更新
お知らせ
この連載が本になりました。ぜひ書籍でもご覧ください。
『ほんのちょっと当事者』青山ゆみこ(著)
女だけで飲んでいるときに、ふとした流れで、子どもの頃や思春期に体験した性的に嫌な思い出話になることがある。
中高校時代の通学時の痴漢体験がごく当たり前のように、あるいは小学生の頃や、もっと幼く記憶もおぼろげな幼少期の体験などが、次々と女たちの口から吐露される。
世の男性が想像しているその何十、いや何百倍も(もっと多いかもしれない)、性的に不快な出来事を経て大人になっている女は多い。
そしてそれは、二十歳を過ぎてなお、続いている場合も少なくない。
2017年10月にジャーナリストの伊藤詩織さんが上梓された『Black Box(ブラックボックス)』にまつわる反響の大きさは、あえてここでは詳しくは触れないが、少しネット検索しただけでも、彼女の身に起きたレイプ体験と、それに対して彼女がどう行動したのかを知ることができるだろう。
同時に、彼女に対するひどいバッシングも目にするかもしれない。
伊藤詩織さんは、現在、イギリスを拠点にジャーナリストとして活躍されているという。なぜ日本ではなく、海外で?
性暴力や性犯罪の被害者が、顔や名前を公開して語ることで受ける誹謗中傷。ただでさえ心身ともに傷ついた状態を、さらにえぐるような、心理的、社会的ダメージを与えるセカンドレイプが、この国には蔓延している。
『Black Box』を一読すると、彼女が伝えようとしているのは、加害者に対する恨み辛みでないことにすぐに気づく。
身体的な暴力と同時に、彼女が『魂の殺人』と表現するほどの体験。本当なら誰にも言いたくない、思い出したくもないことを、なぜ性暴力の被害者としては異例の実名で公表したのか。その理由が抑制の効いた口調で理路整然と記されている。
被害者が口を閉ざし、ことの内容が隠蔽されがちな性犯罪について、彼女がジャーナリストとして選んだ方法は、自らの体験を語ることで予想されるリスクを負ってでも、真実を追求し、伝えることだった。
「密室」というブラックボックスが壁となり、被害者が泣き寝入りをせざるを得ない日本の法律の問題点や、社会の風潮。そして性暴力をオープンに語らせないこの国の、何だろう、空気感というか、見えない圧力のような何かを指摘しつつ、性犯罪の加害者が司法できちんと裁かれることを求めて。
残念、というには言葉が足りない。無念としかいえないことに、加害者であるその人物を司法で裁くまでにいたらなかった。その背景にあるさまざまな"ブラックボックス"。
『Black Box』は、まさにそのことを示唆する秀逸なノンフィクションだ。
折しも、2017年10月には、著名な映画プロデューサーであるハーヴェイ・ワインスタインによる、数十年に及ぶセクシャルハラスメントを、ニューヨーク・タイムズが告発した。
ハーヴェイ・ワインスタインといえば、クエンティン・タランティーノ監督作『パルプ・フィクション』をはじめ、アカデミー作品賞を受賞した『イングリッシュ・ペイシェント』など数々のヒット作をとばしている、ハリウッドの超大物プロデューサーだ。
そんな彼が、「俺にやらせたら役をやるぜ」とばかりに、20年もの間、数十人にもおこなっていたセクシャルハラスメントや強姦ともいえる行為は、ネットでちら読みするだけでもその下劣さに吐き気がしそうになる。
メキシコの女性画家の人生を描いた『フリーダ』を演じたサルマ・ハエックも、実名でハーヴェイ・ワインスタインのセクハラを告発した一人で、生々しい独白の日本語訳をネット上で読むことができる。
女優アリッサ・ミラノによるTwitter上の呼びかけで始まった「#MeToo」はソーシャル・ネットワーキング・サービスで、多くの女優たちだけでなく、ごく一般の女性(時に男性)を含め、セクシャルハラスメントや性暴力の被害体験を告白・共有する場を広げた。
そういう投稿や記事を読む度に、わたしは友人たちから聞いた話を思い出す。
友人の一人は、小学3年生の頃に、若い男に自宅近所の神社で、カッターナイフのようなものを突きつけられ、神社の裏に連れ込まれて、押し倒されそうになった(幸い助けを呼び、逃げることができた)。
もう一人は、小学校に上がるか上がらないかの頃に、公園の砂場で遊んでいたら、中学生くらいの男子(当時の彼女の記憶では)に声を掛けられて、ぼんやりついていくと、スカートをまくり上げられて、下着の中に手を入れられた。
二人目の彼女の場合は、何が自分の身に起きているかを理解するにはまだあまりに幼すぎた。ただ、もぞもぞと動く手が気持ち悪くて、怖くなって走って逃げた。
帰宅して母親に話をすると、母親は娘の服を脱がして風呂場に連れて行き、どうしてそんなことをさせたのかと叱責した。理由は分からないが、母親を怒らせるような何かをした「自分がよくない」のだと感じたという。
自分より弱い存在である子どもを狙った下劣な性犯罪だ。
成りゆき次第で、どちらにも13歳未満の女子に対する強制わいせつ罪が成立するだろう。一人目は命の危険さえあった。でも親には打ち明けることはできなかったそうだ。
2010年に警察庁が、東京・名古屋・大阪に居住し、通勤・通学のために電車を利用している16歳以上の女性2221人を対象に調査したところ、「過去1年以内に電車内で痴漢行為に遭った」と回答した女性は304人(約13.7%)。そのうち警察に「通報・相談」していないと回答したのは271人と発表している。
これは被害にあった女性の9割近くが泣き寝入りしたということを示している。
つまり、この文章を読んでいるあなたの娘も、電車で横行する痴漢行為をはじめ、こうした性暴力の被害に遭っている可能性は低くない。と、あなたが親なら考えるべきなのだ。それぐらい日本には性犯罪が多い。
人は、心を深くえぐられるように傷ついた体験であればあるほど、そのことを言葉に出せない。そんな女性が、日本だけでもまだどれほどいるのだろう。そして、人によっては自分を責めて続けているだろう。
中学時代、わたしのすぐ身近でもそうしたことが日常的に行われていた。そしてわたし自身にもグレーゾーンのような体験がある。
中学時代といえば、もう30年近く前になる。
その男はわたしが通っていた公立中学の保健体育の教師で、担任は持たず学年主任を務めていた。そして、わたしが所属していた女子バスケットボール部の顧問だった。
ずんぐりとした短躯だが、浅黒い肌に骨太で迫力のある体つきのA先生。煙草焼けした低い声と、彼自身がよくエピソードを語った「問題児の多い学校を渡り歩いてきた」経験が刻まれているのか、押し出しの強い顔つきをしていた。
若い世代には信じがたいだろうが、昭和50年代は、体罰は教育の一環としてとらえられていた。
とはいえほとんどの教師は手をあげない。でも、A先生は、まるで体罰のフリーパスを与えられているかのように暴力をふるい、他の教師は見て見ぬふりをしていたような印象がある。
わたしもバスケットの練習中に、どれだけの数の往復ビンタをくらったか思い出せない。また、A先生は常に竹刀を携帯することを好み、練習中の失態への罰として、お尻を竹刀で叩くことも常だったので、何度、お尻に青あざを作ったかも覚えていない。
昭和40年代から50年代は、地方都市の郊外に新興住宅地が続々と開発された時期だった。一気に増えた子どものために、次々と学校が造設された。通っていた公立中学もそんな一校で、わたしは7期生だった。
まだ卒業生を6回しか出していないのにかかわらず、A先生に率いられた女子バスケット部は、既に過去3回も全国大会に出場するという快挙を成し遂げていた。
ある種、その中学の花形である女子バスケット部には入部希望者が殺到し、わたしの学年だけでも30人近くが入部した。
入部してすぐに上級生と練習をするよう指示された一年生もいた。彼女たちは、小学校の頃からミニバスで活躍していたり、170センチ近い長身から、中学入学前にA先生がスカウトして入部させた「特別枠」であることは後から知った。
熱心な指導と、朝練、昼練、放課後の練習。土日はもちろん、夏休みは全日練習のない日が3日という、異常なまでの練習量。A先生は、前任校でもバスケ部顧問として実績があったらしく、中学女子バスケット界では有名な指導者だったようだ。
1学期が終わる頃には、1年生でも3段階のチーム分けがされ、時々、入れ替わりが行われた。熾烈な上下争いも勃発していたはずだが、向上心がなく、チームメイトが好きという理由だけで部活に参加していたわたしは、同じようにやる気のない仲間と共に、チーム3として呑気に過ごしていた。当然、A先生には嫌われた。
比較的新設校であるうちの中学の名を全国へと広めた功績なのか、態度と声のデカさからか、A先生が学内で「権力」を手にしていることは、生徒のわたしたちにも十分に察知できた。
職員室のデスクとは別に、職員の中でも一人だけ、体育館の一角にある「体育教官室」という名の個室を、私物化していたことも異例だった。
さまざまなセクシャルハラスメントはその「密室」で行われていた。
彼には数人の「お気に入り」がいた。
彼女たちを呼ぶ声には独特の甘さが含まれる。中学女子はそういうことに敏感だ。練習の合間に、A先生は練習法を指示して、しばしば体育教官室に引きこもることがあった。そういう時、マネージャーを通して「お気に入り」の生徒が教官室に呼び出された。
練習に対する指導というのは名目だったが、「お気に入り」の女子だけで交わされる目配せや、ときどき漏れ聞こえてくる「お菓子をもらって食べていた」「アイスクリームを一緒に食べた」といった教官室での話。
そのうち、幼児を抱っこするように膝に乗せられて、太ももをさすられた、髪や頬を撫でながら、「○○は可愛いから男子に誘われても気をつけないといけない」といった注意を与えられたという話も耳にする。
一番気をつけなアカンのは、あんたみたいなおっさんやん!
と今なら冷静に突っ込めるが、朝昼晩の授業の合間、休日のほとんどの時間を注ぎ、部活動に打ち込んでいた生徒たちは、どれだけ体罰を受けても、暴言を浴びても、たまに褒めてもらうと喜びを感じるといったように、ほとんどA先生に洗脳されていたような状態だった。
教官室に七輪まで持ち込み、網で焼いてぷうと膨らんだお餅に砂糖醤油をつけて、女子生徒を膝に乗せながら餅を頬張るA先生に対して、違和感を抱いても、もはやそれが良いとか悪いとか考えるすき間さえ、脳みそにはなかった。
それよりも「お気に入り」の子だけが依怙贔屓され、それ以外の自分たちには「価値がない」かのように扱われることで抱かされる屈辱感を打ち消すために、「何もなかったことにする」という歪んだ心理的に状態だったようにも思う。
オウム真理教の実態が暴かれていったとき、信者たちがなぜあんな冴えない風貌の胡散臭いおっさんに心酔していったのか、分からないでもないとも思った。まあ、それは、ずいぶん後になっての話ではあるが。
さておき、在校中に見聞きしていたのは、そうしたA先生のセクハラ行為だったが、卒業後、お酒が飲める年齢になった頃に同窓会がてら集まったとき、耳にしたのはそんなどころではなかった。
わたしの学年で、最もA先生に気に入られていたC子ちゃんは、くりっとした目で、小学校の頃から目立つ存在だったが、中学に入るとますます磨きがかかり、ちょっと素行の悪い(けどカッコいい)男子からすぐに声がかかり、部活の合間を縫って付き合うようになった。
それを知ったA先生は激怒し、C子ちゃんを「密室(ブラックボックス)」に呼び出し、こんなことをもうあいつとはしたのかと、胸を触り、下半身をまさぐり、これはお前を心配しての「保健体育の指導だ」と告げたという。
さらに、そうした「特別指導」を受けていたのは、彼女ひとりでなかったことも明らかになった。
わたしの学年は全国大会には進めなかったが、県大会、近畿大会へは駒を進め、それなりの成績を残した。チームメイトの中には、スポーツ推薦で高校に進学した子も多く、どこかで「言うことを聞かないと将来に関わる」と感じていたのかもしれない。
だが、いくらA先生が指導だと弁解したところで、それらは教師という立場を利用した卑劣でわいせつな行為でしかない。
斉藤章佳の『男が痴漢になる理由』にも書かれているが、性暴力に限らず、すべての暴力は強い者から弱い者へとふるわれる。体格や体力、立場が自分よりも勝っている者に、人は暴力を行使しない。
A先生は、女子中学生を相手に、体格や体力もそうだけれど、特に「立場」を使ってセクシャルハラスメントやわいせつな行為を日常的に行っていたのだ。
チームメイトからの打ち明け話の場においては、当時の行為が深く心の傷となり、その後の人生を変えたという子はいなかったと記憶する。
でも、もしかすると、そういう子は、その場にさえ来られていなかったのかもしれない。今となっては分からない。
私たちのチームが近畿大会に出場したとき、京都の代表チームの一つにK中学があった。大会が終わりしばらく経った頃、そのK中学の女子バスケットボール部の顧問が女子生徒にわいせつな行為を繰り返していたことが報道された。
ああ、手に取るように分かる。ため息だけが漏れた。
スポーツ界のセクシャルハラスメント問題を研究している明治大学・高峰修教授は、「セクハラの前に必ずといってよいほどパワハラがある」という。
それは指導者が選手を完全に自分の支配下に置く必要があるからだ。
その際に「グルーミング」と呼ばれる過程があることに言及している。
「グルーミング」とは、もともと福祉の世界で用いられていた用語だが、猫が足元にすり寄ってくるような状態に対象を追い込むことを指すのだそうだ。
例えば、標的にした選手を、突然、不当に批判して試合や練習から外したりして、精神的に追い詰め、そのあと一転して優しい態度をみせる。選手は追い詰められていただけに、指導者の歓心を買おうと、より依存心を高めるのだという。
A先生そのものではないか。
数年前、たまたま出身中学が同じ男性から、わたしたちが卒業した少し後に、A先生のさまざまな問題(セクハラだけではなかった)が明るみに出て、それなりの処分を受けたことを聞いた。そして、少し前に鬼籍に入ったことも知らされた。
ブログなどのインターネットで個人が自由に発信できるツールを手にしたとき、わたしは本当ならA先生が教師として現場にいる間に、卑劣な行為を実名と共に暴露したいくらいに感じていた。でも、どう説明していいのか分からないが、家族に申し訳ない気がして書くことはできなかった。性犯罪の加害者に罪はあるが、その家族には罪はないからだ。
長くなった。
わたし自身の「グレーゾーン」の体験についても話してみたい。それは大学1年の頃のことだった。
(つづく)
※プライバシー保護のため、一部を意図的にぼかしている部分があります
引用・参考文献
『Black Box』伊藤詩織(文藝春秋)
『ほとんどないことにされている側から見た社会の話を。』小川たまか(タバブックス)
『男が痴漢になる理由』斉藤章佳(イースト・プレス)
「スポーツ界のハラスメントを許しているのは日本社会の風土だ」
聞き手:神田憲行/Yahoo!ニュース 特集編集部