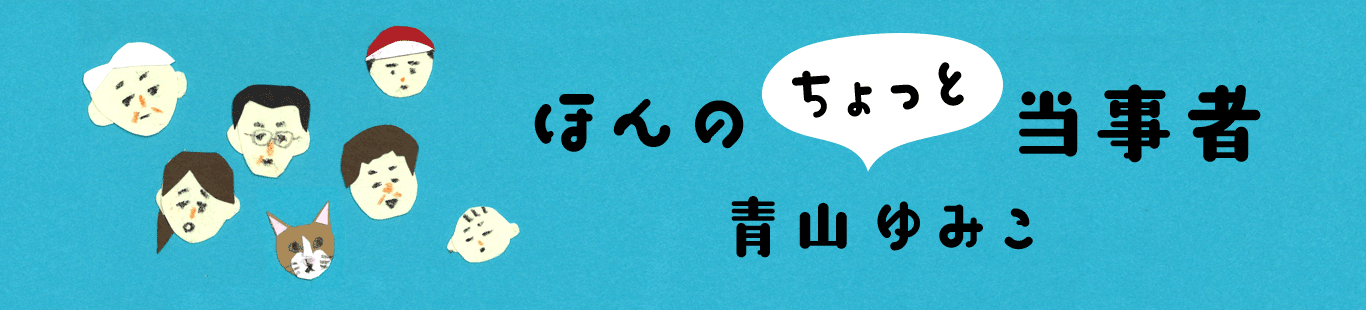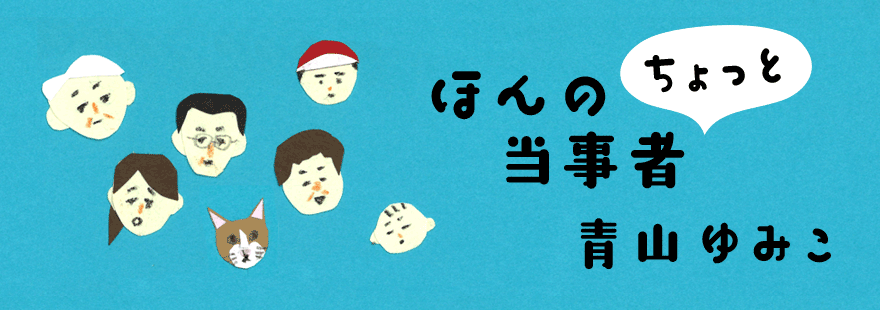第9回
父の介護と母の看取り。「終末期鎮静」という選択。(1)
2019.01.11更新
お知らせ
この連載が本になりました。ぜひ書籍でもご覧ください。
『ほんのちょっと当事者』青山ゆみこ(著)
『毎日がアルツハイマー』という映画作品がある。
監督である関口祐加さんが、アルツハイマー型認知症が進行している実母との日常を記録したドキュメンタリー映像だ。
彼女たちの日常風景は2012年に映画化され、「認知症あるある」が満載の、切実だけれど、どこかユーモラスな作品として公開され話題となった。
2014年には続編『毎日がアルツハイマー2 ~関口監督、イギリスに行く編』が公開。サブタイトルのとおり、関口監督が「パーソン・センタード・ケア=認知症の本人を尊重するケア」という考え方と出会い、認知症介護最先端のイギリスへ飛ぶ。
わたしも介護職員初任者研修(昔のヘルパー2級)の受講時に学んだが、「パーソン・センタード・ケア」とは、認知症の人を一人の「人」として尊重し、その人の視点や立場に立って理解し、個別なケアを行おうとする認知症ケアの考え方だ。
こう書くと当たりさわりのない内容に聞こえるが、関口監督が訊ねるハマートンコート認知症ケア・アカデミーの光景を見ていると、こう、もっと深い、その人個人のナラティブ(物語)を大切にする、肌のぬくもりが伝わるようなケアであることが伝わってくる。
そして、2017年7月には第三作となる『毎日がアルツハイマー ザ・ファイナル〜最期に死ぬ時。』が公開された。(上映情報はこちら)
この「ザ・ファイナル」は、関口監督が両股関節の痛みの悪化から、入院・手術を受ける場面から始まる。
アルツハイマー型認知症が少しずつ進行しつつある母・宏子さんも、脳の虚血症発作を4回起こし、意識不明で緊急搬送された。介護される側も介護者も共に老う、いわゆる「老々介護」の様相が見えてくる。
そのことをきっかけに、関口監督は次第に、「ケアの終わり」と「母の死=看取り」について考え始める。それは、介護者である娘に、認知症である母の命を預かる責任の重さを痛感させることにもなる。
前振りが長くなったが、この『毎日がアルツハイマー』シリーズが、この1月末から神戸の元町映画館で一挙上映されることとなり、2月頭に行われる「ザ・ファイナル〜最期に死ぬ時。」上映会後のトークイベントに登壇することになった。(詳細はこちら)
声を掛けてくれたのは、友人であり、在宅ホスピス・ケア「しんじょう医院」院長で、緩和ケアの専門医である新城拓也さんだ。
わたしには、18年前に二度目の脳梗塞で倒れて以来、左半身麻痺(片麻痺)と高次脳機能障害による認知障害、それらにともなった脳血管性認知症と、最近ではアルツハイマー型認知症が併発して進行している父がいる。介護認定だと要介護3だ。
幸い利き手である右は麻痺がないため、食事は介助なしで可能だが、トイレなどはある程度一人で行えるものの、ふらつきによる転倒を繰り返しているため可能な限り補助が必要で、結局のところほぼつきっきりの見守りと生活介助を必要とする状態だ。
兄、弟とわたしのきょうだい三人が結婚して独立したため、両親は二人で暮らしてながら、母は約16年もの間、父を一人で在宅介護していた。
典型的な男尊女卑の、家父長制の権化のような父は、ごく当たり前に母を自分の手足であるかのように扱った。
その母が一昨年の2月に70歳で逝去した。必然的にわたしたちきょうだいは、残された父を通して「認知症の介護にかかわる」こととなる。その日常(というかほぼ愚痴)をSNSでも発信していたため、映画のテーマに合うのではと考えて、新城先生はお声がけくださったそうだ。
とはいえ、わたしは関口監督のように、在宅で親を介護しているわけではない。
母の最後の入院時に、介護者なしで暮らせない父は、居宅介護支援サービスでの短期入所(いわゆるショートステイ。利用期間が限定される)を利用することになった。
結果としてそのまま母が逝ってしまった。だが、わたしたちは誰も父を自分の家に引き取ることができない。
ケアマネージャーさんや施設の職員さんのご協力のおかげで、その後一年ほど、あくまで居宅支援の延長という形でショートステイをつなぎながら、ようやく介護老人福祉施設(いわゆる老人ホーム)に正式入所することができたのが昨年1月のことだった。
そこは母が生前「ここなら父も安心して過ごせるだろう」と、希望を出していた実家にほど近いホームで、父は今、そこの個室で暮らし始めて1年ほどになる。
老人ホームに親を預ける。そのことに対して負い目があった。自宅で認知症の人を介護されている家族に対して、どこか引け目を感じるのだ。今もそれはある。
ただ、この2年の間、もし親が介護施設でお世話になっていても、家族は「預けっぱなし」になんてできないということも、つくづく実感させられた。
特に1年目の短期入所の場合は、あくまで「居宅介護」を補佐するための介護保険サービス利用となるため、家族に求められるサポートも多い。細かいことで言うと、例えば病院への付添いは家族が行うのが基本のため、歯医者に整形外科、泌尿科、内科などの通院時にも、わたしたちの誰かが仕事を休んで父に付き添うことになる。
通院だけでなく、転倒による脳出血や、胆管結石の手術時などの入院も少なくなく、その際には毎日病院に足を運ぶことになった。
数え切れないほどの転倒などによる突発的な怪我も家族を走り回らせた。しかしそれ以上に頭を悩ませたのは、四六時中そばにいた妻という介護者と、住み慣れた自宅という環境を失い、プライベート空間のほとんどない4人部屋での生活を強いられた父は、そのストレスからか、いわゆる認知症の周辺症状見せるようになったことだった。例えば、「物盗られ妄想」では、入所者間でさまざまなトラブルを起こし、その度に、わたしたちは施設に駆けつけて、職員さんからの説明と父の言い分を聞き、その状況を収める方法を探さねばならなかった。
職員さんはみんな精一杯の手一杯で、わたしたちは申し訳なさでいつも頭を下げっぱなしだった。何もなさそうな日も、父から1日に30回ほど電話の着信がある。直近の記憶が難しいので、電話を掛けたことを忘れてしまうのだ。これもまあまあしんどい。
もしかしたら、誰かが父を引き取って自宅で介護をすればそうした問題は起こらないのだろうか。そうやって自分たちを責める家族も正直辛いが、やはり誰よりも父本人が辛かっただろう。
という父の話はひとまず置いておく(えええ)。
言いたいのは、父を介護施設に任せているのに愚痴ばかりこぼすようなわたしに介護を語るなんて憚られるほど、認知症の家族の在宅介護は大変だろうということだ。
だから、新城先生からトークイベントのお声掛けいただいたとき、正直、わたしなんかで大丈夫なのかという疑問が否めなかった。
ただ、『毎日がアルツハイマー ザ・ファイナル〜最期に死ぬ時。』は、別の意味でわたしを強く惹きつけた。
3作目につけられた副題のとおり、関口監督は介護のあとに必ず訪れる「死」を意識し、お母様のみならず、ご自身の「死に方」について考えるようになる。緩和ケアにはじまり、終末期鎮静(ターミナルセデーション)、そして安楽死や自殺幇助といったテーマを抱えて、イギリスやスイスに飛ぶ。
わたしの母も最期は、緩和ケア、そしてそれでもとりきれない終末期の苦痛をとるための鎮静(ターミナルセデーション)を受けたことを思い出す。というより、この2年、母の終末期のあれこれを忘れたことはない。常に頭のどこかにあのときの光景がこびりついている。
「緩和ケア」や「ホスピス」という言葉は、たいていの人がなんとなく耳にしたことがあるだろう。
厚生労働省の「がん対策について」という政策レポートでは、2人に1人が癌を発症し、3人に1人が癌で死亡するといわれている。
そうしたなかで、末期の癌患者の苦痛をやわらげるための緩和ケアがあり、緩和ケアを専門としたホスピスがある。
緩和ケアとは、簡単にいえば、癌などの病気により死に直面した人がもつ、身体的、精神的な苦痛をできるだけ抑えて、最期までその人らしく生きるために行われるケアだ。
わたしは1年半ほど、あるホスピスを継続して取材したことがある。
ホスピスでは抗がん治療や延命治療は行わないが、痛みを押さえる投薬コントロールなどの緩和ケアはかなり積極的に行われること。そして患者とその家族のQOL(人生の内容の質や、生活の質)を下げないように、そこまでするのかと驚くようなきめ細やかなケアが行われているのを目の当たりにした。
そうしたこともあり、わたし自身がもし癌の末期で余命宣告を受けた場合は、ホスピスでの緩和ケアを希望したいと考えている。
しかし母はホスピスでの緩和ケアを希望することがなかった。なぜならば、彼女の想定する未来には「病気を治して、生き続ける」ことしかなかったからだ。
母はC型肝炎ウイルスのキャリアだった。40代の頃、献血時にその事実を知らされたという。当時、「わたしは血も人の役に立たないのね」と暗い顔をしていたことを思い出す。
C型肝炎ウイルスの最も多いといわれる感染経路は、かつてのずざんな医療現場での注射器具の使い回しや、医療器材の再使用や不十分な滅菌処理だといわれていて、戦後の社会問題の一つともなっている。母もそうした被害者の一人だった。
医療現場の環境は改善されたが、未だ国内のC型肝炎ウイルスのキャリアは約190万人、また、肝炎を発症している患者は約37万人と推定されている(※ウイルス保持者は平成16年度、患者数は平成20年調査による推計)。
C型肝炎ウイルスの保持者は、長期間にわたり肝障害が持続し、徐々に肝臓が線維化し肝硬変に至る。また肝がんを併発することも多い。つまり190万人のウイルスキャリアが、そうした可能性を秘めているというのが日本の実状なのだ。
わたしと異なり酒の一滴も飲まない母だが、肝炎ウイルスは確実に彼女の肝臓を蝕み、典型的な肝炎患者がたどる道を進むことになった。
60の声を聞く頃から、彼女の肝臓には悪性腫瘍の影が映るようになり、3〜4年をおいて2度のカテーテル治療により、ひとまず肝がんの進行をくい止めることができた。しかし肝硬変は確実に進んでいく。肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれていて、多少の悪化では自覚症状はないが、深刻化するにつれて相当な怠さを伴うという。
おそらくかなりのしんどさが常に付きまとっていたはずであろう彼女だが、自身の肝臓を労ることに専念できない事情があった。24時間気が休まることのない父の介護を、一身に背負っていたからだ。
50代半ばから始まった終わりの見えない介護生活。最初は責任感と気力で乗り切っていたが、次第に自身の加齢と肝臓の状態の悪化から、急激に彼女は老いていく。
2度目の肝がん発症の頃には、夜中に何度もトイレに立ち、転倒を繰り返す父の見守りから、ほとんど寝られないという不眠状態にも陥り、ふっくらしていた母の肌はみるみると萎み、実家に帰る度に、あきらかに体重も体力も失っているのが一目でわかった。
「子どもには迷惑をかけたくない」というのが口癖だった彼女は、電話口では大丈夫と言いながら、最後の入院の直前の正月に実家に寄った際には、ベッドから起き上がることもできないほど衰弱しきっていて、力なく笑みを浮かべる姿が目に入った。
「いつもおせちをありがとう」と、母が大変だろうからと、例年実家の分のおせちも手配してくれていたわたしの夫への礼をまず口にして、「折角来てくれたのに、横になったままでごめんね」と娘に詫びた。
ここまで来たか。
わたしは初めて母に死の影を見た(遅い、遅すぎる...)。
どうやら、その半月ほど前に受けたカテーテル治療が、想像以上に母の体力を奪ってしまったようだ。それでも父は、変わらず妻に食事の支度や入浴の介助をさせ、日常のこまごまとしたことを要求した。何十年とそうしてきたように。
普通の人の感覚ならそんなことができるはずがない。脳血管性の認知症か、高次脳機能障害による認知判断力の低下がそうさせたのだろうか(ということは、鈴木大介さんの『脳が壊れた』を読み、後になって気づいた)。
兄や弟と相談して、もはや母に父の介護をさせられない。情けないけれど、自分たちにも難しい。
若い頃から困ったり弱ったりしている人に手を差し出さずにいられなかった母は、「ホームに預けるなんてやっぱり可哀想」と最後まで頑なに拒んでいたが、もはやそんな悠長なことを言っている場合ではない。彼女自身の命がかかっているのだ。
父には申し訳ないけれど、母を父の介護から解放するしかない。ケアマネージャーさんと相談し、正式にホームに入所申請を出したのが、新しい年が明けてすぐのことだった。
ようやく父と離れることを決意してしまえば、これからは一人で好きに生きられるのね。力ない声ではあるが、母はそんな老後を嬉しそうに語り、心から楽しみにしていたようだった。
しかし、正月明けの検査結果を眺めて、これからは治療に専念するという母を前に、担当医は表情をひどく曇らせた。
数値が非常に悪い。正直、いつどうなってもわからない状態にある。自宅での生活の負担が大きいなら、肝機能をこれ以上落とさないために入院してはどうかという提案を受けた。
担当医の提案を一旦断った母だが、翌朝電話があり、あまりにしんどくて動けないのでやっぱり入院したいとほとんど泣きそうな声で訴えてきた。
病院に電話をすると、ひとまず救急外来に来てくださいと返答がある。病院で落ち合った母は、一歩足を動かすにもふーふーと息を切り、見かねて駆けつけてきた看護師が、動かずにここで座って待ってくださいと声を掛けてくれた。
救急から担当医に連絡が入り、即日入院を調整してくれたのだが、父がまだホームへの入所はできないので、入院中のショートステイ先の調整と着替えやらの準備をしておきたい。もう自分が父のお世話をすることはこれで最後になるかもしれないから、と。
それは父の施設入所を考慮した彼女の予想から出た言葉だったが、皮肉なことに異なる意味で現実になってしまう。ともあれ母は責任感からなのか頑固に言い張り、入院は翌週からと決まった。
お前は実家に泊まり込んで母を助けた方がいいのではないか。わたしの夫は心配してそう提案してくれたが、母は気持ちだけで十分だときっぱり断ってきた。どこまでも人に気を遣われるのが嫌な、頑固な人でもあった。
翌週、急性期の病棟への入院時には、弟の嫁ちゃんが母を病院まで車で連れてきて、細々とした手配を手伝ってくれた。母はぼんやりベッドに腰掛けながら、明るい個室をぐるりと眺めて、どこかほっとしたような表情を浮かべていた。
しばらくゆっくり寝て過ごして、とにかくもう少し体力をつけようね。
そうね、わたしはまだまだこれからやりたいことがあるの。もうパパに振り回されなくてもいいと思うだけで、元気が出そうよ。
翌朝、病院を見舞うと、久しぶりにゆっくり寝られたと、明るい笑顔を浮かべていた。そんな顔を見たのはもう何年ぶりだろう。病院併設のタリーズのコーヒーを一緒に飲みながら、母はにこにこしていた。
だが、その翌日、病室を開けると待っていたのは、苦悶の表情でのたうちまわる母の姿だった。
その日から、合併症、感染症と次々と容態は急変し、肺水腫が最後の打撃となり、安静のための入院のはずが、ちょうど2週間で彼女は逝ってしまった。
(つづく)
引用・参考文献
●『脳が壊れた』鈴木大介(新潮新書)
●厚生労働省「がん対策について」
●厚生労働省「知って、肝炎プロジェクト」事務局