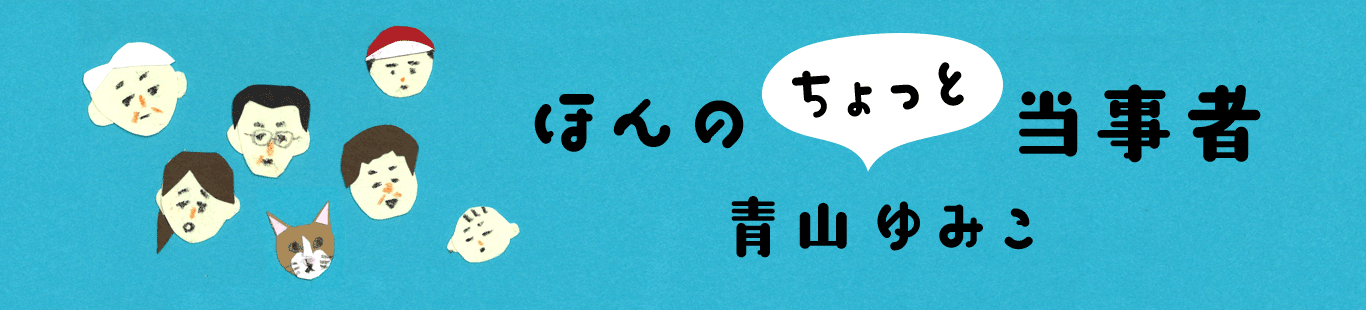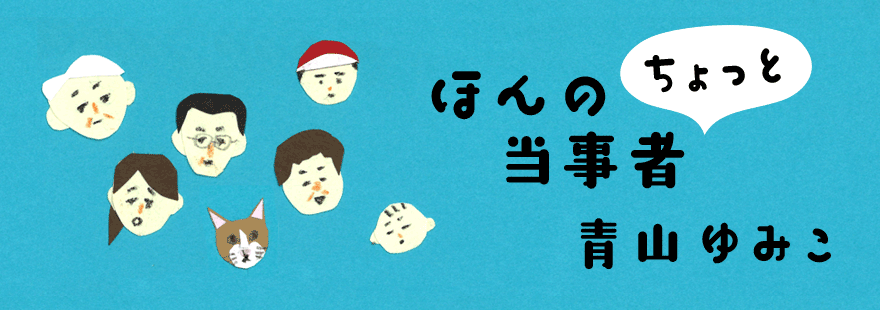第11回
哀しき「おねしょ」の思い込み。(1)
2019.03.09更新
お知らせ
この連載が本になりました。ぜひ書籍でもご覧ください。
『ほんのちょっと当事者』青山ゆみこ(著)
ひょんなことから、社会福祉士の国家試験の受験資格を取得するために、昨年4月から専門学校に通っている。
といっても通信制なので、厳密には「通っている」わけではない。仕事や家事の合間にテキストを開いて、課題をこなすという日々だ。
始めてみて驚いたのだが、社会福祉士(以下、社福士)の国試必修科目はとにかく多い。19科目もある。なので、1カ月に1科目取りかかったとしても1年半は軽く過ぎてしまう。
マイペースでぼちぼちやろうと舐めてかかっていたが(おいおい)、数か月ごとに締切りが設定された課題の量が半端なく、仕事よりもよっぽどタイトでキツい。国家試験まであと11カ月あるのだが、時間が足りるとはまったく思えない。
そもそも、であるが、この連載を読んでくれているなかで、「社会福祉士」と言われて、「ああ、あれする人ね!」とぴんとくる方がどれだけいるだろう。
なんとなく試験勉強し始めたものの、わたしも業務の内容を具体的にイメージできるようになったのは、一年ほどが経ち、実習にも参加したようやく最近のことだ。
思いきりざっくり説明すると、「社会のなかで困っている人に対して、社会福祉制度などを用いてサポートする人」という感じだろうか。また、その人の持っている力(ストレングス)に着目するということも重要な要素の一つだ。
わたしたちは生まれながらにして、既にさまざまな「権利」を持っている。
「社会福祉」に関心を持った最も強い理由も、「わたしがいったいどんな権利を持っているのか知りたい」ということだった。
少し前にドラマ化され話題となったコミック『健康で文化的な最低限度の生活』のタイトルは、日本国憲法第25条第1項で定められた「すべての国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」と定められた文面そのままで、これは「生存権」保障の規定でもある。
生活困窮者やホームレスに対してもさまざまな支援制度があるが、普通に暮らしていてそれらに精通するのはなかなか難しい。
つい先日、駅前のスーパーで、ボブ・マーリーのような天然ヘアをした、もう何カ月もお風呂に入っていないことを裏付ける独特の匂いを放つ男性とすれ違った。
ちらりと横目に入った彼の右手首から先は小刻みに震えていて、左手でそれを押さえようとしていた。アルコール依存症の路上生活者だろうか。或いはパーキンソン病などの何かの病気か障害だろうか。
いずれせよ、彼は明らかに何らかの「困りごと」を抱えていた。
それがわかっているのに、わたしには何もできなかった。
スーパーの隣には区役所があり、なかには福祉課の窓口がある。そこに行けば、何か手があるだろう。わかっているのに、どう声をかけて良いのかわからなかったのだ。いきなり知らない女に声をかけられて、役所に連れていかれるなんて、どう思うだろう。もしわたしがごく自然に、「困っていることはありませんか?」とでも訊ねられたら、何かが変わったかもしれない。でもそんなことができる自信はなかった。
今も彼の震える右手が脳裏に浮かび、不甲斐ない気持ちになる。
先だってより、児童相談所の対応が問題となり両親による虐待の犠牲となった女の子の事件が大きく報道されているが、児童に限らず、高齢者や障害者を含む虐待の事件は増える一方だ。つまり、わたしたちの身近で虐待が起きている可能性も低くないということが簡単に想像できるだろう。
もし虐待を受けている疑いがある児童や高齢者を発見したら、わたしたち国民の全員に、確証がなくても通報の義務がある。「した方がよい」ではなく「しなくてはいけない」のだ。
わたしは社福士の勉強を始めるまで、そんなことも知らなかった。
資格うんぬんではなく知識って大事だ。そしてその知識を使うタイミングが来たときに、さっと取り出せる意識を持つことがなにより大事だと思う。
社会福祉制度の基礎知識や、制度がどうやって生まれて変化してきたのかという歴史的背景、社会保障や年金や保険の制度。現代社会では切実な高齢者に関わる法制度や障害者に関することはもちろん、社会調査の基礎に、地域福祉の理論など、覚えることが「わーわー」と叫びたくなるほど山盛りのテキスト前に絶望的な気持ちになることも多いが、いつか何かの役に立つかもしれない。
もちろん自分自身が助けてもらえるかもしれない。そう思いながら今日もテキストにがりがりと線を引いている。
さて、ようやく本題に入る(前置きかよ!)。
必修科目の一つである『人体の構造と機能 及び疾病』のテキストを読んでいたある日、さらりと書かれているある一文に、思わず「ええ!」と叫んでしまった。それは「幼児期の健康課題」という項目に記載された、おねしょに対する説明文だった。
『夜尿症(おねしょ)は小学校に入る頃にも約1割の子どもにみられ、男児の頻度が高い』
え、うそっ!!!
読み替えれば、「小学校に入る頃には9割がおねしょをしなくなる」ということになる。
おねしょ...。封印していた暗い過去が、にわかにびちょびちょと蘇る。
できれば黙っておきたかったが、わたしはおねしょ歴がとても長かった。
毎晩というパターンではないが、小学校に上がってからもしょっちゅうおねしょをしたし、4〜5年生の頃あたりまで、月に2〜3度ほどは布団をじっとり濡らしたような覚えがある。
さらにいえば、中学に入ってもおねしょをすることが時々あった。そんなこと、恥ずかしすぎて友達の誰にも言えない。そして記憶が曖昧だが、最後におねしょをしたのはおそらく高校時代だったのではと思い出す(セーラー服を着た女子高生だぜっ。ふぅ...)。
話題にすることさえなかったので、他の子がどうなのかも分からなかったが、「おねしょ=小さい子どもの恥ずかしいこと」とは感じていたので、なんとなく自分は「普通じゃないのかもしれない」という意識はあった。
ただ、不思議なことに、おねしょ癖について深く悩んだという覚えはない。
最近、知人に教えられて知ったのだが、作家であり芸術家でもあった赤瀬川源平さんもおねしょがコンプレックスだったそうだ。『NHK知るを楽しむ 人生の歩き方』(2006年・NHK出版)では、自分にとって「貧乏とおねしょがコンプレックスの原産地」だと語っている。中2までおねしょは毎晩治らず、「一生こうなのか」と自分の運命を憎んでいたという(彼の場合はある夜、雑魚寝をしなくてはいけない状況になり、その夜をきっかけにおねしょがなくなったそうだ)。
わたしは赤瀬川さんのように毎晩というわけではなかったし、もっと他にしんどいことがあったので、そこまで思い詰めることはなかった。その理由は後述するが、おねしょとも密接に関係する。
それにしても、40代後半のいまになって、9割の人が小学校に入る前にはもうおねしょをしていなかったという事実を知り、驚きすぎてお漏らししそうになった。今さらだけど、みんなが羨ましいよ...。
テキストではその一文だけだったので、おねしょについて詳しく調べてみた。
すると書籍でもネットでも関連のものがわんさか溢れ出し、多くの子どもとお母さんがおねしょに悩んでいることを知った。と同時に、現在ではおねしょは「夜尿症」として、治療すれば治癒が可能な病気として扱われていることも知る。
たいていの「おねしょ」本では、まず「心配なおねしょ」と「心配ないおねしょ」の線引きがされている。
ある本では、「6歳を過ぎても毎晩2回する場合は、小児科医に相談すること」を勧め、またある本では「小学校に上がっても治らないおねしょは自然におさまるのを待つのではなく、積極的に治す時代だ」と断言されていた。
つまり、おねしょはあるライン(基本は5〜6歳という年齢)を超えると「夜尿症という病気」であるというのが現代医学での解釈なのだ。
そして夜尿症の場合は、毎晩のように、或いは一晩で複数回おねしょをしてしまう子どもが多いという。
ある本では、24歳の娘さんを持つお母さんからの悩み相談で、娘が2年前から付き合っている男性との結婚を控えているけれど、夜尿について打ち明けられず、思いつめて自殺を考えたりもしている。ここまで放っておいたことを悔やみ親の自分こそ娘に詫びて死にたい...というような、読むだけで胸の詰まる切実なものもあった。
ちなみにそれに対する回答は、夜尿は治療すれば治るもので、そうした科学的根拠を示しながら、医師も交えて当人と相手の方とお話をして安心していただきましょう、というものだった。
赤瀬川さんしかり、おねしょ本に書かれている症例に対して、頻度も量も少なかったわたしは、読めば読むほど果たして自分が「夜尿症」という病気だったのか混乱してきた。
ただ、中学生になってもおねしょをしてしまう場合は小児科にかかりましょうと書かれていたので、やっぱり病気だったのか。或いは、いわゆるグレーゾーンといったところだったのだろうか。
もしかすると、これを読まれているお母さんのなかに、子どものおねしょで悩んでいる人がいるかもしれないので、参考までに少しまとめておきます。
夜尿症の治療には、まず生活習慣の見直しがある。
夜更かしをせず、早寝早起きを習慣づけることや、夕食後から寝るまでの3時間は水分を摂らないなど。
それでも難しい場合は泌尿器科や小児科といった医療機関にかかることになる。そこでの治療は、大きくわけると「薬物治療」と「夜尿アラーム」という機器を使った非薬物治療がある。
楽物治療では、寝る1時間前に服用することで、おしっこを濃縮してその量を減らす働きのある抗利尿ホルモン薬が使われることが多い。この薬が夜尿症の治療薬として日本で承認されたのは2012年のこと(当然、わたしの幼少期にはなかった治療法だ)。
『バイバイ、おねしょ!』という本のなかで、順天堂大学医学部附属練馬病院の小児科の大友義之先生は、その具体的な効果をこんなふうに語っている。
抗利尿ホルモン薬の内服薬を処方して夜尿症の治療を始めた子ども32人のうち、1カ月の時点では半数以上の子どもに効果が見られなかった。だが、2か月目には7割以上に効果が表れた。そのうち12人は2カ月目で完全に夜尿が止まり、従来の治癒までの期間が短縮されたと言えると思う、と。
もう一つの夜尿アラーム療法とは、寝るときに子どものパンツに小さなセンサーをつけ、夜尿でパンツが濡れると、本体が電子音やバイブレーションを発信し、夜尿をしたことを子どもに知らせる条件づけ訓練法だ。
日本では、睡眠を妨げるのは夜尿症の治療に逆効果という考えが主流でこの夜尿アラームはなかなか普及しなかったが、欧米では1960年代から使われてきたポピュラーな方法で、近年では日本でも積極的に採り入れられているという。
理由は、アラームで子どもを起こしてトイレに行かせるのではなく、アラームの音や振動が刺激となって夜間の膀胱容量が増え、朝まで尿をためられるようになることがわかってきたからだと、滋賀医科大学の泌尿器科学が専門の河内明宏教授は話す。
こうした治療法を始め、夜尿に対する正しい知識を持つことが、おねしょに悩む親子にもっとも大切なのだ。
昔はおねしょというと、原因は育て方が悪いだのストレスだと言われていたが、それは要因であって原因ではない。また、必ず「おねしょはお母さんのせいでも子どものせいでもない」ということが、現代のおねしょ本のほとんどで繰り返し語られている。
そ、そうだったのか...。
実はわたしはそうした一文にこそ、なにより驚いたのだった。
長い間わたしは、「母の育て方」と「ストレス」こそ、おねしょの原因だと思い込んでいたからだ。
おねしょに対して科学的な治療などまだなかった時代。というか病気ですらなかったわたしのおねしょ時代(1970〜1980年代)に話は遡る。
前述したように、幼少期から始まり思春期まで続いたおねしょについて、もちろん強烈な羞恥心を持ちつつも、不思議なまでに深く悩んだりした覚えがない。なぜだろうと考えてみると、自分なりに理由をつくって納得していたからだと気がついた。
わたしのおねしょには自分のなかで法則があった。それは決まって母から酷い叱責を受けた日に限られた。
母は非常に真面目で純粋な人だった。嘘がつけず、いつも正しさを求め、融通が利かず頑固だった。子育ての一つひとつに真剣で「母親」としての役割を120%の勢いで果たそうとしていた。
同時に、典型的な家父長制の権化のように男尊女卑の考えを持つ父の「よき妻」でもあろうとした。父も一歩下がって黙って従う完璧な妻を求めた。
わたしには一つ年上の兄と、2つ年下の弟がいる。ほとんど団子のようにくっついて生まれた三人の子育てと、黙って座れば、父が飲みたいときにお茶が出てくるような妻を望まれた母は、この歳になって、もし自分が...と想像してみると、毎日が戦場のように大変だっただろう。
父は、家が散らかっていることもとても嫌がった。でも小さな子どもが3人もいたら、当然家のなかはぐちゃぐちゃだ。
また、父は口のおごった人で、鶏はどこの市場が良いだの、魚はどこそこで買えだの、自分が動くわけではないのに買い物ひとつに指示を出し、毎食の支度にも時間と手間を掛けさせながら、家事育児には口だけ出して一切手を出さなかった。
わたしだったらソッコー離婚やで。
当時の母の獅子奮闘を思い返す。父も父だが、母もなぜもっと適当にかわせなかったのだろうか。夫への愛情というより、それが自分に与えられた義務であるかのように、常にフルスロットルで夫の要求に応えようとしていた。
純粋な愛情にも満ちた人でもあったので、子育てにも一生懸命すぎた。
頑張りすぎる人は反動も大きい。彼女は、感情のコントロールも適当にはできず、我慢するだけ我慢して、限界まで来ると、プツンと糸が切れたように怒りを爆発させるということを繰り返した。
母に負のスイッチが入ると、彼女はほとんどパニック状態になる。泣きそうになりながら、自分の思い通りにならない苦しさを、子どもたちにぶつける。
怒鳴り、叫び、手をあげる。普段の優しい母が豹変したよう怒り狂う。本当によく叩かれた。
後年そのことを母に告げると、ほとんど覚えていないと断言し、なぜそんな嘘をつくのかと問われたが、わたしの思い込みではない証拠がある。
基本的にうちのきょうだいは仲が良く、大人になってから、兄と弟と3人で飲みに行く機会も多かったが、そんなときには、よく3人で家出をしたときことを懐かしく酒のネタにしたからだ。
昭和50年代は、新興住宅地に空き地が点在していて、土管のようなものが転がっていた。まだ兄が小4で弟が小1くらいの頃だっただろうか、酷く怒られたある日の夕方に、もうあんな鬼のような母のいる家に帰るのは止めようと3人で話し合い、その土管で一夜を過ごそうとしたことがあった。
結局は、お腹が空くし寒いしで、しょぼしょぼと家に戻り、こんな遅くまでどこに行っていたのだと、また母にこっぴどく怒られたのであるが。
育児ノイローゼもあったのかもしれない。可哀想に、誰も周りで母を助ける人がいなかった。
ともあれ、そんなふうに記憶のなかでは、その頃まではきょうだい三人がある意味分け隔てなく怒られていた覚えがある。
ただ、小学中高学年になる頃からそのバランスに微妙に変化が表れるようになる。(続く)
●引用・参考文献
『バイバイ、おねしょ!』冨部志保子(朝日新聞出版)
『新 おねしょなんかこわくない―子どもから大人まで最新の治療法』帆足英一(小学館)