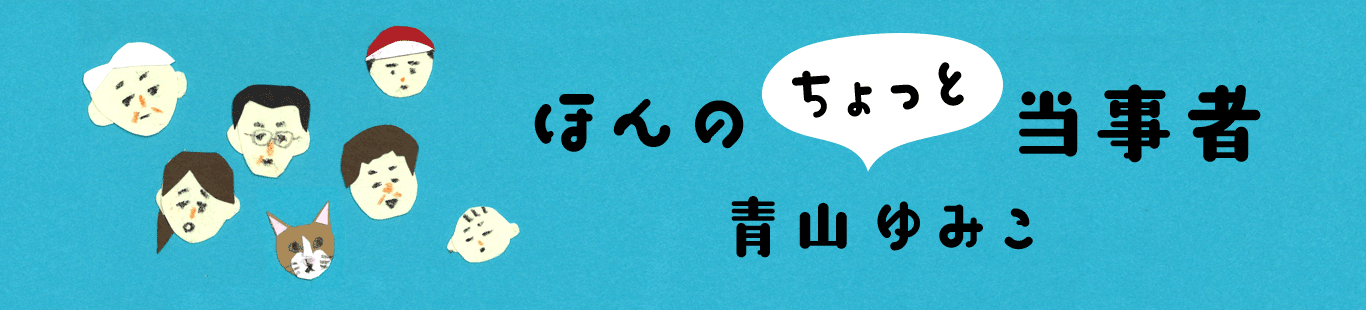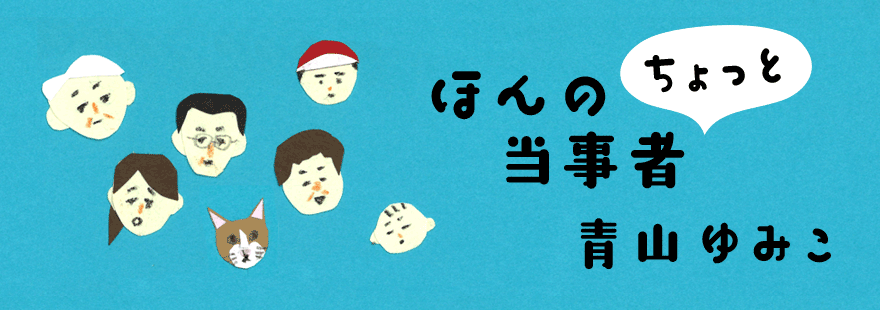第13回
わたしは「変わる」ことができるのか。(1)
2019.05.15更新
お知らせ
この連載が本になりました。ぜひ書籍でもご覧ください。
『ほんのちょっと当事者』青山ゆみこ(著)
長い連休のあいだ、やらなければいけないことにまったく取りかからず、やらなくてもいいことばかり片付けたので、連休最終日にはやり切った感のやり残した感が半端なかった。
というSNSの投稿を見た街の大先輩(バッキー井上さん)が、「それでええやん」とコメントをくれた。ほんまにそうやな、とすとんと落ちた。
どうしてわたしは、こう、いつも「正しさ」を間違えてしまうのだろう。休みの日というのは、「やらなくてもいいこと」をするための時間なのだ。間違ってなかった(きっぱり)。
そんなわけで、やや飛び石ではあったけれど、休みの間は、チョモランマのごとくそびえ立つ積読山を崩したり、ゆく年くる年的な改元の喧騒を横目に粛々と掃除にいそしみ、ぎゅうぎゅうにモノを詰め込んだ押入れをひっくり返して捨てたりあげたり売ったりしつつ、日が暮れたら撮り溜めていたドキュメンタリー番組の録画を再生しながら、キンキンに冷えた安っすい泡をだらだらと飲んでいた。
うちの家は10年ほど前のリフォーム時に、テレビのケーブル部分がはめ殺しになってしまい、ケービルから引っ張っての衛星放送受信ができない。アンテナを立てればいいのかもしれないが、二人ともそこまでテレビに関心がないのでそのままに放ってある(時折、BSの映画放映を羨ましくも思いつつ)。
民放はもともとほとんど見ることがなかったが、この3、4年ほどの間だろうか、NHKのニュースにも違和感を抱くようになり、日常的にテレビを点けることがなくなった。
その代わり、これと決めた特番などをこまめに録画して、時間が空いた時にまとめて見るようになったので、SNSなどで興味を持った番組はとりあえず予約録画するクセがついた。
そのため、DVDプレイヤーの録画一覧にはずらりと番組タイトルが並ぶ。それを眺めると、「わたしが何に関心を持っているのか」が一目で分かる。
休みの間、久しぶりに一覧を遡ってみると、どうやらわたしはここ最近、障害者に関連する話題に強く反応しているようで、4割ほどが「障害」にまつわる番組だった。
その一つに2018年8月に放映されたNHKスペシャル『ともに、生きる〜障害者殺傷事件 2年の記録』という特集があった(1年近く見ていなかったのか...)。
2016年7月26日に神奈川県相模原市にある県立の知的障害者施設「津久井やまゆり園」で痛ましい事件が起きた。
番組は、事件から2年が経った当時、改めてこの事件の意味を考えるという趣旨で、加害者である植松聖被告(事件当時26歳)の言動、被害者やその家族の思いや状況、また植松被告と対話を重ねる人たちなどを捉えた内容だった。
施設入所者の19人が命を奪われ、入所者と職員の26人が負傷。殺害者数は戦後最大という大量殺人事件として大きく報道された。
2018年番組放映時の植松聖被告は公判前整理手続きの最中で、拘置所に勾留中だった(2019年5月現在も同様。本年3月時点の共同通信の記事によると、2019年度内となる2020年1月に初公判が行われるのではないかとの予測)。
多くの人がそうであったように、わたしがこの事件でもっとも強い衝撃を受けたのは、植松聖被告による重度障害者の殺害を正当化する発言だった。
事件の直後から始まり、彼は拘置所からも手紙や手記を通して、「(意思疎通のできない重度の障害者の)存在自体が不幸をつくる」「生産能力の無い者を抱える余裕はこの国にはない」「(自身の行動は)有意義だった」などと、一貫して自身を正当化する発言を繰り返し出し続けている。
彼は捜査段階での精神鑑定で「自己愛性パーソナリティ障害」と診断されているが、横浜地検は完全責任能力を問えると判断して、2017年2月に事件を起訴している。
米国精神医学会による診断基準である「DSM-5」によると、自己愛性パーソナリティ障害(narcissistic personality disorder/ナルシスティック パーソナリティ ディスオーダー)とは、空想や行動にみられる誇大性、賞賛されたいという欲求、共感の欠如を特徴とし、自らの能力や業績を過大に評価して誇大感をもっていて、際限のない成功や権力、美しさの空想にとらわれている、とされている。
もちろんこの障害が犯罪行為に直結するわけではない。横浜地検の判断もそのことを裏付けている。あくまで、植松被告自身の問題なのだ。
NHKの番組でも触れられているが、拘置所で上松被告と接見した人の多くは、彼が非常に礼儀正しく、一見して大量殺傷事件を起こすような人物には見えなかったと語っている。
ぱっと見たところ、どこにでもいるごく普通の青年。
その彼が、重度の知的障害者を「意思疎通のできない人間」、心を失った「心失者(しんしつしゃ)」と決めつけて、存在を否定し続けている。
さらにはその考えを変えることはないと断言し、新聞や本に目を通し、自分に異を唱える人を目にすると、わざわざ手紙を出して積極的に批判さえする。そうやって、拘置所から発信した記事や手紙は300通を超えるという(2018年当時)。
残念というか、受け入れがたいことに、そんな上松被告の発言に同調する声が少なくないという事実もある。NHKに寄せられた意見として紹介されたものの中には、同調するまではなくとも、「できれば障害者と関わりたくないと思ってしまう」と言った声も見かけた。
植松被告にどこか共感するという人が、わたしが生きる社会には確かに存在するのだ。
深いため息が出る。
と同時に、遠い昔のある出来事が、記憶の底からどろりと浮かび上がってきた。
小学5年生の時のことだ。
社会の授業の一環で、校区内のスーパーマーケットや商店を訪れて、その店が持つ役割を調べたり、そこで働く人たちの思いを知る...といった、今でいうグループワークのようなものを行うことになった。
ワークは、「班」をつくることから始まった。
はーい、近くにいる人と5〜6人で集まって、机をくっつけましょう。班ができたら班長さんも決めてくださーい。
「近くにいる人」というやや曖昧な先生の指示を受け、わたしたちはなんとなく周囲をきょろきょろ見渡して、目が合ったクラスメイトと頷き合い、机を抱えてがさがさごそごそと班をつくるために移動する。
教室内には、ほどなく8つほどの机の島が生まれた。
だが一つだけ、どの島にも入らずに離れ小島のようにぽつんと浮かんでいる机があった。それは聴くこと・話すことに障害のある竹原くん(仮名)だった。
補聴器を耳にかけた竹原くんは、大きな声なら聞こえるようだが、口から発するのはぶわぶわと濁った音で、言葉として聞き取るのは難しかった。
年齢的には一つ年上だが、ろう学校(2007年より特別支援学校に改名)より転校してきた時から、わたしたちの学年にいた。
小学校での1年の差は大きい。特に5年生と6年生だと、6年生はもう中学生に近いので、竹原くんは身体もそうだが、醸し出す雰囲気がどこか大人びて見えて、障害の有無を知らずとも、クラスのなかでどこか違って見えたような気がする。
運動神経が良く、走るのがとても速かったので、体育の時間の彼は自信に満ちあふれみんなからも一目置かれていた。
運動会では、ピストルの音が聞こえないので、先生に体をトンと叩いてもらうのが合図となるため、スタートダッシュでやや出遅れる。そんなハンディがあっても、抜群の俊足で、彼は同級生に追いつき追い越し、一番にテープを切る。
見に来ていた父兄はひときわ大きな拍手を送る。彼は息を切らしながら、こんなのたいしたことじゃないとでも言いたいような照れた仕草を見せて、でもやっぱり嬉しそうだ。竹原くんは、言語表現をカバーするからなのか、とても表情が豊かだった。感情もストレートに見せる。
例えば逆に、先生の合図の「トン」が遅すぎて、追いつくのが難しくなり1着になれなかったときは、先生の犯した「ルール違反」に対して、憤慨し、全身で強く不満の気持ちをあらわにした。
彼の口から出る音が「声」として難解でも、身振りと表情から、わたしたちはいつも彼の意思をはっきり感じ取ることができた。
実はわたしは、そうやって強く意思を発信する彼が、ちょっと怖かった。
5年生の教室には、ぎゃあぎゃあと大声をあげたり、プロレスの技の掛け合いで異様に盛り上がるようなバカな男子(あくまで女子目線)が少なくなかったが、そうした子どもっぽさではない、はっきりとした「主張」を竹原くんは持っていた。
障害がどうというよりも、彼の醸すその「強さ」が、まだ子どものわたしにはしんどいものに思えたのだ。
さて、グループワークを開始するという段になり、40代中盤の女性教員は、ようやくぽつんと置き去りにされた竹原くんに気づいた。
あれ〜。竹原くんもどこかの班に入れてあげてください。はい、自分の班に入ってもらおうと思う班長さん、手を挙げて〜。
先生の声が教室内に響き渡る。
沈黙。
教壇でじっと待つ先生。
次第に教室の空気が重たくなる。
しびれを切らす先生。
はーい、では班のみんなで話をしてみてください。先生は決めません。みんなで決めましょう。
あくまで子どもの意思を尊重する先生。子どもたちは誰も竹原くんの方を見ない。なんだかちょっと辛いから。
わたしたちの島は、班ができた瞬間に、全員一致で大木くん(仮名)が班長に選ばれていた。
開業医の息子で、学年で一番優秀と誰もが認める大木くんは、中学受験に強いと有名な進学塾でも常にトップ。全国模試でもかなり上位にあることを誰もが知るような男子だった。
特にハンサムというわけではないが、お坊ちゃん育ちのせいなのか、どこかゆったりと鷹揚な立ち居振る舞いで、いつもシミ一つない服をきちんと着て、適度なひょうきんさを持ちつつ、無駄口を叩かない。バカな男子と楽しそうにじゃれあったりしつつも、抑制の効いた言動を女子は鋭く感じとっている。「モテる」とは異なるニュアンスで、男女を問わず慕われていた(後に灘中、灘高、東大へと進み官僚になった)。
大木くんとは母親同士の仲が良かったこともあり、わたしたちはプライベートでも会うことがあったから、単なるクラスメイトよりやや親しい間柄だったと思う。
先生の言葉を受けて班員が顔を突き合わせると、大木くんは即座に口を開いた。
「うちに来てもらおう」
大木くんが言うなら、そうだね。そうしよう。そんな空気が流れた時、わたしが「ちょっと待って」とストップをかけた。
「どうしたん?」
顔をのぞきこむ大木くん。
「うーん。わたしは嫌やわ」
「なんで?」
「大変やから」
「何が大変なん?」
聞き取り調査などをする時に、竹原くんが同行するとなれば、誰かが彼にぴったりと付いて、交わされている会話の内容を紙に書いたり、口を大きく開いて発音しつつ、身振り手振りで内容を伝えたりしなくてはならない。
竹原くんは、自分がわからないことを我慢する性格ではない。必ず、きちんと自分にわかるように説明してくれと主張するだろう。
ごにょごにょとそんなことを口にするわたしに、大木くんは不思議そうな表情を見せてひと言。
「したらいいだけやん」
黙り込むわたしをじっと見て、いつになくきっぱりと大木くんは断言した。
「青山さんは関わらなくていいわ。俺が言うから」
これまで目にしたことのないような素っ気なさで、これでもう話は終わりとでも言わんばかりに、彼は「先生!」と手を挙げた。
大木くんは立ち上がって竹原くんのところに駆けより、「俺たちと一緒にやろう」と声とジェスチャーで伝え、机を運ぶのを手伝った。
それからグループワークが終了するまではもちろんのこと、社会の授業ではない時も、大木くんは竹原くんを常にさり気なく巻き込んで行動するようになった。
竹原くんは、班決めのやり取りを見ていたのかわからないが、はっきりとわたしに「嫌い」という感情を示した。大木くんとも以前のように親しく口をきくことがなくなり、わたしはなんだか二人から責められているような気分になった。
大木くんと疎遠になったのは竹原くんのせいだ。竹原くんは、やたらとわたしの前で大木くんと親しげに振る舞っているように感じ、その態度を「あてつけか」と憎々しくさえ感じていた。
わたしは竹原くんが大嫌いなまま、小学校を卒業した。
あれから35年以上が経った。
もし今、わたしが小5の自分の言動を目にしたら、どう思うだろうか。
或いは、今の自分が、もしその当時にタイムスリップしたら、どんなふうに行動しただろう。
いろんなことが恥ずかしい。というか、自分が怖い。
(続く)