第15回
2年目のクビ宣告
2025.01.24更新
2025年がスタートし、あっという間に1か月が過ぎようとしています。みなさま、本年もよろしくお願いいたします。今年は息子と初めて過ごすお正月。離乳食のおかゆの上に、おせち料理の人参や大根、タイのほぐし身を載せて、お正月仕様にしました。まだ0歳なので当然理解はしていませんし、数年後の記憶にもないだろうと思うのですが、こうやって食文化を伝えていってあげたいなと改めて思う時間でした。
さて、新年1回目のコラムは、山口朝日放送に入社してわずか2年で受けた"クビ宣告"についてです。
1年目は、今の私の基礎を創ってくれた時間で、前回コラムでは話すだけではないアナウンサーの仕事についてご紹介しました。その中で、希望していた野球の仕事も任せてもらい、記者業が大半を占める中で、私にとってはご褒美のような仕事でした。甲子園出場をかけて戦う夏の高校野球選手権山口大会では、スタントリポートを担い、試合に出られない選手はどのような気持ちでエールを送っているのか話を聞き、試合展開で変化するスタンドの熱気をリポートしました。さらには、この夏に代表となった南陽工業高校について甲子園に出張へ行かせてもらうこともでき、「甲子園で仕事をしたい!」と12歳の夏に目指した場所でのアルプスリポートも、1年目から経験しました。私にとっても憧れの場所だった甲子園でのリポートは、緊張しすぎて、「顔が怖かったぞ」と上司からメールが届く苦いデビューとなりました。
このように、「野球を仕事にしたい!」と遠路はるばる山口県に来た私のアナウンサー生活は最高のスタートを切った! はずでした・・・。2年目も山口大会のスタンドリポートをやる気満々で(勝手に!)、春季大会から気合を入れて取材もしていました。しかし、組み合わせ抽選会も近づいてきた5月末か6月頭ごろだったと思います。高校野球のチーフディレクター(決勝が行われる球場のライト裏に家を建てて、窓ガラスに「球児がんばれ!」という貼り紙をするほどの野球フリーク)に、呼び出されました。
社内で顔を合わせると、挨拶もせずに野球談議が始まってしまうほど、お互いが野球を愛していることを知っている上司です。この夏の展望などを楽しく話すのか、はたまた、この夏はもっと野球にたくさん関われるような企画を任せてもらえるのだろうか。相当ゆるんだ顔で、呼ばれた編集室に向かいました。「本当に申し訳ないんだけど、今年の夏はスタンドリポートをやらせてあげられない」。なぜか毎日会社にはめてくるリストバンドに額をつけるように、深々と頭を下げてそう伝えられました。
スタンドリポートデキナイ?! 何かの聞き間違いかと思いたかったのですが、残念ながら現実。私の野球への愛情を知っているからこそ、本当に言いづらそうに、申し訳なさそうに伝えてくれた上司の顔がその証拠です。早くもスタンドリポートクビ宣告を受けたのです。私は野球の仕事がしたくて山口県に来たのに・・・。なんのためにこの会社に入ったのか。意味ないじゃん。去年の内容がよくなかったのかな。次々とネガティブな言葉が浮かびました。
理由は、後輩の存在でした。地方局は毎年アナウンサーが入社するということはあまりないのですが、たまたま私の1つ下には、男性1人、女性1人がアナウンサーとして入社していました。男性の後輩は大学まで硬式野球部。女性の後輩はスポーツにはあまりなじみがなかったのですが、スタンドリポートは新人アナウンサーの登竜門的業務で、2人がリポートを担当するのは自然の流れでした。ただ、試合はいくつかあるため、私も1試合くらいできると思っていたのです。しかし、それも叶わないということを告げられ、実況アナウンサーの先輩に泣きながら悔しい気持ちを聞いてもらいました。泣いても悔しがってもどうにもならないのに、いつもつま先の尖った靴を履き、髪もツンツンに尖りまくっていて、でもそれとは真逆の穏やかで優しくて真面目な先輩に、この日は朝まで付き合ってもらいました(この先輩がその後の私のスポーツアナウンサーとしての道を作ってくれることになります)。
もちろんそれだけでは納得いかず、でもどうしようもないのでひたすら落ち込んでいたのですが、なんと後日ディレクターから、夕方のニュース番組で毎日の結果を伝える高校野球のコーナーを設けるから、そのコーナーMCを任せる旨を伝えられたのです。絶望していたのを忘れるほど喜びました。そのコーナーで取り上げる選手の取材にも行ってほしいということで、結局大会期間中は毎日球場へ。球児や監督、保護者などに直接取材し、蓋を開けてみれば、スタンドリポーターよりも球場へいる時間は長く、1年目よりもどっぷり高校野球に浸かることができたのでした。
結果オーライの楽しい夏を過ごし、「来年もまた野球の仕事ができるだろう!」。なんてことは、実は微塵も思えませんでした。この私のポジションは社内でも異例だったのです。新人はスタンドリポート、それ以上の年次の男性アナウンサーは実況アナウンサーに。女性アナウンサーは年次が上がると、実況に駆り出される男性アナウンサーの業務を埋めるために、定時ニュースを読んだり、ナレーションを収録したり、内勤が主になります。リストバンドディレクターの心遣いで、コーナーMCを任せてもらったにすぎず、来年以降も高校野球に関われる保証はどこにもなかったのです。山口朝日放送でずっと高校野球に関わることができるのは・・・実況アナウンサーだけでした。
当時の報道制作局の常務は、元アナウンサー。実況経験もあり、スポーツが好きでした。何かにつけて私に「女性でも実況していいんだぞ」と言っていましたが、私はいち野球ファンとして女性アナウンサーの実況を聞きたいと思わなかったですし、それ以上に自分にはできるはずもないし、大変そうだし、やりたくないと思っていました。そのようなことを、尖った靴の先を眺めながら口にすると、「確かに俺も実況していて、準備からすべて大変だ。でも、野球に関わり続けるには実況しかないんじゃないか? 俺が手伝うから。手をあげたらどう?」。いつも以上に髪がツンと立っているように感じさせるほど、鋭く真剣な目で、先輩はそう言いました。
翌朝、「実況やらせてください」。常務にそう伝え、私のスポーツアナウンサーとしての人生がスタートしました。
いよいよ実況アナウンサーへ! 次回は、あの大谷翔平選手の投球が私を救ってくれた?! 初めての研修や、惨敗だったデビュー戦についてお話します。


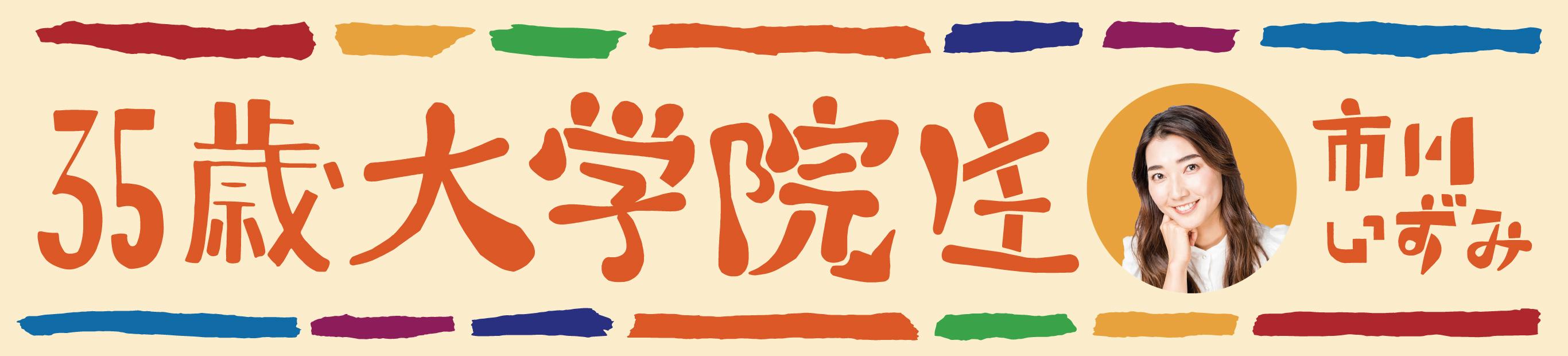


-thumb-800xauto-15055.png)



