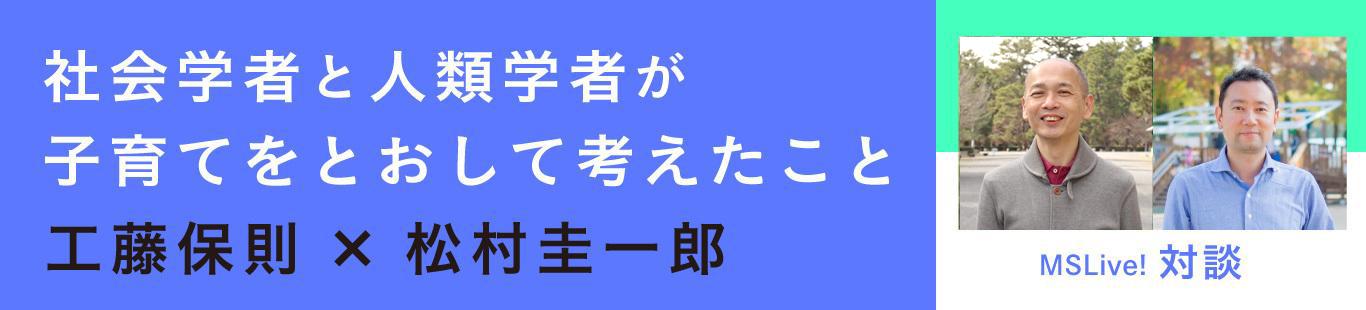第31回
工藤保則×松村圭一郎 社会学者と人類学者が子育てをとおして考えたこと(前編)
2021.06.20更新
今年3月に発刊となった、工藤保則さんによる子育てをめぐるエッセイ『46歳で父になった社会学者』。45歳で結婚、46歳で父になった工藤さんが、共働きで子育てをするなかで感じたこと、手探りであゆんだ日々を綴った本です。
「育児エッセイですが、誰にとっても多くの気づきがある一冊だと思います。(簑島ほなみさん・蔦屋書店海老名市立中央図書館)」「自分の経験と重ねて胸がいっぱいになり、涙が溢れて文字が見えなくなる本(40代読者の声)」など、読んだ方からの静かな反響の声が広がっています。
発刊後の4月16日にオンライン配信・MSLive!でおこなった、文化人類学者・松村圭一郎さんとの対談の模様をお届けします。3児の父である松村さんと、2児の父である工藤さんの対話は、子育てへの共感から社会への問題、生きて死ぬことまで、本書を軸にいろんな話題をめぐりました。
(構成・新居未希)
夫婦二人で子どもを育てるとき、圧倒的に手が足りない
松村 工藤さんは社会学者で、いろんな論文や本なども書いてこられていますが、この本には日常のごく私的な、ご自身の「生活する」ってことだけがあって、冒頭で「社会問題らしきことは出てこない」とも書かれています。でも「生活する」って、人類学者にとっては研究の中心にあるキーワードなんです。何も起こらない、問題があるのかわからないような日常そのものに重要な注目すべきことがある。そんな視点を人類学は大切にしてきました。フィールドワークって、要はそこで生活するってことですからね。
社会学と人類学は制度的には分かれていますが、今日ここで共通点として話し合えるのも、この「生活」というキーワードなんじゃないかなと思うんです。
本書には、ある現代の家族、とくに都市部で共働きの夫婦が子育てをするなかで直面する出来事が描かれています。その記述はすごく共感を呼ぶと思います。生活の場面はプライベートな領域なので、ふだんあまり表には出ないのだけど、みんなが何かしら問題と思っていることと繋がっていて。それがまさに社会問題だと思うんですよね。個人の生活の、自分ごとの中の、自分の空間の中だけで起こっているように見えるけど、それが社会としての問題につながっている。
僕がとくに共感したのは「手の足りなさ」です。夫婦二人で子どもを育てるとき、圧倒的に手が足りないんですよね。本の中で、奥さんが仕事復帰後に体調を崩されたとき、週末にお子さんを保育室に預けようと工藤さんが提案するのだけど、奥さんはちょっと躊躇してしまうという描写があります。月に1回預かってもらうだけで、その手があるだけで助かることってみんなあると思うんです。現代の日本の都市では、家族だけでは手が足りないから、誰かの手を必要とする。家族というプライベートな領域から社会が必要なんだという話になってくる印象的なエピソードだと思いました。
工藤 以前だったら祖父母に頼るという方法があったかもしれないですが、都市で祖父母とは離れて暮らしている人は多いですし、シングルマザー、シングルファーザーだとするともっと手が少ないですよね。でも子どもたちに対して何が必要かというと、一番必要なのはほんとに「手」なんですよね。手の数があると、手によって回復するというか、持ちこたえられることが多い。手が足りないということが一番しんどいです。
私が本に書いた「ばあば」がいる保育室は、ほんとうに助かりました。うちだけではなくて、多くの人が助かっていると思います。シルバー人材センターがその保育室をやっているんですが、子育てをしていたら「社会はこんなこともしてくれているのか、ありがたいな」と気づくことが多くて。できることはしようとしてくれていて、手を用意してくれているんだっていうことに気がつきました。もちろん、足りていないところもあるんですがね。それでも、なんだか社会と繋がった気がしました。
松村 工藤さんは本の中で、そういう手が足りない部分は母親の自己犠牲でまかなわれるべきだという風潮が今の日本に根強くあると指摘されていますよね。ちょっとうしろめたさを感じながらでないと子どもを預けられない状況を社会の側で作ってしまっている。子育て支援のサービスはあるのに、とくに女性が「自分でがんばらなきゃいけない」と思わせられている。だから母親自身がちゃんとケアされないといけないんだ、と書かれています。もっと人に頼ってもいいんだと。
家族の問題だけれど家族だけでは絶対に解決できなくて、そこに手を差し伸べる誰かがいる。それが結局、私たちが社会を作っていることの意味というか、最小単位である家族のなかで起きる社会問題のようなもので、すごく重要だと思うんです。この本は工藤さんの個人的な話がされているようでいて、家族だけでは問題が解決できない、だから社会はこうあるべきだと問われているんですよね。そこはとても社会学的なのではないかと感じました。
工藤 この本を読んだ知人の社会学者が、「これは社会学の本ですよ」と言ってくれるんですが、これを社会学だと言ってくれるのが新鮮で。自分の中では、こっそりそう思っていたのですが(笑)、他の人も同じように感じてくれているのは、嬉しい驚きでしたね。
 (左 工藤保則さん / 右 松村圭一郎さん)
(左 工藤保則さん / 右 松村圭一郎さん)
子どもとのお出かけは何かがある前提で
松村 本を読んで、私も妻が悪阻(つわり)で苦しんでいたときや出産前の不安な気持ちをすごくリアルに思い出しました。妊娠から出産までって、そのときどきで見守っている男の側もいろんな感情がわき起こりますよね。でも子どもが生まれてしまうと、また別の感情に塗り替えられてしまう。記憶は子どもの成長とともに更新されていくので、そのときどきの感情はだんだん遠のいていってしまうんですよね。そこを工藤さんは丁寧に記録されていて、その奥さんやお子さんの状態が自分の経験と重なる。だから、工藤さんの「自分ごと」なんだけど、読んでいる側の「自分ごと」のように読み進めていけるんだと思います。
たとえば、子どもを連れて高速バスに乗って徳島に帰省されている話を書かれていましたよね。うちも東京にいたころは車がなかったので、電車などの交通機関に乗ってしかお出かけできなかったんです。そうなると、常に何か問題に直面していたなと。子連れ家族の「お出かけ問題」ですね。ベビーカーで電車に乗ると迷惑がられるとか、エレベーターを探してうろうろするとか、満員電車で子どもが泣きはじめるとか、いろいろあるじゃないですか。
工藤 お出かけは楽しいというのもあるけど、やっぱり大変ですよね。子どもが小さい時は、へとへとの記憶のほうが多いです。
松村 徳島に帰省される途中で子どもが熱を出してしまう、みたいなハプニングも書かれていましたよね。
工藤 うまいこと行ってうまいこと帰ってくるというよりは、何かがあるのが前提ですね。何かがあっても仕方ない。そこで何かがあることに負けてしまったらよくないなと思っていました。何かあるから出かけないでおこうと思うと、たぶん何も変わらない。それよりは、何かあっても出かけることで、子どもも喜ぶし、自分たちもテクニックが身につくし、あるいはそこで何か交渉することで社会と重なることができて、すこし変化が起こるかもしれない。そう思っていたので、逆に「出かけよう」と意識して、出かけつづけましたね。
松村 それは重要なことですよね。先ほど話していた女性が自己犠牲を強いられるというのと同じで、「出かける大変さ」を、けっきょく子育て家族だけが負担することになる。子連れでないと自由にどこへでも出かけられるけど、小さな子どもがいる人は我慢して電車に乗るのを控えようとか、特急は混むから鈍行で行こうとか、いろんな我慢をしなければいけない。それはけっきょく、社会を「子連れではない元気で自由に動き回れる人」だけのためのものにしているんですよね。
今の社会に設定されているとても狭い「普通」
松村 ちょっと話がずれるかもしれませんが、僕が住む岡山市は世界で初めて点字ブロックが設置された町なんだそうです。2年ほど前、障害者がどういうふうに社会で活動しているかを調査している研究者がフランスから来たときに、その話をしたんですね。すると彼が岡山の街を歩き回ってきて、「たしかに点字ブロックはたくさんあるし、建物の中もバリアフリーになっているけれど、肝心の障害をもっている人がどこにもいないじゃないか」と言ったんです。低床バスのような設備は整ってバリアフリーで行けるのに、障害者が町を歩いていないと。これってなんなんだろうなと思ったんですよね。公共の空間で迷惑をかけるなとか、マナーを守れとか、社会に負担をかけるなとか・・・社会が変わらなければなければならないことを、批判して押し戻すというか。この風潮は、子どものお出かけ問題にも繋がっているなと思います。
工藤 繋がっていますよね。私は、子どもと出かけつづけてよかったというか、負けなかったな、と思っています。圧力に負けないでおこうという努力はしたかなと思いますね。
それは松村さんが話されたバリアフリーの話とも繋がっていて、まだまだ生きづらいというかしんどい空間があるんだけども、そういう空間はちょっとしんどいよ、無理だよと、小さなことでも言うことは大切だなと感じました。このしんどさがもうすこし楽だったら、みんなもっと楽しく出かけられるし、お出かけできたら帰ってきてから子どもは昼寝するし、子どもが昼寝をするとお父さんお母さんは休めるし(笑)。ちょっとしたことかもしれないけれど、すこしずつ広がっていけばいいなと思っていますね。
松村 今の社会には、とても狭い「普通」が設定されていますよね。元気じゃないともう街を歩けない、というような。それは子連れ家族だけの問題じゃないですよね。小さい子や高齢者、怪我をした人、障害のある人、狭い「普通」から外れた人が、普通に生きることが難しい条件設定がされているというのは、社会の大きな問題の一つです。それを社会の側が取り組むべき問題ではなくて、「いや、それはあなたが我慢できないのが問題です」「あなたががんばりなさい」とか、「昔は子連れでお出かけなんてしなかった」「おんぶ紐でやっていた」・・・などと、一部の人が自己犠牲を強いられているのだと思います。
(後半につづく)
工藤保則(くどう・やすのり)
1967 年、徳島県生まれ。龍谷大学教授。専門は文化社会学。自分のことや身のまわりのことから、社会・文化について研究。著書に『中高生の社会化とネットワーク』(ミネルヴァ書房)、『カワイイ社会・学』(関西学院大学出版会/第25回橋本峰雄賞受賞)、共編著に『無印都市の社会学』(法律文化社)、『〈オトコの育児〉の社会学』(ミネルヴァ書房)など。
松村圭一郎(まつむら・けいいちろう)
1975年、熊本県生まれ。岡山大学文学部准教授。専門は文化人類学。エチオピアの農村や中東の都市でフィールドワークを続け、富の所有と分配、貧困や開発援助、海外出稼ぎなどについて研究。著書に『所有と分配の人類学』、『うしろめたさの人類学』(ミシマ社/第72回毎日出版文化賞特別賞受賞)、『これからの大学』、『はみだしの人類学』、『文化人類学の思考法』(共編著)など。
編集部からのお知らせ
本対談のアーカイヴ動画が以下よりご覧いただけます(有料、7/31まで)。
本記事は、この対談のなかの一部です。お二人のやわらかな対話を動画でお楽しみください!