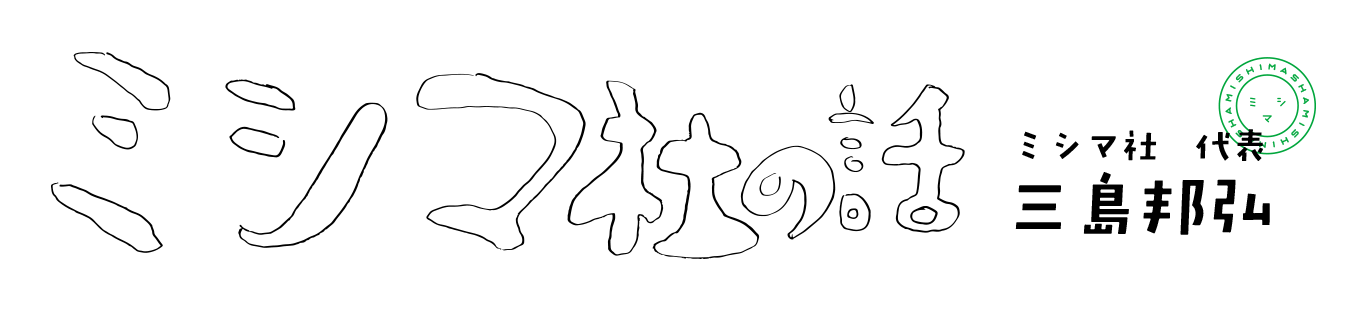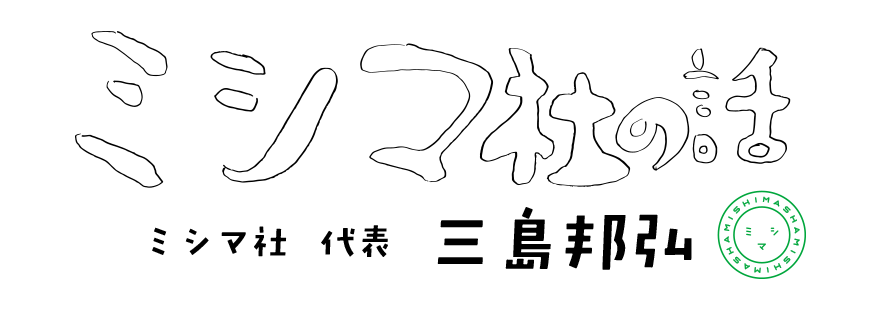第101回
明日の保証はないけれど
――韓国出版交流記(2)
2024.11.15更新
韓国の3泊4日でお会いしたすべての方々のことを思い出しながら、自分のなかで出版というもの、出版社というものの捉え方がずいぶんと進んだことに思い至る。
訪韓初日に対談したタートルネック出版のキム・ボヒさん、現地でお会いした編集者の方々、そしてなんといってもUU出版のステキな面々!
その方たちのことを書き留めねば、という熱い思いがいま、私の体内を巡っている。
こう記したのは8月下旬。早いもので、もう2カ月が過ぎようとしている。
むろん、このことばに偽りはない。すぐに、韓国訪問記のつづきを書くつもりでいた。が、それができなかった。
やらなかったのではない。できなかったのだ。
理由は?
と問われれば、現場仕事に追われていたから。と答えるほかない(言い訳にしかならないが)。
10月24日に発刊となる『tupera tuperaのアイデアポケット』、発刊を4カ月後ろに倒した『ちゃぶ台13』が同時発刊で進み、その制作に追われていたのである。ようやく、今、ひといきついているところだ。
編集の現場仕事は、私を含め4人のメンバーでおこなう。私は編集長として、他の3名を束ねる立場にいる。
束ねる、なんてふうに書くと、偉そうに聞こえるかもしれないが、現場仕事を一緒にやりつつ、結果に対して責任をもつ。
つまり。出版社における編集長の役割は、個々の編集者たちの力を最大限に生かし、会社から託されたミッションを完遂する。これに尽きよう。
会社から託されるミッションとは、たとえば、次のようなものだ。編集長A氏が、C社社長のB氏に指示を受ける。
「A君、来期は年間30冊の新刊を出してほしい。売上は5億円を達成してもらいたい。よろしく」
多くの会社でおこなわれているだろう上記のやりとり(むろん、架空のやりとりだ)が、私という同一人物内でおこなわれているにすぎない。
では、編集長である私はミシマ代表からどのような指示を受けているのだろうか?
ミシマ代表は、細かいことはあまり言わない。ただ、次のような方向性だけをこちらに授ける。
「とにかくいい本をつくってください。その上で、年間15冊前後の本をつくってほしいです。それは会社を経営的に維持する最低の発刊点数なので、それは死守してほしい。そのために編集長であるあなたは、年間20冊は出せる準備をしてください。できるだけ少ない発刊点数で運営する。逆説的ですが、これを実現するためには、クオリティの高い本をいつでもすぐに出すことのできる「数の余裕」があってこそ。それを実現するのが、編集長の役割です」
現場を預かる人間としては、とてもありがたいと感じている。
というのも、各社の編集長クラスの同世代の人たちに会うと、もっと明確なノルマを課せられているからだ。概算で言うと、目標売上の金額、1年間の発刊点数、いずれもミシマ社のばあい、他社の半分から3分の1程度の目標だ。それも、第一には、いい本であること、おもしろい本であること。この大前提があっての数字である。
ありがたいと感じているのは、まさにこの点だ。数字をまっさきに要求するのではなく、あくまでも良質な作品を代表が重視しているからにほかならない。いや、目標達成だけを考えれば、数字の目標のみをめざすほうが楽という考え方もあるだろう。だが、数字のみを求めていては、いつか、自分が虚しくなる。虚しさはあらゆる面で力を奪う。そうして継続の意思を失わせる。
それがわかるだけに、総責任者である人が、なにより質を求めていることに救われるのだ。
・・・おいおい、代表が求めていると言うが、それってあなた自身でしょう。
こう思われる方もいようか。
それに対しては、私ははっきりノーと言いたい。たまたま身体は同じかもしれないが、代表と私はちがう。ちなみに、この文章をいま書いているのは、編集長のほうの私である。
要は、私のなかに出版社代表の私と編集長の私がいる。そして、この二人は別々の立場からそれぞれの役割を果たすために考え、動く。立場が違えば、優先事項が異なってくる。必然、考えがぶつかりあう。張り裂けそうになることもある。
だが、しょせん、と思う。もとを辿れば同じ人物なのだ。どれほど対立したとて、絶対に共通項を見出させる。
自分のなかに他者をもつということは、必ず、突破口を見つけることを約束された「対話」を自らの
なんと。
この気づきは今この瞬間に得た。書いている、この瞬間に、である。
そうして、なるほど、と自ら首肯した。
なるほど、異なる立場の者たちを自分のなかに複数もつことは、社会にいる無数の他者と共生していくための、最初で最良の練習なのかもしれない。すくなくとも、意見がどれほど対立したときでさえ、自分のなかの異なる者とは和解できる。その安心は、「絶対的に相入れない他者とは永遠の対立しかない」と絶望に陥るギリギリのところで救ってくれるだろう。
こうした気づきをこの瞬間得たわけだが、次のことは、以前から思ってきた。
一見、矛盾したり対立したりする二人を自分のなかにもつことは、わるいことではない。むしろ、生きた仕事は、すべてこの過程を通る。その仕事が生きるかどうか。それは、このプロセスを経由したものかどうかに大きく依る。
*
韓国の出版人との交流が、ますます私にその想いを強くさせたのだった。
ソウルに着いた日の夜、私はタートルネック出版のキム・ボヒさんと対談をすることになっていた。場所は、5キロブックス。いわゆる独立系のちいさな書店さん。韓国の独立系書店は生き残りのため、店のコンセプトをはっきりさせることが多い(詳しくは『韓国の「街の本屋」生存探求』CUON)。5キロブックスのばあい、「成長を売る本屋」というコンセプトを掲げていた。ちなみに、2日目の対談者であるチョン・ジヘさんは、坡州市で「私的な本屋」を営む。「薬を処方するように、その人にあった書籍を処方する」のが、ジヘさんの書店の特徴だ(最近、ジヘさんの著書の日本語訳も出たのでぜひ読んでいただきたい)。
初日の対談相手であるキム・ボヒさんとお会いするのは、うっかりしたことに2度目であった。コロナ前、週に1度(2019年からは月に1度)、自社でオープンしていたミシマ社の本屋さんに来店くださっていたのだ(コロナ以降、休店)。その頃はまだ出版社の社員として編集者をされていたが、拙著『計画の無計画のあいだ』韓国語版にも影響を受け、独立。されたらしい・・・。
事前にいただいたご質問からも、私やミシマ社のことをずいぶんよく調べ、知ってくださっているのがわかった。
当日も、私が質問をする余地がないほど、ミシマ社のことを質問くださった。「新レーベル・ちいさいミシマ社をつくってみて、どうだったか?」「ミシマ社サポーターと一緒にどんな活動をしているか?」。しかも、ミシマ社Tシャツを着て!
恐縮するばかりである。私は、ひとつひとつ丁寧に答えつつ、出版社名の由来など、気になっていたことをうかがった。
「タートルネックは、韓国ではスマホ首のことを指します(日本で言う、ストレートネック)。スマホばかり見て、突き出た首のことです。本ばかり読む人のこともそう言うのですが、批判をこめてそう言うわけです。けど、それって本をいっぱい読むってことですばらしいじゃないですか。タートルネック、すばらしい! そういう思いでこの名にしました」
世間で思われている意味とちがう意味をそこに込める。言葉に新しい命を吹き込む。ネーミングひとつとっても、キム・ボヒさんのセンスを感じる。
対談の1時間半は、文字通りあっと言う間だった。
終盤、キムさんはこれまでの笑顔を潜め、神妙な面持ちで口をひらいた。
「もうすぐ出版社をつくり1年になります。実際やってみてほんとうにたいへんでした。正直、つづけていけるか、たいへん不安です。ミシマさんは18年つづけてこられましたが、不安はないですか?」
このとき私は即答できなかったように思う。思うと書いたのは、記憶が定かではないからだ。ただ、走馬灯のようにこのような思いが巡ったことはおぼえている。
――明日の保証なんてどこにもない。それでも本を出す。
出版という仕事の基本はここにあると言っていい。
つい社員を抱えると、そんなこと言っていてはダメだという気になる。もちろん、実際にいつまでも明日の保証がないような状態はたいへんだ。とはいえ、そこから始まり、安定しているようにいくら思えても、今もその延長に自分たちはいる。それは間違いない。
そうだった・・・。
この思いに至ると、しぜんと口がひらいた。
「もちろん、不安です。これまでもたいへんなことは何度もありました。ただ、そうですね、やっぱりたのしい。はい、そう、出版の仕事はたのしいんです。もちろん、しんどい局面はあります。それは避けては通れません。だからこそ、楽しいという気持ちは忘れないでいたい。じゃないと、しんどいに自分が呑み込まれてしまい、くるしいだけになる」
編集の仕事、出版の仕事は、自分が会社員のころから一貫してたのしい。けれど、会社員時代の最後のほう、その楽しさより、会社にいることが息苦しかった。理由はわからない。当時は切実な理由があったはずだが、四半世紀近く経ったいま、理由の中身はすっかり忘れてしまっている。ただ苦しかった記憶ははっきりある。そして、苦しさのあまり、確実にここにあるはずのたのしさを感じられないでいた。
「ぜひ、たのしんでください。本を出す仕事ってほんとうにかけがえのないことだと僕は思っています。自分たちが企画しなければこの世に存在しなかった一冊が、一冊としてかたちになり、それをおもしろいと読んでくださる方がいる。なかには、その本に救われたと思われる方もでてくる。尊い仕事だなと思うときがあります」
キム・ボヒさんに向けて語ったのだが、発した傍から、自分の胸に沁み込んできた。
おそらく、会社員時代の最後、今すぐにどうしようもないことに苦しんでいた。たとえば、自分が望んでいるのとちがうことが会社で起こることに対して。
そりゃ、むちゃやで。
と今なら思う。他者のふるまいをコントロールすることなどできない。まして、組織が自分の望むように動くことなぞ、あるはずもない。
つまり、あのころの私は、叶うこと不可能な願いを掲げ、それが実現しないことに憤り、もがいていた。それは、地球温暖化が今すぐに改善しないことに憤り、もがくに近い。
結果、ずっとたいせつにしてきたものや、編集の仕事、出版の仕事を通して絶対的に感じていたものたちと距離ができた。
キム・ボヒさんの真剣な表情と切実な問いに、私のなかで眠っていた有象無象が目を覚ました。そうだ、たのしむのだ。この瞬間にもここにあるたのしさを、毛穴をひらいて感じることから始めよう。
この瞬間にもここにあるたのしさーー。
はっきりわかるのは、あのころの私のなかには、他者がまだ育っていなかった。存在はしたろうが、まだあまりに幼かった。
そのため、明日の保証はないことを引き受けることはせず、保証された状態で、自分の望みだけを会社にぶつけていた。そうして、
会社をつくって一番大きな変化は、否応なく、明日の保証がなくなったことだ。
もはや引き受けるも受けないもない。あらかじめ、その状態に自分がいる。
必然、会社で怒っていたことなど、思い出す余裕すらなくなった。創業から10年ほど経ったころだろうか、ひといきつけるくらいになったとき、ああして怒っていられたのは、恵まれた環境にいたからこそ、と知る。営業がいる、意見のあわない上司がいる、すべての責任を負う決裁者がいる・・・そうしたいっさいがわが身ひとつにのしかかってきた。
「この本が売れないと、来月の刊行が危うくなりますね」
「はい、それは確かです。なので、思い切った本作りをしましょう」
「思い切った本作りというと?」
「造本、仕様ともに、これまでになかった本をつくる」
「いや、それはリスクすぎます。それで売れなかったら、倒産だってありえます」
「うーん」
「原価は抑えて。できるだけ。これを基本にすえ、他のところで思い切ったことはできないでしょうか」
「売り方を工夫するということ?」
「そうですね」
こうした打ち合わせをひとりの裡でくりかえす。災害時の助け合いに見られるように、危機は他者との協力を促すものだ。同様に、自分のなかの他者たちがいっせいに協力する。どうにかこの危機を抜け出そうと、一生懸命、それぞれの立場で話し合う。
このようなやりとりを無数に積み重ね、いつしか、私のなかにいくつかの私が育っていた。
ふりかえれば、反省ばかりである。なにも会社をつくるという極端な手段をとらずとも、自分のなかに他者を育てることはできただろう。事実、多くの人はそうしている。それができなかったことを反省するのだが、しょうがない。自分にはできなかった。これが事実なのだから。
*
韓国に行く前、日本の出版状況がどんどんきびしくなってきているように感じていた。そう感じること自体、自分のなかでは驚きだった。というのは、創業時から一貫して、出版不況があるのではない、苦しいと感じているのは自らが打つべき手を打たなかった結果でしかない。こう捉えて、たとえちいさな一歩であれ、やるべきことをやるのだ、そう粛々と取り組んできた。
が、そんな私でさえ、「以前のように、売れ伸びない」とつい思ってしまっている。自分たちのやり方の問題ではなく、環境のせいではないか。と部分的とはいえ思ってしまう。
もっとも経営的に言えば、売上は過去最高を記録できた。それでも伸びの感覚が以前と違うことに対して、どう対処していけばいいか、はっきりはわからない。
そういう時期に、韓国に行き、2日間にわたりイベントに出演し、出演者のキム・ボヒさんのみならず、観客として来てくださった韓国出版界の錚々たる編集者たちとお会いした。滞在最終日の夜は、拙著韓国語版の版元UU出版の全社員さんと会食の機会を得た。
UU出版のジョ社長は私と同世代である(たぶん)。口数はけっして多くないが、彼がそこにいることで、社員さんたちがのびのび幸せそうに働いている。圧のすくない、おだやかな存在感をもった素敵なひとだ。
今回、彼とゆっくり話せたことも韓国出張のおおきな喜びのひとつとなった。印刷代や初版部数、増刷部数の単位など出版社運営にまつわる実態を、私たちは共有した。印刷代はそれほど変わらないことがわかったり、原価率の考え方がちがったり、初めて知ることも多かった。なかでも印象的だったのは、
「それはうらやましい」
と静かにジョン社長が言ったときだ。
あまり、そういう言葉を発しない人が、うらやましいと言った。
「日本とのいちばんの違いは、人口です。韓国は日本の約3分の1。初版部数もすくなくせざるを得ませんし、1万部などはめったに出ません」
これを聞いた瞬間、私はわが悩みの小ささを恥じた。
なんて恵まれた環境で仕事をできていることか。縮小していく市場。この現実を直視することを怠っていただけではないか。最初から、自分たちよりはるかに小規模のマーケットで自分たちと同じくらいのコストをかけて出版業を営む。おそらくは、悩みや課題を抱えながら、ときには、しんどいと感じながら。それでも、こうして接している方々はみな、前を向いている。
もちろん、単純な比較はできないが、少なくとも私は、出版の仕事をするのは日本よりもけっして楽ではないと感じた。その地で、真摯にほがらかに同じ職業を営むひとたちの存在を知る。いま、私は、そういう方々と出会えている。
それにまさる楽しさや喜びはあろうか。すべて、この仕事が導いてくれた。環境や状況を嘆くのではなく、むしろ与えられた環境に感謝しかない。
韓国でのこうした気づきがこの数カ月、私のなかで発酵したのだろう。
今に打ち込めばいい。その思いはつぎのように、熟成していっている。
きっと、少し先の未来には、自分のなかのあらたな私、あるいは、いまいる私の何人かが、思いもしない成長を見せてくれているだろう。そして、彼らがそのときのわたしを支えてくれるにちがいない。
まだ見ぬ私と出会えるときが来る。頼れるわたしが育っている。
そう考えると楽しみしかない。
怒涛の現場仕事に追われた数カ月後、楽しみしかない世界が待っていた。
編集部からのお知らせ
「怒涛の現場仕事に追われた数カ月後」とは・・・

今回三島が綴った「現場仕事に追われていた」ときのことを、ポッドキャスト「ミシマ社ラジオ」#17でたくさんお話ししています。『tupera tuperaのアイデアポケット』を作った知られざる過程について、なんとデザイナーの寄藤文平さんと語りました!
著者出演!『tupera tuperaのアイデアポケット』刊行トークイベント
12/2(月)まで、ニジノ絵本屋1号店にて「ミシマ社の本の贈り物展」を開催中!
tupera tupera亀山達矢さんがいらっしゃり、『tupera tuperaのアイデアポケット』刊行トークイベントを開催します。制作時の裏話や、亀山さんが贈り物にしたいミシマ社の本など、ここだけの話がたくさん聞けちゃうスペシャルなイベントです!!
開催日時:2024年12月1日(日)18:30〜
参加方法:オンライン参加(現地参加は満員に達しました)
出演者:亀山達矢(tupera tupera)、三島邦弘(ミシマ社代表)