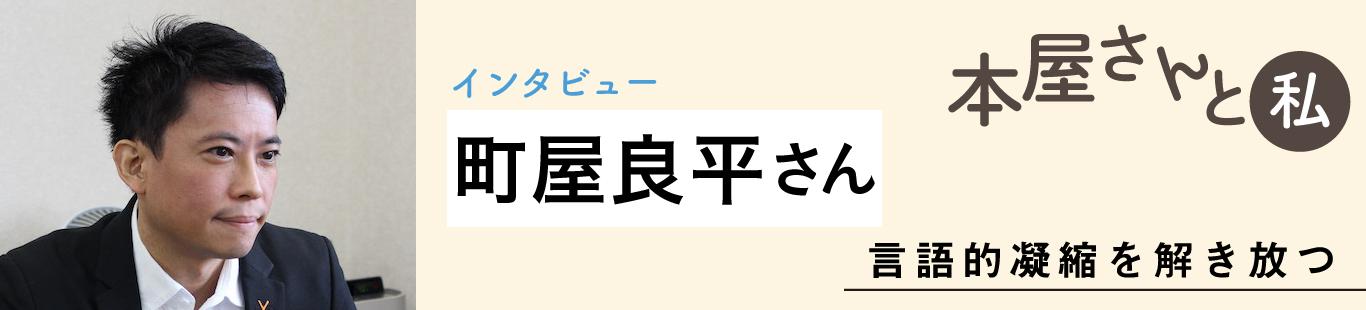第2回
町屋良平さんインタビュー 言語的凝縮を解き放つ(1)
2019.01.14更新
昨年読んだ一冊の小説に、鮮烈な印象を受けました。
町屋良平さんの『しき』。
高校二年生の青春が描かれている、にもかかわらず、読んでいるうちに、いい歳をした自分の体内に、彼らの体感が再現されるような、不思議な感覚。
作中、「きもちがのびやかになる。ひろやか~になる。」という一節が出てくるのですが、まさに、この作品を読んで、そんな気持ちになりました。
その後の最新作「1R1分34秒」が芥川賞候補にもなっている町屋良平さんに、『しき』について、小説を書くことについて、そして本屋さんについて、うかがいました。
(聞き手、構成:星野友里、写真:須賀紘也)
言語的凝縮を解き放つ
―― 『しき』を拝読していて、自分はダンスしたことがないのに、ダンスをしている体感がすごくあって驚きました。
町屋 ありがとうございます、うれしいです。
―― 『しき』ではダンス、『青が破れる』と「1R1分34秒」(『新潮』2018年11月号掲載)では、ボクシングを書かれています。どの作品にも、登場人物たちの、言葉にできない感覚を言葉にする格闘が描かれているように感じたのですが、そのことと、ダンスやボクシングといった運動を描くことがセットになっているのには、理由があるのでしょうか?
町屋 ボクシングとダンスは、自分が実際にすこしずつやっていることですので親しみのある題材ではありました。そうした要因と同時に、小説を書いて生きていると、日常的に生活のなかで起きたことを、小説に置き換えて考えてしまいます。普段会っている友達とかが発した些細なしぐさとかも、「お! 小説に登場させるなら・・・」みたいに、置き換えて考えてしまう癖があって。なので小説の登場人物にも、普通に生きている生活のなかで、些細なことでも何か置き換えて考えてしまうような、日常的に取り組んでいることがあったほうが、書きやすいんですよね。
あとは、スポーツや、本格的なものに限らずなにか運動するというのは、身体の動かし方を人に伝えたり、自分がそれまでできなかったことができるようになったり、人に教えたりするときに、言語的な凝縮というのがあるんじゃないかな・・・と思っています。それをすこし言葉にしたいです。
言語的凝縮というのは、体を動かしているときなどに人から「こうしてみたら?」と言われたりしたときに、すぐには実践できないですよね。すぐにできないから自分でそのアドバイスを「こういうことかな?」と変換したりして考え、自分で取り組んだりします。そのうちにまた、別のアドバイスをうけたりもする。そういう繰り返しのなかで、ことばが、どんどん磨かれたり、逆に鈍くなったりする。そうした言葉と体の試行錯誤の果てにパッと、自分のなかでなにか新しいものが生まれる気がしています。身体を動かすことと、頭のなかにあるものを言葉にする、ということとの関係性に、わりと囚われて生きているというところがあるかもしれないですね。
―― たしかに『しき』のなかでも、主人公の星崎くんが、日常のいろいろなことをダンスに置き換えて理解していくようになる過程が描かれていますね。
「いまのことをダンスにおきかえてかんがえると――」
などというような手つづきをふまえないでも、しぜんそうなっていた。この思考のてつづきをとりはずすことこそが、スポーツでも芸術でも学問でも、生きることのなにもかもにおいても、重要なのだとおもいはじめていた。(『しき』p69)
思ったことと言語化したことはその時点で違う
―― 今おっしゃっていた、町屋さん自身が小説に置き換えて日常を考えている、というのは・・・?
町屋 ある小説に取り組んでいるときというのは、その小説を自分が抱えつつ生活を送っているわけですよね。小説に関係ないことも考えているなかで、普通に、日用品を買ったり風呂に入ったりする時間の延長線上に、パッとなにかを思いついて書き始める、という、その転換があります。
この転換というのは、小説以外のことを考えていたときに凝縮されていた思考が、一段ステップアップするというか、解き放たれているという感じがするんです。それは、スポーツや、競技でなくても体を動かしてなにかに取り組んでいる人が、「なんかうまくできないな」と思いながら練習しているという状況から、なんかこう閃いて、できた! という状況になる、ということと似ているような気がするんです。
 町屋良平さん
町屋良平さん
―― なるほど。町屋さんの文章を読んでいると、言葉と自分が感じていることへのズレに対する逃さなさ、のようなものが強烈だなと感じました。
町屋 その言語化みたいな感覚に関しては、しつこくて細かいところが子どものころからあったと思うので、それが、10代20代とかはとくに、自分でもいやなかたちに出ていたなというのが自覚できていて(笑)。なんていうか、いるじゃないですか、すぐ反論するとか、流行っているものに対してすぐに欠点を言うとか。そういう、ある意味のしつこさが悪い面に出ていたと思います。
―― そうなんですね(笑)。
町屋 その性質というのは、いまもそんなに変わっていないんですけど。ただやっぱり、思ったことと言語化したことというのはその時点で違う、というのはよく考えてますね。しゃべりたいと思ったことと、しゃべってしまった、発話してしまったということは、まったく違うものになってしまうので。『しき』の主人公も、まさにその部分の葛藤があったかなとは思います。
―― そうですね、「ここで言葉にしちゃうと、考えたことになっちゃうから、まだ言葉にしないでおこう」というような葛藤が、主人公の中にたくさんありますね。
かれは意識のわずか外側で、友だちの病気とか、友だちの短命とか、友だちの将来とか、そういうのを「考えてしまいそう」でつらかった。まだ考えてはいない。(『しき』p59)
自分の三人称の可能性をみつける
―― この『しき』では、三人称で書くことに挑戦されていますが、たとえば作中で語りが急に未来からの目線になったり、人の心のなかのことも、ある種、なんでも書けてしまうというのは、やってみてどんな手応えでしたか?
町屋 三人称って一人称に比べて自由! というイメージがあるかもしれないんですけれども、自分としては自由と思わせて不自由なところもある、と思ったりもするんですね。自分の三人称というものがなんなのかということと、自分の三人称の可能性をみつけるということが、『しき』という小説のモチベーションになっています。
要するに、三人称一般というよりは、自分が書くビジョンとしての三人称というのはどういうものか、というのを考えるのが、けっこう楽しかったです。自分のなかでは挑戦する感覚でもあったので、それが好意的に受け入れられているとしたら、ものすごくうれしいなと思っています。
―― 物語の最後のほうで、星崎くんと草野くんのダンスが合ったときに、二人の会話が4つの鍵括弧で書かれていて、その間に入る文章がすべて「かれらはそういった」となっています。それだと、どちらが言っているかはわからないのですが、この場面にはそれが一番しっくりくる感じがしました。
「合ってるじゃん!」
かれらはそういった。
「おまえがんばったな!」
かれらはそういった。
「てっきりモチベさがってんのかとおもってたけど」
かれらはそういった。
「がんばって自主練してたんだな」
かれらはそういった。(『しき』p151)
町屋 そうですね。いま言ってくださったような感想がほんとうにうれしい。ことばの運動とからだの運動が交錯してゆくようなイメージでした。
小説そのものになってもらう
―― 小説には、思いっきり悲しみを味わうものとか、非日常のホラーを感じるものとか、いろいろなものがありますが、町屋さんは小説を読者に渡すときにどんなイメージをもたれていますか?
町屋 小説で共感するということは、実はその、簡単といえば簡単というか、共感能力が高かったら、小説のなかで登場人物に悲しいことがあったら、読者もやっぱりふつうに悲しいですよね。それがいわゆる感情移入や共感といったものになると思います。基本的に自分は、感情移入や共感というものに関しては、小説のなかではちょっとだけ冷たい態度をとっていると思います。
その感情移入や共感というものの裏側とか向こう側を目指すという意味で、もう、小説そのものになってもらうというのが自分としては一番やりたいことです。そのために文章を書いているので、本当に、踊ったことがないのに自分が踊っているみたい、という、そういうのが一番うれしい。
(つづく)