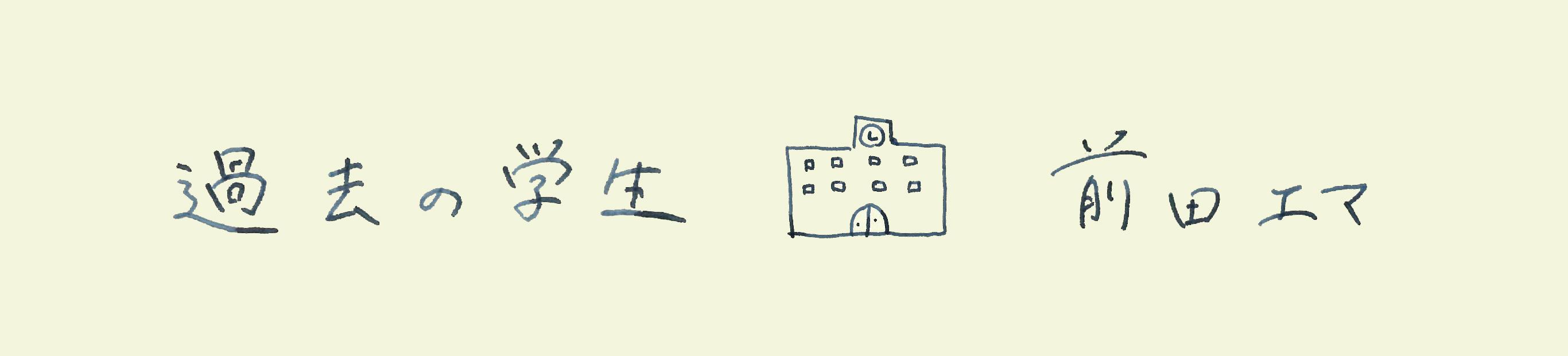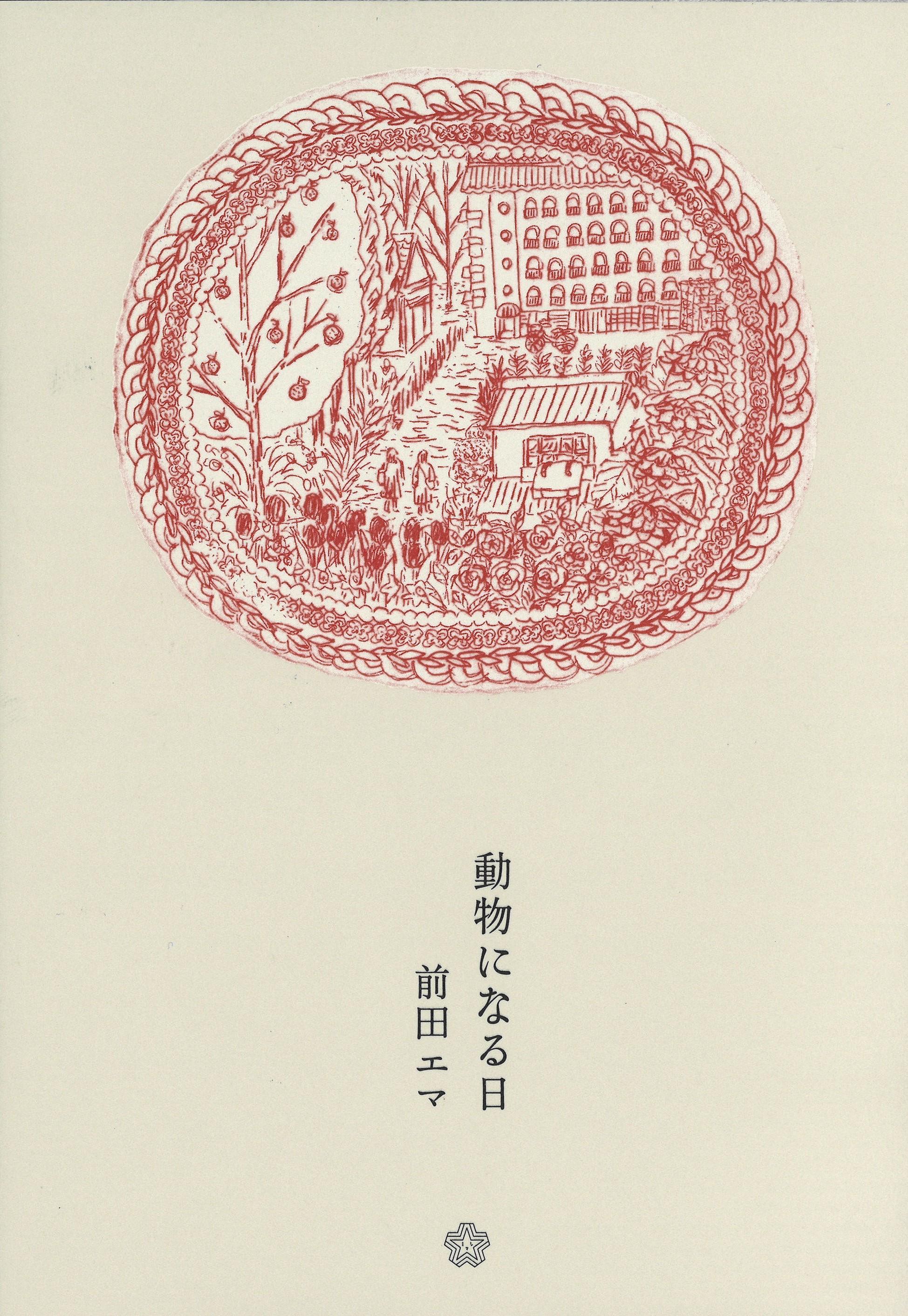第15回
学校えらび(後編)
2023.11.23更新
中学まで地元・川崎の公立学校に通った私にとって、初めての受験は高校入試だった。あれはものすごく不思議なシステムだと、今になっても思う。
日本の入試の多くは、学力で人間をレベル分けするというシステムだ。私はこれがものすごく気に入らず、中三の頃は「受験しなくちゃいけないなら、高校なんて行きたくない」とブーブー言っていた。しかしとても甘やかされて育った自覚があったので、まだ社会に出て自分でお金を稼いで生きていく姿は想像できなかったし、無駄なことを考え、遊び悩む自由を手放す勇気はなかった。
地元の公立学校は、ごちゃ混ぜなところが心地よかった。勉強が得意な子も、苦手な子もいたし、親の収入も職業も、家庭環境も、政治的思考や宗教も様々で、ひとりひとりのことを理解できずとも、その多様さが私の目にはキラキラと映った。そしてそれは、あの年齢だったからこそ可能だった、二度と戻っては来ないであろう大切な時間だったように思う。
子どもが出会う世界を最初に作り出し与えるのは、よくも悪くも親だが、そこを少しだけ離れ、最初に出会う世界が"学校"という場所だったように思う。公立に通わせる親もいれば、公立にしか通わせることができない親もいただろう。しかし、このある意味での無法地帯が、私には合っていた。両親が外国人で日本語がうまく喋れない子、落ち着きが無く授業中に教室を何度も飛び出してしまう子、親にお弁当を作ってもらえない子、宗教行事に勤しむ子などと交わる世界が、自分の人生にあったことが、今の私を作っているような気がする。地元の学校へ通っていると、みんな家が近いので、友人の家に遊びに行くことも多かった。大地主の家から、マンションやアパート、社宅や団地...。家が商売やお店をやっている子も多く、不動産、トンカツ屋、豆腐屋、居酒屋、魚屋、床屋、スナックなど、様々な職業を垣間見た。
先日、友人の友人の話を聞いた。その人は自分の子どもの小学校受験に翻弄されているそうなのだが、お受験のための塾の面接で「お母さん、その眼鏡は変えましょう」と言われたそうだ。"親の受験"とも言われる小学校受験では、大きな縁の個性的な眼鏡だと落ちるのか...。
高校受験の際、美術の先生が「エマさん、美術系の高校へ行ったらどう?」と言ってきたことがあった。結果として私は(勉強ができないがために)美術大学に進学することとなったわけだが、あの時に美術高校へ行かなくてよかったと思う。今、考えてみると、学生時代はできるだけ、似たような思考、似たような家庭環境の人たちとなるべく離れたところで過ごせてよかったと思うからだ。
しかし、子どもはとても弱い生き物だ。身体や心が弱いという意味ではなく、自分でコミュニティを作れる力も情報も、大人に比べて乏しい。親から逃げたい、友人から逃げたい、先生から逃げたい、仲間が欲しい、相談できる人が欲しい、守ってくれる場所が欲しい。そういったときに、子どもがひとりぼっちにならない環境が与えられているべきだ。多様さが野放しにされないようにしなくてはと思う。
大人になればなるほど、私たちは自分でコミュニティを作ることができるようになっていく。自分の身を置く場所や社会を選択できる。会社に属することも、フリーランスになることも、学生になることも、家庭を持つことも、親との距離も、様々な権利への追求も、自分で決定できるスキルがついてくる。しかしそれは、他者を排除することや、理解できない他者への攻撃と、紙一重だと感じることがある。
最近親になったばかりの友人と話をしていたとき「とは言っても、最近の公立学校の教育って、どうなんだろう?」と心配していた。教師の時間外労働はとても重大な問題で、教師へのフォローが不足していることからやってくる授業の質の低下、生徒個人へのフォローの限界はもちろん、性教育や歴史教育の内容などを考えると、子どもに少しでも良い教育をと願う、彼女の気持ちもわからなくもない。
いじめ問題も後を絶たないこの世界で、子どもがいても、そうでなくても、学校を選ぶとはどういうことなのか、これからも考え続けなくてはと思う。