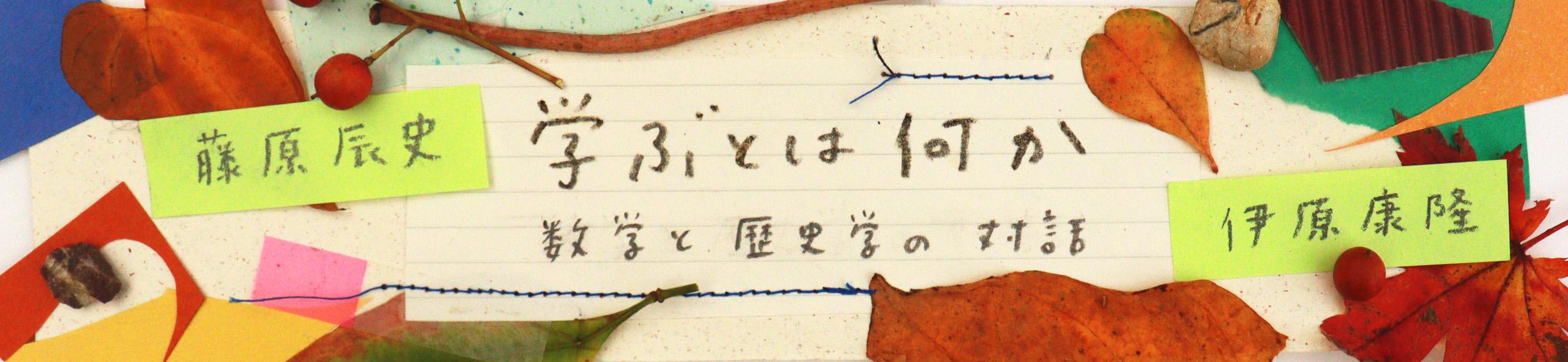第12回
他国語から○○を学ぶ(伊原康隆)
2022.04.20更新
歴史学者の藤原辰史さんと数学者の伊原康隆さんによる、往復書簡の連載です。藤原さんから伊原さんへの前回の便りはこちらから。
伊原康隆>>>藤原辰史
ご謙虚な、そして門外漢にもわかりやすいお話をどうも有難うございました。ご自身の「失敗を思い出しながら」のご記述も、特に若い方々にとってよい参考になると思います――ノーベル賞受賞者の成功談より実質的! 失敗談には事欠かないこの私こそもっと書いてもよかったかもしれません。そして、これからのお互いの第二歩とその共有に向けての試行錯誤がとても楽しみです。
今までのお話によって「歴史は繰り返す」についての新たなポイントが私にも見えてきました。暴力の、時代を経た連鎖はどうして続くのか。それは為政者が、そのときどきの新たな正当化を、過去の歴史の恣意的な解釈によって試み、それが一時的には十分な説得力を持つことによって「こそ」繰り返されているのだと――プーチン論文もその一つ。こうなると旧来の標語「ペンは剣よりも強し」にも新たな意味づけを求めないといけないだろう。「言葉」は暴政側の武器にもなっている。言葉の力という、本来は平和志向側の道具を彼らに引き渡すのは、言葉の「曖昧な使用への鈍感さ」だ。こうした思いをさらに深めることができました。
言語以外の表現の力については後の話題にすることにして、今回は「ミミズの迂回路」かも知れませんが、それぞれの言語文化に特有な「表現のしやすさと表現の自然な強さ弱さ」についての例、そしてその特徴が与える個人と社会への影響、これらの話から始めたいと思います。これは特徴の異なる他国語との比較によってこそ見えてくるものですね。
以前、アメリカの友人(10歳以上年下、北欧系のA君)との共同研究が予想外な荒波を受けたことがありました。第二弾の成果の発表のときでした。主には誤解にもとづく「波」だったのですが、勉強になる厳しい指摘も含まれていました。A君との真剣な相談のやりとりの末、彼が手紙の末尾に書いてくれた言葉が
Well, Live and Learn!
でした。実は幾多の思いの籠った言葉でしたが、あわせて「語感の力強さ」も印象に残ったのです。蛇足ながら解説しますと、まず冒頭の「Well, ...」 は一息ついて手紙を締めくくる「まあ結局、。。。」の雰囲気。続く呼びかけ「生き続け学び続けよう」(Let us が省略されている)の主役は live とlearn。人生で基本的なこの二つの動詞が生き生きと使われています――live は「死ぬに対する生きる」より積極性が強い、learnも「科目の履修」のような study とはやや異なり「具体的な知恵を学ぶ」という意味合いが強い。日本語でなら「まあ、生涯学習だねー」となるのでしょうが、これではインパクトがかなり弱まると私は感じます――「忘れ得ぬ言葉」vs「忘れてしまいそうな言葉」。
ロシアの攻撃に晒されているウクライナでは、個人の Live への意志が(学びどころかあらゆることと無関係に)不条理に抹殺されています。プーチン氏に呼びかけたいのは「(他者の生命を)生かすことを学んでくれ」
Learn, to Let Live!
(後半語気をどんどん強めて)ですね――ロシア語ではどういうのでしょうか?
次に、ご存知の
Black Lives Matter!
(ここでは Black が形容詞、Lives が名詞、Matter が動詞)これは「日本語に訳しにくい」なぜなら「黒人の命 (は)(も)大切だ」が「は」か「も」か決めかねるからといわれます。でも私は
Matterという動詞――この止むに止まれぬ自己主張の叫び――
が日本語では伝えにくいのだ、なぜならそういう用語がないから、というほうに焦点を当てたい。Matter は、「は」「も」等のいわゆる 「be 動詞」によって「大切」という形容詞とゆるく結びついただけでは表現しきれない積極的な心の動きを表現しているのに。。。母親に「そんなこと、どうでもいいじゃない」とあしらわれた子供が「よくはないよ」と言い返すのは否定形になり「いつもの反抗」みたいですが、It doesn't matter に対して It matters! (または It does matter!)と言い返すのなら強い肯定形の自己主張でしょう。
自己主張しやすい言語体系が「弱者にも使いやすい形で」整っていることが肝要だとつくづく思います。「弱者」は親に対する子、先生に対する生徒、を含みますからこれは初期中期の学びの場にとって、従って国の文化にとって、基本的な事柄でもあると思います。人文科学の先生方のお力を是非お借りしたい。
自動翻訳ソフトが進歩しつつある現代、外国語なんかまじめに勉強しないでもすむと思っている若者がおられるかな? 上の二、三の例など翻訳したら良さが消えてしまうと思われませんか? 異文化を知るためには、まずは翻訳物を通してというのも賢い順序でしょうが、精神も込めての多様性を学ぶには、まずはその国の言葉の使い方の「特徴の面白さ」を感じ、その言葉――少なくとも特徴のある表現法――を好きになることから始めなくては。。。他国語は自国語の「第二の鏡」でもありますし。
以前の書簡でイタリア語の表現を借用した責任上、
「文化は言語体系に深く影響されている」
というサピア・ウオーフ仮説の提唱者ウオーフの著作『言語、思考、現実』(講談社学術文庫)、およびそれに対する反論を含むドイチャーの著書『言語が違えば、世界も違って見えるわけ』(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)をひもといてみました(とりあえず和訳です)。これらについては又いずれと思いますが、文化への影響をより深いレベルで真剣に考察しているのはサピア・ウオーフ側のような気がします。この仮説はその後「エビデンス不足」のかどで攻撃され下火になっているようです。エビデンス不足論には半分は納得がいきますが、元々の仮説での「文化への影響」は「深層での影響」であり、直截的なエビデンスなど元来あり得ない、だから沢山の小さなエビデンスから「主張のレベルに応じてその可能性の大小を評価」するしかないという事は明らかです。それなのに反論はせっかちだと私は感じました。
なお、ウオーフについて特に注目したいのは、幾多の「未開人」の言葉が幾多の点で欧米語より分析力などに優れていることにも気づき指摘したことです。彼はアメリカの大学(MIT) では化学を履修し、就職した火災保険会社で主に化学製品由来の火事の原因究明、予防運動と啓蒙活動に積極的に携わっていました。その中で、たとえば「使用済み缶」ではなく「空き缶」と呼ばれ乱暴に放置されていた揮発性ガスを残す危険な缶が「その大雑把な呼ばれ方のために」多くの火災の原因になっていたことにも気づき心を痛めていました。探究心と善意そして感性でしょうか。これらが、以前から中米文化に魅せられ研究していたことと結びついて、言語の「粗雑さと比較」の研究に乗り出したという経歴です。後に言語学の学会でも有名になり大学から引っ張りだこになってからも火災保険会社の仕事を仕事の中心として最後まで辞めなかったとのこと(前述の書物の中の「編者解説」より)。
この「空き缶」の話は研究の「動機」であって仮説の「要因」ではありませんが、それでもここで言及したわけは、「原発事故」の雛形として対比していただきたいからです。言葉の曖昧さに気づかないことの弊害のうちこれらはいずれも、「起こりうる危険性の『過小評価』」だったのでしょう。
日本語の(曖昧、情緒的といった)特徴が文系文化、理系文化それぞれにあたえた影響については言いふるされています。でも私の(限られた)体験から追加したいのは、理系の研究交流の場での表現が西洋では大げさなぐらい「強調すべきことを強調」するのに対して日本人の多くは事実のみを平らに述べているという印象をうけること です。日本人の関心の的は事実だけで、そこに至る「動き」を知ることへの興味がかなり薄いのではないか、これでよいのだろうか?
そして日本語で表現が平板になりがちなのは、状況を基本的には受け入れている人間同士の間で長く使われていた言語だから、静的で精緻な描写が多く、名詞や形容詞と 「be 動詞」が中心を占めている、そういうことかも知れません。それがひいては、動きに対する「言語的な縛り」になっているのでしょうか。もっと調べたいことですが、サピア・ウオーフの仮説は、私は少なくもこの意味で支持したいと思っています。
藤原さんのご書簡で思ったのですが、琉球民族もアイヌ民族も言語を奪われたのでしたね。これによって伝統文化の継承もかなり損なわれたに違いないでしょう。民族衣裳や踊りなど「形が目立つもの」は残されたかもしれませんが、より基本的な「ものの考え方、感じ方」はやはり言語に深く依存しているのでしょうから。ただしアイヌの叙事詩ユーカラが残されたのは有難いこと。芭蕉も永く残されるのは城でも草木でもなく歌や文であろうという趣旨のことばを残しました。
さて上の例(Live and Learn, Matter) はいずれも「主語が自分(たち)で動詞の意味も明瞭」なときの正の表現でした。これに対して
主語が相手または第三者で動詞が「be 動詞」
の場合は、お話にあった負の表現「あいつはクレイジーだ」とか正負二分割の "You are either with us, or terrorist" とか、非文化的な「きめつけ」または暴力的な「味方と敵への二分割」が表現されてしまいます。自己主張しやすい雰囲気が足りないと、他者に対して「〇〇は〇〇だ」と否定したくなる、多分そうなのでしょう。自分の過去を振り返っても恥ずかしながらそんな時期もありました(日記が証拠)。加えて政治家の我田引水、マスコミのせっかちに結論を求めたがる社益本位、これらが大きな問題でしょうね。
二分割、二律背反の危険性もさらに論じ合いたいテーマです。ここでは以下の場合に絞りましょう。
学びの場で「困る二分割」といえば「わかったか、わからないか?」の答えを迫られるときでしょう。「分析的わかりかた」ついては前回フィルターの話でもふれました。今回は
「でも何か変」
型のわからなさについて考えてみましょう。これを感じるのは脳の右半球の作用だという学説をお聞きになったことが多分おありでしょう。私は神経経路のことは知りませんが、半球の左右の区別は鳥や魚にもあるそうで、鳥が沢山の粒の中から餌をよりわけるのは左半球、天敵の接近に感づくのは右半球という話です。餌探しに血眼になっているときはこれが働きにくく危険かもしれません。われわれの場合も、気分をちょっとゆるめる、そして周りを見渡す、つまり視点を変えてみる。能率優先志向だと意識が邪魔をするから散歩に出たり睡眠から目覚めた時とかが「右の出番」ではないのかな。
他人の論文を読んでポイントをつかむためにもこの「何か変」という感覚が必要です。かつて指導教官をしたある院生の学位論文の話ですが、その研究がのちに大いに発展した際(そのごく一部の議論について)私にふっと疑問が生じ、教室の図書室に保管されていた彼の学位論文を再度眺めてみました。するとその箇所にポツンと「?」だけついていました。ご当人もやはり変だと気づいたらしく同じファイルを開いたら「先生も?をつけていた、見てくれていないようで意外に見てくれているんだとわかった」といわれました。そりゃー給料をもらっているのだし、とりあえず「右半球だけ」でも働かなくては。。。
「何か変」を強いて突き詰めると「こういうことを結論できるためには、その周りが十分耕され、それぞれの角度からの観察結果も使われていなくては。。。」という一種の調和感覚でしょう。いったんゆるめないと働きにくいものらしいです("Loosen Thinking" )。なお、巷で詐欺に騙されるのも「そんな都合の良い話が成り立つはずがない」という感覚が働く余裕があったら防げたのではないか? すべて深いところで共通している、どの分野からにせよ学びを通してそれに近づいていけるのではないでしょうか。
次回以降も、人文学と数学の共通要素――虚数と2次元運転! も含む――についての私の考え方を、熟しかけた順序に従って(ただし半熟でも秋まで待つのではなく)書かせていただきたいと思っております。今後もどうぞよろしくお願いいたします。