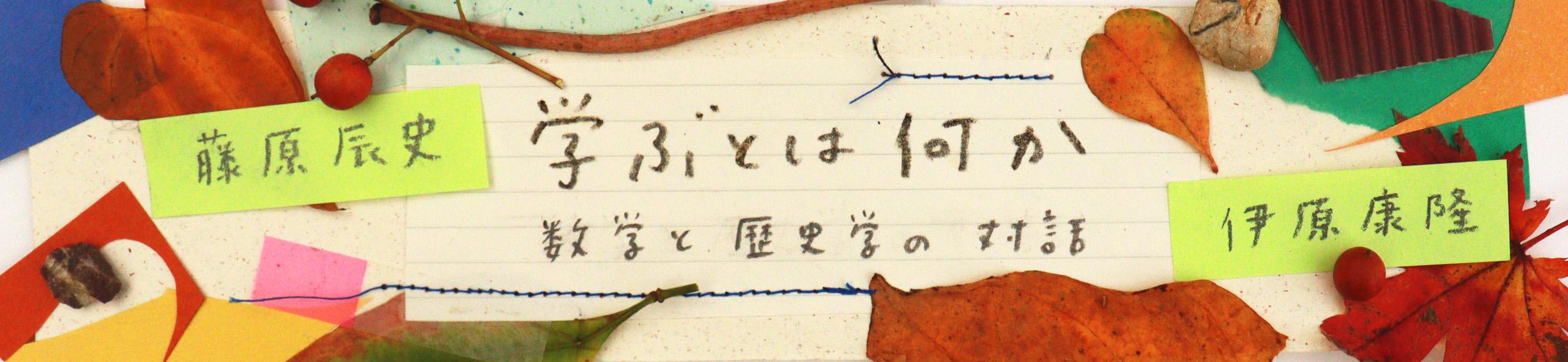第14回
大学の使命とは?(伊原康隆)
2022.05.16更新
歴史学者の藤原辰史さんと数学者の伊原康隆さんによる、往復書簡の連載です。藤原さんから伊原さんへの前回の便りはこちらから。毎月20日に公開している伊原先生からのお返事、今回は言及される内容に沿って、掲載を早めて公開いたします。
伊原康隆>>>藤原辰史
本当に学びたいと思ったら、なるべく「ゆっくり」学びましょう。研究段階でも「じっくり」が大切でしょう。何故こんなことをわざわざ偉そうに書くのかというと、このゆとりを大切にしない風潮の強まりが無視できないと感じるからです。風潮は、環境と個人の双方、の問題ですが、まず環境、それも今回は大学での研究環境についての話からと思います。今回は、後半に言及する事態に対する「緊急アピール」としての意味もこめております。
大学も当然、社会の中にあって財政的支援を受けて成り立っています。学生の教育に加えて学術研究への資金を得るためには、
「長い意味で」研究の成果が社会に「還元」されなければならない
これは当然でしょう。問題は「還元」と「長い意味で」の語感が世間そして政治家たちにどう理解されているかでしょう。双方に対して私なりの意見があります。どこまでを「還元」とみるかは文化の価値の受けとめかたに左右されますね。文化の価値の軽視傾向への危惧の念は他所で書かせていただきました。
「長い意味で」のほうが今日の主題と直結します。「研究らしい研究」には如何に長い年月がかかり、それが世間に理解されるのには如何に更なる年月がかかるのか、実例のいくつかをあげてみましょう。
まず「成果とはすぐ役に立つこと」という考え方に対してです。「電磁気学の父」と後によばれるようになったマイケル・ファラデー。
「そんなことが一体何に役に立つのですか?」
一般のご婦人からのこの質問に対しての彼の答えは
「貴女は生まれたての赤ん坊が将来どういう役に立つのか答えられますか」
そして国会議員からの同じ質問に対しては
「今に貴方は電気に税金をかけろと主張するようになるでしょうね」
だったとのこと。
痛快な返答ですが、ここで更に肝心なのは、ファラデーに限らず、そこに至るまでの萌芽的な研究が必要だったわけで、その資金は無理解な政府の介入によって阻止されてはいなかったということ。研究対象と方向性の選択は研究者たちに任せるというのが文化を育てるための政策の基本であり、当時のイギリスではこの基本は理解され守られていたということを、どこかの国の政府も肝に銘じてほしい。
ちなみに、元は化学分野だったファラデーは、後にクリミア戦争の際、化学兵器の作成を政府から依頼され「作ることは簡単だ。でも絶対に手を貸さない!」と断固ことわったといわれています。
次に、価値判断は先入観に左右されやすいという事例。
集団遺伝学の創始者である J.B.S.ホールデンは、学術上の新説は相手(評価者)側の4段階にわたる反応過程を経て初めて受け入れられる、と風刺しています。
まず
(1)馬鹿げたナンセンス (worthless nonsense)
と言われ、
(2)面白いけれどひねくれた見方 (perverse point of view)
(3)正しいけれど重要なんかじゃない (quite unimportant)
そして時が経ってからは、開き直って、なんと
(4)自分はいつもそう言っていた (I always said so)!
スケールは違いますが私の初期の研究でも思い当たることです。これらに加えて、関連性の新しさが理解されず、キーワードだけしか見えない「識者」からの「そういうことは〇〇(有名人)さんたちがやっていますよ」もありました。客観的という名の外部評価を求めると、どの壁に跳ね返されるのかな。
以前、NHKTVの「クローズアップ現代」で(なつかしき)ベテランキャスターの国谷さんが、締めくくりに「なるほど、独創的な研究を育てるために、研究費をもっと重点的に増やないといけませんね」と相槌をうったときに私が呟いたのは
「独創性」と「育つ段階では周囲に価値が理解されていない」は表裏一体
ではないの? でした。そんな早くから価値がわかられるのは独創的ではないのに、と。
あるエンジンを共同開発した二人がなかなか受け入れてもらえなかった時期にそのエンジンにつけた名前が「タマルカエンジン」だったとか。簡単にわかられてたまるか! この気概が成功のもとでした。
私事で大変恐縮ですが、ある学術賞をいただいたとき夕食会で文部科学大臣が受賞者たちに「でも、もっと若い方々かと思った」と漏らされました。「始めたのは若い頃で、認められるのに何十年もかかったのですよ」と、どなたか代表で言って欲しかった。年月がかかるということが理解されていない。
「 良い研究には時間がかかる」の例外は、ある有名な問題を解けるための材料が整いつつあり機運も高まってきていて、あとは「誰が最初に」ゴールに飛び込めるかという(スポーツ競技でわかりやすい)場合です。
これに対して、見えていなかった問題の発見や分野自体を切り開くという貢献の価値が大勢に認められるのには何十年もかかる、また、今までの常識を覆す理論を作った人々はさまざまな角度からそれを見直すことで並みいる反論を時間をかけて論破してきたわけでしょう。こういう例も枚挙にいとまがありません。
若い人たちの仕事は実績ではまだ評価できません。その場合に見込みのありそうな研究に着目して推挙できるのは誰でしょうか。それは、身近にいて、あるいは論文などで知り合ってディスカッションしたことがあり、当人の視点や切り込んでいく力に強い印象を受けてきている先輩の研究者だと思います。新しい考え方が成果らしい成果を出すまでは、運不運もありますが、かなりの年月を要するものです。
ですから大学の教官たちに任せるべきだと思います。若い人は自分にあった先輩を探し続け、最初うまくいかなくても「捨てる神あらば拾う神あり」で拾ってもらうことを考える、これが本道でしょう。数学では、後に彼の名を冠して呼ばれる「双対性」を思いついて追求していた若い頃のロバート・ラングランズも、論文数が足りないとの「客観的評価」を受けて憤り(当時私も客員としてご一緒だったプリンストン大学から)拾ってくれた他大学(エール大学)に移りました。
さて、現在参議院で審議中の「国際卓越研究大学」法案が通って適用されるようになったら、ますます心配になりますね。潜在的な候補となりそうな大学では、どんな研究計画が立てられ、研究分野ごとの重視と軽視が学内に於いても色分けされていくのか、暗澹たる思いです。選ばれた大学でも特定の研究に資金が集中する一方他方面は痩せ細る。そして研究者はいつも短期的な視野に拘束され研究計画の作文に時間をとられる。大学は「文化」を早く作って安く売るコンビニで学長はその店長。。。であって欲しくありません。
藤原さんは勇気がおありで毎日新聞(4月28日夕刊)「[国際卓越研究大学] 研究の破壊を加速」に、この法案への危惧の念を表明され、反対声明への署名参加の呼びかけもされ(私も当然賛同)ましたが、多くの大学教員が、やれ反対すれば自分が所属する大学に迷惑がかかるだろうとか、大学内での自分の立場が悪くなるだろうとか、やれ無駄なことはしたくないとか、忙しいからとかで反対運動が盛り上がらないとすれば大変残念なことですね。学者は一蓮托生のはずなのに。
数学は比較的資金がかからない分野だし、政治への関心が(以前は)薄かった時期も長く、私にはこれを憤る資格がないかも知れないのですが、少し広い範囲でなら、やはり「義憤が希薄になっている」ような気もしています。
私が心配していることのもう一つは大学の分断化です。卓越クンに選ばれた大学とその他との、たとえば人事交流もどうなるのか、そして、卓越クンの中での分野横断的な研究はどうなるのか。たとえば藤原さんと私(の後輩)、人文科学と数学という一見かなり離れた分野も、少なくとも現在の私の目でみると、本質的な交流を推進すべき二分野ではないか。
たとえば、論理、推理の観点では、人文科学 対 数学 は
人間社会での相関関係と偶然性 対 自然界での因果関係の追求
現代はAI の開発でも、因果関係、相関関係、偶然、を切り離「さない」言語を作る研究から始まっているようです(J. Pearl「The Book of Why」)
ちなみに、この本の中に(前回の「サピア・ウオーフの仮説」と関連して)次のような象徴的なフレーズが見られました。
"Language shapes our thoughts.
You cannot answer a question that you cannot ask;
You cannot ask a question that you have no words for it."
この"words"の作成の試みの説明がこの本の主眼のようです。
また言語としては、人文科学 対 数学は
多くの固有名詞の世界 対 多くの 代名詞の世界
でしょう。数学の「記号系」は実は「系統化された代名詞」にすぎませんから。これらをどう活かしあえるだろうか? これからの対談用としていろいろ考えてみております。
そして、お互いに深いところで影響を受けあうことが文化の醸造につながるのを期待したいのです。「対」と書いたように、対立する要素の方が目立つ中での共通性の追求ですから、人間的な相互信頼があってはじめて実りある討論ができるでしょう。敵対的雰囲気でなく意見の内容には異議をとなえあえること。こういうのが法案によって分断されないことを祈っています。
それともう一つ大切なことがありました。こちらはよく言われているので私が書く必要はなさそうですが、理系の人間は、追求心が際限なく進むという心理的な傾向があり、それによっておそろしい武器を作る歯止めのブレーキがどうも弱いらしい。
上記のファラデーは偉大で、決してそういうことには手を貸そうとしなかったのですが、一般的に「技術的にできることは、良いか悪いかの判断を飛び越えてやってしまおうとする」心理的な傾向を持っていると思います。卑近な例では理系の同窓会でズームの記録を「保存できるから保存しよう」(老化の記録を保存してどうする!)また、大ホームランのリプレーで高々と舞い上がった飛球を追跡しそこだけをズームする技術ができたら「何時もそれ」ばかり。だってホームランの映像で効果があるのは、唖然として空を見上げるだけの外野手であって、単独のボールには何も意味しないのに。要は、ちょっとでも考えるということを全くしないで面白がるのです。
はるかに重要なブレーキの機能のためにも、人文科学系との連携が欠かせないと思います。今後、卓越クンは軍事研究を拒んではダメだよ、となったら一体どうなるのでしょう?
最後にもう一つ補充させてください。上の話から、図式
理系 → [出来る=やる] 傾向性 → 武器開発に加担 → けしからん
を書いて → を論理記号と見ると「だから理系はけしからん!」となってしまいます。ここでファラデーとパール(Pearl)の再登場です。二つ目の → は「原因の一つになりうる」というだけであって、ファラデーの例が示すように論理記号ではなく、その周辺にこそ、知性らしい知性の役割があるのでした。これは、パールたちが示している方向(一つの → と考えられていたものを、逆向きの ← も含む複数に分解する言葉を作る)でもあります。数学では、矢印は構造をもつ2つの集合の間の「写像」A → Bとして主に用いられ、「含まれる」という関係と「類別」との合成に分解して研究されます。たとえば上の図式の最初の → は前者、真ん中のはどれでもなく、最後のは後者(類別)です!
次回これらの言葉にも触れてみたいと思っています。