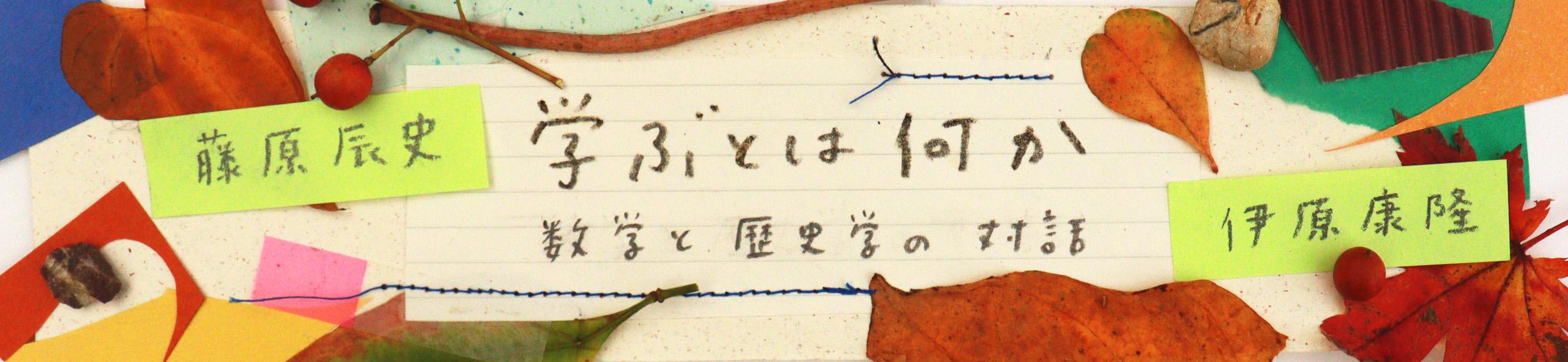第25回
学びが止まらない(藤原辰史)
2022.11.11更新
歴史学者の藤原辰史さんと数学者の伊原康隆さんによる、往復書簡の連載です。伊原さんから藤原さんへの前回の便りはこちらから。
藤原辰史>>>伊原康隆
数学の問題を考えていたのに、インドの演奏家の音楽に惹かれ、いつの間にか壇上に上がって歓談していた伊原さんのお話を聞いて、手にとるようにイメージができました。
伊原さんの知性と感性の話に触発されて、少し話がずれるかもしれませんが、私は学ぶことの喜悦について考えてみたいと思います。小さなころ、何かとてつもなく面白いことに出会うと、つい体がぎゅっとなってこそばゆい感じになりました。喜悦というのは、その感覚といいましょうか。あるいは、背筋がぞくっとするような感覚と言ってもよいかもしれません。私の場合は、心臓の音がドクドク聞こえることが多いです。
少なくとも私が学ぶ過程で心臓が高鳴るのは、こんな出来事です。学びとは、このような学び手の心の動きを切り離せないと私は考えます。
モダンなキッチンの背景
一つ目は、何気なく本を読んでいると、自分にとって仮説に過ぎなかったことが、疑うことのない事実の提示によって論理的に説明されているときです。「やっぱりそうだったんだ!」というあの感覚です。
たとえば、ドイツの台所史を研究していたときのこと。マルガレーテ・シュッテ=リホツキーというオーストリア初の女性の建築家が、第一次世界大戦後のドイツのフランクフルトで、大量生産型で、ガスか電気をエネルギーとし、煤と煙から別れを告げた清潔なキッチン、すなわち「フランクフルト・キッチン」を設計します。残されているこのキッチンの写真を見ますと、食料を入れる引き出し型の収納がたくさんある。とってもモダンで明るくてスタイリッシュなものですが、私は写真を眺めていて、どこかに「暗さ」や「陰」を感じ取っていました。けれど、それがどうしてなのか自分で説明がつかない。「直感」とでもいうものですが、証明するものがなく、ただ頭の片隅に、からまった糸のような散らかった感覚にすぎませんでした。
ところがある日、ドイツ語で書かれた彼女の自伝を読んでいてある箇所に目が釘付けになりました。リホツキーは、第一次世界大戦のときに猛烈な飢餓を経験していたのです。しかも以前に読んだときには引っ掛からなかった箇所です。「え?」と思いました。女性をきつい台所仕事から解放することに加え、二度と人びとが飢えないような台所を設計することが彼女にとって切実な重要なテーマだった、ということが痛いほど伝わってきました。実は、私は、フランクフルト・キッチンの写真を見て、食料を入れておける引き出しの数が多すぎるとも感じていました。諸々の史料を突き合わせると、リホツキーの設計思想に、彼女の飢餓体験が深く関係したことが証明できました。小さな発見に過ぎませんが、思わず「やっぱり!」と声を上げました。
これまでの書簡で既に述べたかもしれませんが、文系でもっと重視されて良いと思われるのが、数学にとって極めて重要であると思われる「予想」という行為でしょう。予想は外れることもあるし当たることもありますが、ただ漫然と資料や本を読むのではなく、事前に予想を立てながら本を読んでいくと、引っ掛かりがたくさんついたかたちの知を得ることができますし、何より、他の研究者たちのヒントにもなります。
研究会での発見
文系の学生も院生も研究者も、1時間から2時間くらい他人の研究発表(それは調べてきたことを概念や理論を用いて分析し、一つのストーリーに仕立てあげるもの)を聞いて、質問したり批判をしたりする「研究会」という共同の「学び」の形式がおそらく理系と同じように、あるいはそれ以上に重視されていると想像します。大体、14時ごろから18時ごろまで続き、お腹がグーっとなったところで終わり、食事に出かけます。歴史学にせよ、文学にせよ、基本は「読む」ことですから、孤高な作業が多い分、他人との対話はブレイクスルーに欠かせません。ひたすら話を聞いて、線を引いて、コーヒーを飲んで、メモをして、批判点を挙げていく、という行為は文系の場合、補助的ではなく、どんなに歳をとっても、本質的な「学び」であり続けます。私も院生のころから、数えきれないくらいの研究会を経験してきました。人文社会科学の分野では、どんなに資料を集めて読み込んでも、数学のように一ミリのブレも許されないような概念の堅牢さがありませんから、独りよがりになりがちです。そこをみんなの目線にさらして、「答え」に到達するのは無理にしても、せめてみんなが共有できる「たしからしさ」を求めて議論を続ける。ただ、研究会は発表者のためだけにあるのではありません。聞いている側にとって創造的な行為にもなりえます。自分の研究分野とほとんど異なる発表なのに、自分の難問を突破するような概念に出会って、興奮する経験がしばしばありました。
たとえば、拙著『縁食論』の元になる文章を書いていたとき、孤食でも共食でもないあり方を、どう表現していいか考えあぐねていました。言葉の表現の仕方は私たちの研究の命です。最初は、ハンナ・アーレントの議論を参考に「公食」という概念を捻り出し、ある研究会で発表したら、「公」という字があまりにも「お上」のイメージが強すぎるので、自治的なイメージが抱かれにくいと不評でした。
ところが、ある研究会で、建築に詳しい哲学研究者の篠原雅武さんから、若い建築家たちが挑戦しようとしている空間づくりを「縁en」という言葉でまとめ、ヴェネチアのビエンナーレにそのコンセプトと一緒に建築家のプランを出品したところ、審査員特別賞をもらった、という話を聞き、その図録をいただきました。「縁」という東アジアの文脈でしか用いられない概念でも海外できちんと評価されることに驚きましたが、翻訳しにくい言葉を用いることにどこか躊躇もありました。そしたら、別の研究会で南方熊楠の発表を聞いていたとき、自然科学と人文科学双方にわたって大きな痕跡を残した熊楠の世界観においても「縁」という概念が重要である、という議論が偶然にも出てきて、それがあまりにも私の悩んでいたこととフィットしたので「縁食」という概念を思いついた、という経緯があります。
読書会の興奮
もう一つ、文系の研究で欠かせないのが読書会です。実は、伊原さんにも友人とたまにやっている読書会に出席いただくことが多々ありましたよね。本当に刺激的でした。たとえば、村上春樹の『猫を棄てる』を課題書とした読書会のとき(参加者はほとんどが文系の人)、伊原さんの解釈があまりにも的確かつ説得力があって、みんなで舌を巻きました。なんと鮮やかな分析なのだろうか、と、私も本当に感激しました。
こんなふうに、読書会は、同じ文章をみんなで読んで、共感したところだけではなく、みんながどれほど異なった(優れた)見方をしているかを確認し、自分の認識の限界と特徴を確認する作業でもあります。そしてそれは、伊原さんの言葉を借りれば、日本の言論空間の傾いた「地盤」を、ささやかな会ではあれ、整え直す作業でもあります。以前第三回で少し触れた「縁学」とは最終的には己一身の学問に向かうステップであるわけですが、その意味で読書会は厳しくも、とてもいい訓練になります。
思えば、私のささやかな学びは、ほとんどが厳しい目を持つ先輩に囲まれた読書会で形成されてきました。たった一文の読みでも、ベテランの方の読みが深くて、自分の浅い読みを反省することを体感してきました。実は今もそういうことが度々あります。じっくり読んでいるつもりでも、どこかで焦っている。読みの反省を繰り返すことでしか、おそらく、読むという精神の営みは深まってきません。若い人の中には、「読むこと」と「知ること」を同じものと考える人もいますが、読むという行為は、もっと壮大で、深くて、どこか恐ろしい行為であると考えます。まず、内容を正確に把握した上で、さらに背景を読み込んでいくと、まるで深い森に迷い込んだような気持ちになります。
心に残っているのは、助手時代に、自発的に始めた読書会で、哲学に詳しい同僚たちと読んだ、マルティン・ハイデガーの『技術への問いDie Frage nach der Technik』でした。正直、最初はチンプンカンプンで、訳すのも苦行でしかありませんでした。でも、一文一文読んでいくと、難解に訳された「ハイデガー語」に日々の暮らしの根っこのようなものをちょっとずつ感じ始めます。Ge-stellというハイデガーの鍵概念はとりわけ難解です。ハイフンを取った「Gestell」ならば、「骨組み」や「ラック」という意味に過ぎません。が、ハイフンを入れることで、ハイデガーが批判するテクノロジー中心世界を指す言葉に変身するのです。つまり、vorstellen(表象する)、bestellen(注文する)、darstellen(描写する)、そしてherstellen(生産する)というstellen(寝かせてあるものを立てる)系の動詞があらわすものに、わたしたちはいつも駆り立てられていて、本来は不必要なものまでも暴き立てて生きているのですが、そのような状況を総合的に説明するために、ハイデガーはGe-という集合をあらわす接頭辞をつけて、Ge-stellという語を造ったのでした。言葉遊びですが、哲学の営みは真剣に言葉遊びをしながら、真理に迫っていく営みだと思います。こんなふうに、一語の概念にくっついてくるたくさんの語が芋づる式につながって見えてくると、議論の構造が目の前に浮かんできて、心臓が徐々に高鳴ってきます。
学ぶ領域が拡大し続ける
心臓の高鳴りを感じつつ学びを続けていくと、どんどんと学ばなければならないことが増えてきて、いつまで経っても収束に向かう気配がありません。私の師匠は、人文学の分野では、学べば学ぶほどどんどんわからないことが増えていくものだ、と昔から言っていました。そういえば、本を書いた後、私はいつも猛烈な読書欲に駆られます。それは、書いて、整理して、論理を組み立てたことでようやく、自分に足りなかったことを切実さをもって発見する機会を得られるからだと思います。それは、底なし地獄にも見えますが、私にはやはり悦びであり、楽しみにほかなりません。