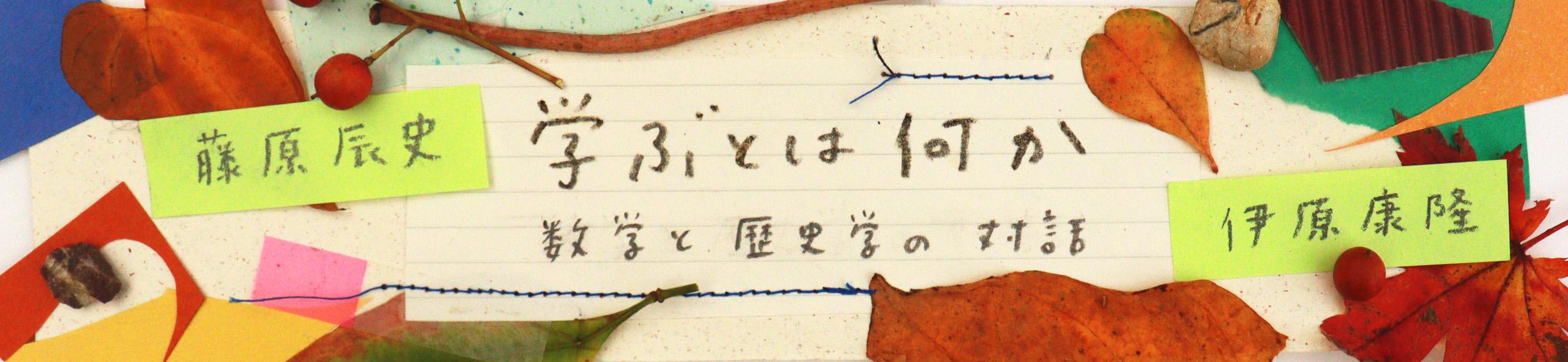第27回
コンピューターの学びと人間の学び(藤原辰史)
2022.12.15更新
歴史学者の藤原辰史さんと数学者の伊原康隆さんによる、往復書簡の連載です。昨年10月からはじまったお二人の連載、今月が最後の掲載となりました。伊原さんから藤原さんへの前回の便りはこちらから。
藤原辰史>>>伊原康隆
「好考爺」というのは伊原さんにぴったりですね。考えることがとかく忌避される時代は暗い時代にほかなりません。考えるよりも従え、という掛け声はファシズムの掛け声であるとともに、現代日本の掛け声にもなってしまっていて、それが余計に私の心を暗くさせます。国会も、地方自治体の議会も、大学の教授会も、議論の場所というよりは、中枢で決められたことをどう処理するかを話し合う場所、あるいは、中枢にとっての意見徴収儀式機関となってしまっていて、成員が主体的に深く考える余地がどんどんと狭まっています。そんな時代に、考えることをこよなく愛する伊原さんと忌憚なく言葉を交わせたことは、やはり幸運でした。
今回が私の最後の手紙なので、これまでのやり取りを読み返しましたが、「考えるよりも従え」という掛け声とは真反対である伊原さんの知のあり方にあらためて深い感銘を受けました。常識と思われることも根本から疑う、理詰めで考え抜いてみる、という伊原さんの知の態度に間近で接することができ、複雑な問題にあたるとついほどほどにすませてしまいたがる私にとって、良い薬となりました。あらためて、お礼を申し上げたいと思います。
余談ですが、歴史学の研究会でも、説を批判するのではなく、その説を訴えた人格を否定するような場面に出くわします。私もある学会での発表で「そもそも藤原先生はこういう人ですから」と人格もろとも否定されたことがあり、しばらく苦々しい気持ちが消えませんでした。このような言動が学会でまかり通っている以上、学問の発展は望むべくもありません。その点、伊原さんが教えてくださったGさんとZさんの関係は学問の担い手のあるべき姿を示してくれています。
さて、伊原さんがAIについてお書きになる、と前便にありましたので、私もその露払いとして、まだ中途半端ですがいくつか考えたことを記させてください。私も人間の知性の全てをAIに吸収されたくないと強く思っている人間ですが、もう一つ私が恐れているのは、AIの答えが唯一の正しい答えであると信じる人が増えていくことです。人間の知性がAI化していくディストピアと言い換えてもいいでしょう。
最近のニュースで、防衛庁が世論誘導するためにAIの力を借りて、SNSの発信を進めているというものがありました。AIに「ディープ・ラーニング」させているのはAIではなく生身の人間です。これまで人間が考えてきたことの中でAIに「最適解」を求めている。防衛庁のやり方に怒りを覚えると同時に、防衛庁はなんと貧弱な人間観しか持っていないのかと驚きました。こんな薄っぺらい思考を持った人たちが防衛を担ったところで、死の恐怖に怯える人びとの心は国から簡単に離れていくことでしょう。
ナチスが各団体を一斉に支配下に置くために工作することをGleichschaltungと言います。「強制的画一化」などと訳されますが、要するに同時にスイッチをつけるという意味ですね。人間は刺激と反応によって内面も変わりうる、という発想がここに見え隠れしていますが、人間の感情はそんな単純なものではない。現に、ヒトラーも、ナチス・ドイツの末期になると、スイッチを押せなかった人間たちの抵抗から逃れることはできませんでした。残余が必ずある。その残余こそが、人間の歴史の動力であると私は信じています。
もしかすると、優れた歴史学の世界中の論文をAIに読ませて、それらしき歴史論文を書かせ、ある程度のレベルの研究論文らしきものができあがってしまう時代が来るのかもしれない。そうすれば歴史学者は廃業だと考える人も出てくるかもしれない。実は、今論文を書いている歴史学者の中でも、ほとんどAIが書く論文と変わらないものがあることも否定できません。私の感覚からすると、それはしかし、動機のない論文です。
友人から聞いたのですが、あるテレビ番組でAIの研究者がこんなことを言っていたそうです。男性が女性にモテるようになるために、いろいろな情報やデータをAIに学ばせ、どうすればうまく女性と言葉を交わし、手をつなげるようになるのか、その道筋をAIが示すことができる、と。そのとき、あるコメンテーターが、手をつなぐ行為に重きをおいていないというようなことを述べて反論したそうです。人間と人間のあいだに存在する樹海のような複雑な心理の動きをAIに「ラーニング」させられると思えること自体とてもおめでたいことだということに、研究者は気づいていなかったわけです。
AIの「ラーニング」には、AI自身の抜き差しならない動機がない。AIの営みは、「世論を操作したい」というような人間の動機に支えられています。他方で人間には、問いと向き合わざるをえない強烈な動機、あるいはそれに向かわざるをえない逃れられない歴史と環境が存在します。
伊原さんが、学問の営みには頂点がない、ある山に登って遠くから山脈を見渡せるように努力することだとおっしゃったのは、「我が意を得たり!」でした。ちょうどプラトンのイデア論にも似ているところがあり、私の心にもすんなりと入ってきます。AIは与えられた世界の頂点を目指すことが重視されます。しかし、私たちは、世界の最終的な真理が手の届かないところにあると知っていて、せめてその姿を一部でも遠くから目にとどめようと飽くなき挑戦を続けているのにすぎません。人間は有限であるから、全知全能の神にはなれないのです。学びはプロセスでしかありません。
もちろん、伊原さんがずっと言っておられるように、動機だけでは学ぶことは不完全です。さまざまな知識や規則をきちんと習得し、それが使いこなせるようにすることが必須です。野球の素振りのように、ひたすら訓練を繰り返すだけの作業は学問にも欠かせません。私もソフトテニスというスポーツを中学校から大学院までやってきましたが、ボールが来ると想定して、足を小刻みに動かしながら、数えきれないほど素振りをしてきました。素振りをすればするほど、スイングの軌道が安定し、実際に予想外のボールが飛んできたときも、体が自然に反応して打ち返すことがしやすくなります。
伊原さんが強調されているように、学ぶには身体を使うこと(たとえば、手を使って書くことや声を出して読むこと)がともないます。身体の疲労、限界、高揚は、学問の営みの邪魔者にもなりますが、そこを通過していなければ学問はただの機械の示す情報の束になってしまいます。伊原さんが分厚い日記に、生活習慣に関わる自分への禁止事項が守れたときにはマルをつけていた、という習慣には心打たれましたし、そのような習慣を自身に課すこと自体、思考が人間の身体を通過してしか生まれないことを示しているように思います。
AIと人間の思考の違いを踏まえた上で、歴史学研究者にとって「考える」とはどういうことなのかを論じたいと思います。
タイムトリップもできない以上、歴史学は永遠に届かない現象に対する想像という行為にすぎません。いや、仮にタイムトリップができて、1933年1月30日のベルリンに到着し、松明行列を担う突撃隊員たちを首相になったヒトラーがバルコニーから眺める、というシーンを目撃し、突撃隊員にインタビューができたとしても、それは歴史学の営みとはほど遠いものになります。歴史学の営みとは、かつて伊原さんが示してくださった、野球でバッターのフライをキャッチする外野手のプレーに似ていて、ある一時期の現象が、これまでのどのような現象の連続の上に成り立っているのか、そしてそれが、どのように進みうるのかを推察する行為と言ってよいでしょう。もっといえば、人間の記憶が誤りうることと自分が「全知全能」ではないことを前提に、その誤りうることの背景も含めて、では実際に何が起こったのかをできる限りたくさんの史料を集めて推察する、ということです。ある現象の背景をいくらAIに「ラーニング」させても、そのうちどれが確からしいかを選択するためには、エラーや、ごまかし、癖といった人間っぽさをどこまで知っているかが問われます。
カズオ・イシグロの、たとえば『日の名残り』や『浮世の画家』のような小説が歴史研究者にとって興味深いのは、自分がどんなバイアスや思い込みに基づいて行動しているのかをその時点で当事者はほとんど意識できないけれど、それが分かり始めたときにはすでに別の現実が動き始めていて手遅れになっている、という人間の現実です。そんな切ない状況の中で自分の陥っていたバイアスだけは残酷にもくっきりと目の前に浮かび上がっていく、という私にもよくある反省が、歴史学の営みに似ていると思います。伊原さんのおっしゃった「攻撃性」を歴史学のジャンルに当てはめると、こういうことにもつながってくるかもしれません。だから、未来だけを向きたい為政者に歴史学の営みは警戒されるのだと思います。
動機とは、その人のこれまでの学習経験や読書経験、そして人間関係や耳学問の総合的な関係から生まれるものです。学習もその動機に支えられて、言語を習得し、ダーウィンのように他の説を精読し納得できないところは批判して、繰り返し自分の知識を鍛え直さなければなりません。だから、人格否定ではない、絶え間ない批判と応答を避けることができません。
歴史学にとって「考える」とは、そういう意味で、雲に隠れて永遠に晴れることのない山の風景を遠くに眺めつつ、それが本当はどのようなかたちであるかを右往左往しながら描いていく画家の試みに似ているかもしれません。温度、湿度、風向き、太陽や月の位置、季節によって山の表情は刻一刻と変わっていくことにも注意を払いつつ、それでも一枚のカンバスにまとめあげる荒技が求められます。
最後に、「回遊的散歩」と「睡眠」について考えてみたいと思います。若い頃はそうでもありませんでしたが、最近は痛いほどこれらの重要性を感じますね。これらの有無で、明らかに思考の質が変わると体感します。ですから、すでに小学校から散歩と睡眠があまりにも軽視されすぎている日本の現状を私は憂慮します。文章を書くときも、散歩しながら「こんなふうに書こう」と思いつく瞬間が多ければ多いほど、心が躍るような執筆作業になりやすい。睡眠をしっかりとったあとの思考は整然としていますし、落ち着いていて、無駄な高揚や下心が排除されている。純粋な学びの喜びを根拠にして、思考を続けることがしやすくなります。
では、私たちから自由な散歩と深い睡眠を奪うものは何か。私たちを深い思考から剥ぎ取り、結論を急かし、焦らせているものは何か。何でも社会や環境のせいにはしたくありませんが、これから学ぶことに人生の貴重な時間を捧げようとしている人にとって、このことも考えておく必要はあるでしょう。とくに今のような時代には。さもないと、自分の学ぶ時間が取れないばかりでなく、学ぶこと自体が中途半端に終わってしまいます。歴史学はこの原因を「近代社会の進化」や「資本主義の高度化」などといろいろな言葉でこのような変化を説明してきましたが、どちらも一面をあらわしているに過ぎません。
さらに残念なのは、雑務に追われる現在の研究者がこのような現実を変えることのできない前提として受け入れすぎていて、少しでも考える時間を捻出するために散歩と睡眠、これに加えれば雑談の時間を削るという本末転倒なことが起こっていることです。実は私もそのような残念な状況にあります。
このような状況を打破するための方法について答える用意はありません。ですが、伊原さんとの往復書簡のように基本的なことをめぐって対話を重ねることは、少なくとも学びの原初的な喜びを再確認することにつながりましたし、忙しさに心までも奪われないようにしようという意識が高まりました。一年をこえる対話が、疲弊していた心の生態系の回復につながったようで、これは考えもしなかった効用でした。このことを最後にお伝えしたいと思います。
(伊原さんから藤原さんへのお返事は、毎月20日に公開予定です。)