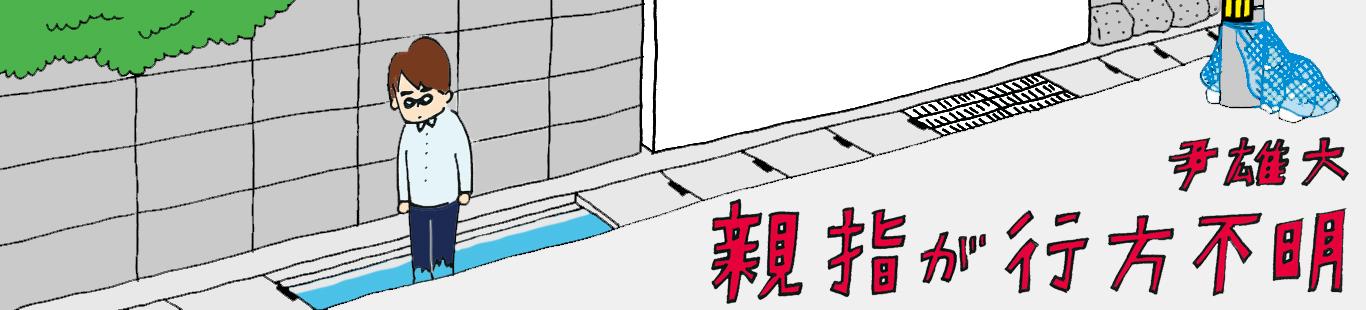第3回
弱い意志、頼りない抵抗
2020.07.25更新
なぜ自分の顔がわかるのか?
心と身体はひとつだという。心身一如といっても、心と身体のそれぞれの字を見れば明らかな通り、指し示す意味が違う。それでも異なるふたつが「ひとつ」であるのはなぜだろう。
今、目の前にチョコレートがある。割れていないのでひとつのチョコレートだとわかる。物事は、対象化してみて初めてわかる。「チョコレートは分かれていない。ひとつだ」とわかるには、チョコレートをひとつの"もの"として見ている観点が必要になる。この場合は僕だ。
僕の観点がチョコレートを"ひとつのもの"として見るとは、それが「マカロンではない」と知ることでもある。対象化とは、僕とチョコレート、チョコレートとマカロンといった具合にそれとこれとを分割していくことだ。
「何を言っているのかちょっとわからない」と思い始めている人もいるだろうから、もう少し例えを交えて説明したい。
僕らは自分の顔を直接見ることはできない。「自分の顔だ」とわかるのは、鏡やカメラを通しての像によってだ。僕らと像が分かれているから「これは自分だ」と自分の同一性、つまり「ひとつ」であることを確認できる。自分の顔と像。このふたつがあって初めてひとつだとわかる。
自分がひとつではないからこそ、ひとつだとわかる。心と身体がスプリットしているからこそ、ひとつだとわかる。分かれているがひとつでもある。
そうだとすれば、分かれているとわかるのも、ひとつだと捉えるのも自分だ。見ているものも見られているのも自分。それぞれの自分はどこにいて、どこから自分を観ているのか。それがわからない。
整列と行進がもたらすもの
そのことについて考えていくと、チック症を抱えながら幼稚園をやり過ごし、小学校へ入った当初を思い出す。最初につまずいたのは、体育の時間に教師に命じられた「小さく前へならえ」だった。それを行うことを難儀に感じたのは、前の人との距離など目測でわかることだし、おまけにちょこんと手を出す仕草がバカみたいに思えたからだ。それでも、この意味のない行為が最も意味をもたらすことは幼いながらにわかっていた。なぜかというと、整列や行進の効能を自得する機会がそれ以前にあったからだ。
前回の連載で述べた自転車の一件から半年ほど経ったクリスマスに、母親からプレゼントされたのは要望していたおもちゃと、別に欲しいとは言っていないショートブーツとシルバーがかった色合いのトレンチコートだった。当時の僕は着せ替え人形扱いで、非常に華美な格好をさせられていた。
正月は京都の親戚宅に泊まるのが恒例で、その年も数泊した。年の離れた従兄弟はミリタリーグッズ、特にナチ関連に夢中になっていた。今では外聞が憚られる趣味だが、部屋にはナチの親衛隊の制服やワルサー、ルガー、短機関銃といったモデルガンがあった。
ナチという存在を知っていたのは、テレビのドキュメンタリーで見たことがあったからだ。ショッキングな映像もあったが、禍々しいがゆえに惹かれたのも事実だ。神妙な顔つきで見る父に遠慮し、それについては口にしなかった。
彼らの行進するさまに忘我を見てとった。全体がひとつになる。そこに直視をためらいながらも、目を離すこともできない異様さと恍惚を覚えた。恍惚という言葉は知らなくとも、その体感がエロスを含んでいることも直感的にわかっていたと思う。5歳にしては早熟に過ぎて、作り話ではないかと思うかもしれない。けれども直感をもたらす下地がすでにあった。
僕はおねしょを一度もしたことがない過緊張の体質だった。寝ようとしてもトイレが気になって仕方ない。まんじりともせずにいると、時折襲われた感覚というか逞しくする夢想があった。奔流に飲み込まれて、何もかもが溶け出して、台なしになってしまうことにこの上もなく喜びを感じるというものだった。それは不治の病を抱えた母がそう遠くないうちに死ぬという破局を強迫的に先取りしようとして訪れた出来事かもしれない。けれども、こういう解釈こそでき過ぎで、今なお解読できない体験がごろりと記憶の中に無造作に転がっている。
そう思うと、大人になってからのほうが、いかにも子供らしい記憶と体感を捏造する可能性があるのではないかと訝しむ気持ちになる。あの時に味わったヒリヒリとした感じを、後年得てしまった知識で眺め始めて、僕らは体験を真摯に扱うことをやめたのかもしれない。世の中に受け入れられやすい幼年期の物語にしない限り、他人から承認されないと学習するようになったからだ。
僕は今なおひりつく感覚とともに、正月のまだ誰も起きてこなかったあの日の朝を思い出す。京都の底冷えに耐えかねてだったのか。室内にいながらにして例のトレンチコートを着ていた。
手持ち無沙汰にうろつくには、親戚宅は広くてうってつけだった。長い廊下の先に客人用の玄関が設えてあり、大きな石が敷き詰められていた。非常に立派な結構で、僕はそこにおろしたてのブーツで降り立ち、歩いてみた。カツカツと音がする。耳朶を打つ音に促されるようにして、もっとかかとを強く踏んでみる。カッカッというリズムが規則正しく響き始めると、従兄弟が制服を着て見せた昨日の出来事と映像で見たナチの行進が脳裏を掠めた。
禁忌を犯す気持ちがありながら、恐る恐る膝を上げ、かかとを打ち据えるように歩いてみた。二、三歩で終えるつもりが止まることなく、そのままガクガクと震える膝のままで続けた。
異様な興奮が身の内から湧いて出てきた。と同時に、これに身を任せてはいけないという声も聞こえ、一往復しただけで僕はやめると、慌てて履いていたブーツを忌まわしいものだとでもいうように脱ぎ捨て、一目散に廊下を駆けていった。
自分が自分でなくなる快感と恐怖
5歳の子供の慄きと高揚感は、自分が自分でなくなることの恐ろしさと快感をもたらした。そこに途轍もない暴力を覚えた。恐怖も陶酔も暴力もすでに体験していたことではあった。
「心がそうさせる」ことが僕にもたらしたのは、自分の指をホチキスで留めたり、力加減がわからずものを破壊することで、社会性を逸脱するほうへと導いていた。身体は滑らかに世界とつながれない。「心のままにある」ことは身体のねじれを意味した。心と身体のふたつはひとつではなく、ふたつはふたつのままでバラバラだった。
自分の身体に手を触れてみる。確かにあるとはわかっても、そこに自分がしっかりとつながっていない。所在がない。自分に触れる時、一方的に触れることはあり得ず、触れた瞬間、僕は僕に触れられる。触れることと触れられることが同起する。でも肝心の僕はどこにいるかわからない。このわからなさは答えは出ないが、日々チック症をはじめ奇妙な振る舞いとして産出され続けていた。
ナチの行進のもたらす高揚感の体験からすれば、学校での「小さく前へならえ」をはじめ、全体にならうことに没我を感じてもおかしくなかったはずだ。だが、僕の思うに任せない心と身体はそれを拒みたがっていた。
教師は全員の動きが揃うまで「小さく前へならえ」「なおれ」「右向け右」「全体止まれ」と言い続けていた。次第に号令に対して機敏にザッと回頭して見せることに興奮を覚えるクラスメイトが現れたことが、僕には感じられた。
身体の外から呼びかけられるこれらの命令に対して、心は従うか従わないかの声しか出せない。内心では従いたくないが、それでは罰を受ける。だから「したくないこと」を身体に強制させていた。
そうであれば身体の声は、命じられたことへの拒否一辺倒になってもおかしくない。だけど、僕の身体の声ははっきりとした拒絶だけではなく、くぐもっても聞こえた。したくはないが、それをし続ければいずれ「自分が自分でなくなる」。そのことで得られる快楽を知っていたことが、明確な拒絶を示すことを躊躇わせていたのかもしれない。
親戚宅での出来事のように、身体を機械のように、もののように扱うと、自分が自分ではなくなることで生まれる快感がある。それは身体の漏らした愉悦の声だろうか。では快感に身を任せてはいけないと声を発したのは、心なのか身体なのか。強烈な抵抗の気持ちの出所は、心なのか身体なのかわからない。どちらにも跨っていたかもしれない。
一回性を生きている
号令とともに動いていると、身体が強張り、足どりは重たく、引き攣り、みんなと一体化を阻む身体にどんどんなっていく。いつまで経っても恐れていた高揚がやって来ない。
おそらく教師は繰り返すことの暴力的なまでの絶大な教育効果を知っていた。彼らは無自覚にも、この現実に再現性があることをわからせようとしていた。生徒は教えられた結果を学べば、教えられた通りのことができるのが当たり前だ。だから勉強ができないなどあり得なかった。正しい答えを教えているのに正しい答えを導き出せないとしたら、それは生徒が無能だからだ。
彼らは「これこそが正しい」と教えさえすれば、それを正しく繰り返すことのできる身体を作り上げようとしていた。そこで根こそぎにされるのは、人は一回性を生きているという事実だ。心臓は鼓動している。毎度繰り返しているように思えるが、心拍は再現されていない。毎回の新たな一回の拍動が次々と継起している。
昨日と同じように今朝も太陽が昇り一日が始まる。過去に起きたことがこの先も起きる。世界に再現性がある。こうした強烈な現実感は嘘ではない。だが、現実感は現実ではない。今という時は繰り返されることなく去っていくのだから。
運動場で整列の動作を行う内に、僕は再現性に溶かされない自分を発見した。バラバラにまとまらない心と身体がその時ばかりはまとまらないままでひとつに感じられた。
いつも心と身体は僕を打ち据えていた。その暴力は容易に自分というあり方を統合する方へと向かわせなかった。それはつらいことではあった。
ナチと同様に学校が教える再現性の世界はひとつのリズム、ひとつの意志に基づいて、自分を作り直すように促した。自分が分裂しているのは苦しい。だが、心と身体の引き裂かれた状態が尊重されることのない暴力には我慢がならなかった。
強固な意志の持ち主でもない。隊列から離れてあからさまに反発するわけでもない。けれども再現性の身体観が教え込まれている最中にあって、僕は抵抗していたのだと思う。
紫外線に弱く、長く野外にいると発熱してしまう。すでに熱を帯び始めていた身体は引き攣って「回れ右」の号令が要求する速度についていけなくなっていた。周囲と合わない存在として、集団に散逸をもたらす身体として僕はそこにいた。
号令は学校が要求する身体像とひとつになるよう急かす。だけど、その理想化された滑らかな動きを備えた身体には到底行きつかない、ねじれて引き攣った心と身体で僕はそこにいた。
このような抵抗をしてどうなるのか。どこかにいる自分が心と身体のふたつを観ている。折り合わないふたつがもたらすバラバラの運動が「今この時」という一回性の中で立ち上がるのが、自分と呼べる存在なのかもしれない。