第11回
「俺の腕だよ」という「普通」を疑う(前編)
2024.11.05更新
未来(みき)、信じられないだろうが、俺は今、江戸にいる。手術をしていると人殺しに間違われるような世の中で、満足な道具も薬もなく、手術をする羽目になっている。とても簡単な手術だ。今なら、まず失敗することなどない。でも、そんな手術に、ここでは青息吐息だ。これまで手術を成功させてきたのは、俺の腕じゃなかったんだよ。今まで誰かが作ってきてくれた薬や技術、設備や知識だったんだ。そんなものを無くした俺は、痛みの少ない縫い方一つ知らないやぶだった。14年も医者をやって、俺はそんなことを知らなかった。自分がこんなにちっぽけだってことを俺は知らなかった。謙虚なつもりだったけど、俺みたいなやぶが、できる手術だけを選ぶなんて、考えてみれば、随分ふざけた話だと、君はずうっと、そう言いたかったのかもしれないな。もしかして、これは、物言えぬ君からの、俺への罰なのか。
『JIN-仁』第1話より
これは、日本のTBSテレビで2009年に放送されていた、『JIN』というドラマでの主人公「仁」の独白です。この物語は、ある事件がきっかけで江戸時代にタイムスリップした現代の脳外科医(南方仁)が自らも幕末の動乱に巻き込まれていく、壮絶な「医学ドラマ」です。
タイムスリップした江戸の街に出た仁は、その時枝豆売りの少年の母が馬に頭を蹴られて倒れこむ場に遭遇、この時代で2回目の手術をするはめになってしまいます。
江戸の町で偶然に出会った男に手術道具を取ってきてもらうように頼みますが、道具を抱えてきたのは、咲(ヒロイン)。しかし、咲は麻酔薬をうっかり忘れてしまい、しょうがなく激痛に耐えながらの手術となりますが、少年のチチンプイプイのおまじないに助けられ、仁は乗り切るという展開になります。
上のセリフは、なんとか手術を無事に終えてからの仁の独白です。
麻酔薬がないまま手術したおかげで仁は自分が「ヤブ医者」だった事を痛感してしまいます。痛みを感じない縫合すら知らなかった仁。今までの手術の成功は、自分の腕ではなく、誰かが作り上げた知識や道具、設備に頼っていただけだとタイムスリップした現場で気づくようになった仁。
僕が「仁」のセリフの中でも、もっとも「面白い」と思ったのは「これまで手術を成功させてきたのは、俺の腕じゃなかったんだよ。今まで誰かが作ってきてくれた薬や技術、設備や知識だったんだ」という言葉です。
仁は、タイムスリップというとんでもない事件に巻き込まれて、麻酔薬がないまま手術をするという経験をさせられなかったら、間違いなく一生手術能力を自分のものだと思い込み続けていたでしょう。いや、実は仁が思い込んでいた、「手術の能力は俺ものものだ」という考え方だけでなく、現代を生きている多くの人は「IQ」だとか、「優秀な能力」だとか、「障害」などすらも自分の個体の中に最初から埋め込まれていると信じ込んでいるのではないでしょうか。つまり「腕は俺のものだよ」という考えは現代を生きている多くの人にとっての「普通の感覚」だと言っていいでしょう。
ある感覚が「普通」であるとき、私たちは往々にして、「その感覚を『普通』だと思っているということ」にすら気づきません。
と書いてすぐに前言撤回するのも気が引けるのですが、 この言葉遣いだとまだ物足りなさを感じます。言いかえれば、言葉の性能が足りないと、「普通」の重力圏に容易に引きつけられてしまうということです。
つぎのように表現するのはどうでしょうか。つまり、こういうことです。一方に仁が気づいてしまったように「『俺の腕ではない』という経験と意識」があり、他方に、「『俺の腕だ』という経験と意識」があるわけではない。そうではなくて「そもそも『腕』=『能力』というものについて何も経験せず、それについて考えることもない」人びとがいるのです。
そして、このことこそ、「普通である」ということなんです。それについて何も経験せず、 何も考えなくてよい人びとが、普通の人びとなのです。「普通である:腕は俺のものだ」から「普通ではない:腕は俺のものではない」までの間には文字通り「千里の逕庭」があると思います。
それでは、この「普通の経験や意識」に気づくためにはなにが必要でしょうか。それは仁のように自らが所属するシステムから離脱することです。例えば毎朝、スマホで新聞を読むという習慣を自覚的に反省するには、スマホが使えない+新聞が読めないという環境に一度身を晒してみる必要があります。スマホで毎朝新聞を読むという行為も、反復的に身体化された技法の一つであると考えれば、我々はある意味で無意識のうちにスマホによる情報中毒になっているといえなくもないですよね。つまり、それが欠けると、我々の身体は一種の生理・情報論的な禁断症状を起こすのです。その禁断症状の存在が逆に、スマホで新聞を読むという行為の機能を明らかにします。
このように、何が「普通の感覚」だとされているかさえわからない場合、それを反省的に省察するためにはある特定の制度(ここでは医療)の歴史を遡及的に辿ることがどうしても必要です。そうすることによってそれが不変のシステムではなく、ある特定の時代に出現したという、歴史的相対性を理解するようになる。実際に仁は1862年に身を置くようになってから、社会生活上我々が「普通」だと思うことの多くが実は「歴史的な発明品」であったということを気づかざるをえなくなったわけです。
仁はとんでもない事件に巻き込まれたおかげで、こうした自明なもの(普通の感覚)に立ち還ることで、社会や世界、そして自分の生き方までをこれまでとは別のかたちで問うこと、さらには描くことができたのだと思います。言い換えると、彼は今自分が囚われている「普通の檻」 から逃れ出て、少しでも常套句ではない言葉遣いで自分が置かれている状況を語りたい、少しでも自分自身を含む光景を上空から俯瞰したい、少しでも長いスパンで物事を考えたい・・・という欲望に駆られたのではないでしょうか。
つまり、仁はありふれた生活の一コマ(手術すること)を注視し、見慣れない出来事(麻酔がない状況)の背景を知ろうとし、小さな驚きに遭遇しつづけながら、必死になって自分の理解の地平を広げていく。
僕はこのドラマを観て、現代を生きている我々の「普通の感覚」はどこからきているのかと、しばらく考え込んでしまいました。そして、忘れていた日本のあるテレビの場面を思い出しました。
最近はほとんどやらなくなりましたが、かつては日本で学会(たとえば、「日本質的心理学会」とか)に参加するために日本のホテルに泊まるときは、朝、目が覚めると、習慣的にテレビをつけていました。そこで、日本のテレビの朝の番組ってどのチャンネルも「都会の暮らし」の広告がはじまるということに、ある時から気がついたのです。若いやせた女の人が、最新のデザインの服を着て、都会で散歩をしたり、買い物したりする風景が延々と続くということですね。
そういう番組を毎日観てると、簡単に、たくさんの人が都会に憧れるようになるのも無理はないと思います。そうすると、こちらとしては「田舎」はどうなってるんでしょうかと聞きたくなりますね。
いつのまにかみんなが都会に憧れさせられる。みんなが、都会が中心、都会が先端、都会が世界をリードしていく、つまり、都会が「普通」だと教えこまれるようになります。都会で、農民たちの姿を見ることはありません。農民たちが都会の中を、鋤や鍬を持って歩き回って、 田舎の暮らしのすごさを見せつける場面を皆さん見かけたことがありますか?
テレビで、漁師たちが恋愛する物語は流れていない。漁師たちは海で素敵な恋愛をするだろうに、 テレビで流れるのは、都会の恋愛の物語ばかりです。(たまにネットフリックスなんか見ると、「漁師たちが恋愛する物語」も見かけることもありますが)
田舎の姿がテレビに映るのは、都会の人が田舎に行った時だけではありませんか。例えば、朝のワイドショーなどで、漁師の暮らしが放送される時は、必ず都会から訪れたレポーターが、「いやあ、 すごいですねえ、おばあちゃん! こんなの見たことないですよ!」などと騒ぎ立てる。
漁師たちにとっては「普通の生活」が、まるで「特別な生活」のように扱われて、どこか見下ろしたような態度で放送される。もし反対に、漁師が都会に行って、巨大なデパートなどに入って行って、「売り子さん!すごいねえ!こんなの見たことないよ!」と騒ぎ立てる番組があったら、どう見えるでしょうか? おそらく、何かの冗談のように見えると思います(僕は面白いと思いますけど)。
テレビで「普通」とされるのは、都会の価値観、都会の暮らし。それ以外の暮らしは、「普通じゃないもの」「特異なもの」として見せられるはずです。
レポーターが「わあ、すごいですね、おばあちゃん! こんなの見たことないですよ!」と騒ぐことで、田舎のおばあちゃんの暮らしは「普通じゃないもの」「特異なもの」として見せられる。都会に住むレポーターの視点が、「普通のもの」「標準のもの」「当たり前のもの」として、設定されるようになる。もちろん、意図的に、です。人びとを都会に憧れさせるために。田舎の若者たちに、「そうか、僕らの暮らしは、驚かれてしまうような、変わったものなのか」と思わせるために。その一方で、全部が「都会の暮らしの広告」のような番組が流される。
資本主義は、人を都会に移動させたい。都会を大きくしたい。田舎にも都会をつくりたい。その、資本主義の意図をまともに食らって、みんなが都会に憧れを持つ。それが「普通」になっていく。 都会の暮らしが「普通」になった今、韓国は合計特殊出生率0.71という超少子化に加えて、全人口の半分近くがソウル近郊に住むという人口一極集中が進行しています。地方では人口減のせいで経済活動が低迷し、学校や病院の統廃合が始まっています。
このように「普通」って、小さな行動の積み重ねでてきているじゃないかと思います。リアルな、一つ一つやることが、「普通」を作っていく。遠くて起こることは、どんなに大ニュースでも、さほど影響しない。 本当に影響するのは、 体がやること。うちの中で、起こること。リアルな、くり返される生活の場面。そういうものが「普通」を作る、と 僕は思います。
私たちは毎日テレビや広告に触れる。今だと、ネットにも触れる。逃げられない現実として、人はそれらに毎日出会う。その小さな場面が毎日、長年くり返されて、「普通」は作られていくと思います。
話を「仁」に戻しましょう。2009年、東京のある大学病院の脳外科医として勤めている仁の時代の「普通」はなんだったんでしょうか。それはまぎれもなく「今までの手術を成功させてきたのは自分の腕だ」という感覚ですよね。つまり「自分の能力は皮膚を境にして自分のなかにビルトインされている」というのが仁にとって「普通の感覚」だったのだと思います。
それでは、この「自分のからだに本質的に埋め込まれている能力観」はいつからわれわれの「普通の感覚」になったのでしょうか。僕の考えでは歴史的に見ると、「銀貨が多くの人のポケットにじゃらじゃらとあるものになった時」からではないかと思います。


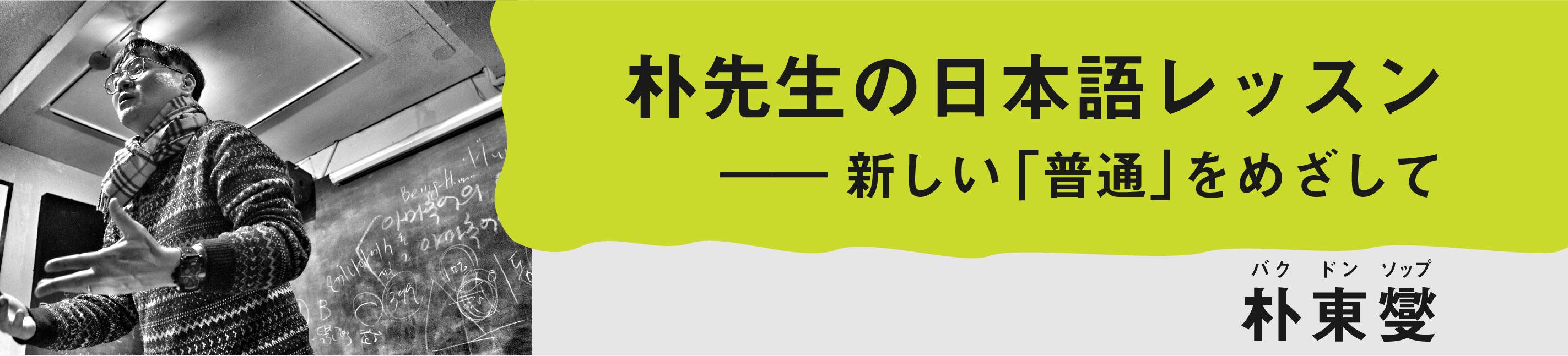


-thumb-800xauto-15055.png)



