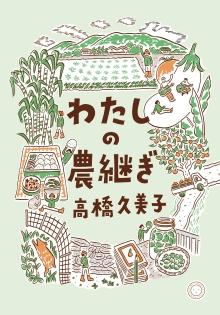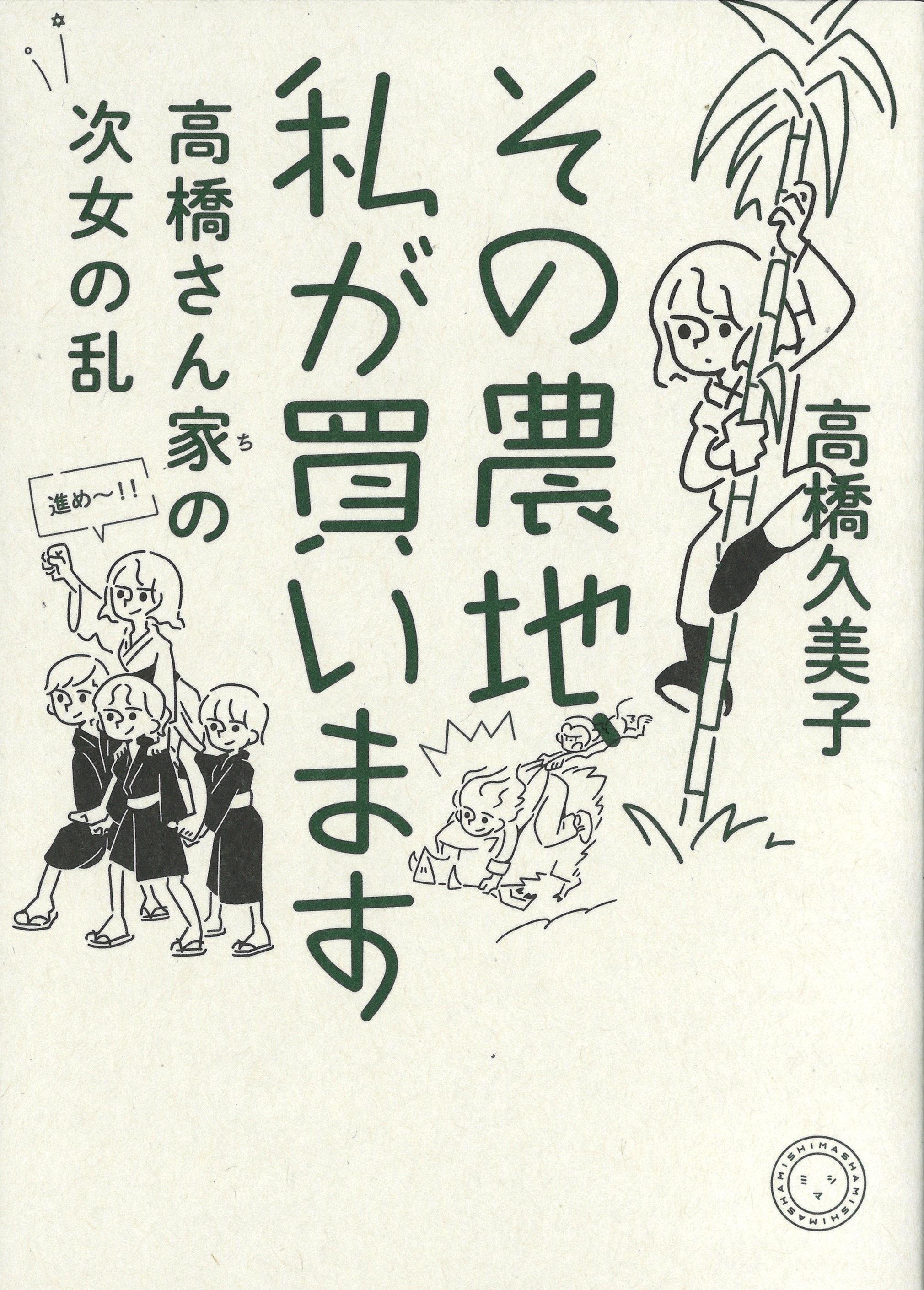第3回
草も木も人も 後編
2022.02.06更新
(前編はこちら)
畑はというと、下の畑は妹が結婚後も、なっちゃんとゾエと母が維持してくれていた。ネットの中には大根やじゃがいもなどの猿に食べられる物を育て、外ではゴボウや春菊、菊芋、食用のサボテンもある。珍しいものを育てたいゾエが植えたらしい。
私は今までの分を取り戻すように、延々と草刈りをする。九月に便利屋の友人に頼んで刈ってもらってからは、まだ何も植えてない上の畑は草がもさもさのまま冬枯れしていた。
やっと全部刈れたぞと家に戻ったら、父にあれじゃあ駄目だと言われる。近所の人との共有のスペースである畦道や水路をもっと重点的に綺麗にするのが基本だという。
なるほど、確かにそうだな。そういうところから近所との信頼が生まれるのだなあ。
翌日、石垣や水路の草を刈る。石垣の間から笹や竹が突き出し、それによりいくつか石が崩れ落ちている。竹の根がこんなところまで入りこんでいるのか。気をつけないと石垣など簡単に崩されるだろう。タイのアユタヤ遺跡や、カンボジアのベンメリアを思いだす。煉瓦も石も最後は草木に崩されて朽ちていた。亜熱帯の植物の力は凄まじい。四国も最近の夏場の気候はほぼ亜熱帯だった。
草刈り機ではもはや刈れなくて、剪定ばさみで飛び出た竹を切っていく。笹、綺麗やなあ。元気やなあ。切るのがもったいないと思ってしまう。田んぼとして活用してないから、水路の溝がわからないくらいに土や草が堆積している。えらいこっちゃ。数日かけて、何とか綺麗になる。
近所の別のおばあちゃんに借りていた畑の草刈りもする。例の茅萱が大量発生してぶどうを移した畑だ。ここにレモンの木を植えて五年。どんどん弱ってきていて、今年はついに一〇個しかならず葉っぱの色も悪い。ぶどうと同じく、根っこが茅萱にやられているに違いない。レモンも別の畑に移すことにした。
金平糖みたいにかわいい野花も、ふわふわの猫じゃらしも、草刈機で無残に刈っていくのが少し悲しかった。美しいから刈らないゾーンを丸く残していたけど、毎日やっていたら次第に慣れて花も刈ってしまうようになった。何だか、草を刈る私は凶暴だった。
綺麗にはなったが、この茅萱のはびこる農地で何を育てたらいいだろう。うーん。保留だ。
毎日、黒糖の手伝いに行くか草刈り。夜に原稿を書こうと思っていたのに、一文字も書けずバタンキュー。健康だけど、効率を考えなければ作家との両輪をまわすには難しいことが分かってきた。
ある日は、なっちゃんと玉ねぎの苗を植えた。愛媛では十一月中には植えないと、大きくならない。野菜は待ってくれない。冬は特に時期を逃したら収穫もゼロだ。ああ、ニンニクを植え忘れたー。と思っていたら、母が自分の畑からいくらか引いて苗を分けてくれた。
夏にはゾエが植えた空芯菜を母にあげたみたい。
「この野菜、茎が空洞なんじゃね!」
と、母は電話でびっくりしていた。空芯菜は地元ではなかなかめずらしい野菜だ。畑の先輩と対等な畑仲間になれるのは、やっぱり野菜の交換だな。
数日後、もう一箇所、別の柑橘を育てている畑へいってみる。こっちの柑橘類は収穫がまだなので油断していた。柑橘の植わっている所は父が草刈りをしてくれているが・・・その他の土地(主に他の方の土地)の草が木になっているではないか!!
その正体は、アカメガシワだった。葉っぱや蔓が巻き付いて元あったみかんの木を枯らしている。水路も畦道も、どこまでも原野に戻っていた。コロナで私が帰れないうちに、木になってしまったアカメガシワは、目を覚ましたゴジラのように辺りをめちゃめちゃにしていた。家の柑橘の木が日陰になってしまっていた。
私は今度は柑橘畑の草刈りに突入するが、二日がかりでも水路や土手の十メートルくらいしか終わらない。こういうところは水利組合の管理するところだと思うんだけど、多分もはや機能していないのだろうなあ。草刈りではないのだった。土手では蔦が覆いかぶさって、それを刈るとその下には木になったイバラが出てきて、鎌で刈ろうとすると容赦なく私の指や手を刺して血が滲んだ。刈っていくと、さらに下から枯れた柑橘の木が出てきた。
ジャングルに夕日がまぶしいわい。ここはもう私の知っている景色ではなかった。
父の協力でチェーンソーで畑の際の木々は切り倒してくれたが、もうこれ以上は無理と言った。うん、これは私が何とかできる範囲を超えているな。ということで、いったん保留。
谷川俊太郎の『二十億光年の孤独』が頭の中でこだましていた。私は、小さな畑の上でネリリし、キルルし、ハララしていた。
――万有引力とはひき合う孤独の力である
火星で同じように闘っている仲間に会いたい。
帰ってすぐ、父から、K太さん達の一反分の畑が太陽光パネルになると聞かされた。もうすぐ着工だそうだ。私が現在続けている畑の隣の畑だ。こっちのも買い取らせてくださいと相談に行ったのは二年前。そうか。やっぱり駄目だったんだ。
でも、あのときやるだけやったから後悔はなかった。淡々と、自分のできることをやる。
黒糖の手伝いに行っていたある日、サトウキビを育てたけど全部猿に食べられて駄目だったんですよと、他のスタッフの方に話すと、空いている知人の畑があるから見に行ってみないかと誘われる。
「いやー、今やっている畑だけで手いっぱいなんで無理ですよー」
なんて言いながら、みんなで見に行く。おお、日当たりも抜群。いいかもしれない。でも、なんか見たことある景色だね・・・と思っていたら、
「あ、あそこ・・・僕らの畑ですよ」とゾエが丘の下を指差す。
ほんとだ。私達の畑の青いネットが川向うに小さく見えた。ということは、ここも猿が出ます! 諦めて車で製糖所へ帰っていると、Oさんが畑の前で車を止めた。
「ここなら猿出ませんよ。サトウキビやりますか?」
その畑の上も太陽光パネルがぎらぎら輝いていた。なっちゃんとゾエは黙りこくっている。でも、やりたいです。安西先生、サトウキビやりたいです。これも保留! 走りすぎてはいけない。
そうそう、猿に食べられたサトウキビから三〇本くらい芽が出て、妹やゾエがOさんの畑に移植してくれたと本にも書いた。それらが今どうなったのか聞いてみる。
「実はあの畑は借りていた畑で、急に持ち主が返してほしいと言うので、全部抜いてしまったんだよ。ごめんね」
突然のことで仕方なかったのだとか。二人と少ししょげて、借りているとそうなることもあるんだねと話した。
その夜、畑でとれた大量の菊芋や、北海道から送ってくれたでっかい蝦夷鹿のお肉をローストして二人や家族と食べた。鹿肉は、北海道の広尾町に入って雪山で猟をしている中村まやさんが送ってくれたものだった。ソースは家でとれたオレンジ果汁を煮詰めて作ったら、すっごくよく合う! 美味しいのなんの。
ジビエを初めて食べたというゾエは、「こんなに美味しいと思っていなかった」と言った。遠くの仲間が仕留めて捌いてくれた鹿を、こちらの仲間が食べ、力が巡っていくことが私はとても幸せだった。菊芋のポタージュも天ぷらも絶品だ。取れたものを一緒に分かち合う時間は、疲れを吹き飛ばす。こういう喜びを大切にしながら続けていこうと思った。
再来週の高橋さんは〜。ついに! ついに! 農業仲間が増えるかも。サトウキビはどうするの。お父さんついに立ち上がる。の三本です。また再来週、読んでくださいね〜。
編集部からのお知らせ
高橋久美子×渡邉麻里子 「怒られの二人 ~それでも今、行動する理由」開催します!
生活者のための総合雑誌『ちゃぶ台』の次号に収録予定の対談を配信イベントとしてお届けする「ちゃぶ台編集室」。その第1回として、高橋久美子さんと、鳥取県智頭町でパンとビールとカフェの3本柱で「タルマーリー」の女将をされている渡邉麻里子さんをお迎えし、対談いただきます!
東京在住でありながら愛媛で農業に携わる高橋さんと、東京で生まれ育って智頭に移住した麻里子さん。
「できれば波風を起こしたくない」という人が多い中、「外から来た人」としての難しさ、高齢化する地域の難しさ、女性として携わる難しさ・・・等々に直面しながらも、「場」を守り育もうとする、その原動力はどこにあるのか??
その行動力ゆえに、怒られることも多いというお二人に、その本音と危機感、動いているからこそ見えてきたものを、たっぷりお話いただきます。どうぞお楽しみに。
イベント日時:2月10日(木)19:00〜20:30
※配信後、申込者全員にアーカイブ動画をお送りします。
久美子さんとチンさんの「農LIFE、どうLIVE?」アーカイブ動画を期間限定配信中です!
・周防大島と愛媛、農業のリアル、今と昔
・農地は「怒られ」を起こす!?
・チーム「怒られ組」の怒られエピソード
などなど、ともにミュージシャンとして活躍を経て、それぞれ東京と地方の両方での生活を経験し、現在は農に取り組むお二人による大いに盛り上がったトークイベントのアーカイブ動画を2/13までの期間限定配信中です。