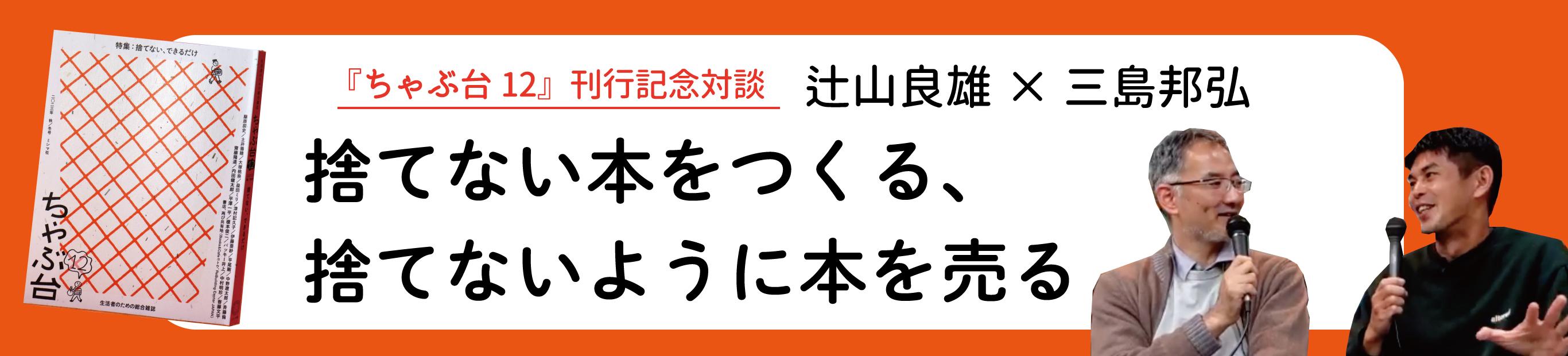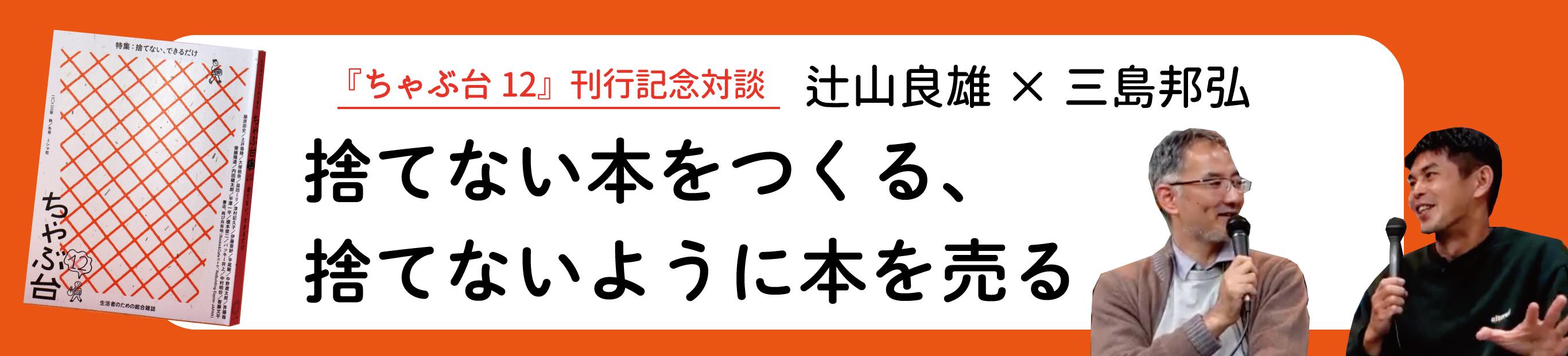第164回
辻山良雄×三島邦弘「捨てない本をつくる、捨てないように本を売る」(前編)
2024.01.01更新
昨年12月7日、生活者のための総合雑誌『ちゃぶ台12』刊行を記念して、編集長の三島と、本屋「Title」店主の辻山良雄さんが対談しました。
辻山さんは、これまでも『ちゃぶ台』の刊行イベントをご一緒したり、誌面に登場いただいたりと、本誌のことをもっともよく知り、応援してくださっている方のおひとりです。
今号が特集に掲げた「捨てない、できるだけ」について、出版社と書店、本をつくると売る、それぞれの立場から語り合いました。
新しい一年のはじまりにぴったりの、出版や本の未来に温かい灯りがともるようなお話をお届けします。今年もみなさまに、素晴らしい本との出会いがたくさんありますように。
(構成:角智春)
自分たちの足元から「捨てる」を考えたい
辻山 「捨てない、できるだけ」という特集テーマは、どこから出てきたんですか?
三島 1年ほど前から、「捨てないミシマ社」という新レーベルをつくる構想があったんです。でも、なかなか着手できなくて。自分の中で「捨てない」ということの意味が全然深まっていなかったので、一度『ちゃぶ台』でしっかり特集しようと考えました。最初は「特集:捨てない」って掲げたんですけど、なんかしっくりこなくて。
辻山 「捨てない」だけだと、言葉が強すぎるというか。
三島 そうなんです。「捨てない」と言っても、実際は、日常でゴミをめちゃ捨てているんですよね。自分が実践できていないことを掲げるのはしんどいなあというところから、「できるだけ」をつけてみました。

(左:辻山良雄さん、右:三島邦弘)
辻山 今回取材されている徳島県の「上勝町ゼロ・ウェイストセンター」という場所には、ほんとうに驚かされました。
町の中にゴミステーションがあり、ゴミ収集車ではなく町民がみずからゴミを持ち込んで、しかも45種類に分別している。
三島 上勝は最先端のゴミ処理を実践している自治体で、そこに料理研究家の土井善晴先生と行ってきました。それから、巻頭では歴史学者の藤原辰史さんにインタビューしました。藤原さんは、今の地球の環境破壊の度合いは「九回裏」で、「10対0とか、圧倒的に突き放されているような厳しい状況」とおっしゃった。その現実から、僕たちが日々している「捨てる」ってなんだろう?ということを考えて、新しい意味を吹き込んでいく。このふたつが大きな柱になりました。
 (『ちゃぶ台12』より、上勝町ゼロ・ウェイストセンターのレポート記事)
(『ちゃぶ台12』より、上勝町ゼロ・ウェイストセンターのレポート記事)
辻山 一方で『ちゃぶ台12』には、「本づくり、どれくらいのゴミが出てますか?」という記事もあって、印刷会社さんにインタビューしていますよね。たとえばある本を、44500枚の紙を使ってつくるとき、そのうち2000枚くらいは予備分で、もともと捨てる前提だということにも驚かされた。4%は廃棄されているのですね。
三島 「捨てない、できるだけ」と掲げてみて、まずは自分の仕事はどうなんだろうと思って、シナノ印刷さんにお話をきいたんです。ずっと出版活動をしてきましたが、あまりよくわかっていませんでした。
シナノさんは、「ミシマ社の本は1冊1冊、判型(サイズ)も紙の種類にもこだわっていて、でも、やっぱり紙には『取り都合』というものがありますからね・・・」と、こちらの本づくりに敬意を払ってくれつつ、恐る恐るおっしゃって(笑)。本をつくるときは、1枚の大きな紙から1冊分のサイズの紙を何枚か切り出すのですが、標準の規格とはちがう判型にすると、そのぶん1枚の紙から切り出す効率が悪くなるんですね。余白が増えて、端材がすごい量になってしまう。
辻山 デザインをとるか、効率をとるか。
三島 じつは、「ちゃぶ台」も特殊な判型なので、ある意味ではたくさんのゴミを出すことで生まれている雑誌です。本というものがそういうふうにしてでき、書店に並ぶということも突きつけられましたね。
 (『ちゃぶ台12』より、シナノ印刷さんインタビュー)
(『ちゃぶ台12』より、シナノ印刷さんインタビュー)
傷んでいる本を売る
辻山 「捨てないミシマ社」の構想は、そうした「もったいない」といった発想から出てきたのですか?
三島 「捨てないミシマ社」はその前から考えていました。本というのは、一度書店に並んだあとに、出版社に返品されることがあります。そのときに傷や汚れがあって、修復もできない本は、「再出荷不能」とされ、断裁されてしまう。その断裁対象となっていた本ばかりを集めて、ひとつのレーベルにして、再び販売しようという試みです。
返品された本は、ほんのわずかであっても修復できない傷や凹みがあったら、再出荷できない。心を込めてつくった本が、内容にはいっさい遜色がないのに断裁されるというのは、ほんとうに自分の身を切られるようにつらいことです。
そこで、ある手売りイベントに参加したときに、再出荷不能の本だけを集めて売ってみたんです。そうしたら定価でもどんどん売れた。断裁されるはずだった本たちを、「それだったらこっちの本がほしいわ」と言って買ってくださる方がいて。
辻山 でも、考えてみれば「傷」や「凹み」などは、性格みたいなものですよね。ちょっと偏っていたり、変なところもあるけど、すこしかわいい、みたいな(笑)。
三島 まさにそうなんですよ。
辻山 私も以前、出版社の三輪舎さんから依頼されて、『本を贈る』という本の少し傷んでいるものを安くして売ったことがあります。お客さんは「探してたんです」とか「読めればいいです」とかさまざまな理由で買ってくださって、すぐに売り切れました。
Titleは「新刊書店」と銘打っていますが、その「新刊」とはなにかと言えば、古本とは違って、「まだ誰も手に取っていない本」という解釈なんですね。
新刊書店としてやっている以上、なるべくきれいな本を届けたいという思いは、職業的な倫理としてあります。Titleではウェブショップもやっていますが、そこでは送った本をどんな方が手に取るかわからないということもありますし・・・。
実際に来店されている場合であれば、特に気にしない方でしたら、傷んだ本でもカウンターに持ってこられますし、「帯が破れてますが、大丈夫ですか」と、私が訊くこともできます。でもウェブショップではそうしたコミュニケーションが取れないので、ちょっとどうかなと思う汚れがあれば、消しゴムできれいにしてから出荷するといったこともしています。入荷した時点で、梱包や輸送に問題があって傷んでいることもあるので、その場合はなるべくいいコンディションに戻して、本を店頭に並べています。
三島 なるほど。
辻山 こうして店をやっていると、紙はとても傷みやすいものなんだなということがよくわかります。本は触って中を確かめないと買うかどうかを決められないじゃないですか。しかし、そのお客さんにはなんの悪気もないんですけど、脂や汚れがつきやすい紙質の本もありますから、手で触っただけで指の油がついてしまったりする。そんな時は、出版社に頼んでカバーだけ掛け替えたり、剥げない程度に消しゴムをかけたりして置きなおしているんですけど。
三島 お店でそういうふう売りつづけてくださっているのはとてもありがたいです。

「本」という広いくくりで捉えてみると
三島 通常のミシマ社本の場合、本屋さんへの卸率は70%ですが、捨てないレーベルは30%くらいにする。そのうえで、こちらとしては定価販売を希望しますが、最終的には自由価格になります。
辻山 本屋が好きな価格をつけていいということですよね。
三島 「捨てないミシマ社」で扱うのは、古本ではなく新刊本です。つまり、一度も買われたことのない本。だけど、いろんな不幸によって再出荷できなかったものを、もう一回再出荷できるチャンスをつくる試みなんですね。
傷はついてるけれど、定義上は新刊。その領域で新しいレーベルをやることで、今の出版の構造のなかで「新刊」「古本」をはっきり分けている境界線に、ちょっと揺さぶりをかけられるかもしれません。境界線がきっちりと固まりすぎていることが、いろんな問題の原因のひとつでもあるんじゃないかと思っています。
たとえば、日本には「再販制度」があって、新刊は価格を変更することが永久にできないんですよね。
辻山 定価1800円の本は、5年後でも10年後でも1800円ということですね。
三島 もしかすると「もっと安かったら買う」という人がいるかもしれないけれど、その可能性がいったんゼロになっている。そうすることで、新刊という市場が守られてきたんですね。でも、地球に資源が永久にあるわけでもなく、商品をどれだけつくってもいいという状況ではない今、このシステム自体を見直さないと、つくったものを届けようがないように感じています。
辻山 Titleでは年末・年始に古本市をやるのですが、お客さんは古本市で古本をみて、同時に新刊もといったように、こだわりなく両方買われる方も多いのですね。「新刊」と名づけるといろんな縛りやプレッシャーもあるけれど、広く「本」というくくりで捉えてみると、もっと柔軟なことが出来そうな気がします。
三島 いまのシステムは、新刊市場の人たちの商売を成り立たせるためだけのシステムになっていて、たとえば「地球」という視点に立ったときには別に幸福な仕組みではないと思うんですね。「紙の本」という大きなくくりで考えなおしてみることで、動くものがあるだろうと思います。

(後編につづく)
編集部からのお知らせ
本対談を全編動画でご覧いただけます!
 この記事のもとになった対談を、アーカイブ動画を配信中です!
この記事のもとになった対談を、アーカイブ動画を配信中です!
『ちゃぶ台12』とあわせてお楽しみいただけましたらうれしいです。
<ライブ配信参加者の声>
・Titleさんが好きで、ミシマ社さんが好きで、紙の本を買うのが生きがいで、実際本が捨てられない性分なので、今回のテーマは切実な問題です。 でも、答えを求めて、というより、おふたりの本や出版流通に関するお話しは永遠に聞いていられるわというくらい楽しく聞かせていただきました。
・あちらこちらに飛びっぱなしの話が実はきちんとつながっていてとても面白かった。
・本の販売ほど効率化に向かないものはないと常々思っていて、だからこそ街の本屋は無くなって欲しくないと再認識しました。