第164回
辻山良雄×三島邦弘「捨てない本をつくる、捨てないように本を売る」(後編)
2024.01.03更新
昨年12月7日、生活者のための総合雑誌『ちゃぶ台12』刊行を記念して、編集長の三島と、本屋「Title」店主の辻山良雄さんが対談しました。
辻山さんは、これまでも『ちゃぶ台』の刊行イベントをご一緒したり、誌面に登場いただいたりと、本誌のことをもっともよく知り、応援してくださっている方のおひとりです。今号が特集に掲げた「捨てない、できるだけ」について、出版社と書店、本をつくると売る、それぞれの立場から語り合いました。
新しい一年のはじまりにぴったりの、出版や本の未来に温かい灯りがともるようなお話。本日は後編をお届けします。
今年もみなさまに、素晴らしい本との出会いがたくさんありますように。
(構成:角智春)
注文していない本が入ってくることで、無駄が生じる
辻山 Titleに仕入れる本は、私が数を決めて注文しています。たとえば、『ちゃぶ台』は買いそうな人の顔が10人くらい思い浮かぶから10冊注文しようとか、この本は売れるかわからないけれど試してみたいから1冊とか、それぞれに理由があって冊数を決めます。そうして自分で注文した本って、あまり返品は出ないのですよね。
でも多くの本屋さんでは、通常「取次」から「パターン配本」といわれる仕組みで、新刊が入ってくる場合が多い。売場で一冊ずつ選んでいられないから、注文しなくても、本が実績で店に入るようになっているのですね。すると、店と合わない本もたくさん入ってきますから、そうした本はすぐに返品されてしまいます。
届けたいという思いで本をつくった人や、書いた人にしてみれば、とても不幸なことですよね。こうした委託制度は、全国各地の書店にまんべんなく本が届きやすくなるといったよい面もありましたが、一方で「売る責任の所在」が曖昧になるという問題もあったと思います。
「この本はこちらで注文していないから、返すときもあまり心が痛まない」といった感覚になるかもしれないし、送ったり返したりするときも丁寧に梱包されないことが多いので、一往復しただけで傷や汚れがつきやすい。
三島 輸送のガソリンも無駄になっていますよね。
辻山 注文していない本が入ってくることで、いろんな無駄が生じているんですね。
でもミシマ社の場合は、書店との取引のメインは取次を介さない「直取引」ですよね?
三島 はい。直にコミュニケーションをとれているので、Titleさんのような個人店や小規模なお店からの返品はほとんどないのですが、やはり、一度にたくさん仕入れてくださる大型店では売れ残りが出ますし、傷んだ本も必ず出るので、返品は生じます。それでも、必ずお店から注文を受けたうえで納品しているので、出版社側も、書店側も、「この本を読者に届けよう」という意思がある状態になっていて、返品率は低く抑えられています。
やっぱり、当たり前ですけど、原点としてみんなが意思を持って仕事をする、というところがなくなってはならないですよね。

(左:辻山良雄さん、右:三島邦弘)
血となり肉となるような本を
辻山 もうひとつ、これは自分の中でもぼんやりと考えていることなのですが、私はこの店をつくったときから、誰かの血となり肉となるような本を売っていきたいと思っていまして・・・。
三島 はい。
辻山 たとえば、『ちゃぶ台』を読んで心を動かされて、こういう行動をしてみました、というような心を動かされることって、本を読むなかで起こると思うんですね。
それぞれの人によって好きな本は違うと思いますが、その本を読んだことで別の本も読みたくなったり、なにかしら行動が変わっていったりするようなものを手渡していきたい。そうした次につながっていく本は、循環しているということだし、なにかを再生産しているということだから、その人のなかで無駄にはなっていない。・・・みなさん、家の本棚には「これが私だ」といった本があると思うんですけど、それはほんとうに、血となり肉となった、自分と不可分なものですよね。そういう「生きるための本」を、店で売っていきたいんですね。
逆に言えば「消費」という言葉がありますよね。たとえば、いま流行っているとか、フォロワーが何万人いるとか、そういう動機で煽られて手にした本は、結局あとから、「これなんで買ったのかなぁ」と思うかもしれない。同じ紙の束かもしれないけど、それでは再生産されていないと思うんです。もしかしたら、いずれ燃えるゴミに出されてしまうかもしれない。
三島 うんうん。
辻山 だから、店でやれることがあるとすれば、「消費」を煽るようにして売らない。そして、読んだあとのことは読者自身のことだからどうすることもできないけれど、こちらとしては品質を保証できるようなものを売る。そうすることが、ひとつの「捨てない本の売りかた」になるんじゃないかなと思います。
三島 なるほど! わかりました、辻山さんは町のレストランのご主人みたいな感じですね。
辻山 町のレストランのシェフは、大量に食材を使い、たくさんつくってたくさん捨てるのではなく、自分にできる数だけ、来た人の身になるようなものを出しますよね。
三島 「捨てない」本づくりって、やり方が難しいなぁと思っていたんです。だから「土に埋めたらすぐ分解される本」とか、「食べられる本」とか、そんなことを考えたこともあったのですが(笑)、その必要はないと今わかりました。
僕たちは本を通して、言葉を分解して消化して、身にしているわけですよね。
たくさんの本、たくさんの言葉が自分をつくっていて、でも、なかには強い記号に煽られて買ってしまって、消化されないような本もある。
いい読書体験は、言葉が体を通って微生物たちがいっぱい増える、みたいなものであって、町のレストランがやっているようなことを、僕たちは本を通してやればいいんだと思いました。

辻山 今号のインタビューで藤原辰史さんがおっしゃっていましたが、ゴミをゴミとして見ると、なんでも捨てればいいといった消費的な考え方にもなり、それでは人間そのものも消費して使えばいいということにもなりかねない。言葉は悪いですが、人のことを使える/使えないで判断してしまう。でも本当はそうじゃないですよね。
本も同じだと思います。だから、出さなくてもいい本を出すというようなことなどは・・・。
三島 ほんとうにやめた方がいいですよね。
出版の世界はこの2、30年で新刊刊行点数がどんどん増えていき、僕が18年前にミシマ社をつくったときは、その傾向を変えたい、点数が少なくてもいい本がきちんとつくられ、売れる流れをつくりたい、という思いがありました。
実際にこの間、そうした流れができている感じがしています。いい本が増えてるんじゃないかと思いますし、それを受け止めてくださる方々もとてもたくさんいるなと。楽観論かもしれませんが、僕はそこはあまり心配していないですね。
本は人間と近い
三島 辻山さんが血となり肉となるような本の届け方をしたいとおっしゃったのは、すごく重要だと思いました。「捨てない」本づくりを表面的に考えると、食べれる本、埋められる本、みたいになってしまいかねませんが、そうではなく、「捨てない」という言葉をどう変え、新しい命を吹き込むか、というところをやっていきたいです。
それは『ちゃぶ台12』をつくるなかで、著者の方々から学んだことでもあります。
たとえば、齋藤陽道さんは、「捨てない」を「沁みこませる」と表現され、はっとしました。また、藤原辰史さんは、私たちは「ゴミ」という言葉によって想像力を奪われてしまっている、とおっしゃいました。「ゴミ」をかつてのように「ボロ」や「クズ」という言葉で言い換えれば、もう使えないと思っていたものがじつは再利用できるものだったと気づける、と。
 (『ちゃぶ台12』より、齋藤陽道さんフォトエッセイ「沁みた記憶」)
(『ちゃぶ台12』より、齋藤陽道さんフォトエッセイ「沁みた記憶」)

(『ちゃぶ台12』より、藤原辰史さんインタビュー「九回裏の『捨てる』考」)
辻山 不要になったものを「ゴミ」として見ると、「捨てる」という発想になるのかもしれませんが、人のように思えばいいのではないかと感じます。
私は、「本は大事にしなさい」と言われて育った世代で、「なぜいろいろなものがあるなかで、とくに本を大事にしなきゃいけないのかな」と、子ども心にも感じていたのですが、やはり本には、人間と近いところがあるからだというように思います。
本に書かれていることは、書いた人の中から出てきたものですし、「本は売れない」と言われながらも、そう簡単にはネットに置き換わらないとところがあるというか、本ってしぶといですよね。それはやはり人間の情緒ですとか、情報には置き換えられないことを扱っているからじゃないかなと感じています。
そう考えると、その扱い方も、人に対する扱い方と同じようにしなきゃいけない。ちょっと極端な言い方かもしれませんが、本の気持ちを考えて返品しましょうというように(笑)。そうすれば、つくり方も、並べ方も、届け方も、おのずとわかってくるような気がしますね。
三島 ほんとうにそうですね。
捨てないミシマ社を構想して以来、各地で「捨てられていた本を生かす流れをつくります!」というふうにお話しして、好評をいただいてきたのですが、なぜか、なかなかスタートできなかったんです。その理由のひとつとして、なにかちょっと「いい話」になってしまっているという感覚があって。
エコやSDGsのような文脈にのらずにどうやるか、というところがけっこう重要だと思っていて、そのやり方は今回の『ちゃぶ台12』を通してすこし見えたと感じています。
「捨てない」との距離のとり方を見直していきたいです。本をつくって売ることでたくさんの無駄を出しているという現実も見つつ、僕たちは言葉を扱う仕事をしていて、そこに血を通わせ、最も届くだろうという形を選んで本をつくっている。ものづくりのなかには、エコの文脈だけでは語れないものがあるから、現時点ではそこに対しても、適切な誇りは持っていていいんじゃないかなと思いました。
辻山 そうですね。エコやSDGsということもありつつ、それだけでは言葉がひとり歩きしてしまうので、なにかもうすこし自分たちに引きつけたあり方が重要なんでしょうね。

(終)
編集部からのお知らせ
本対談を全編動画でご覧いただけます!
 この記事のもとになった対談を、アーカイブ動画を配信中です!
この記事のもとになった対談を、アーカイブ動画を配信中です!
『ちゃぶ台12』とあわせてお楽しみいただけましたらうれしいです。
<ライブ配信参加者の声>
・Titleさんが好きで、ミシマ社さんが好きで、紙の本を買うのが生きがいで、実際本が捨てられない性分なので、今回のテーマは切実な問題です。 でも、答えを求めて、というより、おふたりの本や出版流通に関するお話しは永遠に聞いていられるわというくらい楽しく聞かせていただきました。
・あちらこちらに飛びっぱなしの話が実はきちんとつながっていてとても面白かった。
・本の販売ほど効率化に向かないものはないと常々思っていて、だからこそ街の本屋は無くなって欲しくないと再認識しました。


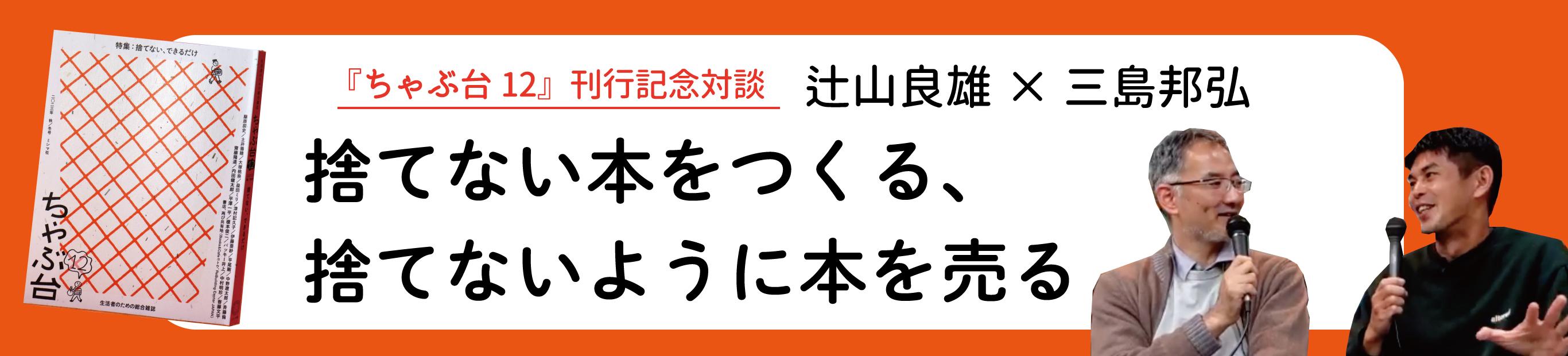
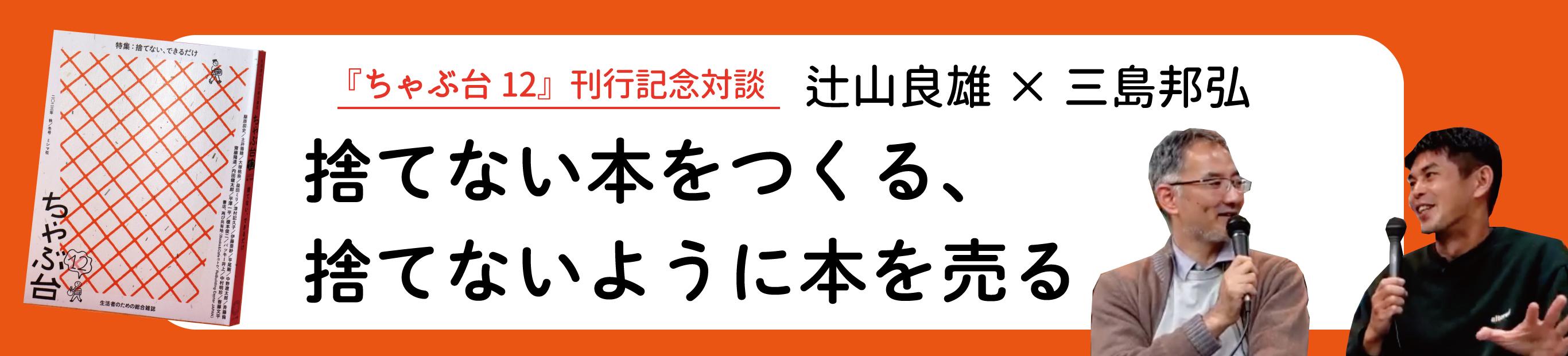


-thumb-800xauto-15055.png)



