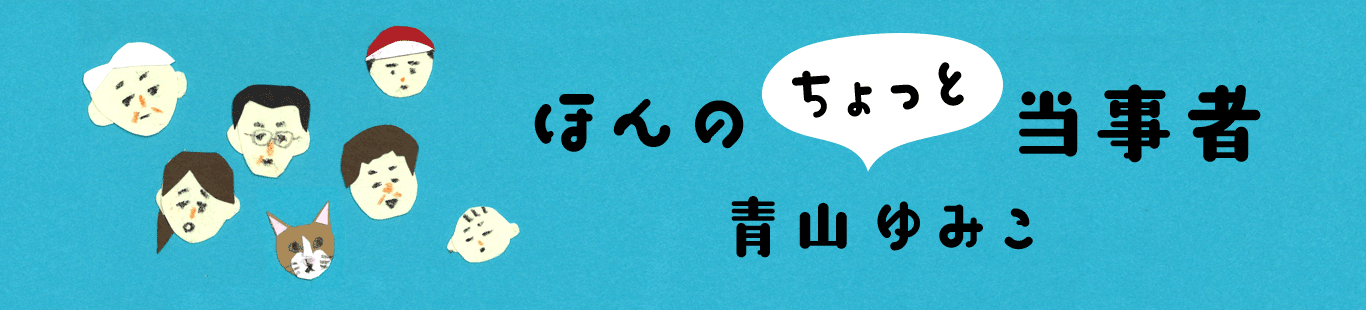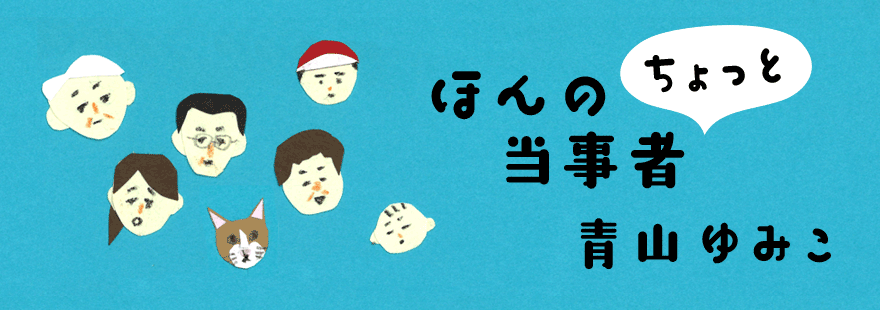第3回
「聞こえる」と「聞こえない」のあいだ。(1)
2018.07.09更新
お知らせ
この連載が本になりました。ぜひ書籍でもご覧ください。
『ほんのちょっと当事者』青山ゆみこ(著)
わたしには生まれつき聞こえない音がある。
遺伝性の高音域難聴で、高い音を受け取りにくい。どうやら父方の遺伝らしく、実家で暮らしていた頃は、冷蔵庫が開けっ放しになっているときに鳴るピーピー音や、ガスストーブを長時間点けっぱなしにすると鳴る笛のような警告音などに気づくのは母と弟だけだった。
冷蔵庫の開放音くらいの音量だと、1mほどの距離に近づけば耳が音を拾うので、聞こえないというより、高い音をキャッチする能力が標準より弱いということなのだろう。
同じ空間にいても、彼らが反応するものを、父やわたしは素通りする。人は「ある」ものには意識を向けられるが、「ない」ものに気づくことは難しい。「聞こえる」彼らがいて、わたしは初めて「聞こえない」音があると認識できるのだ。
小学校に上がる前、検査のために大学病院に何度か通った。
完全密閉で防音された無音の電話ボックスのような箱のなかに座らされ、耳の奥、というより頭のなかから響いてくる音や、耳の下に取り付けられた器具から響く音を必死に探す。意識を集中していると、そこにない音まで聞こえてくるような気がする。音が本当にそこに「ある」のか。あるいは「聞きたいという願望」なのか。わからなくなってくる。
検査結果の聴力と、普段わたしが「どう聞いている」のかが同じかどうかもわからない。
「聞こえる」という感覚は実にあやふやだ。
狭い検査室の扉が開くと、無数の音が一気に流れこんでくる。普段意識していないが、わたしたちが暮らしている日常は、ごく当たり前にさまざまな音に埋め尽くされている。無音の世界を体験する聴力検査は、なによりもそのことを幼いわたしに教えてくれた。
遺伝性の難聴は高音域に限られ、総合的にやや聴力が低いものの「日常には差し障りのないレベル」という判断で、ほとんど意識せずに幼少期、思春期を過ごした。強度の近視だったり、足が少し動かしづらかったりと、同じクラスには目に見える「弱さ」がある子どもがいたが、わたしの弱さは目に見えなかったので、そのことで注目されることはなかった。
難聴について、再び意識するようになったのは、ずいぶんと後になってのことだ。聴力ががくんと低下する出来事が起きた。
始まりはただの風邪だった。30を少し過ぎた頃だったろうか。初めて一人暮らしを始め、月刊誌の編集部で副編集長として昼夜走り回る日々。張り切りすぎて疲れがたまっていたのかもしれない。高熱が続き、近所の耳鼻科に駆け込んで処方された解熱剤と抗生剤などを飲みまくり、3日ほど丸々寝込んだ。症状がおさまると、だるさや倦怠感はすっきり取れたが、なにか違和感が残った。
あれ? どこかで蝉が鳴いている。節分を過ぎたばかりの厳寒の真冬なのに。
うっそうと樹木が茂った夏の神社なんかで降りそそぐ蝉時雨。あるいは、夜中にテレビ放映が終わった後に流れる「ざー」という砂嵐のような音にも聞こえる。電化製品の内臓音だろうか。念のためにテレビのコンセントを抜き、エアコンをはじめ室内の電源をすべてオフにした。それでも響き続ける音。それが耳鳴りだった。
耳鳴りの音を説明するのは難しい。
「聞こえる」というよりも頭のなかで響くという感覚に近い。自分のなかにある音なので、音源として取り出してイヤホンでつないで共有することもできない。同じような耳鳴り持ちの人と話す機会が増えると、どうやら似たような音が響いているようだが、お互いが同じ音を聴いているのかは確認しようがない。
耳鳴りと同時に「聞きづらさ」も抱えたので、スピーカーの電源を切って静寂を取り戻すように、耳の奥の音を消したい。その一心でドクターショッピングをするようになった。
耳鼻科の町医者から権威ある大学病院まであちこち訪ね歩き、MRIで脳の検査も受けたが特に問題はない。漢方医には体質を変える漢方薬を処方され、整骨院では首の骨のずれを整え、民間の整体サロンではリンパの流れを改善する施術を受けたが、頭の奥で響く音に変化はない。ある病院では自律神経の乱れを指摘され、30半ばで未婚で不規則な生活という点に着目したのか、「仕事を辞めて、結婚でもしたら治るかもしれんねえ」と抗不安薬を処方されたこともある。
そ、そんな診断かよ・・・。
今ならなんちゃらハラスメントに分類されるかもしれないが、父親ほどの年齢の先生が、まるで親戚の娘の生活態度を心配するような口調だったので、なんだか思わず苦笑いした。
確かに30代に入ってから、働くことが面白くなり、同時に責任も大きくなり、いろんな意味で突っ走ってしまいがちだった。仕事とプライベートをうまく切り替えられず、心身のバランスを崩していたのかもしれない。軽い抗不安薬は飲んではみたものの、顔に湿疹が出てまたストレスが増えそうだったので、ゴミ箱に捨ててしまったが。
ちょうどその頃、浜崎あゆみやスガシカオが発症した突発性難聴が話題になっていた。突発性難聴とは、その名のとおり、ある日突然、左右のどちらかの耳が聞こえなくなる病気で、ミュージシャンに限らず、慢性の睡眠不足や疲労の蓄積や大きなストレスを抱えた30代〜50代といった働き盛りの世代に患者が多い。多くは難聴と同時に耳鳴りをともない、日本では年間3、4万人が発症するとも言われている。
わたしの場合はこれには該当しなかったが、突発性難聴は音を感じる細胞の血流障害やウイルス感染が関係していると考えられていて、早期の治療だと治癒率が高い(1週間が勝負とも言われる)。全体としては約30%が完全治癒し、約50%は完全治癒までは至らないが改善はする。残りの20%はどのような治療を行っても改善がみられない。
実は、夫も2、3年前にやったことがある。耳にはうるさい(自慢することでもないが)わたしがしつこく脅したせいで、その日のうちに病院に駆け込んで、1週間ほど毎日ステロイドによる点滴治療を受け、幸い症状はおさまった。
また若い世代にヘッドホン難聴も増えている。世界保健機関(WHO)では、スマートフォンなど携帯型のオーディオ機器で大音量の音楽を長時間聞くこともリスク要因だと発表し、音楽プレーヤーの使用などを1日1時間以内に控えることを推奨している。発症すると、聴力低下に加えてこれにも耳鳴りがくっついてくる。
厚生労働省の国民生活基礎調査によると、2013年時点で約380万人が何らかの耳鳴りに悩まされているという結果が出ているが、程度の差もあり、正確な患者数はわからない。でも、100人に3人ほどの結構な割合だ。
実際のところ、耳鳴りの話をすると、すぐ身のまわりでも同じように悩まされていると打ち明け話をされることが多かった。きっと、これを読んでいるなかにもいるだろう。「聞きづらさ」を抱えている人は、想像以上に多いのだ。
日本聴覚医学会では、聴覚障害についてこのように程度分類されている。
○「軽度難聴」小さな声や騒音下での会話の聞き間違いや聞き取り困難を自覚する。
○「中等度難聴」普通の大きさの声の会話の聞き間違いや聞き取り困難を自覚する(補聴器の適応となる) 。
○「高度難聴」非常に大きい声か補聴器を用いないと会話が聞こえない。
○「重度難聴」補聴器でも、聞き取れないことが多い。
日本の障害者福祉法では、平均聴力レベルが70dB以上の「高度難聴」が身体障害者手帳の交付対象となる。
その時々で揺れがあるが、わたしの程度は「軽度難聴」といったところだろうか。
ただ、体調や気圧の変化を受けて、飛行機の離着陸で体験するような耳詰まり(耳閉感)がひどくなる。耳鳴りに加えて、両耳が栓をしたようになった日は、声を拾うためにかなりの集中力を必要とされる。もしかすると70dBの音が聞きとれていないかもしれない。そんな日のわたしは聴覚障害者なのだろうか。
聞こえる。聞こえないっていったいなんだろう。「障害」の線引きも結構あいまいだ。
さておき、わたしの治療行脚の旅に終止符を打たせたのは、「耳鳴りに強い」と人づてに聞いた小さなクリニックのおじいちゃん先生のひと言だった。遺伝性の高音域の難聴があること、大学病院などでの聴力検査や、MRIの診断結果などこれまでの経緯を伝えると、特に問診もせず、聞いているのかいないのか。わたしの顔を眺めながら、おっとりと独り言のように呟いた。
「みんないつかは耳鳴りになるからなあ」
クリニックの待合は白髪の大先輩方ばかりで、なるほど「みんないつかは」というおじいちゃん先生は正しいだろう。でも、あなたにすがりついたのは「今」どうしていいのか困惑しているまだ30代半ばの患者なのだよ・・・。
一瞬、とてつもない脱力感に襲われたが、おじいちゃん先生の発した「現在の医療ではどうにもならない症状がある。でもそれはあなただけには限らない」というメッセージは、当時のわたしに非常に有効なアドバイスともなった。現時点で耳鳴り治療に対してわたしがすべきことはもう何もない。そのことを強く納得させてくれたからだ。人体のなかでも「耳」というのは未だ謎が多い器官だとも教えられた。それならしょうがないや。
とりあえず、治る・治らないは「保留」にして、「折り合い」をつけていくしかない。ほかの誰とも共有できないこの音は、まぎれもないわたしの一部なのだから。
「諦め」というより、そうやって自分を「受け入れ」ることは、良い意味でわたしを少し楽にした。そして、その日からわたしは自分のなかで響く音と外の世界に「折り合いをつける」ことにした。
聴力は現在進行形で少しずつ下がっている。残念ながら標準の加齢よりも少し早い進行で。統計的には、わたしのような遺伝性の難聴の場合は、それが原因で聴力を失うことはないらしい。おじいちゃん先生のお告げどおり、加齢による聴力低下は誰にも訪れる。世界のボリュームのつまみが少しずつ下がるだけだ。
夫の耳は非常に性能が良い。緻密で精度の高い受信機のように、家にいると表通りの話し声や遠くで響く音までキャッチするらしく、彼といると世界は驚くほどわたしの知らない音に満ちていることに気づかされる。
「聞こえる」誰かといるときだけ、わたしには「聞こえない」音が存在する。でも一人でいるときのわたしには、「聞こえない」音は存在しない。なんだか不思議で面白い。
さて、耳鳴りによる「聞きづらさ」や、「聞こえる」「聞こえない」についてずいぶん長々と書いている。それには個人的な大きな理由がある。
わたしはフリーランスのライターで、とりわけインタビューの仕事が多く、「聞いて」「書く」ことが主な生業だ。つまり「聞く」ことは、生活にはもちろん、仕事にも深く関わっている。
大丈夫なの? インタビューなんかでちゃんと聞こえてるの?
そんな疑問を抱いた方がいるかもしれない。耳鳴りを発症したとき、わたしもそのことを深刻に感じた。もうこの仕事は続けられないかもしれないと、怖くもなった。
しかしながら不思議なもので、時に聴力レベルでは問題があるはずなのに、インタビューなどの「聞く」仕事で支障を感じたことはこれまでほとんどない。思い切って言ってしまえば、むしろ「聞こえにくい」ことで、「よく聞く」ことができていると感じることさえ多い。
それには、わたしが耳鳴りの響きを受け入れて「折り合い」をつけたように、「聞く」という行為についても「折り合いをつける」ことが大きく関係しているような気がする。ざっくり言えば「聞くことの仕方」が異なるとでもいうのだろうか。というところで次回に続きます。
引用・参考文献
●全国疫学調査結果を用いた突発性難聴年間受療患者数の地域別検討
●慶應義塾大学病医療・健康情報サイト
●日本経済新聞ヘルスUP
●厚生労働省:平成28 年国民生活基礎調査の概況