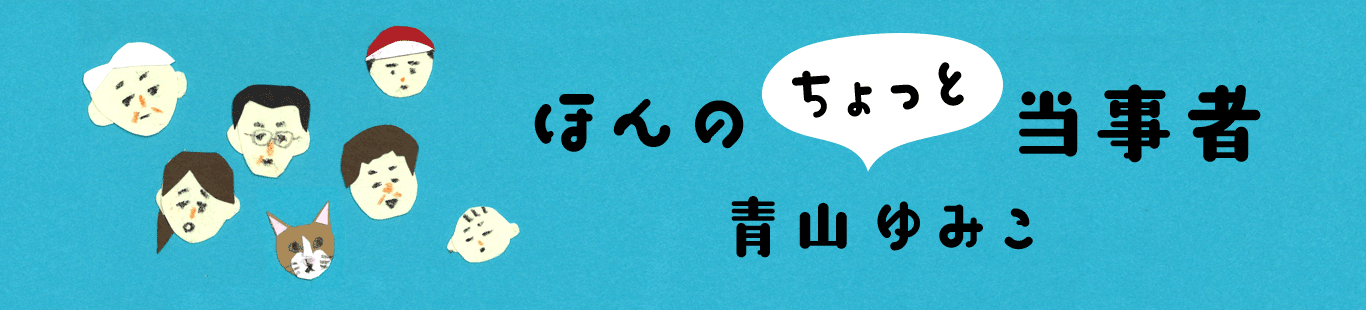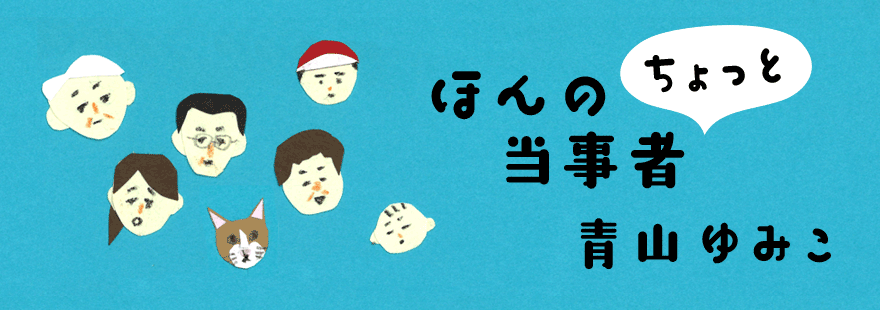第4回
「聞こえる」と「聞こえない」のあいだ。(2)
2018.08.08更新
お知らせ
この連載が本になりました。ぜひ書籍でもご覧ください。
『ほんのちょっと当事者』青山ゆみこ(著)
少し前の話になるが、1年半ほどのあいだ、淀川キリスト教病院のホスピスに不定期で通いながら、入院されている14名の患者さんにお話を聞かせてもらったことがある(『人生最後のご馳走』という本になっています)。
内容は、そのホスピスが独自に行っている「食のケア」をテーマに、皆さんに食にまつわる思い出を語っていただくというシンプルなものだ。
命の限りを受け入れて、そのホスピスをある意味「終の棲家」として選んだ皆さんは、それぞれの状態にあわせて行われるきめ細やかな緩和ケアや、スタッフによる手厚い看護によるものなのか、お会いした誰も苦痛を訴えることなく、穏やかに日常を過ごしている方々ばかりだった。
そのため、末期のがん患者だからといって特別な方法を用いるわけでもなく、いつものように簡単な質問を投げかけ、それにお答えいただき、自由に話してもらうという流れでインタビューは進んだ。
けれども、他のインタビューとは大きく異なることが一つあった。
わたしの頭の片隅にはいつも「この人がこの内容について言葉を口にするのは、これが最後かもしれない」という畏れが居座っていたことだ。
この人の語る言葉を絶対に聞き漏らしてはならない。
そう強く意識させられた結果、なんというか、耳に届く言葉だけではなく、表情の変化や、ちょっとした仕草、声の抑揚を含めて、患者さんが発信する何かを余すことなく受け止めようと、目はもちろんのこと、鼻も皮膚感覚も総動員して、全身を使って「聞く」ことをしていたような感覚があった。
語られるほとんどは楽しい世間話のような内容で、実際のところ笑い声の絶えない時間だったが、取材を終えて病室を後にし、駅までの道を歩くあいだ、毎回腰が抜けてその場にへたりこみそうになるような、激しい虚脱感に襲われたことも思い出す。
通常のインタビューでも意識の集中は高まるものだが、その比ではないほど全身の意識を集中させていたように思う。
それなのに、後になって録音した音源を再生していると、わたしは実は話を聞いていなかったのではと思わされる場面に何度か出くわした。
ICレコーダーは、わたしの弱い耳と異なり、聞き逃すことがない。すべての声を音として正確にキャッチしている。
間の悪いタイミングでの相づちなどに赤面しつつ、「ああ、このときあまり聞こえていなかったのだな」と脇の下がぐっちょり濡れることもあった。だが同時に、そんなときに限って、相手が一所懸命に言葉を重ねて、話を広げてくれることにも気づかされた。
もしかすると、自分の言葉がわたしの耳に届いていないかもしれないという疑問が、彼らの発信能力を高めていたのだろうか。
強い思いで何かを伝えたいとき、人は、言い淀み、重複を繰り返す。ともすれば言葉は曖昧であったり、活字にしてしまうとほとんど印象には残らないような平易なフレーズだったりもするのに、胸に深く突き刺さってくるものがある。
全身を使って発せられる「声」には、その人だけの温もりや湿度や感情の揺れが含まれていて、「聞きづらい」耳にも届いてくる。その「声」は聴力検査では測れない「聞こえる」力を持っている。
「聞こえる」人でも、すべてを聞くことができるとは限らない。耳がキャッチするものが「すべて」ではないからだ。「声」とは耳だけで聞こえるものではないのだ。
音を拾う器官である耳の受信能力が低いわたしにとって、「聞く」とは「見る」でもある。口元はもちろん音を推測するのに役に立つし、ちょっとした仕草や反応の変化は、口に出す音よりときに饒舌だ。そして「見る」こともまた、目だけで行うものではない。実際に見えていなくても、感じることで浮かび上がるものもある。
こう言ってしまうとなんだが、よく聞こえる人は、耳で聞きすぎるのではないだろうか。同じことが目、耳、皮膚、鼻、舌などの感覚器官でもいえるだろう。それぞれの器官の能力の高低は、あくまでごく一部を数値化したものから判断した、一つの基準でしかないかもしれないとも思うのだ。
これはインタビュー時に限らないが、わたしの耳にはしばしば時差がある。
相手の口から発せられる音はその瞬間に耳がキャッチしているはずだが、聞きづらいときは、音が断片となり、まとまって音をとらえられない。
だが、話者が発する気配や揺らぎや震え、あるいは怒りや悲しみなどの感情が音に加わることで、音のパズルがはまるように文脈がつながると、音は「意味」を持つ「声」となり、深まる。
まるで海外中継のように、わたしの耳には音にほんの少し遅れて「意味」としての声が届く。耳で「聞く」とは、そうやって「意味を感じる」ことの、ごく一部分でしかないのではないだろうか。
仕事では、これまでに1000人以上の人に話を聞いてきた。テレビに出て「喋り」を仕事にしている人にも、幾度となくインタビュー経験がある。
彼らの言葉には淀みがない。また、通りの良い声質と音量で言葉を発する人が多いので、しっかりと「聞こえている」はずなのに、なぜだか言葉がつるりとわたしの耳から滑り落ちていくことが多かった。政治家にもそういう人が多い。音は聞こえても声が届いてこない。その人だけの「声」を聞くことができない。そういうとき、わたしは自分が無力に感じて、落ち込んだ。「聞きづらい」とき以上に。
さておき、耳に関連する体験でもう一つ、本当はあまり話したくないことにも触れたい。
少し前のことだが、手話講座に参加したことがある。地域コミュニティの主宰する、ごくごく入門編の講座で、自身の聴力的には手話は特に必要としないが、なんだか面白そうというごく単純な理由で受講することにした。
日本語の手話は「日本語を翻訳する」ものではなく、一つの独立した言語であることを知り、とても興味深かったが、平日の午前中に開催される半年間の連続講座に毎週通うのはなかなか大変だった。重ねてちょうどまとまった仕事が入り、受講を継続するのが難しくなってしまった。
というのが主催者に伝えた受講中止の理由だった。
だが実はもう一つ別の理由があった。
初回参加時のこと。年齢もばらばらの10数名の受講者が自己紹介をした後に、スタッフの方がこんな補足をした。
「この中には聴覚障害をお持ちの方がいるので、その方と話すときは、声を大きくしたり、きちんと口元が見えるように意識してください」
続けてその対象である3名の名前が読み上げられた。驚いたことに、自分の名がそこに含まれていた。
そういえば、その数か月前の講座申込時、提出した受講動機に「日常には支障のないレベルだが、遺伝性の高音域の難聴があること」に触れた。スタッフの発言はそれに対する配慮だった。
しかしながら、わたしは自分の名を読み上げられ、みんなから視線を浴びた瞬間、落ち着かない、いや、なんだろう、納得がいかない気分になった。
わたしは「そっちのチーム」じゃない。「普通」なのに!
思わずそう声を上げそうになった自分に驚いた。いわば難聴当事者でさえある自分が健聴者と聴覚障害者を線引きし、障害者であると指摘されて気分を害するような人間であることを思い知らされ、ダブルでショックだった。わたしは「きれいごと」の人なのだ。それを指摘されたようで強烈に恥ずかしくもあった。
わたしの中には障害のある人とない人を「線引き」をしようとする意識がある。残念だがそういう人間なのだ。ということに自覚的で、かつ否定的でいたつもりだった。
けれども、実際に自分自身が線引きをされた瞬間に、それはあっけなくどす黒く噴出した。わたしのなかの黒いものは消えないかもしれない。だから「きれいごと」であろうと、意識し続けることが必要なのだ。わたしの弱い耳はそのことを改めて教えてくれた。
翻って、耳鳴りや難聴について。
前回の投稿には驚くほど反響があった。現役の音楽家や、世界的に活躍するDJといった「耳が商売道具」であろう人たちからも、実はわたしも、僕も・・・という声がいくつも届き、耳鳴りの感じ方やとらえ方も人それぞれに異なることを知った。
わたしの場合は、やや高音の「きーん」に「ざあ」を混ぜたような耳鳴りが、日常的に頭のなかで響いている(という感じがする)。日によって音量に変化こそあれ、常にそこに「耳鳴りが在る」という感覚はこの10数年変わらない。
ただ、何かに集中しているときは、その音を「忘れる」ことができる。
前回の投稿を読んで反応くださった一人であるアジアン・カンフー・ジェネレーションの後藤正文さんから、鈴木惣一朗さんの『耳鳴りに悩んだ音楽家がつくったCDブック』を教えていただいた。
本の内容は、本のタイトルどおり、耳鳴りに悩む音楽家である鈴木さんによる、主治医である慶應義塾大学附属病院の大石直樹先生と、同じく「耳鳴りに苦しむ音楽家」である坂本龍一さんとの対談が中心となっている。
同じ耳鳴り持ちの身には、音楽家でなくても深く共感することが多く、医学的な見解を知ることで腑に落ちることもあった。耳鳴りの原因はまだ解明されていないし、具体的な治療法はないものの、読んでいるうちに、心強く、そして前向きな仲間に出会ったように励まされたので、耳鳴りに悩む方にはわたしからもお勧めしたい。
対談のなかで、大石直樹先生が耳鳴りをロウソクの炎に例える記述があった。
真っ暗な部屋ですごく小さなロウソクの炎を見るとものすごく明るく見えるけれど、明るい部屋にロウソクの炎があってもその存在に気づかない。「周りが真っ暗だと、明るく見える」というのが耳鳴りと同じ感覚だと大石先生は言う。
例えば、無響室で耳鳴りが聞こえてしまうと、否が応にも耳鳴りにしか注意が向かないけれど、周りに雑音がある場合、あらゆる音がある中での耳鳴りはさほど気にならない。そうした意識(アテンション)が、脳の状態にも影響して、耳鳴りの感じ方に大きく関係しているのではないかと。
坂本龍一さんも同じような感覚について話しておられた。なるほどなあ。わたしが時々、耳鳴りの存在を忘れるのも、意識が耳鳴りからそらされるからなのだろう。
耳鳴りを恨まず、悩まず、過剰に意識することを止めて、自分の一部として共存する。そんなふうに、ただそこに「在るもの」として受け入れられるようになったら、逆に耳鳴りが「在る」ことを忘れる時間が長くなった。人間の感覚や意識というのは本当に不思議なものだ。
最後にもう一つだけ。話が少しずれるかもしれないが、最近よく耳にする「発達障害」についても思うことがある。
発達障害とは、生まれつき脳の機能の発達がアンバランスなために、日常生活にさまざまな困難を抱える障害だが、その症状の一つの「感覚過敏」に「聴覚過敏」というものがある。聴覚過敏だと、普通の人には感知できない音まで識別し、例えば、蛍光灯のチリチリという音や、時計の秒針の音のような小さな音まで大きな刺激として感じてしまうのだそうだ。どんなに苦しいことだろう。
発達障害は、耳鳴りや難聴とは原因も症状も異なるものだろうけれど、「見えない病」を抱えるしんどさは少しだけ想像できる気もする。そんな人がすぐ傍にもいて、でもまるで気づくことができていないのかもしれない。ということを想像し続けることしかできないけれど。
そんなこともわたしの弱い耳が教えてくれる。
ざあざあと愉快ではない音が響き、音を拾う能力も低い耳ではあるが、その実、この耳はわたしが思っている以上に、いろんなことを届けて聞かせてくれているのかもしれない。
引用・参考資料
『耳鳴りに悩んだ音楽家がつくったCDブック』鈴木惣一朗(DU BOOKS)
『発達障害を生きる』NHKスペシャル取材班(集英社)