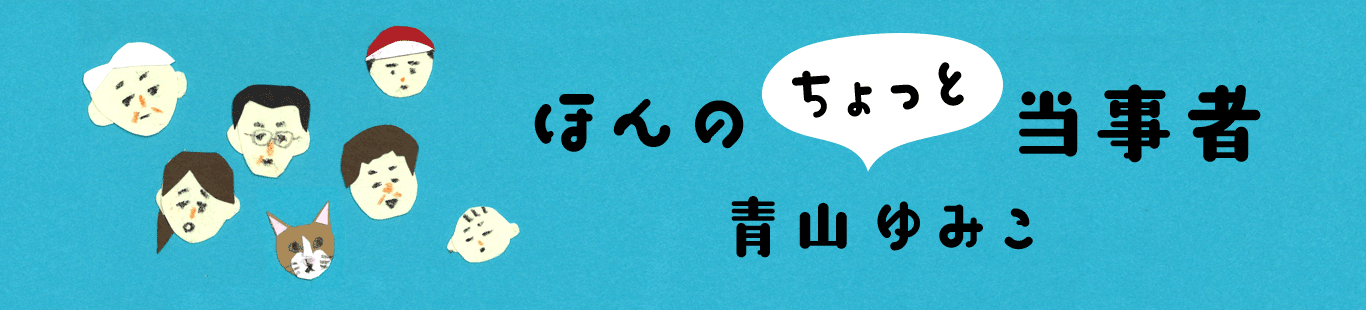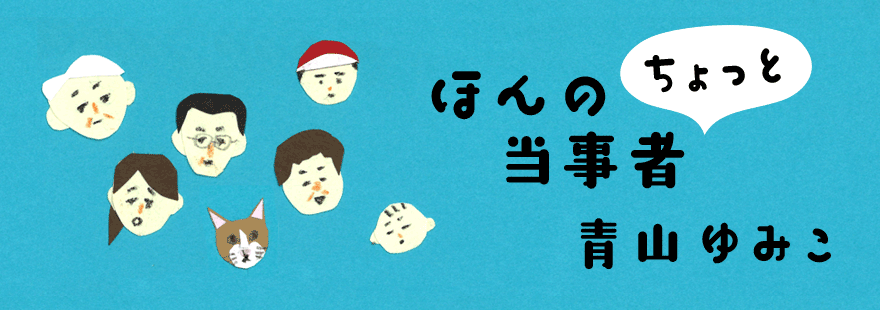第8回
あなたの家族が経験したかもしれない性暴力について。(2)
2018.12.01更新
お知らせ
この連載が本になりました。ぜひ書籍でもご覧ください。
『ほんのちょっと当事者』青山ゆみこ(著)
あなたの家族が経験したかもしれない性暴力についての第1回はこちら。
大学一年生の冬にスキーで転倒して、膝を痛めた。膝に小さな穴を空けて内視鏡検査したところ、前十字靱帯が切れていて、半月板もかなり損傷している。しかしそれはかなり以前からのものではないかと医師に告げられた。
思い当たるのは、中学時代に所属していた例のバスケット部の練習時に、一度激しいねんざをして以来、膝に水がたまるようになったことだ。
おそらくその時に靱帯も切れていたのでしょう。ねんざの腫れや痛みが酷かったため、当時、靱帯の損傷は見過ごされたのではないかと。
膝関節には4本の靱帯があり、そのうちの1本である前十字靱帯が損傷していても、激しいスポーツをするのでなければ、日常生活にはほとんど支障はない。
実際、高校では軟式テニス部に所属していたが、膝に問題を感じたことはほとんどなかった。結果、「経過観察」となり、事実上放置することになった。
ただ、転倒して以来の痛みも残っており、急な動きで左の膝の関節がずれるような感覚があり、無意識に左脚をかばって歩くクセがついてしまった。そのことを気にした父親が、知人を介して「知る人ぞ知る整体の名医」を探してきた。
普段から人付き合いが良く、家事・育児の類いは一切しないものの、外では頼まれごとを好み、世話焼きを面白がる面を父は持っていた。
商売をしており、比較的顔が広かった父が、人づてに探して連れてきた「名医」は、診療所を持たず、有名なスポーツ選手の遠征などについて身体のメンテナンスに携わる、いわばフリーランスの柔道整復師だった。
治療は自宅に来てもらい、行われることになった。
「名医」の年の頃は50代半ば。非常にガタイが良く、角刈りに短い首と太い声、冬でも身体にぱつぱつに張った半袖のポロシャツ。大阪の難波あたりによくいそうなオッサン、というのがわたしの第一印象だった。
彼はなぜかいつも、真っ赤な口紅を塗った彼と同年代の女性を伴っていた。秘書かと思いきや、生命保険の外交員をしている友人だという。
二人が特別なカンケイであることは、18歳のわたしにもほどなく察知できた。妻子持ちのはずの名医のセンセイに、母はその時点で良い印象を持たなかったようだ。
センセイは、自宅がある奈良から神戸まで、白いクラウンを走らせて来た。「足代」+「治療費」として、父は毎回3万ほど包んでいたと記憶する。もちろん保険の効かない自由診療である。
顔合わせ的な初回時に、わたしの身体をひと通り診ると、「必ず治せます。まかせといてください」とセンセイは太い声で断言し、月に1〜2度、我が家を訪れることが決まった。
「名医」がわざわざ足を運んでくれるのに、患者がわたし一人では勿体ない。
人が集まる賑やかな場が好きで、同時に「特別な人」と知り合いであることを自慢したがる傾向がある父は、知り合いに声を掛け、腰痛などの持病持ちを5〜6人集めて、「治療の会」のようなものを立ち上げた。
センセイの連れの女性は、治療を待つ間、さり気なく生命保険の勧誘をし、なるほどそういうコンビかとわたしは妙に得心したが、その片棒を担がされることで母の笑顔は次第に強ばった。
父は患者である客に感謝され、自分が褒められたかのようにいつも満面の笑顔を浮かべている。あれこれ接待を言いつけられて愛想の少ない母に、「人の役に立つことがそんなに嫌か」と正論を振りかざし、センセイの帰宅後によく両親は口論になっていた。
治療は、リビングにつながる和室に薄い布団のようなものを敷いて行われた。治療中はセンセイと患者の二人きりになるが、治療待ちの客や父母がリビングにいるので、こちらにもその声は聞こえるし、彼らが和室に目をやれば、治療風景が目に入る。
名医の治療を数回受けたが、わたしの左足の不調はあまり改善しなかった。
5回目の頃だったろうか。
いつもの治療を施術したあと、「ちょっと強めの治療で効果を見てみよか」とセンセイは野太い声で提案してきた。
その治療には、段差のある場所が必要なので、和室ではなく、玄関脇の階段に移動して行うことになり、待合室化して世間話で盛り上がっている客たちに声を掛けて、部屋を出る。
リビングのドアを閉めると、わたしたちは階段で二人きりになった。
「コカンセツをほぐすわな」
今なら股関節だと理解できるが、当時はよく分からない。とにかく指示されるがままに、左足だけを一段上にかけた。
「ちょっとびっくりするかもしれんけど、痛くないから」
治療の日は、わたしはいつもゆったりしたスウェットパンツを穿いていた。センセイはそのスウェットを少しずらして下げて、その中に分厚い手を差し込んできた。そして下着のすぐ横の、太ももの付け根あたりの股関節をぐりぐりと揉み始めた。
最初は下着の横にあった指が、下着の上へと少しずつ位置を変え、そして気づけばその手は下着の中にも入ってきていた。センセイの身体も手の動きとともにわたしの身体に密着してくる。
「ゆみちゃん、ケイケンあるの?」
一瞬、何を聞かれているのかわからなかった。「えっ」と驚いて小声を上げたわたしの陰部をまさぐりながら、「ここをほぐしてあげたら、もっと効果があるんやけど、ゆみちゃんはまだ無理かな」
センセイはごつい顔を紅潮させながら、口元ににやにやと笑いを浮かべていた。
ケイケンが経験であると思い当たり、わたしは身体を固くした。センセイはそれ以上、指を深く差し込んではこなかった。
特別な治療を終えると、わたしたちはリビングに戻り、センセイは何もなかったように両親や客たちと談笑をし、残りの患者たちの治療を終えて、次回もまたお待ちしていますと両親は深々と頭を下げた。
センセイは謝金の入った白い封筒とお土産のお菓子袋を手に、保険外交員の彼女と一緒に白いクラウンで走り去った。
もう二度とセンセイの顔を見たくもない。
けれども治療を止めにして欲しいとは言えない。他に楽しみにしている人たちがいたからだ。
ただただ気持ちが悪かった「特別な治療」について、両親に話すことはできなかった。恥ずかしさもあったし、それが治療か治療でないか、混乱していたのもある。
唯一わたしにできたことは、その次の治療の際に、再び階段での「特別な治療」を持ちかけられたとき、「あの治療は効果がないのでいらないです」とリビングにも聞こえるように、わざと大きな声で告げることだけだった。客たちは、なんて失礼な物言いの娘だと思っただろう。
「ゆみちゃんは、気が強いな」
首と声の太いセンセイがこそっと呟き、またにやにやと笑いを浮かべたことを今でも思い出す。
こんなおっさん、死ねばいい、と思った。
数回後、両親には「もう良くなったから」とわたし自身の治療を断り、センセイが来る日はなるべく家にいないようにした。
顔を合わせても、挨拶もそこそこのわたしに父は当然のように不機嫌で、「お世話になったのに」とセンセイに恐縮したが、年頃の女の子は難しいもんですよ、わはは、と鷹揚に構えるセンセイに、死ねばいいのに、とやっぱり思った。
「特別な治療」について両親に話したのは、それから15年以上経ってからのことだった。
日頃から折り合いの悪い父娘だったが、ある日、父との口論がいつもより激しくなり、わたしは次のような意味のことを叫んだ。
あなたがわたしの人生に良いと勧めたことで、良かったことは何もない。
なんやと、こら!
激高した父に、わたしは初めてセンセイの特別な治療について話した。そういうことを娘にしたのは、あなたが連れてきた男なのだと。
娘の口から聞かされた話に、父は激怒した。母はなぜすぐそのときに言わなかったのかと泣きそうな顔で問いただしてきた。
センセイとは、実は金銭的な面倒なことがあり、「治療の会」の数年後に縁が切れていた。やっぱりややこしい人間だったのだ。もうセンセイが赤の他人だから口にできたというのもある。
最初に会った時から、わたしも母もそのセンセイが嫌いだった。そう責められると父は黙り込んで、その分、怒りを大きくしているのが伝わってきた。
特別な治療が、わたしに大きな心の傷を残したという覚えは、実は正直ない。不快感と嫌悪感。そちらの方が大きかった。そういう恥を知らない、卑劣な行為を平気で行える人間がこの世にはいる。そのことが強く自分のなかに深く刻まれたというのはある。
わたしがその体験で行き場のない苦しさを感じたのは、ソイツを連れてきたのが父であったことだった。過干渉で、存在が重たすぎる父ではあったが、娘の身を案じてしてくれたことだと理解できるほどには、わたしも分別はついている。
でも、この人は善意や悪意に関係なく、娘のわたしに嫌な体験をさせる。それが自分の父である。そのことに絶望感を抱いた。
今になって、悔しさを感じるのは、「治療」なのか「わいせつな性行為」なのか、線引きができなかったことで、怒り、恥ずかしさをどこに向けていいのか分からず、その混乱と苦しさを父に対する憎しみへと転嫁したことだ。
父を憎むことは「正義に反する」。わたしの生々しい感情は、行き場のない袋小路へと追い込まれた。「子を思う親を憎む」というジレンマに陥ることを避けるように、父の存在をよりいっそう避けた。
わたしたちが抱えていた問題はもちろんそれだけではないけれど、あの出来事が父娘の関係を、大きく歪ませるきっかけとなったことは間違いない。それをとても不幸に感じるし、今となっては、どこか父に申し訳ないという気持ちもある。なのにまだ腹立たしい気持ちも同時に浮かぶ。
もう30年だぜ。
それぐらい性暴力は根深い傷跡を残すのだ。
そして今なら分かる。あれは治療なんかではなく、単なるわいせつな性行為であったことが。
この話を仲の良い友人に話せたのもごく最近のことで、こうして文字にするのは初めてだ。
強姦されたわけではない。陰部に指を入れられただけだ。
「だけだ」なんて書くのは問題があるだろう。現在も似たような経験をして、追い詰められている人もいるだろうから。「だけだ」と思い込みたい、というのが正直なところかもしれない。
ふてぶてしいセンセイに「気が強い」と太鼓判を押されるほどのわたしでさえ、性被害の体験を語ることは、重い。そして、それを乗り越えて語る女には、好奇の目と、いわれのない誹謗中傷が投げつけられる。
どうなんだろう。50間近の女がおおっぴらに語る遠い過去にも、いわれない批判が飛んでくるものなのだろうか。この文章を持って、それを知りたいという気持ちもある。
それぐらいの図太さがあって、こうして書けるほど、しんどいものなのだ。
今になって書くことができたのには、他に大きな理由がある。
母がもうこの文章を読むことがないからだ。彼女が生きていたら、娘の身に起きたことを思い出し、母親として傷ついただろう。父も認知症が進み、この文章を読むことはない。だからこうして書ける。
二人をもし傷つけてしまうなら、不特定多数の目に触れる場で、わたしは自分に起きた体験をまだこうして文字にすることはできなかっただろう。
性暴力は被害者を何重にも傷つける。
たかが痴漢だなんて思わないで欲しい。その被害者が、あなたの大切な娘であり、妻であり、家族であるかもしれない。
そして、それは女性に限ったことではない。あなたの大事な小さな息子が、性被害を受けて傷ついているかもしれないのだ。他人事ではない。そう感じて欲しいと切に願う。
実は、前回の更新以降、驚くほど多くの人から「実はわたしも...」と性被害にまつわる体験を打ち明けられた。それほど身近に、間違いなく性暴力がある。
最後に、たった今、性暴力や性犯罪被害で、傷ついたり混乱したり悩んだりしている人がいたら、安心して相談できる支援団体を記しておきたい。
日本全国にたくさんのそういう支援団体があります。ここに記すのは、わたしの友人が直接関わっているNPO法人なので兵庫県ですが、遠方の方には、きっとあなたの近くで相談できる窓口を教えてくれるはずです。
どうか一人で抱えこまないでください。被害者のあなたにまったく落ち度はありません。加害者だけに問題があるのです。自分を責めないでください。あなたは何も悪くないのだから。
引用・参考文献
『ほとんどないことにされている側から見た社会の話を。』小川たまか(タバブックス)