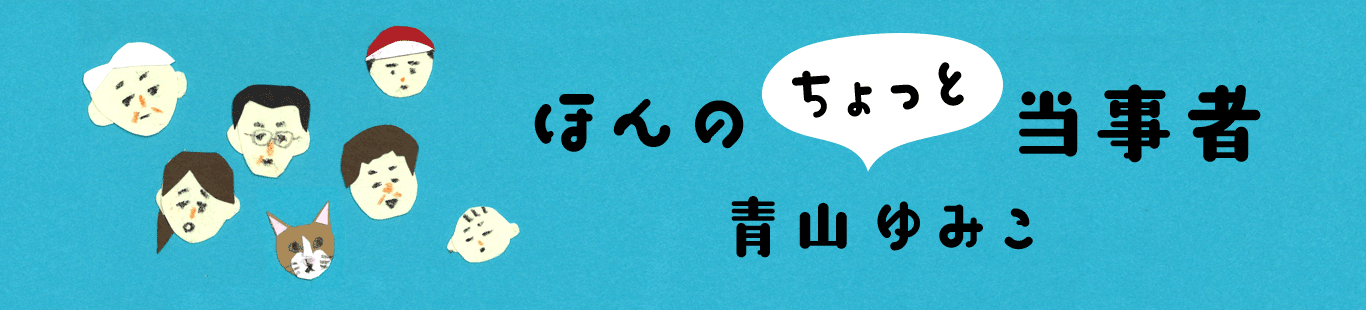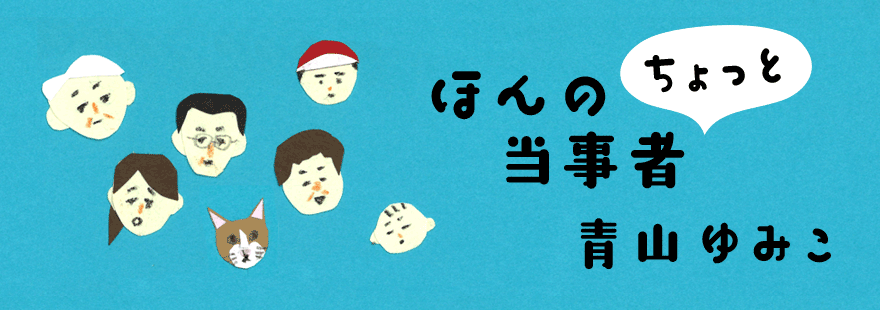第10回
父の介護と母の看取り。「終末期鎮静」という選択。(2)
2019.01.29更新
お知らせ
この連載が本になりました。ぜひ書籍でもご覧ください。
『ほんのちょっと当事者』青山ゆみこ(著)
「父の介護と母の看取り。「終末期鎮静」という選択。」の第1回はこちら
母の死は、あっけないものではなかった。
入院2日目からさまざまな症状が彼女を襲い、苦痛は彼女を不機嫌にさせ、唸り、叫び、悶え、常に気丈に振る舞っていた母が、どんどんわたしの知っている母ではなくなっていった。
ごくたまに苦しさがましになったとき、母は必ず今後の楽しみについて話をした。わたしたち母娘は二人で旅行に行ったこともなく(それは父を起因として、ある時期まで母娘関係がよくなかったことに関係するのだが)、一緒に温泉に行こう。ね、いいでしょ。そうやね、行こう。だから頑張って治療して元気になろう。
同じ内容を、母が苦痛にあえいでいるときに励ましの意味で持ち出すと、「これ以上、何を頑張れっていうのよ」と、彼女は強い口調でわたしを責めた。いや、わたしが彼女を責めてしまったのだと、今ならわかる。病人は限界を超えて頑張れる以上に頑張っているのだ。
ふと気づいたことがあった。
わたしはその半年ほど前から、母の通院や検査に付き添っていたが、いわゆる「余命宣告」を受けたことがなかった。
肝がんはひとまず落ち着いていたが、肝硬変に対する担当医の所見はたいてい「いつ何があってもおかしくない」というもので、あれがいわゆる余命宣告だったのだろうか。
だが、具体的な期限というか数値を伝えられることは一度もなかった。
容態が急変し、思いきって担当医に訊ねてみたのが入院3日目のことだった。「長くて半年」と返ってきた言葉に愕然とした。わたしは全く現実が見えていなかったのだと思い知らされた。
入院4日目には全身に力が入らなくなりほとんど自力で寝返りさえ打てなくなった母を目にし、5日目以降は病室で付き添うわたしは医師から頻繁に呼び出しを受けることになる。
その度に、あとひと月、あと半月と、彼女に残されたであろう時間は短くなっていった。
同時に、急性期の病棟では、これ以上できることはないため、安静のための転院の話を持ちかけられた。
そして「もしかすると1週間も難しいかもしれません。会いたい人がいれば呼ぶように」と告げられたとき、「死」はすぐそこに現実として見えた。
ああ、もうだめなんだ。
ホスピスを取材したことがあるわたしは、治療の継続を望む母がホスピスに入れないことを知っていた。ホスピスは本人が命の限りを受け入れた末期のがん患者のための場所だからだ。
苦痛を緩和するためにホスピスを選択するためには、彼女にその過酷な現実を伝えなくてはならない。ただひたすら、病気を治して自由に生きたいという希望だけで気力を保っている母が、その希望すら失ったときのことを想像するのが、わたしはなにより怖かった。
娘らしい孝行もせず、父の介護のすべてを押しつけたことで彼女をここまで追いやってしまった。
その挙げ句、苦悶の表情を浮かべながら唸り苦しみ抜いても、その時間のすべてが回復につながり、その先には自由な人生が待っていると信じて、けして希望を捨てない母を、結果として騙しながら、ただそばで見守るしかできないことは、これまで生きてきてこんな苦しいことはないという時間でもあった。
担当医とはこまめに相談を重ねた。ありがたいことに、母の要望を尊重して肝臓のための治療も継続しつつ、できるだけ痛みをやわらげる緩和ケアも始めてくれていた。
だが、彼女はすでに十分すぎるほどに頑張っている。今後、彼女自身が壊れてしまうほどの苦しみが襲うとき、「終末期鎮静(ターミナル・セデーション)」を行ってもらえるかどうか、わたしから相談をした。どうか最期はできるだけ苦しまずに眠らせてあげて欲しい。
担当医はそれを理解して、そのときが来たら、相談しながら鎮静を行いましょうと答えてくれた。
兄や弟にそのことを伝えると、最初は「安楽死はさせたくない」と拒否反応があった。
よく誤解されるが、終末期鎮静と安楽死はまったく異なるものだ。
緩和ケアの専門医の新城拓也先生は、著書『がんと命の道しるべ 余命宣告の向こう側』でこのように説明している。
「鎮静」とは、癌の患者が亡くなる前おおよそ1週間以内に、あらゆる緩和ケア、治療をしても苦痛が緩和されないとき、鎮静薬(睡眠剤)を使って眠ることで、苦痛がない状態にする方法である。鎮静薬は、亡くなるまで使い続けることがほとんどだ。亡くなる前に治療できない苦痛がある時、薬で眠ったまま死を迎えるようにする治療と考えてもよい。
また、新城先生はこうも書いている。
よく患者から、「最期に苦しんだらモルヒネを注射して楽にしてください」と頼まれることがある。しかし、モルヒネは痛み止めに使うもので、鎮静に使う薬はそれとは違う。モルヒネは痛み以外の苦痛にはそれほど効かないので、最期の苦しみをとるには不向きなのだ。
つまり、最期の苦しみとは、肉体的な痛みだけではないということだろう。
わたしも母が辛そうなときに、何度も「どこが痛いの?」と訊ねたが、「痛いとかじゃないのよ。わからないけど苦しいのよ。どうしてこんなに苦しいの」とほとんど悲鳴のような声で逆に怒って訊ねられた。
看護師さんは、よく「身の置きどころがないような感じですか」と母に声を掛けていた。そうして背中を優しくさすったり、温かいタオルで手足を拭いてくれたりした(同じことをわたしがしようとすると、あなたには無理。プロに任せてちょうだいと叱られた...)。
この「身の置きどころがないような苦痛」は肉体の苦痛だけではなく、心の苦痛で、「死にたいほど辛い」ものだという。母の場合もそうだったが、肉体的・精神的な苦痛から、せん妄と呼ばれる、意思の疎通が困難な意識の混濁した状態も見られるようになった。
そうした状態になったとき、もはや緩和ケアではとれない苦痛をとるために、終末期鎮静は行われる。
鎮静を行うには本人の意思が尊重される(本人の確認が難しい場合は家族の意思決定だけで行われる場合もある)。
母の命がもう限界であることは本人には伝えないで、鎮静について本人に確認することは、担当医にはかなりの無理難題だっただろう。
医師として嘘は言えない。でも全部を伝えることもしないという方法を採って、母の意識が少ししっかりしているときに、少し噛み砕いてこんなふうに説明をしてくれた。
眠ることさえできないほどの苦しさなんですよね。それを和らげるために、眠って苦しさをおさえる方法もあります。もう十分頑張ったので、眠って休んだほうがいいのかもしれないですが、どう思われますか。
よくわからない。でも、死んだ方がましなくらい苦しい。弱音を吐かなかった母が担当医にそう訴えた。
母の意図は「生きるため」のものではあったが、母自身が言葉にしてくれたことにどこか安堵した。
鎮静により、最期は苦痛から逃れることができるはずだと感謝すると同時に、決して「生きること」を諦めない母を裏切って、彼女の「死」を想定している自分はいったいなんだろうと、心が引き裂かれもした。
ほどなくそのときが訪れた。
担当医はとても注意深く、ごく低用量から鎮静薬を使いはじめ、母は少しずつ少しずつ意識を低下していった。
それでもなお、時折、苦しそうにうめき声をあげる母本人が、実際のところどう感じていたのかわからない。
看護師さんたちは、「もう苦痛はないはずです。でも、意識はありますし、耳は聴こえていますので、話しかけてあげてくださいね」と言うのだけれど。
ママ、どうしてそこまで頑張るの。もう頑張らなくていいよ。
思わずそんなふうに声をかけてしまう娘に、きっと母は腹を立てていただろう。勝手なことをして、わたしの人生なのに、と。
今でもそう思うときがある。
現在、SNSなどのweb上でご自身が末期ガンであることを公表され、終末期鎮静や安楽死について言及されている、写真家で狩猟家の幡野広志さんという方がいる。2017年12月に多発性骨髄腫という血液ガンを発病し、余命3年という宣告を受けたという。
彼が、昨年(2018)12月26日に、noteというブログのようなweb上の媒体で、「死ぬかもしれないから、言っておきたいこと。」というタイトルで、こんなことを書かれていた(一部抜粋)。
(※表記は原文ママ)
もしものときはセデーション(鎮静死)はできますか?とこちらから質問すると概ねいい答えが返ってきたので安心をした。
苦しんで死ぬというパターンも、助からないのに延命治療で生かされるというパターンも避けられる。そしてその両方のパターンを妻と子どもに見せなくて済む。
医師と患者がこのやりとりができたことが、ぼくはとても良いとだとおもった。医師がおなじ質問を家族にしてしまうと、こうはならない。
(略)
患者が望む最後と、家族が望む最後は違う。
患者は苦しみたくないが、家族は悲しみたくないのだ、意見が一致するわけない。
そして医師が尊重するのは、家族が望む最後なのだ。
野次に負けた妻が人工呼吸器を使って延命してほしいといったり、心臓マッサージを希望すれば、医師はやる。なぜ医師がそれをやるかというと、それが医師の望む最後だからだ。
そして鎮静死、セデーションは医師の裁量で行うものなので患者が希望しようが関係ない。
患者の意見が尊重されない仕組みになっている、それが日本の医療の現実だ。
誤解しないでほしいのだけど、医師や家族だけが悪いわけじゃない。
意思表示を明確にしない患者も悪いのだ。
患者の意見が尊重されないというくだりは、もしかすると、意思疎通が難しくなった状態でのことかと思うのだが。
確かに母の場合は、「生きたい」のに、家族(わたし)の判断によって鎮静が行われたという点では、幡野さんとは逆の意味で「患者の意思が尊重されなかった」ともいえるかもしれない。
書かれているように、幡野さんは終末期鎮静に対して前向きだ。自分のためにも家族のためにも。また、安楽死にたいしても肯定的で、「言いにくいことだけれど」という前置きで、こんな意見も述べている。
ぼくが肌で感じたなかで一番強く反対するのは、家族や大切な人をトラウマや後悔を抱えるかたちで、ガンなどで亡くしてしまった一部の人だ。
(略)
なぜなら"安楽死"という言葉を想像したとき、賛成する人は自分の命に置き換えて、自分だったら苦しみたくないなぁと、必要性を感じて賛成をする。 反対する人は"安楽死"という言葉で、家族や患者の命で想像するから、死なせたくないという気持ちで反対するのだ。
(略)
必要な人は選べばいい、不必要な人は選ばなければいい、ただそれだけのことだ。
全文はここで読める。ぜひご一読いただきたい。
幡野さんは、それぞれの立場で思いはあるが、患者本人の意思を尊重することがなにより大切だと繰り返している。
最期まで生きたがった母のことを思い出すと、やはり複雑な思いがある。あのときは最良の選択だと思い込ませたが、後悔がないとはやはり言えない。母に対する申し訳なさは、この先消えることはないだろう。
安楽死については、わたしは否定も肯定もできない。なんだか情けない言い方になるが、正直、想像がうまくできずよくわからないのだ。
『毎日がアルツハイマー ザ・ファイナル』(上映会情報はこちら)で関口監督は、スイスの自死幇助クリニックの院長である、エリカ・フライツェック博士を訪ねる。スイスでは32年前から「自死幇助」を認める法律があり、実質、安楽死が合法化されている。
ただ、安楽死と自死幇助は混同されがちだが、異なるものだ。
安楽死では医師が患者の命を断つが、自死幇助では医師は薬の準備をするが、命を絶つことは患者自らが行うという違いがある。この違いは大きい。
エリカ博士自身も、彼女の父の強い願望によって自死幇助を経験することになった。彼女の肩によりかかって、父は眠るように逝ったという。
彼女の自死幇助クリニックでは、家族に自分の意思を説明した患者しか自死幇助を受け付けていない。患者は家族に自死幇助についてオープンに話した上で、家族の見守るなか、患者は自ら死んでいくことになるのだ。
「家族に最期のお別れも言えるし、新しい死に方の文化」だとエリカ博士は語る。
ただ、エリカ博士のクリニックがある村では、99%は緩和ケアを選択するのだそうだ。その緩和ケアには終末期鎮静も含まれている。
鎮静を行った患者さんは意識がないまま深い眠りのなかで命をまっとうするが、そうした終末期鎮静は自死幇助とは無関係だと彼女は話す。
エリカ博士自身が恐れるのは、認知症になったり、脳卒中の後遺症で自分で決断ができなくなって、自分で「死」に対する意思決定ができなくなることだと言う。自死幇助に必要なのは、「健全な精神」なのだとエリカ博士は語った。
映画『毎日がアルツハイマー ザ・ファイナル』は、認知症の人の死を誰が決定するのかということも問う作品だ。
これは、わたし自身にも切実なテーマだ。父がこの先、もし緩和ケアが必要となるような苦痛に満ちた終末期を迎えたとき、彼が「どんな死を選択するか」を誰が決めるのだろうか。おそらくそのときの父は、自分で判断することはできない認知機能の低下した状態にあるだろう。
わたし自身は、自分に何かあったとき、延命措置をしないで欲しいこと、緩和ケアや終末期鎮静についても肯定的であることを身近な家族に伝えてある。
エリカ博士が言うように、また幡野広志さんが発信されているように、「自分で決める」ことが大切であると考えている。ただ、それでもやっぱり自分の意思が変わらないとも限らない、とも思う。
こうして自分が「どう死ぬか」を考えることは、同時に「どう生きるか」と同じように思うのだ。例え余命宣告を受けて、どんなに死が近づいたとしても、人は死ぬ瞬間まで生きている。だからどんな「死に方」を選ぶかを考えることは、「どう生ききるか」という意味を含む。それはけしてネガティブなことではない。そんなふうに感じている。
余談になるが、ほぼ2週間つきっきりで、最後は病室に泊まり込んでいたわたしだが、母の死に目には会えなかった。
その日も苦しい夜をなんとか乗り越えて、今日もまだ頑張ってくれそうだと、兄や弟と交代しながら食事をとったりしているなか、ふと鏡に映った自分の顔が目に入った。そこには化粧のはがれたみすぼらしい40女の姿があった。
母はわたしが身なりに構わないことをとても嫌がる人だったので、手鏡をのぞき込みながら、アイブロウで眉毛を真剣に描いていた。すると背後から、緊迫した気配で兄が母を呼ぶ声が聞こえて、振り返ると彼女は静かに息を止めていた。
ま、眉毛かよ...。
そういう意表を突いた逝き方も母らしくて、思い出すたびにいつも切なくて、でもちょっと可笑しくなる。人の死に際というのはほんとうに分からないものだ。
引用・参考文献
●『がんと命の道しるべ 余命宣告の向こう側』新城拓也(日本評論社)