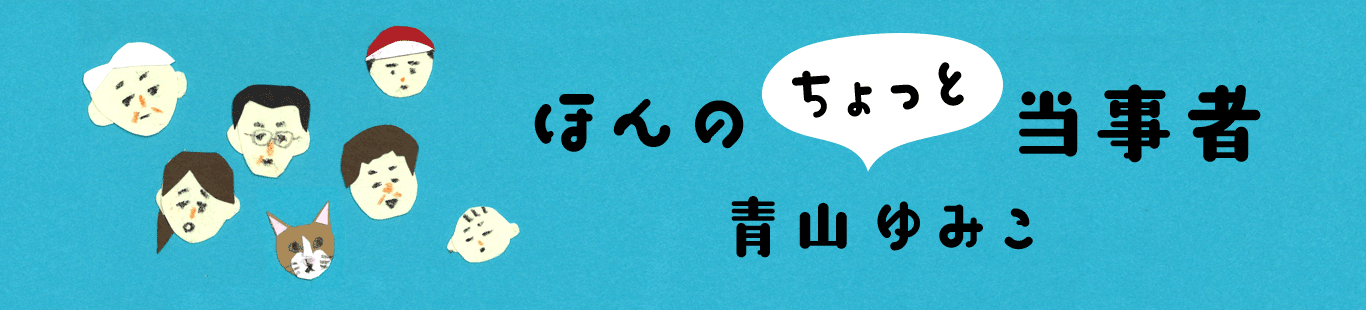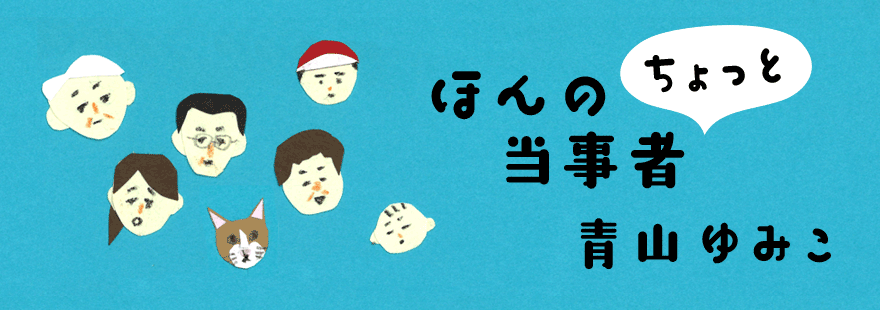第12回
哀しき「おねしょ」の思い込み。(2)
2019.04.03更新
お知らせ
この連載が本になりました。ぜひ書籍でもご覧ください。
『ほんのちょっと当事者』青山ゆみこ(著)
前回連載分、哀しき「おねしょ」の思い込み。(1)はこちら。
中学受験を控えた兄は、めっきり大人びてきて、母を無闇に刺激しないようになり、まだおぼこく素直で無邪気な性格の弟は「男の子はやんちゃなくらいでいい」と、末っ子ならではのかわいさもあってか、何かと上の二人に較べて容認されることが増えた。
身長の伸び、それなりに母の家事の「戦力」ともなってきたわたしは、「女」であることが「子ども」であることよりも優先されるようになった。
母にとっては、家族のなかに「女の味方」ができて、その女の子は自分を助けてくれる存在になるはずだと期待しただろう。
父は大声で怒鳴ったり、酒癖が悪かったりなどということは一切なく、どちらかといえば、外面のよいお調子者で、同時に几帳面で真面目な部類の人だったが、前述したように強い男尊女卑の主義のもと、「女は黙って家の用事さえしていれば良い」という考えを押しつけた。
母に対しては、妻である彼女はもちろんのこと、娘にもそうした教育をするように圧を与えた。
わたしが従順に従える性質だったら特に問題はなかったのだろうが、残念なことに、わたしは口答えしかしない娘だった。加えて、人の感情の揺れに敏感なところがあり、その上で、わざと逆なでするようなふてぶてしさを持っていた。
小5〜小6の頃だろうか。ある日こんなことがあった。
弟の部屋がいつものように非常に散らかっていた(大人になっても彼の部屋は常にものが散乱し、部屋はカオスの状態だった)。
お前が掃除をしろ。父にそう命じられた。
なぜ、わたしが? 自分のことは自分でやればいいでしょ?
はあ? という小憎たらしい表情で言い返す娘の言葉に父はみるみる激昂し、隣にいた母は「どうして女の子なのに、弟の世話をしてあげようという、優しい気持ちを持てないの」とわたしを怒鳴りつけた。
年長者が年下の者の面倒をみるという理に異論はないが、「女の子だから」となると話は別だ。ましてや「女の子らしい優しさ」を自明の事実として要求されると、疑問と憤りしか湧いてこなかった。
「わたしの優しさ」ではない「女の子らしい優しさ」ってなんなんだ。
なぜ「女」であることが理由となるのか。そんなことなら「女」なんかに生まれたくなかった。そうやって「なぜ」「なぜ」「なぜ」を連発する度に、怒鳴られて叩かれた。
母自身、明確な答えを持っておらず、責めたてられたような気持ちになったのだろうと今は思い当たる。
また、わたしはどこかで、父に従属的に生きる母を同性の立場から責めていたのだ。なぜ母がそう生きざるを得なかったのかも考えずに。
わたしに足りなかったものは、「女の子らしい優しさ」ではなく「人間らしい優しさ」だったのかもしれない。
虐げられた女同士、味方になるはずだった娘に裏切られ、やり切れなかったのだろう。言葉にもできないものが、負の感情となり、どうしていいのかわからず娘に手をあげずにはいられなかったのか。
夜、家から追い出されて鍵を閉められることも多々あった。庭先の犬小屋の横でうずくまって、仕事の関係で10時半頃に帰宅する父を待った。そういうときだけ父は「もうゆるしてやれよ」と良い役回りを演じて、母はそのことでまた苛立った。
何一つ明解な答えを得られないまま、わたしの身体と心には行き場のない疑問と哀しさと憎しみと痛みが蓄積された。
そんなふうに怒られた夜に、わたしは決まっておねしょをした。
朝、湿った布団にバスタオルを当ててごまかしてから学校に行くのだが、帰宅すると、鬼のような形相で母が待っている。
手に持った布団叩きでわたしはまた叩かれまくった。するとその夜にまたおねしょをしてしまうのだ。翌日のことは言うまでもない。
それは中学生になっても時折、起きた。
高校生になる頃には、わたしの身長は母と同じくらいになり、ヒステリックに怒鳴る母が口だけではなく、手をあげそうになると、自分の身体をぐいぐいと母に押しつけて、威嚇して対向できるようになった。
母は驚いて怯んだ。以来、叩かれる回数は減った。わたしももう布団を濡らすことなどはなくなっていた。そしてもう「なぜ女だけが」という答えの返ってこない不毛な質問をすることを諦めた。
叩かれたり怒られたりする代わりに、あなたのような難しい娘を持って辛いと母から泣かれるようになり、身体の痛み以上に胸がきりきりと刺されるような気持ちになることが増えた。
高校は地元の公立に進学したが、第一志望はとある私立の女子高校だった。なぜかというと、その高校には寮があったからだ。こんな家にいたくない。その一心でその学校に願書を出した。
面接では、自宅から十分に通える距離なのに、なぜ入寮を希望するのかと面接官に訝しまれた。結局は落ちて、寮にも通えなかったのだが、願書を出すときに、入学したら寮に入るからと言い放つ娘に母が聞いてきた。
どうして?
この家が嫌いだから。
驚いた母の顔を今でも覚えている。
わたしからすると、その言葉に驚かれる方がもっと驚きだったのだが。
我が家のお正月は、日頃からばたばたしている母がもっともぴりぴりする時期なので、わたしは毎年冬休みが大嫌いだった(小学生の頃、大晦日は決まって母のぴりぴりに反応して熱を出して倒れ、この忙しい時期に...とよけいにびくびくしていた)。
余談だが(ほとんど余談だけど)、わたしは初潮が遅く初めて下着に血を見たのが15歳の元旦の朝だった。2月生まれなので、もうほとんど16歳になりかけていた。
わたしは絶望的な気持ちになった。母がもっともばたばたと神経をすり減らす正月のこんな日に、なぜ...。
また、わたしにとって初潮とは「女」であることを決定づける忌むべきものでもあった。そのまま誰にも告げず自分なりに処理をしていたが、3か月ほど経った頃に母が生理用品を渡してきて、あれこれと教えてくれた。
高校3年生か大学1年ぐらいの元旦のこと。
その年も、前日の大晦日にわたしもおせち作りを手伝いながら、母は家中の掃除に追われていて、元旦の朝はおそらく精神的な疲れがピークだったのだろう。
寝床から出てリビングに行くと、兄や弟がのんびり正月のテレビを観ていて、母が台所でばたばたしていた。お皿を出すよう言いつけられて、用事をこなしながらなんだか兄や弟に腹が立ってきた。
お兄ちゃんたちも手伝ってよ。
そのわたしの言葉を耳にした母が、キレた。女の子なんだから黙ってあなたがやればいいでしょ。思わずまた、「なぜわたしだけが」と口答えすると、母はいきなり手に持っていたものを床に叩きつけ、わーと泣きながら寝室に閉じこもり、もう嫌だ嫌だと大声で泣き続けた。わたしはただ「ごめんなさい」と謝った。
親に泣かれる。これを書きながらも、そのときに感じた胸の痛みとやり切れなさと怒りと哀しみと、いろんな感情がこみ上げる。正月は長いあいだ嫌いだった。
外の世界ではそうではなかったが、「家」にいると、自分の意思は拒絶され、存在が役立たずだと叫ばれているような気がした。その頃から、しょっちゅう「ああ、もう死にたいなあ」と感じるようになった。いっそ腹いせに自殺して、母を後悔させたいと思うまで、いま思えばわたしの心は完全にねじ曲がっていた。
子どもたちが高校、大学へと進学し、子育てがひと段落してくると、母にも余裕が出てきた。ヒステリックに怒られる回数も減った。
母もまた、父の「女」への要求や態度に疑問を膨らませるようになり、娘はいつの間にか「横暴な夫の愚痴」を聞かせる対象になっていた。
推薦入試でなんとなく選んだ女子大では教育学を専攻し、ゼミのテーマだけにはこだわった。選んだのは幼児教育のゼミで、卒論のテーマはジャン=ジャック・ルソーの『エミール』の教育論だった。
わたしは子どもを可愛いとは思えなかった。自分よりも弱い存在で、大切にされる「子ども」が鬱陶しいとさえ思っていた。わたし自身がそんなふうには扱われなかったからだろう。
そのため幼児教育になんて本当はまったく興味が持てなかったのだが、ある恐怖感を持っていた。
もし、将来的に自分が親になってしまったとき、母のような子育てだけはしたくない。自分の子どもが思い通りにならないときは、わたしは間違いなく母と同じように激しく感情をぶつけて、子どもの身体と心を傷つけるだろう。そのことが怖かった(結局、子を持つ選択をしなかったのだが)。
しかしルソーの教育論は、わたしが求めたような現実的な教育指南書ではなく(そんなこと読めばすぐにわかったはずなのに)、書かれていたのは理想論であり、教育哲学だった。
卒論のテーマに選んだことを後悔したが時すでに遅しで、卒論はただ文字で埋めただけの内容だったと思う。恥ずかしぎる。同じゼミの子が選んだシュタイナー教育の話が面白く、それが聞きたくてゼミに通ったようなものだ。
ちなみにこの文章を書くときに、20数年ぶりに岩波文庫の『エミール』を読み返そうとしたが、即座に挫折した。でもNHK100de名著シリーズの西研著『自分のために生き、みんなのために生きる ルソー エミール』はめちゃくちゃ面白かった。そんな本だったのかと目から鱗が何千枚も落ちたので、わたしがいうのもなんですが超お勧めです。
翻って母の話。
父からの呪縛からも少しずつ解き放たれて、もともと本を読むのが好きな彼女は、さまざまな女性の生き方について書かれたものを読み漁るようになった。そして自分の子育てを反省するような言葉を口にすることが増えた。
本当に真面目な人だと思う。その真面目さゆえに、また違う意味で傷つけられるようにもなる。
ある日、我が家にもよく遊びに来ていた大学時代の親友から、わたしの母が「ゆみこちゃんを可愛がってあげられなかった。申し訳なかった」と打ち明けられたと告げられた。
傷ついた。もういっそなかったことにしてくれたら良かったのに。
母は真面目に後悔し、自分を責めるようになった。そのことでわたしがまた責められるような気持ちになることも知らずに。
人は何かを押しつけられなくなったとき、初めて自分の世界が始まる。ようやく二十歳を迎えた頃にわたしの人生が始まったのかもしれないとも思う。
大人になると、仲の良い母娘と同じくらいの割合で、どうにも噛み合わせが悪いわたしたちのような母娘がいることを知るようになった。
わたしはただ愛されたかった。「女の子」とか「男の子」とか関係なく、ただ母の「子ども」という大切な存在として扱ってもらいたかった。
男というだけで威圧的な態度を取る夫を持ったなら、娘にはそういう目に遭わせたくないと思う母でいて欲しかった。
ただ、今では同時にこうも思う。
なぜわたしだけでも母の味方でいてあげられなかったのだろう。わたしは常に「わたしは」「わたしは」から離れることができなかった。わたしもまた父と同様に自分本位で身勝手な人間だったのだ。
「おねしょ」と母から受ける叱責や叩かれる痛みはセットなので、今でも「おねしょ」と聞くと恥ずかしさと惨めさ、そして心の痛みが蘇る。
そうした個人的な経験から、長い間、おねしょは心身的なストレスによるものだと思い込んでいた。
夜尿症について調べていると思い当たったのだが、わたしは幼少期の頃、夜驚症と夢中遊行症もあった。
夜驚症(やきょうしょう)とは、3〜10歳くらいの子どもによくみられるもので、入眠2〜3時間後に突然目を覚まし、何かに怯えたように泣いたり叫んだり歩き回ったりする一種の睡眠障害だ。
わたしも子どもの頃によくこうしたことがあり、父と母のいる部屋や、トイレの前に立ってわんわん泣いた。そして突然、また自分の布団に戻って寝たのだそうだ。
夢中遊行症も、夜驚症と似ているが、これも睡眠障害の一種で、突然起き出して、うろうろと部屋を歩き回っては、話しかけても寝ぼけたような感じで反応せずに、また布団へと戻る。
おぼろげな記憶のなかでは、わたしはどちらかのパターンの夜もおねしょをすることが多かった。そして、その日の日中は母に激しく怒られていた。そのため、夜驚症も夢中遊行症も、自分のなかでは「可哀想なゆみこちゃん」の惨めなおねしょの思い出とセットになっていた。
だが、現代医療では、夜驚症も夢中遊行症も神経系の未発達が発症の根底にあるといわれていて、ほとんどは成長とともに症状が消失する深刻な病気ではないことがわかっている。そして、親に怒られたからというストレスが原因でもなさそうだ。
どちらも幼児期に見られる、深刻ではない病気でしかなかったのだ。
医療は時代とともに発展しているため、おねしょにしろ、昔とは大きく捉え方が変わっている。もし、わたしの子どもの頃に「夜尿が病気」だとわかっていたら、母もわたしのおねしょ癖に対して、あそこまで怒らなかったかもしれない。わたしもおねしょと母を結びつけて、恨んだりせずに済んだかもしれない。
無知というのは哀しい。
今現在もおねしょに悩んでいる子どもが少なくない。でもおねしょは治療により治癒する病気なのだ。
そう知れば、おねしょがお母さんのせいでも子どものせいでもないと開きなおれて、少しは気が楽になるかもしれない。ぜひ末尾に明記した関連書籍などに目を通してみてください。
幼児虐待の報道などで、たまになかなかおむつが取れないとか、おねしょが一つの原因となり、しつけと称した体罰が過激になり、哀しい事件につながるのを見聞きすることがある。
夜尿だけが原因ではないだろうが、知識がないがゆえにお母さんのストレスが増大することもあるかもしれない。うちの母もきっとそうだったように。
どうかそんなことが少しでも減りますように。
今だったら、もっとお互い楽になれる方法もあったかもしれないね。そんなふうに亡き母に語りかけるのであった。
という文章を書いてすぐの、3月15日のことだった。
愛知県の30歳の母親が、生後11カ月の三つ子の次男を床にたたきつけて死なせたとして傷害致死の罪に問われた裁判員裁判で、懲役3年6カ月の実刑判決が言い渡された。
不妊治療の末に授かった三つ子だったそうだが、3人の子を同時に育てる生活は想像以上に過酷で、ミルクは3人あわせると最低でも日に24回。寝る暇もなかったという。彼女が、事件前に重度の産褥期うつ病(産後うつ病)を発症していたとも新聞報道で読んだ。
そんな報道を受け、SNSでは大きな反響があった。双子や三つ子といった多胎育児を経験した母親たちはもとより、「一人でも大変なのに」と多くの子育て経験者から悲痛な叫びが、わたしのタイムラインを埋めた。
うちは三つ子ではないが、ほとんど年子の3人きょうだいなので、彼女と自分の母親の子育ての風景がオーバーラップして、胸が詰まった。
彼女と、乳児院に保護されたという、残りの2人の子どもにどんな救いの手があるのだろう。そのことを考えずにいられない。
●引用・参考文献
『バイバイ、おねしょ!』冨部志保子(朝日新聞出版)
『新 おねしょなんかこわくない―子どもから大人まで最新の治療法』帆足英一(小学館)
『睡眠障害のなぞを解く 「眠りのしくみ」から「眠るスキル」まで』櫻井武(講談社)