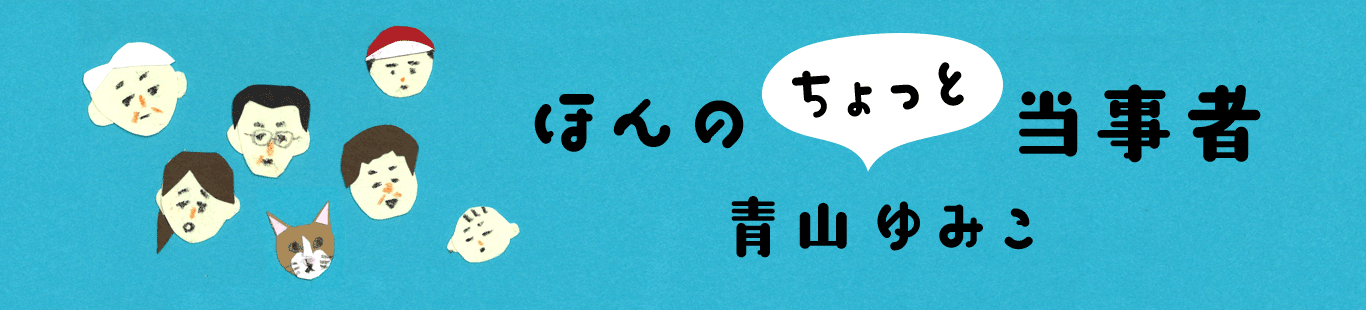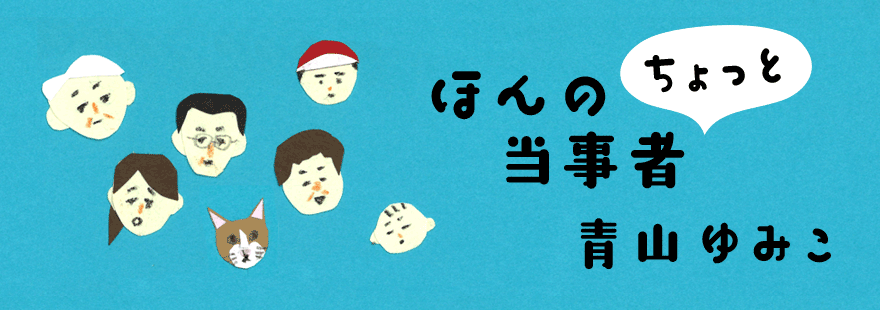第14回
わたしは「変わる」ことができるのか。(2)
2019.06.04更新
お知らせ
この連載が本になりました。ぜひ書籍でもご覧ください。
『ほんのちょっと当事者』青山ゆみこ(著)
前回連載分、わたしは「変わる」ことができるのか。(1)は、こちら。
ここ数年、いろんな「困りごと」を抱えている人に話を聞いたり、ボランティアというには大層だが、何かしらの問題により一人では生活ができない人が集って暮らす場所に足を運んだりする機会が増えた。
お会いする人のなかには、身体的に、あるいはメンタルの面で障害のある人も少なくない。
35年前、困りごとを抱える人を意図して遠ざけようとしたわたしが、今なぜ彼らと一緒の時間を過ごしたり話したりしたいと思うのか、自分でもよくわからない。
わたしという人間が大きく変わったという自覚はない。
生きるということは、自分ではない誰かと関係を持つことだ。人はひとりでは生きられないから。毎日口にするお米だって野菜だって、会ったことはないけれど、誰かが作ったものを食べてわたしは生きている。
それと同じく当たり前のように、学校で、職場で、ご近所さんと、行きつけのお店の人と、わたしは関わりを持ちながら暮らしている。
そんな時間の積み重ねが影響して、人は知らないうちに変わる。
という一般論以上の、何か特別なエピソードには思い当たらない。
小学5年生のわたしには竹原くんが「面倒な存在」に感じた。
今のわたしは、なんというか、彼を面倒に思わなくなったというより、自分自身もまた面倒な存在だと自覚するようになった、という気がしている。
恵まれた人が困っている人に手を差し伸べる。そんな一方向の話ではなくて、お互いさまのどっちもどっち。同じ社会で生きるというのは、互いに迷惑をかけあっていくのが当たり前。
そう思うほど、私自身が幾度となく「面倒な存在」になってきたように思う。あの日あの時、誰かに助けてもらった、という強い思い出があるわけでもないが、なんとなく、わたしも許されて生きてきたもんなあ...という、ぼんやり頼りないスタンスなのだけれど。
この春先に、大空小学校という大阪にある公立小学校の、初代校長である木村泰子先生の著作まとめのお手伝いをした(『「ふつうの子」なんて、どこにもいない』という書名で7月上旬発行予定)。
大空小学校の日常を追ったドキュメンタリー映画『みんなの学校』(2015)が話題となり、今も継続して上映会が開催されているのでご存じの方も多いだろうが、簡単に説明したい。
2006年、「すべての子どもの学習権を保障する学校をつくる」という理念を掲げて大空小学校は創立された。理念はごく当たり前の文言に思えるが、実はこの「すべての」を実現している学校は、残念ながら多くはない。
文部科学省による平成29年度の調査発表によると小・中学校の不登校者数は14万4031人(前年度13万3683人)、1000人当たり14.7人となり、調査の始まった平成10年度以降、最多となっている。うち小学生の不登校者数は3万5032人。
こうしたデータだとぴんとこないかもしれないが、わたしの身近でも友人・知人の娘や息子が不登校であることは珍しくない。これを読んでいる人も同様ではないだろうか。
そんななか、木村泰子先生が在任中の9年間、大空小学校では不登校の生徒がたったひとりもいなかったという。
さまざまな理由から他の小学校に通えなかった子どもを、わざわざ校区内に引越をして大空に転校させる親も少なくなく、その9年の間に特別支援の対象とされた児童は50人を超えたそうだ。
それなのに不登校ゼロ。
大空小学校は特別支援学級を設けていない。他にも、よその小学校にあるものがいくつもない。号令もない。校則もない。
あるのはたった一つ、「自分がされて嫌なことは人にしない。言わない」という約束だけ。
例えば、授業中、じっと椅子に座っていられない子、友達に暴力をふるってしまう子、さまざまな障害のレッテルを貼られた子...いろんな子どもがいる。
大空小学校では、彼らを「矯正」することはない。
矯正とは、欠点や悪習を正常な状態に直すことだが、大空ではその「正常な状態」、いわゆる「ふつう」って何だ、「当たり前」って何だ...というところから問い直し、どんな状況であれ、まず子どもたちのあるがままを受け入れる(聞く限り、これがなかなか壮絶だったりもする)。
もし誰かが何かの困りごとに直面したら、マニュアルではないその時々のやり方で、子どもたち自身が向き合っていくように大人は場をつくる。
と書くと、それこそ「当たり前」のことかもしれないが、これがどんなに大変で難しいか、子育て中の親や、学校教育の現場に関わる人なら想像がつくだろう。
大空で行われていることは実にシンプルだ。
さまざまな養育環境で育った子ども、困りごとを抱えた子どもが、「みんなで一緒に過ごすためには、どうしたらいいか」。ただそのことを考えいくだけだ。
そんななかでは、お互いが少しでも気分よく過ごすために、日々、小さな「工夫」が生まれる。その積み重ねにより、他の小学校で不登校になった子どもたちも通える「場」が創り上げられる。
この工夫についてはここでは紹介し尽くせないので割愛するが(木村先生の著書をぜひ)、全員が共有する一つだけの約束、「自分がされて嫌なことは人にしない。言わない」にすべてが集約されているように感じている。
人がされてもっとも嫌なことって何だろう。
それは「自分という存在を排除される」ことではないだろうか。
大空小学校では、子どもも教員もどんな小さな排除の芽も見逃さない。
子どもに限らず、大人だってしんどい時には、うっかり「あっちへ行け」とやってしまうこともある。大空ではそんな時、必ず自分の行動をふり返って「やり直し」をする。
誰かを傷つけたり、手をあげてしまったり、「嫌なこと」をしてしまった時は、何がどう悪かったのか。どう解決するのかを言葉にして相手に伝える。自分の意思で。
そうした行動は、本人だけでなく、なにより周りの意識を変えていく。この「周りが変わる」という話はわたしには強い驚きだった。
子どもたちは、友達や大人の行動をものすごく「見て」いる。目にした状況を空気のように吸いこんだ子どもたちの変化は、ごく自然に広がって、今度は目に見えない強いつながりを生む。
どんな子も排除しない。いろんな子どもが同じ「場」にいる。
独自の、というより極めてシンプルな「場」だから、他では不登校だったのに、再び学校に通えるようになった子がこんなにもたくさんいるという事実。
木村泰子先生は、この「事実をつくる」ことが、何にも代えがたく圧倒的な意味を持つのだと繰り返し口にされた。
大空出身の子どものなかには、中学校に進むと他の小学校から来た生徒にいじめられる子も出てくる。
木村先生はこんな話もしてくれた。
大空1期生の卒業生の数人が、中学に上がってほどなく、浮かない表情で大空小学校にやって来た。木村先生に相談があると言う。
彼らと同じ中学校には、知的障害と自閉症の診断名を与えられていたある男の子が一緒に進学していた。彼は涎を垂らしながら、教室内を「アー」と言葉にならない声を上げながら走り回ったりする。大空ではそんな子が同じ教室にいるのは「当たり前」だ。彼が何をしていても、自分たちが勉強に集中すればいいだけと知っているので、まったく気にしない。もし助けを求めていそうなら、自分にできる方法を考える。
ただ、別の小学校から上がってきた子のなかには、「なぜこんなアホなヤツが自分たちと一緒の教室にいるのだ」と、批難の言葉を投げる子がいるという。
卒業生たちは、木村先生に助けを求めて母校を訪れたわけではなかった。
彼らはこう指摘した。友達を排除しようとする子が「ものすごく不幸だ」と。
このままだと、彼らは不幸なまま大人になってしまうだろう。そうならないようにするには、自分たちにいったい何ができるのだろうか。
それが卒業生による相談だった。
大空小学校の子どもたちは、誰かを排除するという発想を持つ子は、その子自身が「困っている子」であることを感覚的に学んでいる。同じ場にずっと一緒にいるから肌でわかる。
中学校という「社会の入口」で、その排除が起きることにも動じない。ただ、そのままでは「誰かを排除して生きる子ども」が、「不幸な大人」になるだろう。彼らはそのことを危惧していたのだ。
木村先生はそう知って驚いたと、笑って話してくれた。
あの痛ましい相模原の障害者施設殺傷事件に話を戻そう。
事件後、多くの論者がこれは障害者を標的にした犯罪、「ヘイトクライム」だと指摘した。その根本にあるのは、社会的弱者やマイノリティ(少数派)を「排除」しようとする考えだろう。
その気配を、わたしは自分のすぐ身近に感じる。
誰が書いたのか顔の見えない差別的なトイレの落書き、ネット上で匿名の投稿により標的を定めてなされるいわれの無い誹謗中傷の書き込み。また、実際に在日コリアンの多く暮らす街にわざわざ乗り込んで、口汚い言葉を暴力的かつ一方的に投げつけるネトウヨの言動は幾度も見せられている。今現在も進行形で。
そんな彼らとわたしとは違う。
そう思い込んでいたけれど、35年前の自分を思い出してみれば、わたしは彼らなのかもしれない、とも思う。
35年の間に、わたしは人間が変わったのだろうか。
再びそこに戻ってくる。
前述したように、自分もまた「面倒な存在」であると感じるようになったこと。
あと、自分の持つ「嫌な部分」に自覚的になり、できるだけそれを「出さない」ように意識するようになったこと。もし何か変わったとすればそんな程度だろうか。
誰だって、「嫌なやつ」だと思われたくない。本当は嫌なやつだったとしても、できればそれを隠しておきたい。情けないことに自分の言動は表面的なきれい事にしかすぎないかもしれないが、きれい事でいくしかないのだ、と。
そう考えた時、もう一つ思い出したことがある(次々にどす黒い闇が...)。
あれも小学校の高学年の頃だった。
母親に、アウシュビッツの収容所に関するドキュメンタリー番組を見せられた。モノクロの画面に映し出される光景はあまりに過酷で残酷で衝撃で、シャワーを浴びる度に水ではなくガスが噴き出すのではないかと、長い間、風呂場の扉を開けることが怖くてたまらなかったほどだ。
番組を見終わると、恐怖にかられたわたしは母親にこう告げた。
もし自分が同じような状況におかれたら、わたしはナチスに入る。痛いのは怖いし、悪いとは思うけど、ユダヤ人の友達がいても裏切る。親や兄弟だって密告するかもしれない。わたしは強い方につく。それでしか生き残れないから。
母は驚いて目を見開いて、「この子は...」と黙り込んだ。
根本的なところで、わたしは卑劣で弱い人間だ。本当に。誰かから理不尽な恐怖にさらされることが恐ろしくてたまらない。それは今も変わらない。
独裁者が現れて、圧倒的な暴力で人を支配する世の中になったなら、わたしはきっとその暴力に屈するだろう。だから、そういう世の中になって欲しくないのだ。切実に。自分のために。
自分が弱く愚かで、正義とは真反対にいる人間であることを、わたしは日常でもよく思い知らされる。その度に、自分の弱さが誰かに対して暴力に変わるかもしれないと、とても怖くなる。
それを自覚しているのなら良い人だ。
そう言われるともっとも落ち着かない気分になる。相手がそう思いたいだけで、残念ながらそんなんじゃない。ほんとに嫌になるくらいの卑劣さを持っているから、ごまかしているだけだよ。そう叫びそうになる。恥ずかしい。
そんなわたしでも、いつかは変わることができるのだろうか。考えれば考えるほど、わからない。自分が「本当はいったいどんな人間なのか」もわからなくなる。
そもそも本当の自分って何だ。本当の自分ってそんなに重要なのか?
ふと思う。木村先生が口にしたように「事実をつくっていく」ことこそ、いちばん重要なのではないだろうか。暴力や排除をゆるさないこと。ヘイトスピーチだってそうだ。時には声を上げることも必要だろう。大声でなくてもいい、小さくてもすぐそばにいる誰かに自分だけの生の言葉が届けば十分だと思う。その小さなさざ波は、時間はかかっても力強い大きなうねりになるかもしれない。
この先も許しがたい事件が起きるかもしれない。時代が大きくカーブして、予想もしなかったような排他的な世界に身を置かねばならない時がくるかもしれない。
と書いた矢先に、川崎登戸の路上で、児童たち20人が殺傷されるという痛ましい事件が起き、その影響を受け、76歳の元農林水産事務次官が、児童に危害を加えるという発言をした44歳の長男を殺害したとされる事件の報が届いた。
報道からは、前者の加害者、後者の被害者が、社会から排除され孤立していた気配が濃く感じられる。
言葉を失い、ただただ立ち尽くしそうになる。
そんななかで自分に何ができるのだろう。
きっと「いろんな人が当たり前にともに暮らす」という事実をつくって、積み重ねていくしかないのだ。切り取ったところで特筆すべきものもないだろうごく普通の日常こそが、その先の未来のための確固たる「事実」をつくるのではないだろうか。
NHKスペシャル「ともに生きる」には、事件後から発言を続けてきた社会学者の最首悟さんが登場する。
娘の星子さんは、ダウン症で重度の知的障害があり、最首さんご夫妻は40年にわたり自宅で彼女を介護してきたそうだ。
事件の背景に、経済合理主義の風潮を感じた彼は、新聞の論評でそのことを指摘する。するとある日突然、植松被告から最首さんの意見を否定する手紙が届いた。
そのことをきっかけに最首さんは拘置所にいる植松被告と実際に接見するが、深々と頭を下げて礼儀正しく現れた植松被告は淡々とした口調で最首さんを批難するだけで、意思疎通のできない重度の障害者の存在自体が不幸をつくるという持論を変えることなく、やり取りは平行線をたどってしまう。
「わたしはあなたに手紙を書くつもりです。長い期間にわたってのやり取りになるかもしれません」
最首さんは接見の最後に植松被告にそう語りかけた。
記者からのインタビューに最首さんがこう続ける。
命の問題が入ってくるので、相当長い返信になるでしょう。植松青年に語るということを超えていきますね。多くの人に向かって答えていくということになるだろう、と。
最後に、最首さんがこんな言葉を残した。
「わからないからわかりたい。でも、一つわかるとわからないことが増えているのに気づく。人にはどんなにしても決してわからないことがある。そのことが腑に落ちると、人は穏やかな優しさに包まれるのではないか」
その言葉は、真っ直ぐわたしにも向けられている。