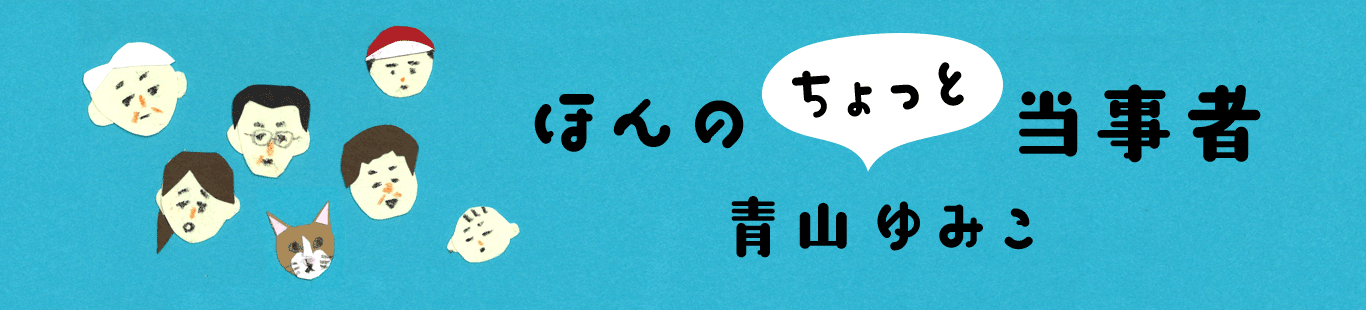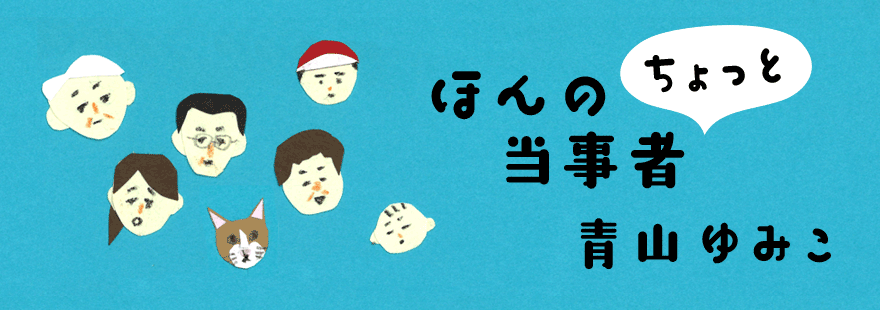第15回
わたしのトホホな「働き方改革」。(1)
2019.07.25更新
お知らせ
この連載が本になりました。ぜひ書籍でもご覧ください。
『ほんのちょっと当事者』青山ゆみこ(著)
「ボロ雑巾」というドキリとするような文言が見出しから目をひくハフポストの記事を読んだのは、7月4日の昼下がりのことだった。
「ボロ雑巾のように捨てられた。世の中変えたい」
7月4日は先の参院選の公示日だ。
タイトル通り、参院選に関連したニュースで、渡辺照子さんという女性が、山本太郎参議院議員(当時)が代表を務める政治団体「れいわ新選組」から立候補したという内容だった。
選挙の度に女性の新人候補が現れる。
元キャスター、タレントなど、テレビメディアで顔の知られた女性が少なくない。「子育てをしながら働いてきた女性としての立場」をベースに、育児や教育の問題を掲げる候補者が多い(各政党が「政治的に」担ぎ上げた女神輿のような候補者もいるが)。
また、弁護士といった専門職としての活動から、社会的弱者の抱える困難や、そうした状況を生む社会の暗部を目の当たりにして、立ち上がる女性も増えている。頼もしい。
出馬の経緯はさまざまだが、「社会的に認知された立場」や、名刺じゃんけんで強い札となるような「肩書き」を持ち、男性社会のなかで、その優秀さから積み重ねてきたキャリアがプロフィールを埋めるような女性がほとんどだ。
立候補した女性の紹介を読むと、「ああ、この人なら出馬してもおかしくないよな...」と感じさせられる人ばかりだったりもする。
と書きながらふと思う。
その「おかしくない」ってなに? 政治家に立候補するのに「おかしい女性・おかしくない女性」の基準が自分の中にはあるのか?
無意識にかけていたくもりきった眼鏡に気づかせてくれたのが、冒頭の渡辺照子さんの存在でもあった。
元派遣労働者のシングルマザー。
といっても、シングルマザーはもはや珍しい存在ではない。前述したように、現役議員として育児問題に切り込んでいる人もいる。そういう人は、ビミョーな響きだが「ママ候補」「ママ議員」などと呼ばれることもある。
しかし渡辺照子さんからは、そんな「ママ候補」とは異なる気配が漂う。
インターネットで検索してみると、ハフポスト以外にも、彼女が発信する言動を取り上げた記事や動画が溢れていた。
一つひとつ見聞きするうちに、彼女は「労働問題」を焦点に、この国の政治・政策を変えたいと考えていることが次第にわかってきた。それには彼女自身の体験が大きく影響している。
渡辺さんは、私鉄車掌の父と、内職で服の型見本を作っていた母の長女として1959年に新宿で生まれた。大学時代は、女性史研究会などに所属し、学生運動にものめり込んだ。いわゆる成田闘争などにも参加したそうだ(年齢から推測すると、1966年の三里塚闘争ではなく、1978年開港後にゲリラ事件が多発した頃だろうか)。
同じ活動家仲間であった男性との間に子どもができて出産し、大学は中退。一人目を出産したのは真冬の酷寒の時期で、当時は家がなく、宿泊施設に泊まるお金すらないので、新生児を抱いて野宿したこともある。そんなホームレス状態の生活を5年ほど経験したという。
は、ハードすぎる...。
誰か助けてくれる人はいなかったのか。幼児を抱えてホームレス状態というのはなぜなのか。そんなことが可能なのか。夫は何をしていたのか。わからないことが多すぎるが、インターネットではそのあたりの詳細が拾いきれなかった。
二人目の子どももできて、彼女が25歳の時、当時の夫が失踪(まぢか!)。いきなり2人の子どもを抱えるシングルマザーとなったという。
その後、スーパーのパートや、生命保険会社の営業など、「職を転々としてたどり着いたのが、派遣労働という道だった。40歳になっていた」とある記事で目にした。
「職を転々として」というワンフレーズに、どれだけ困難に満ちたエピソードが含まれるのか想像もできないが、ある動画では、「大学を中退してシングルマザーになったことで職務経験が無いため、正社員になれる確率が低かった。40歳になったとき、パートよりはまだいいのかな、という感じで派遣労働者になることを選んだ」と語っていた。
そのことから、25歳からの15年間、パートタイム労働者として2人の子どもを育てたのだろうと推察できた。
日本で、労働者の派遣事業が可能になったのは1986年の労働者派遣法施行以降のことだ。
当初はソフトウエア開発、事務用機器操作、秘書など専門13業務に限られていたが、その後の改正で26業務にまで拡大。1999年には医療、製造業などを除き、原則自由化された(2004年には製造業も解禁)。
40歳という渡辺さんの年齢から計算すると、彼女が派遣労働者になったのはおそらく1999年頃のことになる。それは、社会的にも「派遣社員」という名の非正規雇用労働者が増加し始めた過渡期でもあったのだ。
渡辺さんの派遣先は、東京文教区のコンサルタント会社だった。彼女はここで約17年勤めることになる。
事務用機器操作という専門業務だったが、電話対応や海外招聘者のアテンドなどにも関わったそうだ。彼女の親切なアテンドが評判となり、中東の顧客からは「会うのを楽しみにしていた」とお土産をもらったこともあると、ある動画でハンドメイドのアクセサリーを手にして笑う彼女が映っていた。まるで大切な宝物を扱うように。
しかし、「派遣労働者」である彼女の賃金は10歳若い女性正社員の半分以下だったそうだ。それも3カ月ずつの更新で、いつ雇い止めに遭うかわからない不安定な日々だった。
社員であれば福利厚生面で配慮される、「忌引き」もなかったことにも言及されていた。それが「忌引休暇」なのか「弔慰見舞金」を指すのか記事からはわからなかったが、渡辺さんはそのことについて、「差別され、自分の親族の人格さえ認められないように感じた」と語っている。
渡辺さんは黙って耐えている女性ではなかった。
2011年頃からは、日弁連の集会で話をしたり、専門誌に寄稿するようになる。
2015年8月には、改正派遣法を審議した参院厚生労働委員会の参考人質疑においては、「宇山洋美」という活動名で「派遣労働者が3年ごとに失職する法律は廃案を望む。派遣労働者は間接雇用で、派遣元も派遣先も責任を負わない。労働三権(団結権、団体交渉権、争議権)を主張しても、契約を更新されないだけだ」と意見を述べている。
職場での状況を変えようと、努力も重ねた。秘書技能や貿易業務、ビジネス実務法務、ファイナンシャル・プランナーなどの資格も取得した。正社員になるのに役に立つかもしれないと思ったからだ(ある記事では、数千冊あるという自宅の蔵書の一部が写っていた)。
そうやっていくつもの資格を取ったが正社員にはなれず、2017年12月、その日が来た。16年8カ月もの間勤めてきた派遣先の企業からの契約終了を告げられたのだ。いわゆる「雇い止め」だ。
通告したのは派遣先の企業ではなく、派遣元の営業マンだった。
約17年通ったコンサルタント会社の総務部からは、「最終日に入館カードを返してください」とひと言告げられた。その日の終業時間をもって、渡辺さんは同僚に入館カードを託し、会社を後にし、無職となった。
賞与や交通費が出ない派遣労働者には、退職金もない。時給は1750円で始まり、3カ月ごとに60回以上契約更新したが、昇給はたった80円だったという。
ある日の参院選の街頭演説で、渡辺さんはこんなことを語っている。
『私、記者会見の後に、新聞記者の方から、「どういう肩書きだ」と非常に詳しくというか、まあ、しつこくですね、聞かれたんですけれども、私にはしかるべき団体や会社の肩書きなんてまったくございません。元派遣労働者、そしてシングルマザー。この2つです』
記事などから知る渡辺さんの足跡に感じるものは山のようにあるが、わたしが最も強いインパクトを受けたのは、実は上記の発言だった。
まるで見たかのように、この記者とのやり取りの風景が目に浮かんでくる。
「新聞記者」というある意味、強い「肩書き」を持った男性だか女性だかわからないが、その誰かに、執拗に「肩書き」を問われたときの違和感が、わがことのように感じられた。自分が言われたわけでもないのに、屈辱感まで抱いた。
肩書き、かあ。
思わず呟いた。
フリーランスのわたしの名刺には、「編集・ライター」という肩書きがある。
よくニュースで「自称○○」と報道されているのを目にして苦笑していたが、いやいや、自分だってそうじゃないか。名刺に添えた「編集・ライター」だって自称でしかない。この「編集・ライター」の7文字は、わたしという人間の何を「証明」するのだろう...。
そのことを痛切に感じた出来事を思い出した。
実はわたしは、一度だけ「派遣」に登録したことがある。
母が逝ってしまうちょうど半年ほど前のことなのでよく覚えているが、2016年の夏から秋にさしかかる頃。つい3年ほど前のことだ。当時も今と同じように、フリーランスとして編集・ライターの仕事をしていた。
めっきり体力を落として、目に見えて痩せてきた母とは、病院の付添いなどで行動を共にしたり、わたしたちは距離が近い仲良し母娘ではなかったが、二人で話をする時間が急に増えた。
母はかねてより「フリーランス」という不安定で実態のよくわからない職に就いている、というか彼女にとっては「職に就いていない」娘を心配していた。
我が家(夫とわたし)は共働きなので、会計が別で、夫から特に経済的な援助を受けていない。そのことで、「あなたは食べていけているのか」と心配されてもいた。特に結婚10年ほどは、夫から生活費を渡されていなかったことが、母には理解しがたかったらしい。
「だって買い物して、ご飯をつくるのはあなたでしょ? どうして生活費をもらわないの?」
母娘といえども、生きてきた時代も考え方も違う。特に専業主婦ひと筋で、社会に出て働いたことがなく、二十歳そこそこで結婚して、夫から毎月生活費を渡されてきた母とは、状況も考え方も異なるのが当然かもしれない。
わたしたち夫婦が暮らすマンションは、元々夫が購入していたもので、マンションの購入費はもちろん共益費や光熱費の類いもわたしは払ったことがない。そのせいか、わたしには「人んちにタダで住んでいるんだから、食費くらい出すのがちょうどいいのかも」という考えがあった。
そのあたりは夫婦の考え方で母の関与することではないと思うのだが、わたしの「フリーランス」という不安定な状態が、病気の母の心身的な負担の一つになっていることについては、次第に申し訳なくなってきた。そんなことよりも自分の身体の心配をして欲しいのが、娘としての心情ではないか。
実際のところ、フリーランスの経済状態なんて、霧の摩周湖より見通しがわるく、「発注」がこないかぎり、湖を頼りなく漂う小舟の行き先すら自分ではわからない。
今は運良く小舟はゆらゆら港を往き来しているけれど、先行き不透明なことこの上ない。
多くの同業者が、首がもげるほど頷いてくれると思うが、この業界、この職種のフリーランスとは、いつどれだけの収入があり、今後どれほど仕事ができるのかわからない。未来は希望的観測だけで成りたっている。
その上、この連載の第1回を読んでくださった方はお察しのとおり、わたしはお金の計算が非常に苦手だ(ただのバカともいえるが)。貯金もできない。あるならあるだけ使い、なくなればないで我慢する。自分でも思う。経済的に無能にもほどがある。
母はそれを理解しきっていた。まだパートナーがいる限りは何とかなるかもしれないが、離婚でもして独りになったら(なぜかそのことも強く危惧していた)、この娘はたちまち住む場所も失い、人生が立ち行かないことになるだろう、と察していたのだろう。
ことあるごとに、「安定した会社に勤めたらどうなの?」と、もう40も半ばの娘に忠告するのだった。
「女がひとりで生きていくなんて、大変なことよ」
(い、今はまだひとりじゃないけど...)
ややもすれば感情を暴走させがちな元気だった頃の母の言葉なら反発していただろう。だが、病魔に蝕まれた老いた母の言葉は、いつになく痛々しくわたしにしみた。
でも、フリーランスとしてライターや編集の仕事はできれば継続したい。
不安定な希望的観測と、確固たる経済基盤を両立させるためには...。
思いついたのが、アルバイトだった(安易にもほどがある)。月の半分をアルバイトに当てて、月の半分をフリーの仕事に当てればうまくいくんじゃね?
行き当たりばったりで、ツメのあかほどの人生設計能力を持たない自分にしては、所得倍増計画のような斬新なアイデアにも思えた。
思い立ったが吉日。早速、求人サイトにアクセスした。
(つづく)
引用・参考文献
●『パート・派遣・契約社員の法律知識』藤永伸一(日本実業出版社)
●『新しい労働者派遣法の解説』中野麻美・NPO法人派遣労働ネットワーク(旬報社)
●『働く女性の労働法』第1東京弁護士会・人権擁護委員会・両性の平等部会編(ぎょうせい)
●レイバーネットTV第130号「非正規が声をあげるとき」(改訂版)
●『れいわ新選組』【動画&文字起こし全文】れいわ新選組街頭演説会19.7.6 新宿駅東南口
●『ハフポスト』【参院選】元派遣労働者のシングルマザーが立候補へ。「ボロ雑巾のように捨てられた。世の中変えたい」
●『47NEWS』当事者が闘うしかない 渡辺照子さん連載企画「憲法 マイストーリー」第2回
●『日本経済新聞』派遣社員、3年勤務なら時給3割上げ 厚労省が指針