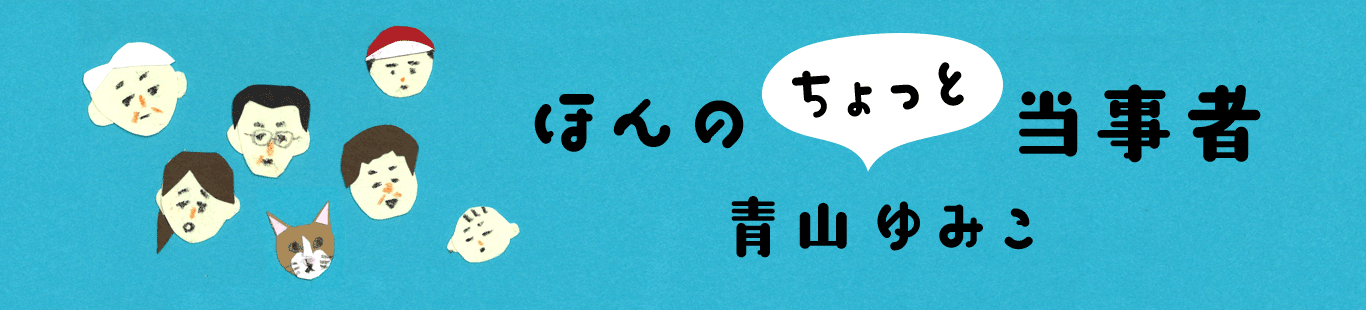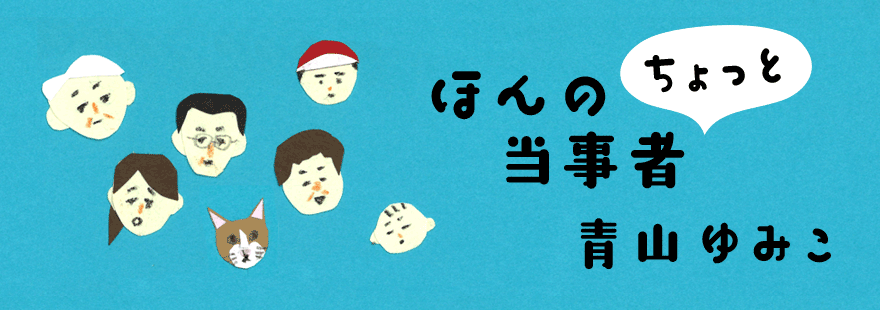第18回
父のすててこ。(2)
2019.10.12更新
(前編はこちら)
遺品の処分は、今後深刻な社会問題の一つとなるだろう。わたしが暮らす市の社会福祉協議会の人から、そう教えられたことがある。
2025年には団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)に達することで、介護や医療などの社会保障費の急増が懸念されている。同時に、増加する一人暮らしの高齢者が亡くなった後の整理や、空き家問題も深刻化するだろう。
大量のゴミが発生する遺品整理は、基本的に遺族が行わなければならない。近い親族がいない人だと、少し遠縁でもその任が回ることもあるだろう。作業を行う専門の業者も多いが、想像しているより結構な費用が掛かる。故人が賃貸住宅に住んでいた場合、早急な退去を迫られる。待ったなしなのだ。
一人暮らしから介護施設に入所して亡くなった場合は、入所前の住居が生活空間のまま残されることも多い。一軒家の場合はそのまま放置され空き家となるケースも増えていて、不審者が住みついたり、放火などの標的ともなりやすく、地域の治安悪化の一因ともなる。
遺品整理は行政が関与しないため、地域行政はこうした状況を防ぐべくいろんな意味で生前整理を推進したいが、力を入れて取り組む地域はまだまだ少ないのが現実だ。
また、生きている間は、「死」を遠ざけて、あまり考えたくないと思う人も多い。それも「遺品」という名の「ゴミ」の問題を生んでいるのかもしれない。
遺品はゴミなんだけれど、やっぱりゴミじゃない。テレビなどで「ゴミ屋敷」を目にすると、きりきりと胸が締めつけられる。結果としてゴミかもしれないけれど、一つひとつに誰かの時間と思いが含まれているのだ。
少し話が変わるが、うちには「Mさんの鍋」と呼ぶル・クルーゼの直径18センチの両手鍋がある。
Mさんは、あるホスピスの食のケアを取材した『人生最後のご馳走』という本の冒頭でも、取材を始めることになったきっかけとしてエピソードを書かせていただいた。
飲むこと食べること、人生をふくよかに生きることを教えてくださった街の大先輩だ。そしてがんと闘い抜いて、でも最後まで自分のスタイルを崩すことなく生ききって命をまっとうされた。
その大先輩と夫は、わたしよりも何倍も長年の親しい関係にあった。Mさんの忌明けの頃、夫宛に香典返しのギフトブックが届いた。二人とも何かを選ぶような気持ちになれず机の上に放っていた。
ある日、ふとぼんやりぱらぱらと捲ってみると真っ赤な両手鍋が載っていた。我が家には同じ型の白色があり、とても使いやすいことがわかっていた。真っ赤な色がぱあっと明るく、粋で華やかな雰囲気だったMさんを思い出した。
その品番を書いて葉書を出したのを忘れた頃に鍋が届いた。その日の夜、赤い鍋に油をどぼどぼと注ぎ、ちょうど身がぷっくりしてきた牡蠣をフライにして揚げた。
保温力の高い琺瑯の鍋は、冷たい具材を入れても温度が一気に下がることなく、牡蠣フライはこれまでに家で揚げものをしたなかで、いちばん美味しくカラリと揚がった。
レモンをぎゅっと絞り、二人で争うように牡蠣フライをはふはふと口に運びながら、Mさんも好きやろうな、そうやねと、冷えた白ワインを空けた。以来、赤い鍋はMさんの鍋として、揚げものの際にいつも抜群のパフォーマンスを発揮してくれている。
季節が移ると、その時々の旬の食材をフライや天ぷらにする。その度にMさんを思い出す。わたしたち夫婦の日常を、Mさんがそうやって美味しくしてくれている。
そういえば、母の愛用していたフィスラーの小鍋を夫が好んで使っていて、カレーなどを煮込む度、「お母ちゃんの鍋でやると旨いなあ」と叫ぶ。
死者はそんなふうにわたしたちの日常に存在している。
という文章を、わたしは今、父の遺品であるすててこを穿きながら書いている。昨日が四十九日の法要だった。
今夏のお盆前、肺炎を発症して入院した父は、2週間ほどであっさりと逝ってしまった。まだまるで実感がない。
父の遺したモノはあっけないほど少なかった。介護付き老人ホームに入所した際に必要最低限にしていたからだ。父が脳梗塞で倒れる前に身に着けていた衣類は、介護の際に支障が出て着られなくなったため、実家整理の際にほとんどを処分していたこともある。
そもそも父はあまりモノにこだわらない人だった。「家族」という関係には重苦しいほどに強く執着したが、年中同じような服を着て長年はき慣れた靴を磨いて愛用し、無駄にモノを買うようなこともなかった。遺された衣類の大半は、倒れて以降の、介護のしやすさを優先した機能性を重視したものばかりで、父自身が愛着を持って身に着けていたわけでもない。
父の葬儀の際、わたしたちきょうだいはつい2年半前に母の葬儀を経験したばかりだったので、変な言い方だが、どこか慣れて余裕さえあった。兄は喪主として仮通夜、通夜、葬儀の段取りをスムーズに決めていき、諸々の打ち合わせもすんなり進んだ。
仮通夜の前、きょうだい家族と揃ってゆかんに立ち会う時間まで持つことができたのだが、潔癖が過ぎるほどに清潔好きだった父が、温かいお湯をくぐってヒゲも剃り落としてもらうと、すっきりときれいな姿になったことに、家族はほっと安堵した。
さっぱりした父の顔をのぞきこんで、兄と弟とわたしは揃って息を呑んだ。
半身麻痺の後遺症は顔面にも出ていて、倒れて以降は筋力低下のため左半分がだらりと下がり人相も変わっていたが、ゆかんを終えた父の顔は、麻痺する前のように左右対称に戻っていたのだ。
そうだ、父はこんな顔をしていたよなあ。19年ぶりに目にした顔つきに、わたしたちの心には懐かしさが溢れ出した。
葬礼が終わるまでの合間を縫って、きょうだい三人で父の思い出話ばかりした。母がいなくなってから、いろんな意味で振り回された時間を回想し、あのときは大変だったよな、だったよね、となぜかすべてが笑い話になる。そういうふうに感じさせる愛嬌が父にはあったよな。なんやろな。不思議やな。そう頷きあった。
元気だった頃の顔に戻った父を前に、それぞれが持つまだ若かった頃の父の思い出を話すと、お互いに知らない姿ばかりが浮かび上がる。父よ、あなたはいろんな意味で面白い人でしたね。
よく働き、よく遊んだ。自己中心的ではあるけれど、我慢強い、スジのとおった考え方をする人でもあった。
いや、どうだろう。人というのは多面的で、その人がどうであるかをひと言では言い表せない。まあ、別になんでもええんとちゃうか。父が飄々と呟く声が聞こえてくるような気がする。
思えば、父が倒れて、母が逝くまでの16年は、母を通しての父しか見ていなかった。この2年半ほど、父と向き合わざるを得なくなってから、父とわたしの関係はずいぶんと変わった。
いがみ合っていたと思っていた父は、相変わらずマイペースで、なんだかわたしが独り相撲で苦戦してきたようにも思えた。将棋が好きだったことを思い出し、夫に習って、父と将棋を指すようになってからは、その合間に時折、母の思い出話をした。わたしが母にどれだけ怒られたかとおどけて悪口を言うと、父は「ママはあまり怒らなかったけど、怒ると怖かった」とニヤリと笑みを浮かべることもあった。
認知症のせいなのか、日に何十回と掛かってくる電話に辟易としたが、今はもう鳴らない電話に時折、胸が詰まる。
夫に振り回されっぱなしの人生だった母が父より先に逝ったとき、彼女が不憫で申し訳なくて、順番が逆ならどんなに良かったかとさえ、絶望した。鬼のような心で。
でももし逆だったら、わたしはこんなふうに父の不在を寂しく想えなかったかもしれない。
憎しみを抱えたままで父を亡くさずに、わたしたちの関係が変わることができたのはこの2年半という時間があったからだ。複雑な心境もあるが、もしかするとこの時間は母がくれた贈りものだったのかもしれないとも思う。
ごく限られた父の遺品から、まだ新しい、綿のつるりとした生地で、外にでも着て行けそうなデザインのすててこを見つけたとき、どこか小紋のような柄が気に入ってなんとなく除けておいた。眺めているうちに、自分で穿いてみたくなった。自分のすててこを娘が穿くのを、父は間違いなく嫌がるだろうと想像したら、なんだか可笑しくて、よけいに穿いてやりたくなった。
わたしたち父娘は、いつもそうやってお互いに妙な意地と我を張り合ってきたのだ。
わたしが笑うのを見て、たぶんあの人はもっと嫌そうに、同時に小さくニヤリと笑みを浮かべるだろう。父の遺したモノは、不思議とわたしを明るい気持ちにさせる。
あんなお父ちゃんなのに、美化されすぎてやしないかと、自分に突っ込む。また父のニヤリが浮かぶ。母が逝ったあと、笑わなくなった父。その父が笑ってくれるのがいちばん嬉しかった。パパ、ありがとう。