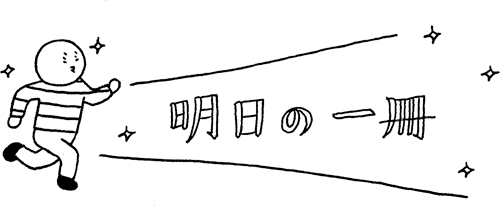2019年1月
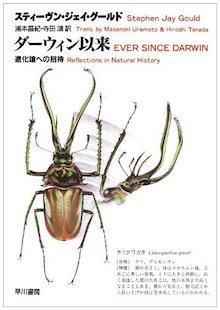 早川書房
早川書房-
『ダーウィン以来―進化論への招待 』
生物が不必要なまでに多産である理由、無駄死にさえ見える生命の浪費、生物の多様性を生み出す意外に単純なメカニズム。この本がそれらを分かりやすく教えてくれた。目の前のものの見え方が変わり、世界の成り立ちに、少しだけ自分なりの道筋を見つけられた。S.J.グールドは最高の科学エッセイストである。引き続き『ワンダフルライフ』『個体発生と系統発生』と読み進めば、もはやダーウィンと進化から引き返せないだろう。
2019.01.30
 新潮選書
新潮選書-
『卵が私になるまで―発生の物語 』
女性科学者による発生学書。作者が5歳のころクモを見つける。その膨らんだお腹の中が知りたくて、少女は石をぶつけて、その様子を絵に描いた。それは作者にとって記念すべき日になった。
「とにかく生まれてはじめて実験をして、その結果を記録したのですから」
つぶれたクモの絵が素晴らしい。成長した少女は優秀な科学者になり、愛すべきこの本を書いた。自筆のイラストが秀逸。ヘッケルの発生原則を写した胎児が笑っている。2019.01.28
 ダイヤモンド社
ダイヤモンド社 -
『顧客が熱狂するネット靴店 ザッポス伝説 』
「顧客満足度第一主義」を真剣に追求して大成功しているアメリカの通販会社、ザッポス。顧客の幸せとはなにか、幸せを届けるにはどうすればよいか、を突き詰めた結果「コールセンターで何時間も顧客と話をする」「お腹が空いた顧客のためにピザを注文する」など数々の伝説が生まれ、顧客を感動させている。一方で、活動を続けるための利益構造や人財育成の仕組みもきっちり作り込む。すごい。こういう仕事をしたい。
2019.01.25
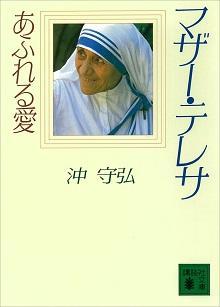 講談社文庫
講談社文庫-
『マザーテレサ あふれる愛 』
『奇跡の本屋をつくりたい』で久住さんが「一番大切にしている本」と言っていた本。マザーの情熱と信念、そしてアイディア(ローマ法王からもらった車を宝くじの賞品にして収益を慈善事業に使うなど)に驚かされる。そうか、久住さんて札幌のマザーテレサだったんですね。
2019.01.23
 亜紀書房
亜紀書房-
『水島シェフのロジカルクッキング 』
「99%成功する」料理本。なぜなら、「塩は肉の重量の0.8%」「肉の重量が火入れ前の80%になったら焼き上がり」など厳密にレシピが書いてあるので、その通りに調理すると自分史上最高の鶏肉のソテーが出来たりする。最高。だが、料理の醍醐味は、自分の感覚で調理したら美味しいものが出来た!という感動なのではないか。偶然の美味との出会い無しに料理を愛し続けられるのか。自由意志とは・・・。などと葛藤することで料理がより楽しくなる名著。
(ミシマ社 岡田森)
2019.01.21
 東京糸井重里事務所
東京糸井重里事務所-
『ボールのようなことば。 』
夏になったら麦酒が飲みたいし、
冬に飲む熱燗は最高。
お風呂上がりには牛乳で、
デートの時には珈琲が合う。
でも、どの季節でもどんな時でも、
水という飲み物だけは、すっと身体に入ってくる。
糸井重里さんのことばは、
いい意味で、水のよう。
深い森の、新鮮な湧き水みたい。
明日を生きることが、すごく楽しみなときにも、
明日を生きることが、ちょっと辛いときにも、
優しく静かで水のような、
心に沁み入ることばを求めて、
私はこの本を開きます。2019.01.17
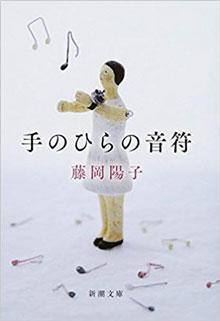 新潮社
新潮社-
『手のひらの音符 』
みんな手のひらに音符を持っている。
音符を紡ぎ音楽を奏でることで誰かに私の存在を知らせている。
だけど音楽が奏でられない時がある。
大切な人との別れ、理解が得られぬ歯がゆさ。不条理に見舞われたとき私たちは手のひらの音符を握り絞めてしまう。うまく音が出せなくても悲しさをとじこめて、孤独に耐えるのだ。だけど十分に温めたら、またそっと手を開いてみよう。きっと誰かがあなたの音を受け止めてくれるから。そしてあなたも誰かが紡ぐ音楽に耳を傾けて。
世界が優しい音楽で溢れますように。
苦しみの中にも希望が見える素晴らしい作品。2019.01.14
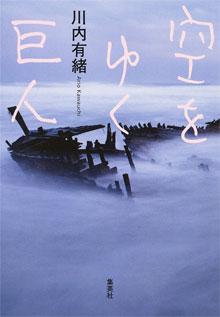 集英社
集英社-
『空をゆく巨人 』
2018年第16回開高健ノンフィクション賞受賞! 現代美術のスーパースター蔡國強といわきの経営者志賀忠重。2人の出会い、交流を中心に、文化大革命から3.11以降のいわきが描かれた作品。同じ時代を生きていると思うと鳥肌が立つが、読み終えた後は、では自分は? と内側にベクトルが向く。夢の見方を忘れた人必読!!
(ミシマ社サポーター 宇都宮咲子さん)
2019.01.11
-thumb-220xauto-1667.jpg) 角川書店
角川書店-
『光圀伝 』
"水戸黄門"の生涯を描く熱い大河小説。光圀が義を巡って迷い、決断し、歩みを進めるさまは、何度読んでも胸が熱くなる。初読以来、8回ほど読み返しているが、毎回胸が熱くなる。自分の生き方に自信がなくなったとき、人生の岐路に立ったとき、読み返すと勇気がみなぎってくる一冊。
2019.01.09
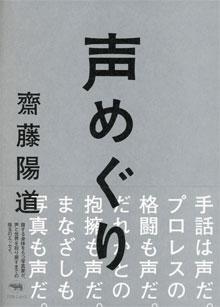 晶文社
晶文社-
『声めぐり 』
写真家である著者が、多様な「声」をめぐりながら、これまでの自分と他者のことを綴ったエッセイです。ずっと気にかけながらもなかなかこの本との時間をとれず、やっと年末年始のお休みに読みました。読み終えたとき、ひとつひとつの言葉の穏やかさに、心がじんわりほぐれていく感覚が残りました。装丁も美しく、いつまでも大切に読んでいたい一冊です。
2019.01.08
 blueprint
blueprint-
『作詞のことば 作詞家どうし、話してみたら 』
作詞家の岩里祐穂さんが、5名の作詞家と、互いが書いた歌詞について語り合うトークセッションの模様をまとめた対談集。音と言葉を合わせる技術、言葉選び、歌詞のストーリー性など、作詞家によって歌詞の作り方はそれぞれ。この本に載っている曲を知っていても知らなくても、その面白さにページをめくる手が止まらなかった。作詞家の頭の中を覗ける貴重な一冊。
2019.01.07
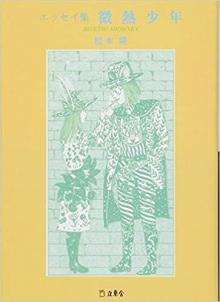 立東舎
立東舎-
『エッセイ集 微熱少年 』
平川克美さんの『21世紀の楕円幻想論』でもふれられている「木綿のハンカチーフ」はじめ、松田聖子さんの楽曲など数々のヒット曲の作詞を手掛ける松本隆さん。本書は、1975年に刊行されたエッセイ集の文庫版です。歌詞を書く上で「その時代にどこまでくいこんで、人の心の中を流れることができるか」という言葉がでてくるのですが、これは出版でも同じことだよなあ、と感じ入りました。近年拠点を関西に移し、また新しい創作をはじめられているとのこと。お会いしたいです。
(ミシマ社 田渕洋二郎)
2019.01.06
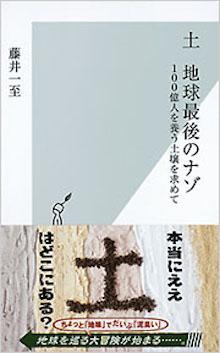 光文社新書
光文社新書-
『土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて 』
デイヴィッド・モンゴメリーさんの土三部作(『土の文明史』『土と内臓』『土・牛・微生物』、いずれも築地書館さんより刊行)をきっかけに土への興味が湧いて尽きません。そんななかで出会った本書。藤井先生の文章の面白いこと! プププがとまらないです! 土研究のため地球を巡るご自身の道中をユーモラスに描きつつ、奥深い土の世界へといざなってくれる最高の"土"エンタテインメントです。2019.01.05
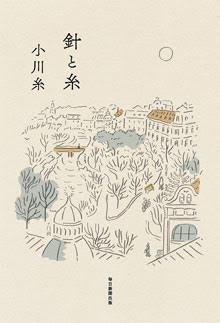 毎日新聞出版
毎日新聞出版-
『針と糸 』
ドイツと日本を行き来する暮らし。ソーセージ屋さんのにおい、友達との遠足、愛犬との森歩き。平穏な日々がゆったりと綴られる一方で、母親との確執や、町で見かけたナチス統治下の傷跡など、ドキッとするような話も出てきます。「特筆すべきことなど何もないよう」な日常にも、大切なことはたくさん隠れていて、みんな日々、いろんな思いを抱えて、生きている。わたしにも、みんなにも、いい日が訪れますように。読みおわって、そんなことを思いました。
2019.01.04
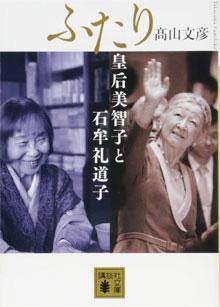 講談社文庫
講談社文庫-
『ふたり 皇后美智子と石牟礼道子 』
昨日、本書を読み終えて深い印象を受けたのですが、まだお腹と胸の間のあたりに、その感銘が渦巻いていて、うまく言葉にすることができません。ひとりの人でありながら、「近代」「国家」という、とてつもなく大きなものと正面から向き合わざるを得なかった方々の格闘の軌跡が、丁寧に描かれています。平成が終わる節目の今年、自分なりに、その足元を見つめてゆきたいと思います。
2019.01.03
 岩波文庫
岩波文庫-
『職業としての政治 』
ふと思い立ち、24年ぶりくらいに再読した。同時代を生きる政治家のことと、いま私が日々向き合っている仕事のことを思いながら読んだ。最後のほうでヴェーバーが言っていることに、とても勇気が湧いた。"情熱と判断力の二つを駆使しながら堅い板に力をこめてじわっじわっと穴をくり貫いていく作業"を、今一度、自分に課してやっていきたい。その積み重ねをもって、"現実の世の中が――自分の立場からみて――どんなに愚かであり卑俗であっても、断じて挫けない人間。どんな事態に直面しても「それにもかかわらず!」と言い切る自信のある人間。"になれたら、きっと素晴らしいと思う。本書を年頭に読むことができ、本当によかった。
2019.01.02
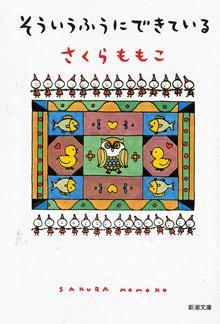 新潮文庫
新潮文庫-
『そういうふうにできている 』
昨年他界されたさくらさん。もちろん「ちびまる子ちゃん」は知ってましたが、生前、エッセイは読んでなかった・・。不覚というかうっかりというか。遅まきながら読み出すと、どれもとても面白い! 妊娠出産をテーマにした本作は、男性が読んでも「わかる」ように書かれています。つわり、マタニティブルー、帝王切開、こうした未知の体験がさくらさんの言葉にかかると、そうなのか、とえらく腑に落ちてくる。出産の瞬間、宇宙とのつながりを感じるところは圧巻の筆致。初読みにもおすすめです。
(ミシマ社 三島邦弘)
2019.01.01