第15回
S区の奇妙な体験。
2025.04.15更新
ジャルジャル。シソンヌ。男性ブランコ。空気階段。
稀代のコント師4組である。お笑い好きなら1組ごとに心ときめくし、この4組がコント番組をやるとなれば満潮時の潮騒のように心ざわつく。そんな番組のストーリーパートを依頼され、わが劇作丸が漕ぎ出さない手はなかった。御しがたい波に揉まれることは想像に難くないにしても、だ。
前回の「青春文化祭」に続いて、今回はお笑い界への出帆である(時系列としてはこれの方が前だけど)。せわしないけど望ましい。
自分は劇作家であるし「劇団」をやっている。その上で、なるべく横断的に、ほうぼうの海域に節操なく顔を出したいと思っている。演劇海では見られない景色がたくさんあるし、得られる宝もある。そして海域によって潮目やルールが違う。
ことさら海まわりに喩えすぎてはいるけれど、この越境感、横断感はたいへん僕にとって重要だ。好奇心、ということもあるし、「劇の力」は演劇の中に留めておくべきではなく、色んなところで役に立てたい、と考えている。
こと「お笑い」に対しては、とっても抜き差しならない領海ながら、礼節とコード感をわきまえたうえでなら(ここ大事)、劇や物語がもっと働ける、とかねてより思っているのであった。僕もコメディ、つまり笑いをやってはいるが、今回そこは辣腕の4組がいるので、自分は違う働きかたをすることにした。
番組のプラットフォームはDMM TV。ジャンルをまたいだコンテンツ開発を盛んにやっているところで、以前にもお世話になった。
そのときは、劇団ひとりさんのアドリブ芝居にあわせて、リアルタイムで刑事ドラマを生成していく(=脚本を現場で書く)という、野心しかない企画だった。「横道ドラゴン」というタイトル通り、アドリブは横道にそれ続け、なぜか山梨県で最終話を迎えた。
今回は、冒頭に書いた4組でコント番組を作る。
そして、単なるコントの羅列にはしたくなく、なにか全体として世界観を持った、ひとつの大きなストーリーのようにしたい。全6話で構成し、最終話まで観つづけたくなるような「ヒキ」も作りたい。それはコント単体の面白さとは別の、謎だったりサスペンスであってほしい。
そういったことを踏まえて、番組全体をつらぬく世界設定や、縦に走るドラマパートを担当してください、というのがオファー内容。
大変そうだけど面白そう。各芸人さんとはそれぞれ接点もあるし、これを他の人が手掛けていたら悔しいだろう、なら自分がやりたい。そしてそれは足掛け半年に及ぶ、想像以上というか想像通りというか、コントと物語と謎のタペストリーを、編んではほぐすような大仕事となった。
大切にすべきは「4組のコント番組」であること。
劇作家として肩を回したくなるが、ストーリーがプライマリであってはならない。そこはあくまでもコントが主体。見え方としては「コント番組」になっていること。
そしてコントは皆さん新作を作る。そう、僕がコントを書くのではなく、各芸人さんがコントは書く。ならばまず、その「土台」を作らなくてはならない。無二のコントを作る4組の、コントの培養器となるような、想像を掻き立てる、それでいて実のところ何も限定しない「土台」。
いろいろ考えて「S区」というのを提案した。東京のどこかにある24番目の「区」。「区」は掻き立てる。文字面がいいですよね。「凶」を横にした形でちょうどいい。都市伝説めいた謎やサスペンスも孕むし。
好感触をえて、「区コントサスペンス番組」という方向性に決まった。聞いたことない方向だけど、決まった。いつだって未踏を行くのがいい。
まずは、「S区」という謎の区を舞台にした、コントの種を各芸人さんに考えてもらう。そこから縦軸へとまとまっていきそうなネタをチョイスして、また芸人さんたちにフィードバック。それを繰り返して、芸人さんたちはコントを、僕は「S区」を巡る謎と、それに迫るサスペンスドラマを編んでゆく。
すらすらと書いているけど、全然これは混迷を極める作業で、どこから手を付けていいのか、何をもって種えらびの決め手とすればいいのか、お互いに手探りだった。芸人の皆さんは「何でも大丈夫ですよ」「合わせますよ」って態度で一貫していて。
僕がすべてをトップダウン的に決めていければ楽だっただろうし、芸人さんたちもそう思っていたと思う。でもそういうものでもないのだった。先ほども書いた通り、あくまでこれは「4組のコント番組」として立ち上がってほしかったし、それは再三口に出して確認せねばならないほど、ついうっかり世界観やストーリーで牽引したくなるのだった。
多分そのやり方でもコンテンツはできる。けどそれだと全体として「ドラマ」に近いものになる。そうではなくてこれは「4組が主体の」「コント番組」。物語や謎はそれらにブーストをかけるために存在する。今でも何度も言い聞かせるように書いてしまう。もうほんとこれの繰り返し。
それほどまでに4組の芸人さんたちはそれぞれ、慎重で、抑制的で、手の内をあかさず、互いの世界観にも気を遣われていて(リスペクトし合ってはいるけど、おそらくお互いに親しくはない)、そしてもちろん僕が書くものに対してもで。
そもそもコント芸人さんは、漫才師に比べると外向的というよりは内向的だと思うし、この4組はとくにそんな印象で、もちろん不愛想とかそんなことではなく、むしろめちゃくちゃ気を遣ってくださる。し、できる限り協力的であろうとしてくださる。それでいて、秘めたるものは最後に出したいし、一番大事なものはコンビの中で持っておきたい。
そういうものだと思う。それがコントの中でのみ爆発するから素敵なんだし、そこを大事にしているから、普段はほとんど単独ライブやコンビ活動にのみ命を懸けているような4組なんだ。
そんな4組が、一堂に会するのはまたとないことで、だから僕は心がざわついたし、なるべく住み心地のいい(あるいは住みがいのある)S区に住んでもらって、その奇妙で魅力的な生態ぶりをいかんなく発揮してもらう。なんならクロスオーバーもしてもらう。
これはそういう、厚かましくもスペシャルな企画なのだった。ある種、禁足地に踏み入れるようなところもあった。そんな風にして、4組の芸人さんそれぞれとやりとりを重ねながら、コントを書いてもらい、それらが織りなす謎を編んでいった。
ジャルジャルさんは、徹頭徹尾、コンビ間のセッションのみでコントを生み出す二人。ネタ帳さえ二人で一冊。そして台本はなく、ネタ帳には(おそらく)タイトルだけが書いてあって、あとは二人のアドリブ的(に見えるけどどこまでどういうルールで決まっているのか分からない)なやりとりで、コントができていく。つまり非常に介入しづらいコンビ。単独ライブのスタッフにさえ、どうやって情報共有しているのか分からない。と思っていたけど、聞くと、コントを楽屋などでテスト撮影して、その映像をそのまま渡しているのだという。
今回もまさにそのやりかたで、どこか雑な場所でテスト撮影されたコント映像(後ろに普通に社員さんとかが通ったりする)と、それをスタッフさんが文字起こししたものが、がさっと送られてきた。「S区」の設定を汲んでくださっているんだかいないんだか、土地の匂いがほとんどしない、二人のやり取り「だけ」による結晶みたいなコント空間。これがジャルジャルのコントの凄いところ。いつも衣装も舞台も、極力削ぎ落した中に、二人だけがいる。
この感じを大事にしつつも、縦軸に繋げたい部分には、大胆に加筆させてもらった。人づてに聞いた話だと、お二人は台本を読んで笑ってくださったらしい。嘘かもしれない。でも実は以前にも、ジャルジャルさんのコントにヨーロッパ企画が混ぜてもらったことがあり、そのときもこうして、ジャルジャルさんの結晶みたいなコントに、装飾を描き足すようにして僕らが関わる余地を作らせてもらったんです。
シソンヌさんは、じろうさんが4組を代表してコント監修も担当され、S区の全体設定についても相談させてもらった。けどその姿勢はたいへんおおらかで、これは違うこれはいい、などと神経質に言うようなことはひとつもなく、「いい感じじゃないですかね」「みんなやりやすいと思いますよ」「全然いけるんじゃないですか」などと、僕の設定をひたすら生暖かく肯定してくださるのみ。
どうやらご自身の単独ライブも迫っていて、そっちで気がそぞろらしい。そりゃ自分がその立場だったらそうなる。出してくださったコントの種も、詳しく聞こうとすると「これなんだっけな」「こんなん書いたっけな」みたいないい加減な調子。
だけどその種には、S区をかたちづくる芳醇な物語の予感が、たしかに宿っていた。だからじろうさんとそれ以上ごちゃごちゃ話すのはやめにして、じろうさんがくださった種たちと対話するようにしながら、S区の設定を考えていった。そこには天気と話せるおばさんや、960円を1000円札に変えてくれるおじさんが住んでいる。それぞれのキャラの過去を掘ってゆくと、S区の奇特で悲しい歴史が見えてきた。
単独ライブがひと段落ついたじろうさんは、追い上げるように自身のパートのコントを書き上げられ、それらは奇矯さと湿度を伴った、まさにS区に根差した比肩なきコントになっていました。相方の長谷川さんは打ち合わせには一切現れず、しかし現場ではリーダーとして4組をぶん回していた。これがシソンヌのバランスか、と合点がいった思いがした。
男性ブランコさんは、舞台「鴨川ホルモー、ワンスモア」でもご一緒していて、僕とこの時期もっとも関わりが深かったお二人。
ネタを書く平井さんとは、作家談義もするような仲で、単体のコントネタで面白く見せるというよりは、縦軸のストーリーに有機的に絡んだ、連作としての面白さを見せていきたい、との意向。それはそれでもちろん嬉しい。なので半ばドラマパートにも関わってもらうような勢いで、綿密にやり取りしながらコント案を選んでいきました。
種もたくさんくださった。ツチノコ探検隊、虫男、シャケ男、ヒル男。生物系のコントがお好きらしい。いつも何らかの生物をあしらった服を着てらっしゃいますしね。
造形物を伴うコントは、美術さんや衣装さんとの連携も大事になってくるけど、平井さんには明確なイメージがあり、色付きでイメージスケッチを描いてくださった。おかげでS区のビジュアルはずいぶん気持ち悪く充実し、バイオ方面のグロテスクな土地の歴史も付与された。浦井さんが演じた「虫男」は、ねっとりした嫌な光沢感とともに、この番組のキービジュアルのようにもなりました。
あと「個室探偵」というネタがあり。それは探偵のキャラクターの特異性(個室がないと考えられない)もありつつ、推理要素もともなうコントで。ここはまさに縦軸の謎解きにも使わせてもらおうと、番組の終盤における探偵役、のような位置づけにしました。処理してもらいたい推理展開を混ぜ込みつつ、エレガントにコントへと落としてくださった平井さんは、このコントサスペンス番組の立役者でした。
空気階段さん。涼しい顔でクレバーなネタを書く雰囲気の水川かたまりさんと、だらしないクズキャラでおなじみの鈴木もぐらさん。と思ってたけどそれはイメージで、かたまりさんはパトスにまみれたイカれたネタも書くし、そしてもぐらさんもネタを書くのだった。
空気階段さんから送られてきた種をもとに打ち合わせをしたとき、「このコントは...」「これは...」と、二人がかわるがわる説明するので、どういうことだろうと思ったら、二人でそれぞれネタ案を出し合う、というシステムらしい。
かつ、それぞれの案はそれぞれが脚本も書く、ということになっているらしく、もぐらさんも2本、コントを書くことになった。これが難産だったようで、制作チームのグループラインでは「もぐらさんからのネタがまだ届きません」「今半分くらいだそうです」「カツラと小道具が新たに発生したようです」などと、もぐらさんの状況をリアルタイムで伝えるメッセージが飛び交った。もぐらさんはやはりだらしなかったし、かたまりさんは涼しい顔をしているんだろうな、と思った。
現場でももぐらさんはだらしなく、僕が見学しに行った日は、ドラマパートと合流するコントの撮影で、監督や、剛力彩芽さんと初めましてだったにもかかわらず、撮影が始まってすぐ、カットとカットの間に居眠りをしていた。芸人さん皆から「そりゃないだろう」とツッコまれていた。脇役だったから寝たとかじゃなく、そのコントではもぐらさんが一番しゃべる主役だったのにだ。そして演技は素晴らしくうまく、哀愁があった。芸人だぜと思った。
長く書きすぎていることは知っている。ほんとに長きにわたるプロジェクトだったのだ。だから未見の方にはぜひ見ていただきたい。1話ならYoutubeで見れますから。
僕のした作業の本領はやっとここから、なんだけど、それを書くとさらに倍ほど長くなってしまうし、書きたかったハイライトとしては芸人さんそれぞれと接してのプロトコルの違いだったので、ここからはかいつまみます。
4組から集まった珠玉のコントを繋ぐようにして、縦軸のドラマパートを書いた。先ほどちらっと登場した剛力彩芽さんが主演の、S区に迷い込んだ女・フウカの物語。コントって基本的に時間が進まないので、ドラマパートはもうぐいぐい進めるようにした。剛力さんの抜けるような演技とアクションは、S区を駆け抜け、物語に大きな推進力と、最後には温かみをくれた。
あと、各組のコントとは別に、どうしても芸人さん8人でのユニットコメディが見たかったので、別パートとして「密室に閉じ込められた8人の、爆弾をめぐるサバイバル脱出劇」を書いた。これは僕が高校生のとき、文化祭で書いた劇をアレンジしたもの。28年ごしに再び日の目を見たし、それはこの物語とも合致している気がして、埋もれていた歴史を紐解きました。
タイトルは「S区の奇妙な人々」。
ここに書いたようなコントと物語が、複雑に折り重なり、知られざる東京24番目の区として大いなる異貌をなしています。僕がおずおずと漕ぎ出したような手つき足つきで、おもしろ禁足地へおっかなびっくりどうぞ。
編集部からのお知らせ
前代未聞のコントサスペンス「S区の奇妙な人々」
上田誠さんが脚本を務める「S区の奇妙な人々」が、DMM TVにて配信中です!
第1話をYouTubeで無料でご覧いただけます。
<概要>
ジャルジャル・シソンヌ・男性ブランコ・空気階段が豪華コラボ!
今もっともチケットが取れない人気コント師たちが贈る新作コントは必見。
8人が演じるのは「S区に住む奇妙な人々」…果たしてその正体は!?
<出演>ジャルジャル / シソンヌ / 男性ブランコ / 空気階段 ほか
2025年1月15日(水)配信開始
全体構成・脚本:上田誠
上田誠さんの新作「リプリー、あいにくの宇宙ね」
上田誠さんが脚本・演出を務める舞台「リプリー、あいにくの宇宙ね」が、5月~6月に東京、高知、大阪で上演されます!
「リプリー、あいにくの宇宙ね」
<イントロダクション>
スクランブル発生! 今度は何が起きている? 宇宙はつねに変化に満ちているし、いつだって射撃訓練所の中だ。たえず11人目がいるようなものだし、スタービーストは暗黒の森林で息をひそめている。それにしてもひどすぎないか、と二等航海士・ユーリは思う。量。このトラブルの量はなんだ。マザーCOMはなぜ答えない。船長はなぜ判断しない。ロボ、三原則いまはいいから。アーム、そんなポッド拾わなくていい。漂流詩人乗ってこなくていい! これどこからのスライム? 石板、いまは進化させていらない! ユーリは白目で歌う。リプリー、あいにくの宇宙ね。ってハモんのやめて。
<公演スケジュール>
●東京 本多劇場
2025年5月4日(日・祝)〜5月25日(日)
●高知 高知県立県民文化ホール オレンジホール
2025年6月3日(火)
●大阪 森ノ宮ピロティホール
2025年6月6日(金)〜6月8日(日)
<チケット発売>
◎一般発売
2025年3月20日(木・祝)〜
『ちゃぶ台13』に上田誠さんのエッセイ掲載!
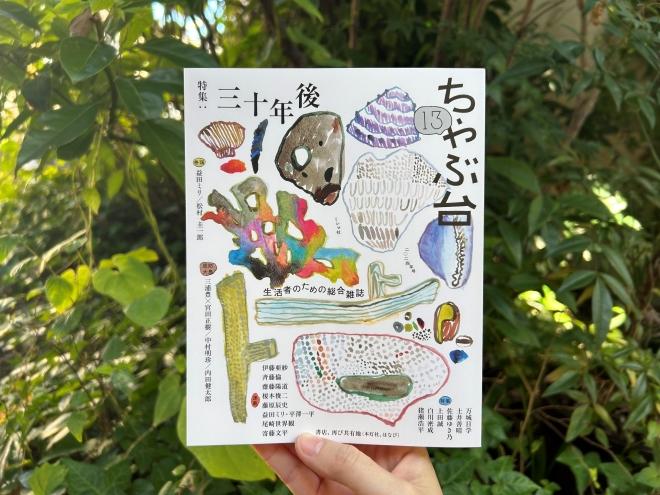
2024年10月刊の雑誌『ちゃぶ台13 特集:三十年後』に、上田誠さんがエッセイ「劇団と劇の残しかた ~時をかけるか、劇団」を寄稿されています。ぜひ、本連載とあわせてお楽しみください。
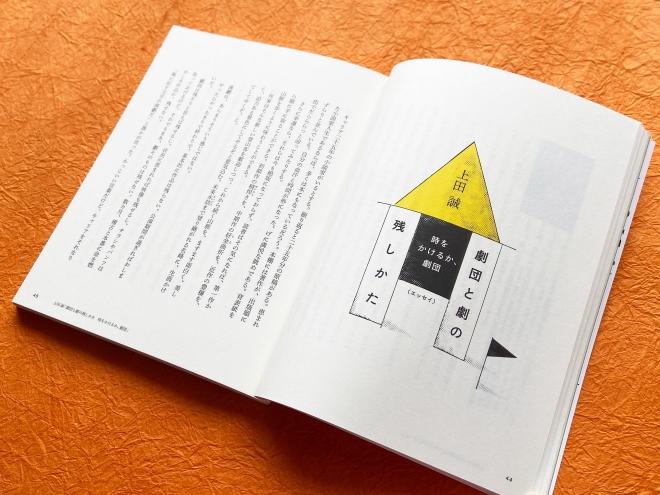
上田誠さん、ミシマ社通信に寄稿!
万城目学さん著『新版 ザ・万字固め』(2025年1月17日発刊)にはさみこまれている「ミシマ社通信」に、上田誠さんが熱い原稿を寄せてくださいました。タイトルは「万城目文学の恐ろしさ――脚本化を許さぬ文章の完成度について」。こちらから一部お読みいただけます!
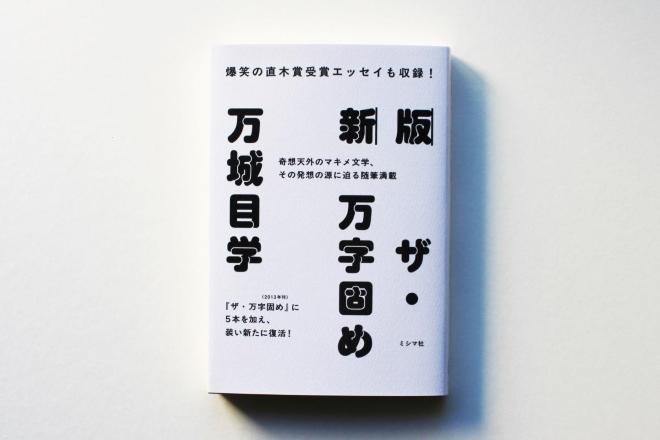


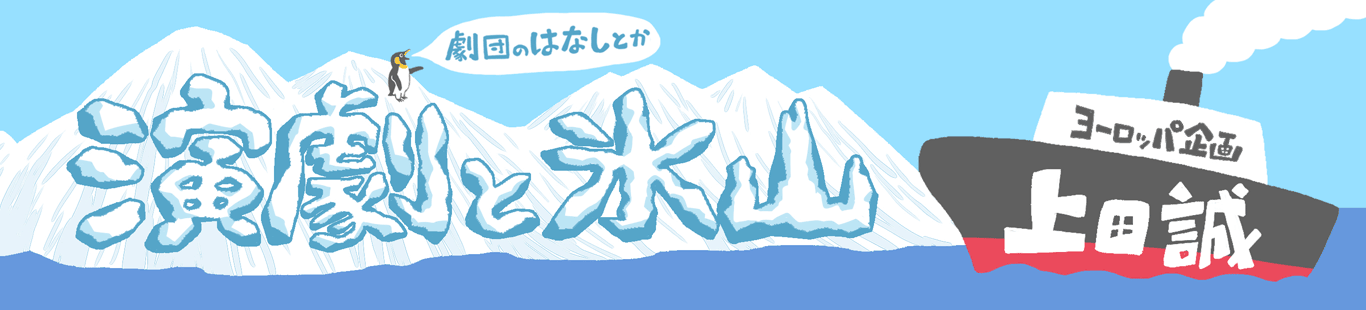
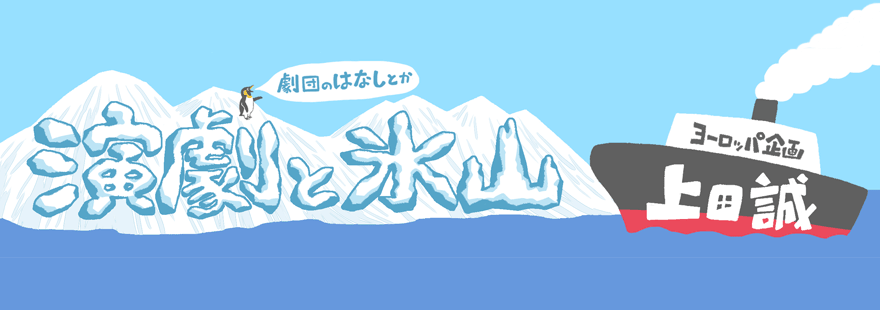

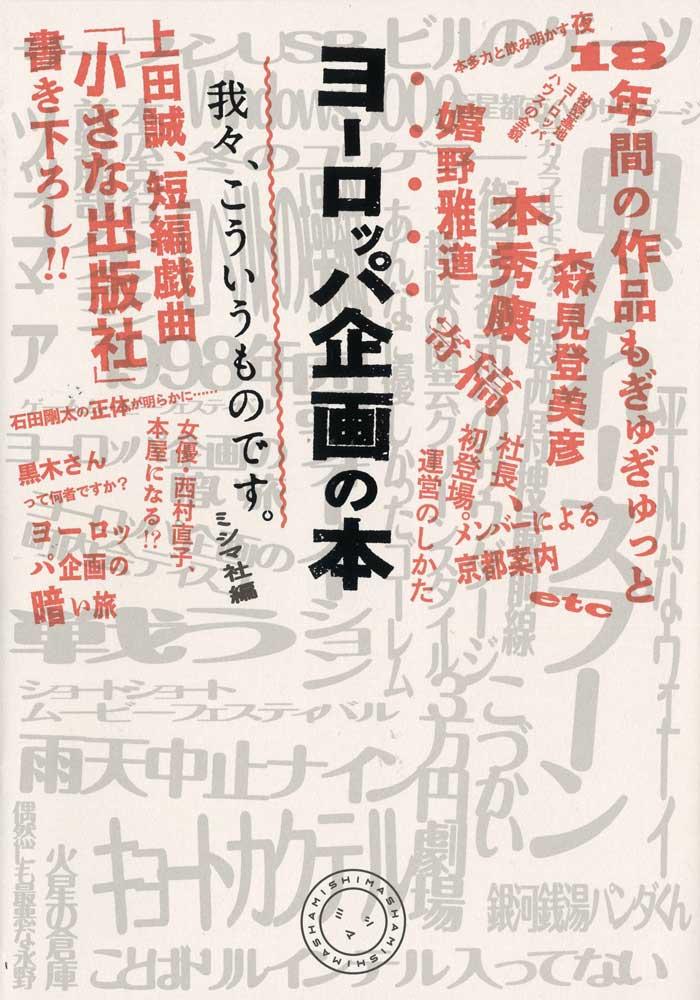

-thumb-800xauto-15055.png)



