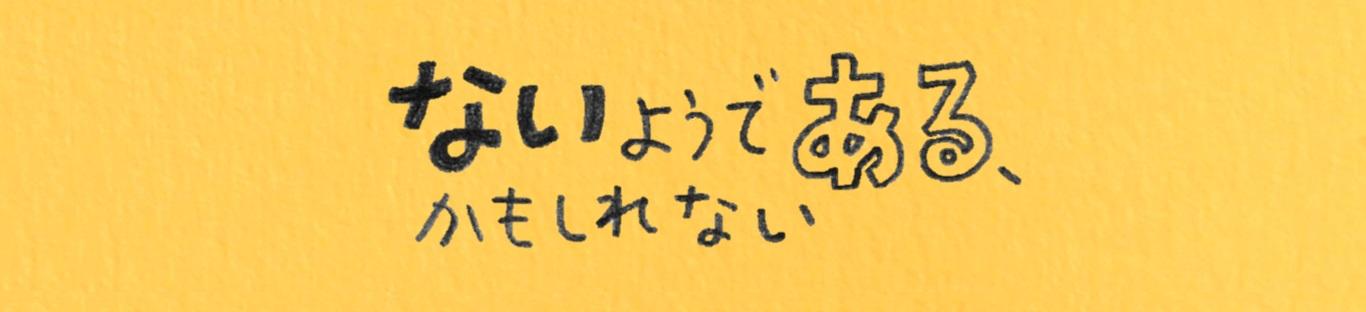星野概念・いとうせいこうの「まとまりません!!」 『ど忘れ書道』×『ないようである、かもしれない』W刊行記念イベント(前編)
2021.05.11更新
先日、青山ブックセンターさん主催で、星野概念さん『ないようである、かもしれない』と、いとうせいこうさん『ど忘れ書道』(ともにミシマ社)のW刊行イベントを開催しました!
『ラブという薬』『自由というサプリ』(ともにリトル・モア)という共著も出されているおふたりのトークは息もピッタリ。お二人の本の話を中心に、一見すると不要にも思える「意味がわからない」ものの良さや、小さなコミュニティの可能性について語っていただきました。その様子の一部を、二回に分けてお届けします!
(構成・岡田森、構成補助・染谷はるひ)

続けることで、バカバカしさに重みが出る
いとう 今回は『ないようである、かもしれない』と『ど忘れ書道』という二つの名著について話しましょうということで。
星野 ふふふ(笑)。はい。
いとう 『ど忘れ書道』はどんな本かというと、僕がど忘れしてしまった言葉を思い出すたびに、筆ペンを使って真剣な気持ちでその言葉を書く「ど忘れ書道」をしてたんだよね。なんで俺はこんなにど忘れしてしまうのかというエッセイを9年間ほぼ隠れるようにしてやってたわけ。

(左:いとうせいこうさん / 右:星野概念さん)
星野 この書道じたいは誰かに頼まれるでもなくやってたんですよね?
いとう そうそうそう(笑)。そこがすごく重要。あまりにも物を忘れるんで不安になって脳も診てもらったりとかして、ど忘れについては真剣に恐怖心があるんですよ。それと同時に、なんでこんなこと忘れちゃうんだろうっていう「忘れたおもしろさ」も忘れちゃう。なんでサッカー選手のバティストゥータを思い出そうとしてたのか。そこからもうおかしいわけじゃない。
星野 たしかに(笑)。
いとう このおもしろさは残しておくべきなんだけど、それをただメモに残すのは企画としておもしろくない。それで、僕はすごく字が下手だから、忘れてしまうという欠点と字が下手という欠点をわざと生かしてクリエイティブにしてみたらどうだと思った。そしたら自分でちょっと笑ったわけですよ。これはおかしいと。
そのときルーカス B.B.がやってる「PAPERSKY」での連載を頼まれていて、「こういうのを思いついたんだけどどう思う?」って言ったら「イイね」って言うから連載をはじめた。続けたらいつかはまとまるんじゃないかと思ってて、9年ぐらいたってようやく分量として手ごたえがある状態になって、そのときの喜びったらないね。
星野 それは分量としてってことなんですね。
いとう そうそう。内容としては箸にも棒にもかからないおじいさんの戯言だからさ(笑)。
星野 はっはっは(笑)。
いとう それが本になったときに勘づいたやつがバカリズムだったね。
星野 そうなんですね。
いとう 他にも俺は本を出してるのに「あれはちょっとすごいですね」っていう反応があった。俺が重要だと思ってるのは、9年間じーっとやるってことなんだよ。「思いつきを1年やりました」ならどんな芸人でもやるわけじゃん。9年間やって出したときのバカらしさはその9倍ある。
星野 人知れず続けるってことですね。
いとう それって簡単なことじゃないから、バカバカしさに重みが出るんですよね。笑いにとって他では真似できないものって、単に才能とか切れ味以外に、時間があるんだよね。これはどんなに才能がなくてもやろうと思えばできるんだよ。30年間毎朝同じネタをやってましたとか。その狂気って愛らしいもんね。
名指されてない98パーセント
星野 僕は『ど忘れ書道』にふれて、これはアール・ブリュットみたいだと思いました。
いとう なるほど。
星野 美術教育を受けてない人たちがつくった魅力的な作品がアール・ブリュットと言われるものですよね。僕は障害のある人のいる施設に行くんですが、そういう施設ではダンボールで精巧な作品をつくったり、素晴らしい作品を残してる人がたくさんいるんです。
以前いとうさんとトークさせていただいたアールブリュットの企画展で度肝を抜かれたのは、お菓子の袋とかをとめる針金(ツイストタイ)だけで戦隊ものの戦士を何体もつくっている人の作品です。
いとう めっちゃかっこいいんだよね。
星野 あれは展示するためにつくったわけじゃなくて、やりたいと思って続けているものを主催側が「展示させてほしい」と依頼して展示に至ってるんですよね。そういうのって、見たことで直接的に何かを思うわけじゃないけどめちゃくちゃ心に残る。それっていいなあと思うんです。意味がよくわからない、わかる必要もないようなものに触れて、でも自分のなかに確実にその良さは残っていて、それに出会うのと出会わなかったのとではたぶん自分は違っただろうなという感覚です。
いとう いわゆるキャンバスに描かれる絵が長く続いてきたところにインスタレーションが出てきて、美術がフレームから飛び出したかのように見えるけど、結局美術らしいものだけが美術であることは変わらない。そうなると98パーセントはまだまだ自由な領域があると思う。その98パーセントのなかにアールブリュットの人たちはポツンポツンといる。美や畏れとか、何かを感じさせる、人間がつくった世界はそっちのほうが広いわけだよね。そのことを僕らはついつい忘れる。
言葉も、100パーセントあるなかの2パーセントぐらいを言ってるだけで、名指されたことのない感情がまだまだたくさんあるわけじゃない。
星野 そうなんですよね。
いとう それを僕らはどういうふうに切り開くのかというモチベーションだけで飯三杯食える感じだよね。
ゲレンデみたいなうなじ
星野 びっくりするような視点でものを見てる人ってたくさんいますよね。僕が驚いた作品のひとつが、広島県福山の鞆の津ミュージアムでの展覧会で観た、人のうなじをクローズアップして描いた作品です。その人の野球観戦の絵は、野球は背景としてぼやかしてあってメインは前に座っている人のうなじなんですよ。ものの見方の当たり前が揺れる感覚を得られるってすごいなあと思います。
いとう 野球を観に行ったらうなじは目の前にあるわけだから、本当はそれを無視してるほうがおかしいとさえ言えるね。僕らもじつは鼻の頭がぼんやり視界に見えてるのに、それはないことになってる。見たものを絵に描いてみても、鼻の頭はなかったことにしてる。よく考えたらそっちのほうがおかしいもんね。
星野 そういうのを体験すると、「うなじってすごい魅力的なんだな」ってなるわけじゃないですか。そうすると人のうなじが気になってくるわけですよ。
いとう やばいやばい(笑)。
星野 でも周りからは怪しく見えるんですよね。
いとう 普通はうなじに注意する人がいないからね。
星野 人と違う視点を持ってる人って、こういうことになってるんだなと思います。
いとう そうだね。そういうことで疎外されてる。谷崎潤一郎の『痴人の愛』はナオミという女の子に入れあげちゃう男の話ですけど、その有名なシーンのひとつで、ナオミのうなじから背中にかけてえんえん描写してる。だから、最終的に頭のなかに大きなゲレンデみたいなうなじが見えるんだよね。うなじを精密に書いたらうなじじゃなくなって、「これが文学だ!」って体験をそこで得るんですよ。
それがそれであると名指すことは芸術でもなんでもなくて、それをそれじゃなくしてしまうのが文学や芸術の感覚の世界。うなじのようなものとも言えないとか、世界って本当はそういうものだらけなんだよね。
星野 そうですね。だからそういうものに触れると自分が凝り固まってるなと思うんです。
(後半につづく)
星野概念 (ほしの・がいねん)
1978年生まれ。精神科医 など。病院に勤務する傍ら、執筆や音楽活動も行う。雑誌やWebでの連載のほか、寄稿も多数。音楽活動はさまざま。著書に、いとうせいこう氏との共著 『ラブという薬』『自由というサプリ』(以上、リトル・モア)、2021年2月に初の単著『ないようである、かもしれない~発酵ラブな精神科医の妄言』が刊行。
いとうせいこう
1961年生まれ。編集者を経て、作家、クリエイターとして、活字・映像・音楽・テレビ・舞台など、様々な分野で活躍。1988年、小説『ノーライフキング』(河出文庫)で作家デビュー。『ボタニカル・ライフ―植物生活―』(新潮文庫)で第15回講談社エッセイ賞受賞。『想像ラジオ』(河出文庫)で第35回野間文芸新人賞を受賞。2020年、初の備忘録、ならぬ忘却録『ど忘れ書道』(ミシマ社)で自らの非記憶力を露呈。近著に『福島モノローグ』(河出書房新社)などがある。
編集部からのお知らせ
星野概念さんによるほかの対談もお楽しみください!
『ないようである』刊行を記念して、装画を担当された榎本俊二さんや、人類学者の磯野真穂さんとの対談イベントがおこなわれました。その一部が文章としてミシマガに掲載されています! ぜひご覧ください。